「1970年代の日本とチリ 左翼の崩壊と新自由主義」 関川宗英
1970年10月、人民連合政権アジェンデ政権がチリに誕生した。
選挙によって成立した、世界初の社会主義政権だった。
しかし1973年9月11日、ピノチェトによる軍事クーデターが起き、アジェンデ政権はわずか3年で崩壊する。
ピノチェト軍事政権はクーデター後、左派の弾圧を強めた。逮捕者は政府発表で54万人、うち9000人が国外に追放された。また、チリの人口の1割にもなる100万人が国外に亡命した。そして、処刑、あるいは行方不明となった犠牲者は3000人以上になったと言われている。
アジェンデ政権を支持した人々の願いとは何だったのだろうか。
クーデター直前の9月4日、およそ100万人のチリ国民が「アジェンデ!アジェンデ!国民はあなたを守るぞ!」とシュプレヒコールを上げながらデモ行進した。それは、チリ史上最多の参加者を集めたデモだったという。
僅差で大統領となったアジェンデを、アメリカやチリ右派はさまざまな工作で陥れようとしていたが、一般民衆の支持は高まるばかりだった。
アメリカはアジェンデのチリに対して、露骨な金融封鎖に踏み切る。米国の銀行および国際金融機関に対し、チリに融資を行わないよう圧力をかけたのだ。そして、チリの輸出収入の80%を占めていた銅の輸出と生産を妨害した。さらに、右派勢力の系列下にあるトラック業者によるストライキを扇動した。チリ国内の流通の生命線であるトラックが止まれば、モノは回らなくなり市場の物資は不足する。商店にはモノがなくなり、人びとはわずかな食料を求めて長蛇の列を作った。一方商品の買いだめ、闇市場にあふれる商品。チリはインフレを招き、経済は衰退、社会的混乱に陥った。
しかしチリの民衆は、自分たちでトラックを動かした。ストには参加せず工場に働きに出た。自分たちで調達した商品を、地域別グループが自主的に運営した店で人々の手に配る。工場や農地を占拠・運営・警備し、暴利をむさぼる闇市場に対抗し、近隣の社会奉仕団体と連携していく。こうした活動は、アジェンデを支持する人々の結束をさらに強め、1973年3月の総選挙では、アジェンデ側はさらに得票を伸ばす。
そんな人々の動きが、クーデターの直前まで盛り上がっていた。アジェンデ政権は崩壊したが、政権を支持する人々のうねりは高まるばかりだった。
2020年の今、あらためて考えてしまう。1973年、人民連合政権を支持した労働者たちやアジェンデは、何に負けたのだろうか。
「一つの妖怪がヨーロッパにあらわれている、ーー共産主義の妖怪が。」
『共産党宣言』の最初の言葉だ。マルクスとエンゲルス共著の『共産党宣言』は1847年に発表された。
資本主義の発展により矛盾が増大すると、社会革命(社会主義革命、共産主義革命)が発生する。プロレタリア独裁の段階を経由して、共産主義社会が生まれる。階級抑圧の機構としての国家・軍隊・戦争なども消滅するとされた。
ロシア革命、キューバ革命、共産主義革命のうねりは世界を席巻したが、マルクスの言ったような世界革命につながらなかった。逆に、ソ連や東欧など社会主義国家は崩壊していった。
アジェンデ政権が誕生した1970年、日本では三島由紀夫が割腹自殺している。
日本の60年安保闘争は敗北、70年安保闘争も盛り上がらないまま、左翼運動は衰退して行く。日大全共闘、東大全共闘の敗北後、1972年に連合赤軍あさま山荘事件が起きる。日本の左翼運動は壊滅的な打撃を受け、さらに衰退して行く。
北川透は安保闘争について、次のように書いている。
《視線と拠点》創刊号では、中森敏夫が「真にラジカルな精神とは何か(Ⅱ)」を書いている。主として渡辺武信の詩の批評にあてられているが、「今も私達の私達である根拠は、その貧困のさなかにしか求めようがない」「貧困の自覚とその質的転換こそが、私達の今日負っている闘いでなくてなんであろう」という彼の批評の基調になる意識にぼくは共感する。この貧困というのは、たとえば樺美智子の死をヒロイックな死として演出するような内部の貧困さをさしており、そしてそれこそが時代的貧困、空白への広がりをもつものとされている。安保体験は少数の知識人の孤立せる営為を除いて、まだ何ほどかの思想的な結実をも、もたらしていない。(『未明の構想』1982年)
「安保闘争は戦後大衆運動の原点」(手塚英男 『薔薇雨(ばらう)1960年6月』 2020年刊)の声もあるが、北川透が書くように、日本の左翼運動は安保闘争を総括できないまま、いわゆる政治の季節を終えた。その後は、衰退の一途をたどって、今に至っている。
三島由紀夫の自殺を、左翼の崩壊と重ねて考えることは難しい。しかし、三島の自殺も左翼の崩壊も、戦後日本が突き進んできた時代の高揚といったもの、人々が共有できた熱いもの、その終わりを象徴しているように思える。
1970年代の日本の左翼の崩壊は、高度経済成長後の新しい日本の模索、混迷の時代の始まりだった。
そして、1973年のチリのアジェンデ政権の崩壊。
チリと日本が、同じような時期に混迷の時代を迎えたことは、偶然ではないだろう。
その意味を考えていきたい。












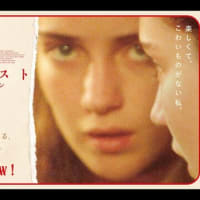
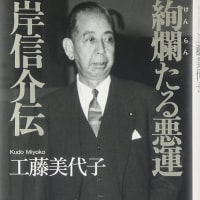
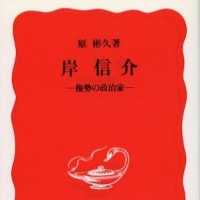

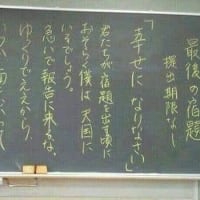

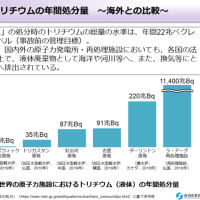
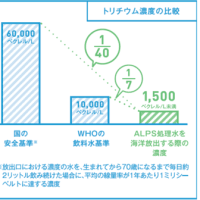





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます