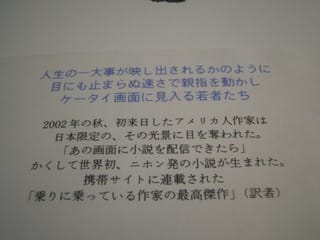「高学歴ノーリターン」中野 雅至/著読みました。著者は同志社大学卒業後、地方公務員を務め、国家公務員試験を受けて官僚(厚労省)になり、現在は兵庫県立大学で助教授を務めているそうです。1964年生まれということですので私とほぼ同じ世代ということになります。
まずこの本で語られる高学歴というのは基本的には高学校歴と言い換えた方がより的確にその意味合いが伝わるのではないかと思います。東大に象徴される難関大学を卒業したこと、入学までに払った勉強に対する努力やコストに対して現在の社会の体制は見合った待遇を与えられていない、というのが考えのベースにある。勉強に対する努力に見合った結果(主に報酬)が伴わなければ努力をする人がいなくなるというのがその主張で、その対策なども提案している。
また一方でスポーツ選手は報われすぎと主張もある。あくまで相対的にということでしょうが。
考えからのスタンスとして共通していると思われるのは、努力が報われるべきだということ。
ただ、現在の状況に対する捉え方などはまったく違う。また、見合っているのかどうかということに対する認識はずいぶん違う。
この方が地方公務員、官僚というのが経験のベースなので、そこでの経験や見てきた待遇がそのベースになることは当然です。
東大と中心としたキャリア官僚の勤務実態や待遇が、その努力に見合ったものかどうかということに大いに疑問を持っているようです。
実際高校時代の友人からは若手官僚の恐ろしく長い勤務などの話は聞いたことがある。この本でも実際その勤務の長い点や仕事の中身の馬鹿馬鹿しさ(コピー取りなどの凡そその優秀さが必要とは思われない仕事の中身)も語られているが、私も確かにその点では疑問があるがそれは2つの点で、つまりその馬鹿馬鹿しい業務を相対的には待遇が悪いとしても将来的なものも含めれば高コストの人を使っていることで、その分をもっとコストのかからない人を使い、もっと官僚といわれるような人を減らした方がいい。
地方の役所などの窓口業務など、かなりマニュアル化が進められるような単純作業に今のような公務員が必要なのか。もっとコストの安い(生涯コスト)人を多く雇って雇用対策の一環にして、ジョブローテーションで土日も開けてください。
著者はこの本の中でいわゆる学歴とビジネスの成功との相関関係は非常に薄いと語っている。
優秀といわれるようなものでいうと知識的な面と、知能的な面がある.学歴という面で言えば、そこで測ることのできる能力は知識的な面が大半である。
この本では中盤からやたらと100円ショップの茶髪のオーナーという存在がたとえとして語られる。ちゃらちゃらした運だけで成功し、必死に勉強した者が豊かとはいえないサラリーマンに過ぎないと比較するが、どうだろうか?
もちろんこの100円ショップのオーナーが単に親の会社を引き継いだような形というのならば話は別になるが、通常そのビジネスが軌道に乗るにはある程度の時間がかかる。また、よく語られることに企業寿命は25年程度といわれる。
長期に繁栄している企業はその業態や中身は当初のものではなくなっているということにもなるでしょう。
ビジネスがある程度成功するまでにはある程度の期間がかかるから、仮にうまくいってもその果実を得る期間はそれほど長くない。また、もし起業するということであれば個人保証などを金融機関は要求するから背負うリスクはかなり大きい。
もちろん持つものと持たざるものとの不平等という意味ではその通りだが、起業して成功するという意味ではそれこそ戦後であろうがその状況は実は変わりないのではないか。
スポーツの部分で語られる視点はまったく的外れであると思います。著者は甲子園出場者と東大入学者で比較をしているが、東大に入学している人数は甲子園出場者と比較にならないほど多い。そもそも東大入学レベルと甲子園出場校の4番を比較することは私に言わせれば、はっきり言って失礼。せめて理3と比較して欲しい。
しかも著者が考えているような報酬を得ているものは甲子園で4番を打ったというようなレベルではない。
しかも残念なことに野球としか比較していないようです。柔道でオリンピックで金メダルを取った人はどうですか。サッカーにしろプロになっただけではプロというだけでJ2レベルではアルバイトをしていたり、どこがプロかわからない。
ほどんど超高収入といえるような報酬を得ているようなスポーツ選手は日本レベルなのではなく、世界的なレベルであるか、キャラクターがたっているなどの付加価値がある人だけです。(しかも人気種目)
例えば荒川静香選手は子供の頃から、受験勉強と比較しても恐ろしく長い期間を、しかもコストを掛けてスケートに費やし、ついに金メダルを取った。もしかすると日本選手権のわずかな違いや浅田選手の出場が認められればオリンピックに出られなかった可能性もある。
フィギアで言えば、世界的にも有数なレベルにある他の選手は学校職員であったりというレベルに過ぎない。しかもこれが人気種目なのである。
より熾烈な競争のスポーツ界でというようなことを書いているが、それは成功するという意味であって努力を評価するということとは別でしょう。それは東大に入ったこと(入ったという努力)を評価するということと同様に考えればいい。
著者は高学歴がビジネスに役立たないと書き、努力が大事だと書きながら、スポーツの努力はまったく評価しようとしていないように見える。
勉強では東大に入った努力を評価し、甲子園には出れば成功が約束されているように書いている。
おそらくスポーツにおける努力はこの著者にとっては、遊びの延長に見えているのでしょう。プロレベルやオリンピックレベルに行くということはそんなに甘くはない。
大体例えば阪大を出れば年収2000万円を保証するなどが必要だと書いているが、そんなことをしたら、阪大の卒業生は雇わないなどの状況が出るのではないだろうか。そうならないとすれば、恐ろしい受験競争が起きて今以上にコストを掛けて教育を受けないと勝ち残れないような状況になると思われる。勉強ならスポーツのように故障もない。
また、受験勉強に費やした努力はもし仮に東大に入れなくても、旧帝大、早慶、6大学、関関同立など段階的にリスクがヘッジされている。
だからこそ努力に見合ったものをという主張なのだと著者は言うだろうが、企業に入ってからの努力で置き換えられないのだろうか?
現実には出身大学により就職での有利不利は存在するし、景気回復が言われているがこの10年で収入が増えたのはいわゆる大企業で、その他は実は所得は減っている。
転職に際しても正社員で働いていたか、担当していた業務などは問われ、就職時のアドバンテージはそれほど小さくない。
社会人になってからの入学などにも触れいるが、これは反対しないが現実には、それだけの余裕があるものがより有利になるというのが、たぶん実態になるでしょう。大変残念ですが。
著者が国家1種に受かることができたのは、はっきりいってよほど優秀か、公務員が暇だったからでしょう。普通の企業で新人がそんなにまともに勉強する時間がありますか、年収数百万の人が就職してから勉強して、学費まで貯めることが考えられますかね。
マラソンでレベルの高い大会に行くと公務員比率の高さにびっくりしますよ。年代別表彰ではなくて、公務員部門と他にしてもらいたいくらいですね、私は。
つまりは会社を辞めるにはそれだけの財力が必要ということです。
官僚といわゆる金持ちとの世間の敬意の変化についても書いているが、私も優秀な官僚がそれほど多くない給与で必死に働いているのはすごいと思っていました。
ただ、最近の報道を見る限りでは天下りや渡りなど利権を作るためにもその労働の時間や力は使われいるようです。
もはや高潔なイメージがなければ誰が尊敬するでしょうか?尊敬と安定と高収入とすべてを得ようのはそれは虫が良すぎるというものでしょう。しかもそれで国は借金漬けというのですから、要するに自業自得です。
開業医だって昔ほど、誰にもお医者様とは思われていないし、機材や医学部への投資、大病院への集中など経営的な感覚がなければうまく回らなくなってきている
。
もっとも厳しい方、条件が悪いほうにそろえてもしょうがないが、安い労働力の国と競争するグローバルな競争になった結果の側面で、学歴で何かを保証するということは社会主義にでもならないと無理でしょう。
この本がいうギャンブル社会というより、持たざるものが希望を持てない「希望格差社会」ということに問題があるのでは?
起業して成功するといっても成功し続けるという点ではギャンブルばかりではないと思います。
努力が報われない社会ではダメだという意見にはまったく賛成なんですけどね、なんか違和感のある本でした。
「下流社会」などとくらべると話題にならなかったことは分かりますね。
そう言えば東大の大学院生は学部生よりも在籍者数が多いんですよね。ちょっとした学校は大学院の枠が必ずしも多くないため、出身の大学の大学院へ進学するよりも、東大の大学院に行くほうがやさしい例もあるらしい。