
まるで昨日のことのように憶えている。今から二十五年も前、うだるように暑い夏の日に、
日本将棋連盟の理事から呼び出しを受けた私は、新宿将棋センターの社長金田秀信氏に
付き添われて、千駄ヶ谷と向かっていた。
札幌市で生まれ育った私は、小学校高学年のときにある壮大な夢を描いた。
小説家になりたい、と思ったのである。
子供のころから本が読むのが好きで、母や兄の本棚に並べられた小説を読みあさっていた。
将棋界に入ってくる多くの天才少年たちが、驚くほど早熟なように、こと本を読むという
ことに関しては、自分も同じだった。棋士を目指すのならば近くの将棋道場に通い、ただ
ひたすら腕を磨けばよい。もし才能があれば近くの大人がきっと目をつけてくれて、道を
拓いてくれるだろう。
しかし、作家への道はそうはいかない。白黒もなければ試験も昇段制度もない。
そのかわりに、年齢制限もはっきりとした挫折もない。いつまでも不安定な夢と、曖昧な
諦めがあるだけである。
中学に入学した私は、作家になるための大きな計画を打ちたて、それを実践していった。
中学の三年間に読む本、高校三年間に身につけるレトリックや哲学、大学進学後に読む本。
おそらく羽生義治や村山聖が、小学校低学年から計画的に自分を棋士に仕立て上げるため
カリキュラムを組んで、詰将棋や定跡書などをどんどんこなして将棋の勉強をしていった
ようにだ。
中学時代には世界文学の名作を次々と読破し、読むことへの体力と持久力をつけた。
高校時代はドイツ哲学を中心に哲学書を読み漁り、どんな難解な文章も読み下す訓練と理
論武装をした。大学へ進んだあとには、そのころ最先端と思われたアメリカ文学を中心と
する世界文学をときには原書を交えて読み続けた。一日二作というノルマを自分に課して
いた時期もあった。すべては計画通りに進んだ。中学のころに直感的に本能をたよりに立
てたカリキュラムがほとんど終了し、そしてあとは卒業試験を待つばかりだった。
卒業試験、つまり小説を書くこと。
小学高学年から志し、そのために青春時代の十年以上を費やしてきたことが試されると
きがきた。コクヨの原稿用紙を二百枚ほど用意して、ある夜中に私は忽然と机に向かった。
胸は高鳴り、体が熱くなった。
そして、そこでかつて一度も考えてみたことも思ってみなかった起こった。
書けないのである。
何も書くことが思い当たらないのである。
一時間が過ぎ二時間が過ぎ、そして半日が過ぎても、ただ私は机に向かっているだけで
原稿用紙一枚も埋めることが出来ないでいた。
愕然とした。
これまでの自分の努力や計画は一体なんだったのだろうかと思った。
要するに私は理論や理屈や体力といった外側ばかりを鍛え上げ、小説家としての内面的
なことの鍛錬をおろそかにしてきた、というかそんなことには思いもはせなかったのだ。
文章を書くにはそれなりの人間としての経験や厚みが必要となる。それをすっかり看過し
ていた。
それでも一週間は頑張った。それは自分が積み重ねてきたことを無駄にしたくないとい
うただの執着心からであった。しかし、いくら頑張ってみたところで、何を書けるわけで
もない。手の中は空っぽで、いくら広げてみたところで何の材料もないのだ。
アパートにこもる日が多くなった。
大学には一切足が向かなくなった。
小説が書けない---。空を舞う翼がもがれたような気分だった。もし、それがなければ、
自分には何もないのだ。
それから一年近くも部屋にこもり、ただだらだらと本だけは読み続けた。社会という輪
の中から自分が確実に遠ざかっていることを感じていた。ドロップアウトしていく実感。
そんな状態で何週間かが過ぎても電話が鳴ることもなく、一通の手紙も届かず、誰が部屋
を訪ねてくることもなかった。
そんなころたまたま出かけた新宿の場末スナックのカウンターの上で将棋と出合った。
私が顔を出したその日は、店が暇だったらしく、常連客と二人で盤をはさんでいた。
小学校六年生のときに教室でブームが起こり、一時は近所の将棋道場に通っていた経験も
あった私は、二人が指す将棋にぐいぐいと引き込まれていった。
大の大人が物も言わずに真剣に盤に向かい合っている姿には、新鮮な驚きがあった。
なぜかわからないけれど、そこには当時の私に不足し、そして持つことが出来なかった
様々なものが内在しているという直感が働いた。二人の対局が終わったら、すぐに私は
頼み込んだ。
「僕にも一局、やらせてください」
そうやって夢に破れ、自分の目標を見失い、進むべき方向性もあやふやになってしま
っていたころ、私は新宿の片隅のスナックで将棋と再会した。将棋を指すのは小学生以来
のことだった。
スナックのマスターに新宿将棋センターを教えられ、一年間三百六十五日の道場通いが
はじまった。小説というあやふやで、到達点が果たしてどこにあるのかもわかりにくい
目標に比べて、将棋は実に明快で心地よかった。自分の努力や研鑽の度合いは、すべてが
嘘偽りのない、白と黒というしるしによって証明された。勉強や努力は勝ち星や昇級、昇
段という数字によって明確に示された。そのことも当時の私には救いであった。
やがて私が小説に向き合うこともなく、大学に足を向けることもなく、ただひたすら道
場通いをするようになったのも当然のことだったかもしれない。朝十時の開店から夜十二
時の閉店まで、ほとんど毎日、将棋を指し続ける日々だった。そんな時間を二年間ほど過
ごすうちに、私は六級から四段になっていたかわりに、社会人とも学生とも呼べないあや
ふやな存在になった。
アマチュアとはいえ四段に上がれば、そこから先は苦しいことばかりだった。県代表ク
ラスの強豪にはいくら頑張っても歯がたたない、アマチュアといえどもそのくらいになる
と将棋を本格的に始めた時期や、環境、そして才能といったものが大きく影響してくるよ
うになる。全生活を注いだといっても過言ではないほどに将棋に打ち込んだのだったが、
やはり二十歳を過ぎてからでは限界があった。小学校時代からまるで体の一部のように吸
い付くように将棋を覚えた強豪たちとの溝は深すぎるのだ。
それでも私は毎日、将棋センターへ通い続けた。二十四歳になっていて、もう他に行く
場所もなかったからだ。夜勤明けのタクシーの運転手や営業マンや、すでに仕事を引退し
た老人や、昼からうろうろしだす真剣師たちに混じって、私は真昼間から将棋ばかりを指
して過ごした。大学の友達は次々と就職して社会へと旅立っていく。それを横目で眺めな
がら、私は体中に巨大な氷の塊りを抱えているような気持ちで、将棋を指し続けた。自分
は棋士を目指しているわけでも、県代表といった目標があるわけでもない。ただもう今更、
将棋から離れるわけにいかない。
不毛だったし、非生産的だった。
無目的で、自虐的だった。
しかし、道場の他にもうどこにも行く場所はなかったのである。
そんなある日のこと、社長の金田さんにお茶を誘われ、思わぬ提案を受けた。将棋連盟
で働いてみないか、というのである。学生の身でありながら、毎日毎日朝から晩まで自分
の道場へ通いつめる私を、心配してくれていたのだ。日本将棋連盟の棋士以外の人たちが、
どういう仕事をしているのかは知らなかったが、「将棋世界」と「将棋マガジン」という
雑誌を発行しているのは知っていた。だから、そこへ行けばきっとその二つの雑誌のうち
のどちらかの編集をできるようになるかもしれないと思い、私はその提案を受け入れた。
本当は抵抗があった。それは若き日の夢を自分から打ち消すことになるからだ。
しかし、もうどうしようもない。他にあてもなかったし、そういう状態で日々を過ごす
こと自体に限界がきていたのだ。
汗だくで向かった喫茶店には、スーツ姿の勝浦修理事がいた。私は肩まである長髪で、
ボロボロのジーパンにTシャツという姿であった。普通に道場に将棋を指しにいったら、
金田さんからすぐに千駄ヶ谷へと連れていかれたのだから仕方がないといえば仕方ない。
将棋連盟の道場で急に欠員が出たのだ、金田さん経由で履歴書を提出していた私に声が
かかったのだ。しかも、これが理事による面接のようなのだ。
「君、出身地は?」と勝浦は眼鏡の奥で鋭く目を光らせて私に聞いた。高段の棋士と面と
向かうのは生まれてはじめての経験で、それだけで結構緊張した。なにしろ目の前にいる
のは雑誌でよく見かえるA級棋士なのである。
「北海道札幌市です」と私が答えると勝浦は「そうかあ、北海道かあ。いいところだね」
と快活に笑い、「それでは」と言ってスーツケースを手に喫茶店を出て行ってしまった。
面接はそれで終わりだった。
昭和五十七年秋、日本将棋連盟の道場課に配属され、私は社会人としてスタートライン
に立つことになった。それは作家への夢の挫折を意味し、それと同時に青春時代の不毛な
放浪の終焉したことを意味した。なによりもまずは胸に抱えた大きな氷を、ゆっくり溶か
していかなければならなかった。
あのスナックで偶然に将棋と出会わなければ、自分はどんな人生を送ったのだろうかと
時々考える。あの日将棋を指してくれたマスターは昭和五十八年に撃墜された大韓航空機
に乗り合わせて死亡、あの店はもうない。
---大崎善生---













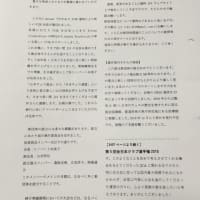

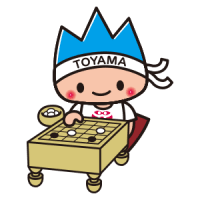




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます