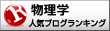今まで黙ってきたけど、クォークからはクォーク凝縮にNG複合量子が憑依したモノがひっきりなしに放出されているんだよね、そしてB状態だけ他の状態よりも電荷が1だけ減るんだ。
qHにおいては+1→+1→0だから平均して+2/3、qlにおいては0→0→-1だから平均して-1/3、このように推移するというのが韓=南部模型であり《クォーク荷電に関する整数模型》なんですよ。π中間子などのUFTのグルオンたちはクォーク凝縮から励起したクォーク反クォーク対ですから、これまでファインマンを批判する形で考察して結論を出して来たように「いずれも時間を順行している」のですけど、無数のクォーク凝縮の方はクォーク騾馬反クォーク対ですから時間を順行する成分と時間を逆行する成分とから出来ています。
時間を順行して逆行して順行して逆行するならば一瞬にすべての状態を重ね合わせることが可能ですから【陽子深部非弾性散乱実験】においても「荷電状況の平均値しか出てこない」という恨みが残ります。
これは逆に言うなれば「昔のデータを蒸し返して論議する必要がなくなる」といった点においてはメリットです。
UFT黎明期のオリジナルモデルでは「T反N・N反N・N反Tの三種が組み合わさって6成分からなる雪の結晶のような構造体(crystal snow)が生じる」と論じてあります。言わば、その雪の結晶を芯にして周りに「3つのクォークがたぐり寄せられるように集まってきて封じ込められる」というのが(当時、思い付いた言葉では)《ハットトリック機構》というモノでした。
まとめますと
1)量子もしくはデジタルインフレーション宇宙からビッグバンに移行した際に、物質ユニバース粒子がトップクォークとボトムクォークを生んだ直後に、アイソ対称性の自発的破れから生じた南部=ゴールドストンボソン(NG量子)の振る舞いが【ザ・ファースト】
2)NG量子はクォークに憑依し、その取付くNG量子がひっきりなしに入れ替わって整数荷電のまま平均値が分数になるように、NG量子交換子のような役割を果たすNG複合量子3重項 T反N・N反N・N反T が生じることが【ザ・セカンド】
3)NG複合量子3重項がさらに集合して6成分からなるNG超複合量子クリスタルスノウが生じることを【ザ・サード】
4)3クォークが封じ込められることが【ハットトリック】
これが原型でして、最後のハットトリックというのも面白いけどファーストセカンドサードと来ているのだったら【ザ・ホーム】というのが穏当かな、と思ったりもしておりました。しかし、このようにエベレストにおいてマロリーがたどったルートを設定してみましたら、ファーストステップ・セカンドステップ・サードステップ・頂上ピラミッド・山頂ってゆーのが正しいかな、なんて言葉遊びを楽しんでおる次第。
その昔のハットトリックでは間違っていたことが一つございまして、本当のヒッグス機構によってゲージベクトルスピンを得るという手法では【ΛΣ問題】が不合理に終わるので無理です。あるいはヒッグス機構に入ったからと言ってスピン1を貰う必要がナイ(W粒子やZ粒子と違う)としたら~、いや、当面は《σ模型》の示唆に従って「強い相互作用におけるヒッグス粒子の代わりとなる約600Mevのスカラー中間子による統率」であると信じてまいりますか?
UFTでは「中心にあるのはω中間子ではナイか」というのが元の説で、その理由が「3πに割れるし3πから合成されるのではなかったか」ということでした。しかし「中心にベクトル粒子があってはいけない」ことが組成sss等から見出されましたので(不本意ながらも)η中間子を候補としております。η中間子は3πに割れるのは非常に良いのだけれども、ストレンジフレーバーを含んでいるのでクリスタルスノウから生成されるかどうか疑問です。
いずれにせよゲルマンのudsクォークからなるSU(3)対称性に対して、日本の理論はudクォークのSU(2)から始められる、ただし2^2-1=3種というのはハイパーゲージボソンたるπ中間子3重項でイイのだが、ヒッグス粒子の代わりとなるη中間子というのは「ちょっと頼りないな」という印象を残します。
しかし、それは「すぐ手の届くところにストレンジフレーバーが存在することを示唆している」とも言えますでしょう・・。
(クリスタルスノウとヒッグス粒子とが化合してくれれば“手っ取り早い”のですけど?)
qHにおいては+1→+1→0だから平均して+2/3、qlにおいては0→0→-1だから平均して-1/3、このように推移するというのが韓=南部模型であり《クォーク荷電に関する整数模型》なんですよ。π中間子などのUFTのグルオンたちはクォーク凝縮から励起したクォーク反クォーク対ですから、これまでファインマンを批判する形で考察して結論を出して来たように「いずれも時間を順行している」のですけど、無数のクォーク凝縮の方はクォーク騾馬反クォーク対ですから時間を順行する成分と時間を逆行する成分とから出来ています。
時間を順行して逆行して順行して逆行するならば一瞬にすべての状態を重ね合わせることが可能ですから【陽子深部非弾性散乱実験】においても「荷電状況の平均値しか出てこない」という恨みが残ります。
これは逆に言うなれば「昔のデータを蒸し返して論議する必要がなくなる」といった点においてはメリットです。
UFT黎明期のオリジナルモデルでは「T反N・N反N・N反Tの三種が組み合わさって6成分からなる雪の結晶のような構造体(crystal snow)が生じる」と論じてあります。言わば、その雪の結晶を芯にして周りに「3つのクォークがたぐり寄せられるように集まってきて封じ込められる」というのが(当時、思い付いた言葉では)《ハットトリック機構》というモノでした。
まとめますと
1)量子もしくはデジタルインフレーション宇宙からビッグバンに移行した際に、物質ユニバース粒子がトップクォークとボトムクォークを生んだ直後に、アイソ対称性の自発的破れから生じた南部=ゴールドストンボソン(NG量子)の振る舞いが【ザ・ファースト】
2)NG量子はクォークに憑依し、その取付くNG量子がひっきりなしに入れ替わって整数荷電のまま平均値が分数になるように、NG量子交換子のような役割を果たすNG複合量子3重項 T反N・N反N・N反T が生じることが【ザ・セカンド】
3)NG複合量子3重項がさらに集合して6成分からなるNG超複合量子クリスタルスノウが生じることを【ザ・サード】
4)3クォークが封じ込められることが【ハットトリック】
これが原型でして、最後のハットトリックというのも面白いけどファーストセカンドサードと来ているのだったら【ザ・ホーム】というのが穏当かな、と思ったりもしておりました。しかし、このようにエベレストにおいてマロリーがたどったルートを設定してみましたら、ファーストステップ・セカンドステップ・サードステップ・頂上ピラミッド・山頂ってゆーのが正しいかな、なんて言葉遊びを楽しんでおる次第。
その昔のハットトリックでは間違っていたことが一つございまして、本当のヒッグス機構によってゲージベクトルスピンを得るという手法では【ΛΣ問題】が不合理に終わるので無理です。あるいはヒッグス機構に入ったからと言ってスピン1を貰う必要がナイ(W粒子やZ粒子と違う)としたら~、いや、当面は《σ模型》の示唆に従って「強い相互作用におけるヒッグス粒子の代わりとなる約600Mevのスカラー中間子による統率」であると信じてまいりますか?
UFTでは「中心にあるのはω中間子ではナイか」というのが元の説で、その理由が「3πに割れるし3πから合成されるのではなかったか」ということでした。しかし「中心にベクトル粒子があってはいけない」ことが組成sss等から見出されましたので(不本意ながらも)η中間子を候補としております。η中間子は3πに割れるのは非常に良いのだけれども、ストレンジフレーバーを含んでいるのでクリスタルスノウから生成されるかどうか疑問です。
いずれにせよゲルマンのudsクォークからなるSU(3)対称性に対して、日本の理論はudクォークのSU(2)から始められる、ただし2^2-1=3種というのはハイパーゲージボソンたるπ中間子3重項でイイのだが、ヒッグス粒子の代わりとなるη中間子というのは「ちょっと頼りないな」という印象を残します。
しかし、それは「すぐ手の届くところにストレンジフレーバーが存在することを示唆している」とも言えますでしょう・・。
(クリスタルスノウとヒッグス粒子とが化合してくれれば“手っ取り早い”のですけど?)