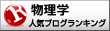まず、ちょっと分かりにくかったワインバーグ=サラム理論による真空期待値246Gevを流用できる根拠が明確化できましたよw)
クォークは封じ込められているので、外界において真空と接しているのはレプトンの方であって、そこにはクォークは一つもございませんから、まさにワインバーグ論文の標題になっているように《レプトンの理論》が適用される真空なのです。さらに、グラショウら大統一理論の担い手たちがいみじくみも指摘したように、レプトンに関してアイソ対称性が成立していたのではありませぬ。アイソ対称性については、ユニバース粒子が崩壊した際に「クォークに関して自発的に破れた」とするのがユニバーサルフロンティア理論の特徴ですから、ワインバーグ=サラム理論とは対立しませんし、むしろ完全に補完する関係であることを誇りに思っております。
次に、観測されてはいるがCP破れの原動力だということは否定されてきた超弱相互作用に素晴らしい合理化を導入できましたw)
相互作用の強さは結合定数だけに依存しますから、知られているゲージ力同士では弱い相互作用と電磁力とは同じ強さのはずなのですが、弱い相互作用では三体崩壊をするという理由で実効的な結合定数が非常に小さくなったと等価になるそうです。しかし、何が原因となるかまでは私の研究は進んでおりませんが、超弱相互作用という物が存在した場合には関与する素粒子の質量はかなり重くなると考えています。その正体がユニバース粒子だとすれば、CP破れに直接に関与するはずなのですが、そうではないということから私は別の方策を立てました。
小林=益川模型によるペンギン過程のW粒子をユニバース粒子で置き替えた上でtクォークからスーパーW粒子を放出させるのです。
スーパーW粒子はZ粒子とW粒子とが非常に弱く結合した物で、出た直後に両者に崩壊してしまう性質を持っており、その質量が171.4Gevであることから、tクォークからcクォークに変化するユニバーサルフロンティア理論独自の《トリー・ペンギン過程》では(tクォーク質量からスーパーW粒子質量を引いた残りは0.6Gevしかないので)半端なエネルギーの中間状態でのみ出現します。当理論におきましては、仮想ボソンは時間を逆行して現れるので、tフレーバーに遷移した所からスーパーW粒子が出て、その後でcフレーバーになり、さらに小林=益川模型および標準理論によるペンギン過程ではW粒子が戻ってくる所が「まさにユニバース粒子が時間を逆行して出ていく所」となるので、エネルギーダウンしてsクォークになったりできます。
その超弱相互作用説によればZ粒子が即座にニュートリノ反ニュートリノ対になるのでCP破れの規則からは非常に都合のよいことになるのです・・。
Kl中間子やBl中間子であるはずのハドロンが、Ks中間子やBs中間子として崩壊するのがCP破れ現象の骨子なのですが、
その質量を比較すると「Ks(Bs)よりもKl(Bl)の方がわずかに重い」からですw)
「CPが破れる際にはニュートリノ反ニュートリノ対を放出してわずかに質量が軽くなってから崩壊する」ことを仮定すればすべてが説明できます・・。
ですから、超弱相互作用はCP破れそのものの原動力ではなかったものの、CPが破れることによって超弱波動が観測される理由になっていることが雄弁に証言され得るようになりました。
さらに、基本的に大統一宇宙と異なる点は「ハドロン形成に従って古い真空が内部に取り込まれていく」というプロセスが出現してくることです。古い真空の中で新しい真空がインフレーションを起こすという考え方は採用しません。それは、まるで高校時代に化学という教科で学習したような、水上にできているなんとか酸の膜にスポイドでなんとか酸を垂らすとスーッと広がるといった情景を思い浮かべます。フマル酸とマレイン酸じゃなかったかな、間違いだったら<m(__)m>な、で、ゲルマンはマレイ・ゲルマンというのだっけ、クォークの周期表ともいうし、もしかしたら元を正せば化学畑の人じゃないのかな、これも間違ってたら<m(__)m>なさいね。
ま、僕も高等学校において物理学が特別優秀な成績が取れなかったという理由もあって地球科学科出身で、おまけに単純な地震学教授でツマラナイという理由もあって地球物理学教室の出ですらない、むしろ地球化学教室出身だったりする。
あ~あ、学問ってのは第一希望は貫かねばならないな、もっと受験勉強をすればよかったよw)
クォークは封じ込められているので、外界において真空と接しているのはレプトンの方であって、そこにはクォークは一つもございませんから、まさにワインバーグ論文の標題になっているように《レプトンの理論》が適用される真空なのです。さらに、グラショウら大統一理論の担い手たちがいみじくみも指摘したように、レプトンに関してアイソ対称性が成立していたのではありませぬ。アイソ対称性については、ユニバース粒子が崩壊した際に「クォークに関して自発的に破れた」とするのがユニバーサルフロンティア理論の特徴ですから、ワインバーグ=サラム理論とは対立しませんし、むしろ完全に補完する関係であることを誇りに思っております。
次に、観測されてはいるがCP破れの原動力だということは否定されてきた超弱相互作用に素晴らしい合理化を導入できましたw)
相互作用の強さは結合定数だけに依存しますから、知られているゲージ力同士では弱い相互作用と電磁力とは同じ強さのはずなのですが、弱い相互作用では三体崩壊をするという理由で実効的な結合定数が非常に小さくなったと等価になるそうです。しかし、何が原因となるかまでは私の研究は進んでおりませんが、超弱相互作用という物が存在した場合には関与する素粒子の質量はかなり重くなると考えています。その正体がユニバース粒子だとすれば、CP破れに直接に関与するはずなのですが、そうではないということから私は別の方策を立てました。
小林=益川模型によるペンギン過程のW粒子をユニバース粒子で置き替えた上でtクォークからスーパーW粒子を放出させるのです。
スーパーW粒子はZ粒子とW粒子とが非常に弱く結合した物で、出た直後に両者に崩壊してしまう性質を持っており、その質量が171.4Gevであることから、tクォークからcクォークに変化するユニバーサルフロンティア理論独自の《トリー・ペンギン過程》では(tクォーク質量からスーパーW粒子質量を引いた残りは0.6Gevしかないので)半端なエネルギーの中間状態でのみ出現します。当理論におきましては、仮想ボソンは時間を逆行して現れるので、tフレーバーに遷移した所からスーパーW粒子が出て、その後でcフレーバーになり、さらに小林=益川模型および標準理論によるペンギン過程ではW粒子が戻ってくる所が「まさにユニバース粒子が時間を逆行して出ていく所」となるので、エネルギーダウンしてsクォークになったりできます。
その超弱相互作用説によればZ粒子が即座にニュートリノ反ニュートリノ対になるのでCP破れの規則からは非常に都合のよいことになるのです・・。
Kl中間子やBl中間子であるはずのハドロンが、Ks中間子やBs中間子として崩壊するのがCP破れ現象の骨子なのですが、
その質量を比較すると「Ks(Bs)よりもKl(Bl)の方がわずかに重い」からですw)
「CPが破れる際にはニュートリノ反ニュートリノ対を放出してわずかに質量が軽くなってから崩壊する」ことを仮定すればすべてが説明できます・・。
ですから、超弱相互作用はCP破れそのものの原動力ではなかったものの、CPが破れることによって超弱波動が観測される理由になっていることが雄弁に証言され得るようになりました。
さらに、基本的に大統一宇宙と異なる点は「ハドロン形成に従って古い真空が内部に取り込まれていく」というプロセスが出現してくることです。古い真空の中で新しい真空がインフレーションを起こすという考え方は採用しません。それは、まるで高校時代に化学という教科で学習したような、水上にできているなんとか酸の膜にスポイドでなんとか酸を垂らすとスーッと広がるといった情景を思い浮かべます。フマル酸とマレイン酸じゃなかったかな、間違いだったら<m(__)m>な、で、ゲルマンはマレイ・ゲルマンというのだっけ、クォークの周期表ともいうし、もしかしたら元を正せば化学畑の人じゃないのかな、これも間違ってたら<m(__)m>なさいね。
ま、僕も高等学校において物理学が特別優秀な成績が取れなかったという理由もあって地球科学科出身で、おまけに単純な地震学教授でツマラナイという理由もあって地球物理学教室の出ですらない、むしろ地球化学教室出身だったりする。
あ~あ、学問ってのは第一希望は貫かねばならないな、もっと受験勉強をすればよかったよw)