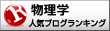ゲーデル命題Gの場合には「Gまたは¬Gがいずれかが真であるにもかかわらずいずれも証明できない」「Gは数学の無矛盾性と同値である」というのです!
これが“立場が逆”であってみれば「数学の定理形式の命題の中にも無矛盾性と同じように正しいにもかかわらず証明できない命題が出現する」「その事態は、まさに数学の不完全性という様相を呈するだろう」ということになるのです。私が高校時代に数学などの話をした知人の中には【第一不完全性定理】から「証明不可能な真実は存在する」との認識に到達して卒業アルバムの寄せ書きに認めた者もおりました。彼は、それなりに優秀な当時一期校扱いの公立大学において26歳で大学院から引き抜かれて助手(いまでいう助教)を務めておりますけれど、ひょっとしたら博士論文のテーマをそこに持って行こうとしていて引きとめられたのかも分かりません・・w)
そこらの事情がアインシュタインなんかでしたら本人が正しいのですけど、そして大学から追放同様になってしまって助手人事に掛からなくなったのですけど、学問の歴史には同様に理不尽な事柄が異様に多く散見されますよね?
それは学者風情に向く性格が“異様に冷たい人柄”だ、ということが大きいでしょーけど、国際物理学会の“終わりたがり”と“遊び好き”が甚大に暗い影を落としているのだと存じます・・w)
そんなじゃ、自らの“こころの闇(やみ)”じゃないですか、自分で気にならないのですかね、えー、あっと、話題を元に戻しましょう!
確かに、ペアノ公理だけを使って自然数の無矛盾性を証明することは不可能でしょうし、そんなことを言い出せばフェルマー定理やゴールドバッハの予想(とは、ちと大袈裟だが)を証明することだってできないですから、そもそもゲーデルの業績を広範囲にとらえ過ぎた向きが社会思想方面になど誤用してしまったという経緯があったのだと思いますよ。不完全性定理なんぞ、一つの数学的体系が存在したとして、その内部には「この命題は証明できない」という意味を持つ物が存在し、それは正しいことが分かっているにも拘らず証明も反証もされない、そしてG「Gは証明できない」と書きなおしたそのゲーデル命題は「数学の無矛盾性と同値であると証明される」というじつに狭い世界のお話なんですよ・・w)
応用するとして「良いクラスであればこのクラスは良いクラスだということをそのクラスの者の発言だけでは証明できない」「良い授業であればこの授業は良い授業だということをその授業内容だけでは証明できない」などなど、そもそも「証明できないどころか証言できないというのが正しい」でしょうね?
それと「だから生徒から褒められなければならない」「だから第三者の目が必要だ」というのとは千里の開きがございます・・w)
それは評論活動の正当性と妥当性というまったく別のテーマとなるからですけど?
教育委員の人たちは中小企業診断士のように学校教育診断士としての活動をしたら仕事だと思うのですけどまったくですね?
ここでG「Gは証明できない」の自己言及性を重要視して「この命題は証明できない」に戻せば、その否定命題は「この命題は証明できる」になりますから、そこから¬G「¬Gは証明できる」になりますよね。そうすると、¬Gは自明だということになりますから(Gを数学命題だとしたら)Gすなわち数学の無矛盾性は間違っている、さらに「すなわち数学は矛盾している」にはなりません。こうやったら、Gは数学の無矛盾性と同値ではなくなってしまっているし、数学命題ではなくなってしまっているでしょう。
そこで山野命題を登場させます、山野命題とは「この命題は反証されない」という意味を持ち、そこからY「Yは反証されない」と定式され、否定形は「この命題は反証される」から¬Y「¬Yは反証される」となります。
後は次回に回します、あー、しんど・・w)
これが“立場が逆”であってみれば「数学の定理形式の命題の中にも無矛盾性と同じように正しいにもかかわらず証明できない命題が出現する」「その事態は、まさに数学の不完全性という様相を呈するだろう」ということになるのです。私が高校時代に数学などの話をした知人の中には【第一不完全性定理】から「証明不可能な真実は存在する」との認識に到達して卒業アルバムの寄せ書きに認めた者もおりました。彼は、それなりに優秀な当時一期校扱いの公立大学において26歳で大学院から引き抜かれて助手(いまでいう助教)を務めておりますけれど、ひょっとしたら博士論文のテーマをそこに持って行こうとしていて引きとめられたのかも分かりません・・w)
そこらの事情がアインシュタインなんかでしたら本人が正しいのですけど、そして大学から追放同様になってしまって助手人事に掛からなくなったのですけど、学問の歴史には同様に理不尽な事柄が異様に多く散見されますよね?
それは学者風情に向く性格が“異様に冷たい人柄”だ、ということが大きいでしょーけど、国際物理学会の“終わりたがり”と“遊び好き”が甚大に暗い影を落としているのだと存じます・・w)
そんなじゃ、自らの“こころの闇(やみ)”じゃないですか、自分で気にならないのですかね、えー、あっと、話題を元に戻しましょう!
確かに、ペアノ公理だけを使って自然数の無矛盾性を証明することは不可能でしょうし、そんなことを言い出せばフェルマー定理やゴールドバッハの予想(とは、ちと大袈裟だが)を証明することだってできないですから、そもそもゲーデルの業績を広範囲にとらえ過ぎた向きが社会思想方面になど誤用してしまったという経緯があったのだと思いますよ。不完全性定理なんぞ、一つの数学的体系が存在したとして、その内部には「この命題は証明できない」という意味を持つ物が存在し、それは正しいことが分かっているにも拘らず証明も反証もされない、そしてG「Gは証明できない」と書きなおしたそのゲーデル命題は「数学の無矛盾性と同値であると証明される」というじつに狭い世界のお話なんですよ・・w)
応用するとして「良いクラスであればこのクラスは良いクラスだということをそのクラスの者の発言だけでは証明できない」「良い授業であればこの授業は良い授業だということをその授業内容だけでは証明できない」などなど、そもそも「証明できないどころか証言できないというのが正しい」でしょうね?
それと「だから生徒から褒められなければならない」「だから第三者の目が必要だ」というのとは千里の開きがございます・・w)
それは評論活動の正当性と妥当性というまったく別のテーマとなるからですけど?
教育委員の人たちは中小企業診断士のように学校教育診断士としての活動をしたら仕事だと思うのですけどまったくですね?
ここでG「Gは証明できない」の自己言及性を重要視して「この命題は証明できない」に戻せば、その否定命題は「この命題は証明できる」になりますから、そこから¬G「¬Gは証明できる」になりますよね。そうすると、¬Gは自明だということになりますから(Gを数学命題だとしたら)Gすなわち数学の無矛盾性は間違っている、さらに「すなわち数学は矛盾している」にはなりません。こうやったら、Gは数学の無矛盾性と同値ではなくなってしまっているし、数学命題ではなくなってしまっているでしょう。
そこで山野命題を登場させます、山野命題とは「この命題は反証されない」という意味を持ち、そこからY「Yは反証されない」と定式され、否定形は「この命題は反証される」から¬Y「¬Yは反証される」となります。
後は次回に回します、あー、しんど・・w)