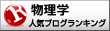【フォトン交換による荷電粒子の等加速運動】
以上の考察結果を初心に沿ってまとめ直してみると、曲率を持ったレールに沿って運動する車両を流し撮りすれば、微小なブレが放射方向外向きに出ることになり、それが向心力による運動である証だということになる。そして、それだけでは物足りないところを補えば「曲がった境界条件にとって直進は逆向きの湾曲に等しい」ことから「レールは作用としての車両からの遠心力を受けてから反作用として車両に向心力を与えている」ということだった。
その際の作用と反作用とは、Δp・Δt、すなわち距離に比例したディメンジョンを持っている、と、私は考えている。
ここで量子現象の世界に話を移そう。
荷電粒子、たとえば電子が、中心にある逆の電荷を持った粒子、たとえば陽子から、絶えず一定量のフォトンの供給を受けて運動したとしたらどうなるだろうか。Δp=hν/cなるフォトンが作用したとすれば、Δtの反応時間の間には、Δp・Δtに比例し距離だけ陽子から遠ざかるだろう。電子はそこから同じ運動量のフォトンを180度後方へ向けて放射したとすれば、同じだけ陽子に近づくだろう。いや、正確には、直線的な流し撮りと比べての値であって、陽子からの距離そのものとはまた異なるのだが。そうしたら(レールのような境界条件との間の相互作用がなくても)「電子は陽子の周りを近似的に等速円運動する」のではないだろうか。
さて、本当にそんな魔法のようなことが起こっているのだろうか。それは運動量交換としてワーサムの過程だから少し慎重に検討し直す必要があった。そこで、舞台を変えて、一定の静電場中のおいて静止している荷電粒子のその後の振る舞いを論じることにしたのである。
静止した荷電粒子が前方からきたフォトンを吸収するとΔp・Δtに比例した距離だけ後ずさりする。問題は、その瞬間に荷電粒子は後方へ向けた速度を獲得してしまっているから、同じ運動量のフォトンを180度後方へ放射したところで前方には向かってくれないということである。運動量交換の結果は本当にワーサムとなってしまって、あまけに、先にあとずさりしてしまっているから、その後ずさりした地点で止まってしまう。
まあ、これじゃ何もならない…。
そこで湯川のマルを思い出して素粒子にも体積があるようにイメージしてみることにした。それでも最近の研究成果にはあまり逆らうわけにもいかない。電子とクォークとは殆ど数学的厳密に点でなければ加速器による実験結果が説明できないそうだから電子は点であるとしてみた。次は、フォトンをどう近似するかだが、ここは結論を最優先して、こじつけでもかまわないと考えて、フォトンを完全に均質な棒のようにして計算してみたら巧くいった。
フォトン棒が接触した瞬間がもっとも電子に与える運動量が大きくて、時間経過に従って減少し、棒の中心が通過する瞬間には電子が受ける運動量はちょうど0になる。運動量を受けることによる電子の移動量はこれもまたΔp・Δtに比例するから、棒の中心が通過する瞬間には電子の動きはデッドポイントになっていることだろう。
鉛直投げ上げの頂点と同じ状態だ。
ならば、電子はフォトンによる運動量交換によっていったん後ずさりはしたが、後ずさりした地点において後ろ向きの運動量は持たなくて済むのである。その位置における電子の速度は正確に0になる。フォトン棒の中心が電子を通過してから電子は前向きの運動量を得始めて、フォトン棒の端が通過し終わる瞬間には、完全に元の位置に戻ることになる。調和振動子の動きの下半分と同じであり、自然長さのバネに重りををつるしてから自然長さの位置に戻るまでと同じだ。これで運動量ワーサムで加速度を得る機構を合理化できる説明になった。
これが近似的に等加速になることの数学的証明はそう難しくない。ギザギザだと思っていた運動は二次曲線による等加速近似の動きだった。おそらく少なくともフォトンは数学的厳密な点ではなくて波長に比例した長さがあるのだろう。
このことからF=maが近似式だということが言える。
二十年ほど前に「理論物理学をやるならハミルトニアンなしでは生きていけない!」とか言っていたそうだが、その理由として最大のものは、たとえニュートン力学の世界であっても「F=maのままでは正しくない!」というものだった。あちらの人は科学者であってもシンプルイズベストに関しては過ぎたるは及ばざるが如しとして嘲弄の元であるように考える流儀の人が多い。どうしても比例式なんかで終わったらそこを心配するようで、フックなどもF=-kxは暗号だけで残したほどだ。それほど世人に笑われるというのは怖いものらしい。私なども用心して十分に詳しく難解に書いてからイージーイズベターザンシンプル(簡単は何より)とでも言って世人を喜ばせるほかにないようである。
私の誇りは「自然が飛び飛びに運動するのが真の原因だ!」と(プランクのように)分かって、しかも、同じように半ば証明できたことにある。ま、このような宣言は一流を自負するばかりの理論学者にとって顰蹙を買うばかりの愚言なのだろうが、私が自分で考えても世の中に笑われるよりはまだましだと思う。それが真の原因であるのならば抽象性に逃げるのは愚かしいとこちらから指摘できるからだ。
理論物理学者がプランクの裏切り者ばかりだというのはあまり良いことではないだろう。どうせなら裏切るべきはボーアの対応原理の方であろうか。プランク定数hを0にした極限をとったとしても自然はニュートン力学そのもののようには動いてくれないことを私は証明できた。たとえプランク定数hが0だったとしても自然現象はデジタル的に進行するからであるというのが真相である。完全になめらかな厳密な微分のような加速運動がいったいどこにあるだろうか。どのような動力もロケットと同じように飛び飛びに加速している。
飾り文字の大きなHは美しいが誤魔化しであるように思う。
彼らの物理学がアナログ放送なのであって、こちらが地上デジタルであるとすら思っている、か、そこまで言ったらお終いだとしても、あるいは、とにかく黎明期の最初の作品というものはデジタルオーディオであってもエジソンの蓄音機のような音だったということで、当方としてはそのうちのどこに位置していようと恥じることなどない。ハミルトニアン主義は物理学らしい具体的な認識に失敗している所をむしろ安直な抽象性によって誤魔化すことを蔓延らせている罪悪であるだろう。
ゲージ場はちゃんとしたデジタル主義で描くべきである。
以上の考察結果を初心に沿ってまとめ直してみると、曲率を持ったレールに沿って運動する車両を流し撮りすれば、微小なブレが放射方向外向きに出ることになり、それが向心力による運動である証だということになる。そして、それだけでは物足りないところを補えば「曲がった境界条件にとって直進は逆向きの湾曲に等しい」ことから「レールは作用としての車両からの遠心力を受けてから反作用として車両に向心力を与えている」ということだった。
その際の作用と反作用とは、Δp・Δt、すなわち距離に比例したディメンジョンを持っている、と、私は考えている。
ここで量子現象の世界に話を移そう。
荷電粒子、たとえば電子が、中心にある逆の電荷を持った粒子、たとえば陽子から、絶えず一定量のフォトンの供給を受けて運動したとしたらどうなるだろうか。Δp=hν/cなるフォトンが作用したとすれば、Δtの反応時間の間には、Δp・Δtに比例し距離だけ陽子から遠ざかるだろう。電子はそこから同じ運動量のフォトンを180度後方へ向けて放射したとすれば、同じだけ陽子に近づくだろう。いや、正確には、直線的な流し撮りと比べての値であって、陽子からの距離そのものとはまた異なるのだが。そうしたら(レールのような境界条件との間の相互作用がなくても)「電子は陽子の周りを近似的に等速円運動する」のではないだろうか。
さて、本当にそんな魔法のようなことが起こっているのだろうか。それは運動量交換としてワーサムの過程だから少し慎重に検討し直す必要があった。そこで、舞台を変えて、一定の静電場中のおいて静止している荷電粒子のその後の振る舞いを論じることにしたのである。
静止した荷電粒子が前方からきたフォトンを吸収するとΔp・Δtに比例した距離だけ後ずさりする。問題は、その瞬間に荷電粒子は後方へ向けた速度を獲得してしまっているから、同じ運動量のフォトンを180度後方へ放射したところで前方には向かってくれないということである。運動量交換の結果は本当にワーサムとなってしまって、あまけに、先にあとずさりしてしまっているから、その後ずさりした地点で止まってしまう。
まあ、これじゃ何もならない…。
そこで湯川のマルを思い出して素粒子にも体積があるようにイメージしてみることにした。それでも最近の研究成果にはあまり逆らうわけにもいかない。電子とクォークとは殆ど数学的厳密に点でなければ加速器による実験結果が説明できないそうだから電子は点であるとしてみた。次は、フォトンをどう近似するかだが、ここは結論を最優先して、こじつけでもかまわないと考えて、フォトンを完全に均質な棒のようにして計算してみたら巧くいった。
フォトン棒が接触した瞬間がもっとも電子に与える運動量が大きくて、時間経過に従って減少し、棒の中心が通過する瞬間には電子が受ける運動量はちょうど0になる。運動量を受けることによる電子の移動量はこれもまたΔp・Δtに比例するから、棒の中心が通過する瞬間には電子の動きはデッドポイントになっていることだろう。
鉛直投げ上げの頂点と同じ状態だ。
ならば、電子はフォトンによる運動量交換によっていったん後ずさりはしたが、後ずさりした地点において後ろ向きの運動量は持たなくて済むのである。その位置における電子の速度は正確に0になる。フォトン棒の中心が電子を通過してから電子は前向きの運動量を得始めて、フォトン棒の端が通過し終わる瞬間には、完全に元の位置に戻ることになる。調和振動子の動きの下半分と同じであり、自然長さのバネに重りををつるしてから自然長さの位置に戻るまでと同じだ。これで運動量ワーサムで加速度を得る機構を合理化できる説明になった。
これが近似的に等加速になることの数学的証明はそう難しくない。ギザギザだと思っていた運動は二次曲線による等加速近似の動きだった。おそらく少なくともフォトンは数学的厳密な点ではなくて波長に比例した長さがあるのだろう。
このことからF=maが近似式だということが言える。
二十年ほど前に「理論物理学をやるならハミルトニアンなしでは生きていけない!」とか言っていたそうだが、その理由として最大のものは、たとえニュートン力学の世界であっても「F=maのままでは正しくない!」というものだった。あちらの人は科学者であってもシンプルイズベストに関しては過ぎたるは及ばざるが如しとして嘲弄の元であるように考える流儀の人が多い。どうしても比例式なんかで終わったらそこを心配するようで、フックなどもF=-kxは暗号だけで残したほどだ。それほど世人に笑われるというのは怖いものらしい。私なども用心して十分に詳しく難解に書いてからイージーイズベターザンシンプル(簡単は何より)とでも言って世人を喜ばせるほかにないようである。
私の誇りは「自然が飛び飛びに運動するのが真の原因だ!」と(プランクのように)分かって、しかも、同じように半ば証明できたことにある。ま、このような宣言は一流を自負するばかりの理論学者にとって顰蹙を買うばかりの愚言なのだろうが、私が自分で考えても世の中に笑われるよりはまだましだと思う。それが真の原因であるのならば抽象性に逃げるのは愚かしいとこちらから指摘できるからだ。
理論物理学者がプランクの裏切り者ばかりだというのはあまり良いことではないだろう。どうせなら裏切るべきはボーアの対応原理の方であろうか。プランク定数hを0にした極限をとったとしても自然はニュートン力学そのもののようには動いてくれないことを私は証明できた。たとえプランク定数hが0だったとしても自然現象はデジタル的に進行するからであるというのが真相である。完全になめらかな厳密な微分のような加速運動がいったいどこにあるだろうか。どのような動力もロケットと同じように飛び飛びに加速している。
飾り文字の大きなHは美しいが誤魔化しであるように思う。
彼らの物理学がアナログ放送なのであって、こちらが地上デジタルであるとすら思っている、か、そこまで言ったらお終いだとしても、あるいは、とにかく黎明期の最初の作品というものはデジタルオーディオであってもエジソンの蓄音機のような音だったということで、当方としてはそのうちのどこに位置していようと恥じることなどない。ハミルトニアン主義は物理学らしい具体的な認識に失敗している所をむしろ安直な抽象性によって誤魔化すことを蔓延らせている罪悪であるだろう。
ゲージ場はちゃんとしたデジタル主義で描くべきである。