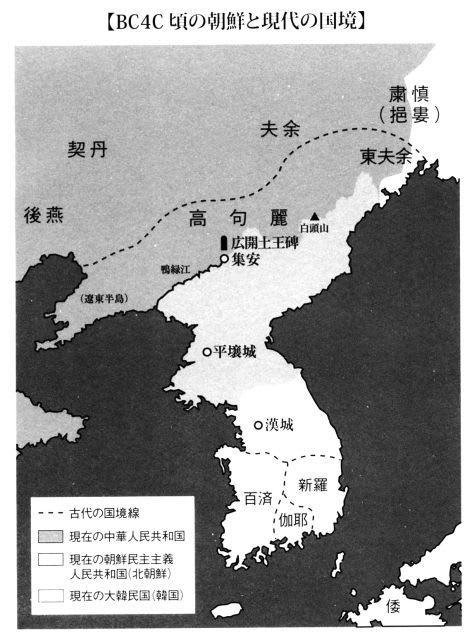今朝の「みのもんたの朝ズバッ!」で、エキスポランドで起こったジェットコースターによる死傷事故を取り上げていた。そこでの今日のゲスト、失敗学の権威である畑村洋太郎氏のコメントが新鮮に思えた。「車軸の金属疲労は例え点検を行っていても分からなかっただろう。問題は基本的な設計にある。どんどん高くなる市場の要求に答えるために知らず知らず危険ゾーンに入っていく。人は見たくないモノを見ないものだ・・・」。
この番組に限らず多くのマスコミは過去、シンドラーエレベーターや回転ドアにおいてメーカーや管理会社の責任を追及していた。エレベーターに自転車にまたがったまま乗ることや、ビジネス施設に幼児が紛れ込むという想定外の行いは不問に付して、一方的に施設側のみを攻めるのはいかがなものか。死という現実の重みの前、被害者の責を問うのは酷ではあるが、こうしたマスコミの攻撃で全国の回転ドアが撤去されたり、世界最大のエレベーターメーカーが駆逐されるがごとき事態は異常ではないかと思ったものだ。
67年に登場したホンダのN360の例がある。当時軽乗用車に求められたのは時速60km。そこに楽々100kmも出てしまう軽の登場だ。スピードの出し過ぎでカーブでの転倒事故が多発した。そして、パッシングが起き、優秀な車が市場から消えた。
飛行機においては、61年、アメリカの資金援助を受けて配備されたロッキードのF-104の例がある。本国アメリカでわずか2年で退役したこの機は敗戦国に廻され、西ドイツではあまりの墜落事故の多さから「空飛ぶ棺桶」と揶揄された程だが、何とかマニュアルの整備で長く空防の任にあたった。
かつて、建設省は入居者の高齢化から全国の低層階公団住宅全てにエレベーターを、1基1,000万以下で設置して欲しいとコンペを実施したところ、国内メーカーの拒否で計画は頓挫した。
エレベーター文化の長いヨーロッパでは今だに手動式ドアのモノが現役で働いている。一方、自動制御に多額の費用を掛けて、エレベーターは高額なものとなっている。要はモノの上げ下げ、止まった時に床と多少の段差があってもよいと割り切れば、どれほどコストが下がることか。現に先の建設省のコンペでは海外のエレベーター装置を導入して900万で販売できるモノを試作したメーカーがあったと聞く。
乗り物はそもそも危険なモノだ。そのことを忘れて「安全で当たり前」という心の持ち方に問題があるのでは。死傷事故を繰り返さない為にはどうすればよいか、要は失敗に何を学ぶかだ。