三井記念美術館で11月末まで開催中の「茶人のまなざし~森川如春庵の世界」に
行ってきました。
この森川如春庵という人物、16歳にして本阿弥光悦の黒楽茶碗「時雨」を入手、
さらに19歳で光悦の赤楽茶碗「乙御前」も所持と、茶人としても目利きとしても
恐るべき経歴を誇る超大物数寄者の一人。
しかし世を去るにあたり、そのコレクションの多くを寄贈した名古屋市に対して
一般に公開するのを禁じたためか、広く世評に上ることがありませんでした。
かくいう私も、3月ごろに見た「新日曜美術館」と「芸術新潮」3月号を読んで
この大人物を知ったわけですが。
まあコレクションもすごいけど、人物もまたスゴイんですよ。
名古屋の大地主の家に生まれてから92歳で亡くなるまで、一生働くことなく
茶と数寄の道を追求したというんですから、まさに趣味人の鑑。
人間だれしもこういう人生を夢見るものですが、それを実際にやってしまって
なおかつ周囲の尊敬を集めていたというのが、スゴイところ。
晩年には勲五等にも叙されてるというのが、さらに輪をかけてスゴイところです。
さて、この門外不出のコレクションが、約40年の沈黙を破って世に現われたのが
今回の「森川如春庵の世界」展です。
3月に名古屋博物館で開催された内容からやや点数は減ったものの、一目見たいと
切望していた「乙御前」をはじめとする名品たちが、いよいよ東京にお目見え。
さらに国博の「対決展」でも拝見した「時雨」に加え、瀬戸黒茶碗の最高峰である
「小原女」も登場、さらに特別ゲストとして三井が所蔵する国宝の「卯花墻」まで
見られるという、まさに国焼茶碗の頂上決戦という様相です。
茶碗好きがこれを見ずして、何を見る!といわんばかりの内容じゃありませんか。
さて、念願かなってついに対面した「乙御前」のすばらしいこと!
朱色とも橙色とも見える赤く柔らかな肌の色、全身にまとった貫入の優雅さ。
一方で見込をのぞくと、高台が碗の底を突き上げんばかりに盛り上げており、
まるで地の底から山が盛り上がってくるかのようなダイナミックさを感じます。
器形は見る角度によって、丸く見えたり扁平に見えたりと変化に富んでおり、
いつまで見ても飽きることがありません。
とりわけ強烈なのが口づくり。ゆったりしているように見えて実は強い造型意識に
統制されている、緊張感に満ちた形をしています。

奔放に弾け飛びそうな創造力と、それを茶碗の形に収めようという自制の力。
そのギリギリの釣りあいが、「乙御前」の姿に結実していると感じました。
今まで見た光悦茶碗では、「時雨」「雨雲」を超えて最高と思える一作。
ずっと期待して対面を待ち続けた甲斐がありました。
この「乙御前」の斜め向かいに置かれていたのが、瀬戸黒茶碗「小原女」。
瀬戸黒そのものが希少な碗で、私もこれが瀬戸黒初体験でした。
この「小原女」も、今は人手に渡っていますが、元は如春庵愛蔵の品。

どてっとした形に見えて、実はかなり薄づくり。そのアンバランスさがいい。
その大きさと見込の深さ、黒々としているのに不思議と親しみを感じる色合い、
硬そうにも柔らかそうにも見える器形など、見どころの尽きない茶碗でした。
黒楽の「時雨」は、次の間に展示。

「対決展」のときよりじっくり見られたおかげで、高台まわりから立ち上がる
黒釉の筆づかい、「乙御前」と同じように角度によって変わるシルエットなど
新たな見どころをいくつも発見できました。
ある意味「雨雲」以上にストイックさが際立つ茶碗です。
さらに角を曲がると、他の展示から離れて「卯花墻」が。
ぽつんと置かれているのが災いして、目もくれず通り過ぎるお客さんの姿を
何人も見ました。おいおい、会場唯一の国宝だってば。

でもこの「卯花墻」、やや小ぶりなうえに一見すると目立たないんですよね。
よく見れば織部的に豪快な作行きなんだけど、厚がけの志野釉のおかげもあって
やはり全体的にはぽってりと穏やかな雰囲気。光悦碗とは対極ですな。
こういう人好きのする碗は、見るより使ってこそ真価を発揮する気がします。
それにしても、この森川如春庵といい、いま畠山記念館で取り上げられている
益田鈍翁といい、やはり尋常な眼力の持ち主ではありません。
凡人が勘違いで自分の非凡さを誇示するのとは次元の違う「感性の鍛えられ方」に
つくづく唸らされました。
ここまでいかないと、人を感動させる「数寄」の域には到達できないんだなぁ。
実業家としても活躍した益田鈍翁と違って、純粋に「好き=数寄」を極めることで
名声を得た如春庵こそ、究極の数寄者なのかもしれません。
茶碗以外にも棗や香合などの茶道具、茶道具との取り合わせで使われた書画など
一級の美術品が多数展示されていました。特に篠井秀次の真塗中次は必見です。
行ってきました。
この森川如春庵という人物、16歳にして本阿弥光悦の黒楽茶碗「時雨」を入手、
さらに19歳で光悦の赤楽茶碗「乙御前」も所持と、茶人としても目利きとしても
恐るべき経歴を誇る超大物数寄者の一人。
しかし世を去るにあたり、そのコレクションの多くを寄贈した名古屋市に対して
一般に公開するのを禁じたためか、広く世評に上ることがありませんでした。
かくいう私も、3月ごろに見た「新日曜美術館」と「芸術新潮」3月号を読んで
この大人物を知ったわけですが。
まあコレクションもすごいけど、人物もまたスゴイんですよ。
名古屋の大地主の家に生まれてから92歳で亡くなるまで、一生働くことなく
茶と数寄の道を追求したというんですから、まさに趣味人の鑑。
人間だれしもこういう人生を夢見るものですが、それを実際にやってしまって
なおかつ周囲の尊敬を集めていたというのが、スゴイところ。
晩年には勲五等にも叙されてるというのが、さらに輪をかけてスゴイところです。
さて、この門外不出のコレクションが、約40年の沈黙を破って世に現われたのが
今回の「森川如春庵の世界」展です。
3月に名古屋博物館で開催された内容からやや点数は減ったものの、一目見たいと
切望していた「乙御前」をはじめとする名品たちが、いよいよ東京にお目見え。
さらに国博の「対決展」でも拝見した「時雨」に加え、瀬戸黒茶碗の最高峰である
「小原女」も登場、さらに特別ゲストとして三井が所蔵する国宝の「卯花墻」まで
見られるという、まさに国焼茶碗の頂上決戦という様相です。
茶碗好きがこれを見ずして、何を見る!といわんばかりの内容じゃありませんか。
さて、念願かなってついに対面した「乙御前」のすばらしいこと!
朱色とも橙色とも見える赤く柔らかな肌の色、全身にまとった貫入の優雅さ。
一方で見込をのぞくと、高台が碗の底を突き上げんばかりに盛り上げており、
まるで地の底から山が盛り上がってくるかのようなダイナミックさを感じます。
器形は見る角度によって、丸く見えたり扁平に見えたりと変化に富んでおり、
いつまで見ても飽きることがありません。
とりわけ強烈なのが口づくり。ゆったりしているように見えて実は強い造型意識に
統制されている、緊張感に満ちた形をしています。

奔放に弾け飛びそうな創造力と、それを茶碗の形に収めようという自制の力。
そのギリギリの釣りあいが、「乙御前」の姿に結実していると感じました。
今まで見た光悦茶碗では、「時雨」「雨雲」を超えて最高と思える一作。
ずっと期待して対面を待ち続けた甲斐がありました。
この「乙御前」の斜め向かいに置かれていたのが、瀬戸黒茶碗「小原女」。
瀬戸黒そのものが希少な碗で、私もこれが瀬戸黒初体験でした。
この「小原女」も、今は人手に渡っていますが、元は如春庵愛蔵の品。

どてっとした形に見えて、実はかなり薄づくり。そのアンバランスさがいい。
その大きさと見込の深さ、黒々としているのに不思議と親しみを感じる色合い、
硬そうにも柔らかそうにも見える器形など、見どころの尽きない茶碗でした。
黒楽の「時雨」は、次の間に展示。

「対決展」のときよりじっくり見られたおかげで、高台まわりから立ち上がる
黒釉の筆づかい、「乙御前」と同じように角度によって変わるシルエットなど
新たな見どころをいくつも発見できました。
ある意味「雨雲」以上にストイックさが際立つ茶碗です。
さらに角を曲がると、他の展示から離れて「卯花墻」が。
ぽつんと置かれているのが災いして、目もくれず通り過ぎるお客さんの姿を
何人も見ました。おいおい、会場唯一の国宝だってば。

でもこの「卯花墻」、やや小ぶりなうえに一見すると目立たないんですよね。
よく見れば織部的に豪快な作行きなんだけど、厚がけの志野釉のおかげもあって
やはり全体的にはぽってりと穏やかな雰囲気。光悦碗とは対極ですな。
こういう人好きのする碗は、見るより使ってこそ真価を発揮する気がします。
それにしても、この森川如春庵といい、いま畠山記念館で取り上げられている
益田鈍翁といい、やはり尋常な眼力の持ち主ではありません。
凡人が勘違いで自分の非凡さを誇示するのとは次元の違う「感性の鍛えられ方」に
つくづく唸らされました。
ここまでいかないと、人を感動させる「数寄」の域には到達できないんだなぁ。
実業家としても活躍した益田鈍翁と違って、純粋に「好き=数寄」を極めることで
名声を得た如春庵こそ、究極の数寄者なのかもしれません。
茶碗以外にも棗や香合などの茶道具、茶道具との取り合わせで使われた書画など
一級の美術品が多数展示されていました。特に篠井秀次の真塗中次は必見です。










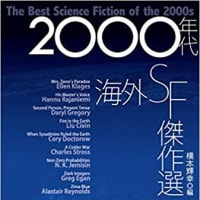


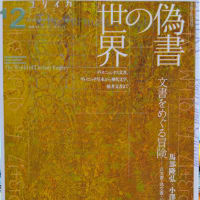












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます