ごきげんよう
公開模試の後、荒木ゼミの最後の補講に行ってきました。
模試の終了時刻の関係で60分以上遅刻してしまい、ほとんど先生の顔を見に行っただけになってしまいました。
一応、5月1日に最後の面談の予定があるんで、会うのは最後という訳ではありませんが。
その後は、火曜クラス向けのK先生の特訓授業を聴講。
先生が今担当している事件を題材に、証拠調べの手続の話をされて興味深かったです。
最後のゼミで、もはや失うものは無いので積極的に発言したりました。
毎回ゼミで一回は質問するようにしてましたが、周りの人を見るともっと貪欲に発言しても良かったかもしれません。少なくとも先生に顔と名前を覚えられるくらいには。
そしたらTOMODACHIも出来たかもね…。
一応、何とか挨拶出来るくらいの方はできましたが、本当はもっと他のロースクールの話とか聞きたかったですね。
なんちゃってストイックキャラじゃなくて、もっとフレンドリーなキャラを演じれば良かったです。キャラ作り失敗したわ。
ゼミ自体について言うと、ゼミ生同士で討論するというより、先生相手に質疑応答を繰り返して、先生の思考方法を通して理解を深めていく感じだったので、それは最初に想像していたものとは違いました。
ただ、私は現役の時から“実務家の思考”という、一種の職人的感覚を身につけることをテーマに勉強していたので、常に実務を意識した先生の指導は、私に良く合っていたと思います。
ゼミを受けるまで、条文を一つずつ押さえていくことと、判例で条文の具体的な使い方を勉強するいう発想も無かったので、その点も大きいです。
あとはゼミで学んだことを本試験で出すだけですね。
最後の刑事系の結果は以下の通り
22年刑法 65点(67点)
22年刑訴法 40点(43点)
(※左が先生の添削の点数で、括弧内が研究所の一般採点者の点数です。)
刑訴は、秘密録音とおとりの事実評価が甘かったのと、伝聞まだ混乱している箇所があったのが原因でしょうか。伝聞はもう少し詰めないと。
刑法については、自分で納得のいくパフォーマンスができましたし、それを評価してもらえたので、満足しています。模試に本試験と、この感覚でいきたいです。
両科目とも先生の採点と一般採点が一致して、最後はきれいに締まりました。
ファイナル模試の方は色々と書きたいことがありますが、明日も早いので、2日目終了後に一緒に書こうと思います。
公開模試の後、荒木ゼミの最後の補講に行ってきました。
模試の終了時刻の関係で60分以上遅刻してしまい、ほとんど先生の顔を見に行っただけになってしまいました。
一応、5月1日に最後の面談の予定があるんで、会うのは最後という訳ではありませんが。
その後は、火曜クラス向けのK先生の特訓授業を聴講。
先生が今担当している事件を題材に、証拠調べの手続の話をされて興味深かったです。
最後のゼミで、もはや失うものは無いので積極的に発言したりました。
毎回ゼミで一回は質問するようにしてましたが、周りの人を見るともっと貪欲に発言しても良かったかもしれません。少なくとも先生に顔と名前を覚えられるくらいには。
そしたらTOMODACHIも出来たかもね…。
一応、何とか挨拶出来るくらいの方はできましたが、本当はもっと他のロースクールの話とか聞きたかったですね。
なんちゃってストイックキャラじゃなくて、もっとフレンドリーなキャラを演じれば良かったです。キャラ作り失敗したわ。
ゼミ自体について言うと、ゼミ生同士で討論するというより、先生相手に質疑応答を繰り返して、先生の思考方法を通して理解を深めていく感じだったので、それは最初に想像していたものとは違いました。
ただ、私は現役の時から“実務家の思考”という、一種の職人的感覚を身につけることをテーマに勉強していたので、常に実務を意識した先生の指導は、私に良く合っていたと思います。
ゼミを受けるまで、条文を一つずつ押さえていくことと、判例で条文の具体的な使い方を勉強するいう発想も無かったので、その点も大きいです。
あとはゼミで学んだことを本試験で出すだけですね。
最後の刑事系の結果は以下の通り
22年刑法 65点(67点)
22年刑訴法 40点(43点)
(※左が先生の添削の点数で、括弧内が研究所の一般採点者の点数です。)
刑訴は、秘密録音とおとりの事実評価が甘かったのと、伝聞まだ混乱している箇所があったのが原因でしょうか。伝聞はもう少し詰めないと。
刑法については、自分で納得のいくパフォーマンスができましたし、それを評価してもらえたので、満足しています。模試に本試験と、この感覚でいきたいです。
両科目とも先生の採点と一般採点が一致して、最後はきれいに締まりました。
ファイナル模試の方は色々と書きたいことがありますが、明日も早いので、2日目終了後に一緒に書こうと思います。













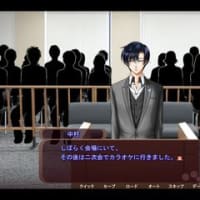

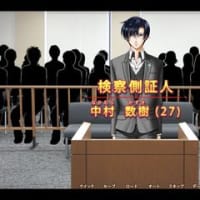


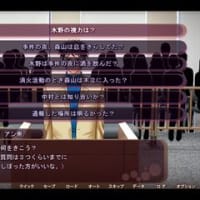

荒木ゼミもついに終わりましたね。
最終日はなぜか質問が非常に少なかったですね…。
その中で質問された方のうちの一人が帝王さんだったんですね。
自分もぼっち浪人なんで、このゼミを通じて周囲の方とホントはもっとうちとけた話がしたかったけど、結局あまり出来なかったことが多少心残りです。
どこかでまたご挨拶できる機会がありましたら、よろしくお願いします。
お互い頑張りましょう。
荒木ゼミお疲れ様でした。
あまりお近付きにはなれませんでしたが、私はゼミ生の方々を勝手に同志と考えているので、みんなで良い結果が出せれば良いですね。
合格したら研究所が楽しいイベントを開いてくれるようなので、是非その時にお会いしましょう。
お互いがんばりましょう。
荒木先生の講座が、過去問ゼミを含めて10月から複数開講するようです。
いろいろ考えつつ、検討中です。
ゼミで習ったとこを本番で出し切れなかったのは残念でした。
苦しい戦いになると思いますが、頑張りましょう。
荒木先生だけでなく、あのK谷先生も本格的に基幹講座みたいなものを始めるようですね。
予備校どうしようかな・・・。
来年新試初受験のあるぱかと申します。
都内ロー未修3年目です。突然失礼致します。
昨夜、辰巳で行われた荒木先生のガイダンスに参加してきたのですが、気持ちを引き締められたのと当時に、その内容に大変共感致しました。そして、受講しようか検討していたところ、本ブログにたどり着いたわけです。なかなか、荒木先生の講座はネット上に情報が少なくてですね苦笑
ブログ拝見させて頂きましたが、やはり、学習の仕方から気持ちの持ちようまで、本質を付く指導をされているように感じました。
さて、関連して少々質問させて下さい。先生の講座は、過去問答練(ゼミ)、実務家能力と二つあるようですね。この二つには、過去問を素材に使うという点以外に、どのような違いがあるのでしょうか。もしご存知でしたら、ご教示頂けると幸いです。未修者が受講するには、後者の方が適切なのでしょうか。一応過去問はこの夏にゼミを組んで一通り見たところですが、来年に間に合う気がしません苦笑 こちらの情報がわからない状態でのアドバイスが難しいことは承知ですが、受講の感想でも良いので、お教え頂けると幸いです。昨夜、辰巳の職員の方に軽く説明頂きましたが、受講者の方に直接お話伺うのが一番だと思いまして。ぜひ、よろしくお願い致します。
柏谷先生の合格開眼塾も気になっております。悩みどころです苦笑
荒木先生の講義の情報を求めてこのブログまで遊びに来ていただいたようですが、あまり有益な情報がなくてすみません。
ご質問がありました、過去問答練(ゼミ)と実務家能力なんとかの違いですが、後者は今年から始まった講座であるため、私も何をやるのか分かりません。
お役に立てずに申し訳ないです。
まぁ、あのパンフを見ても正直検討がつきませんよね(笑)
代わりといったらなんですが、去年は過去問答練の解説講義と、ゼミを両方受講していたので、これらについてお話しようかと思います。
まず、過去問答練の解説講義は、荒木先生がチョイスした優秀者の再現答案の分析をメインに、適宜問題文の読み方や、重要論点の解説などがされていました。
時間に限りがあるので、問題の全ての論点を解説する、徹底解析講義のような形ではありません。
ゼミの方は、先生の講義に、受講生からの質問の機会(かなり頻繁に設けてくれます)と議論の時間(ゼミ生同士で議論になることはあまり無かったように思います)、そして先生による答案の添削(今年は毎回の添削でなく輪番になるようですが・・・)と計3回ほどの個人面談が加わります。
講義の内容は上記の過去問答練の解説とほぼ共通といった感じでした。
ゼミといっても、去年で30人近くいたので、自分から積極的に質問・発言しないと、普通の講義とあまり変わらないかもしれません。
あと、ゼミ生は浪人生が多かったですが、現役生の方もいらっしゃったので、ご自分のレベルみたいなものは気になさらないでも良いかと思います。
思いついたところはこんなもんですが、他に何か不明な点がありましたら答えられる範囲でお答えします。
合格開眼塾は第一回の憲法が割安で体験できるらしいので、“柏谷ワールド”を体感しに私も行くかもしれません。
なるほど。だいぶ具体的なイメージが掴めてきました。辰巳の方が、昨夜の時点で12、3人申込済との情報を漏らしていましたので、今年も大人数になりそうです。しかし、講義とゼミ内容が同じようなもので、添削が輪番となると、過去問答練のみを受けて、授業後に質問に行くという形でも、先生のエッセンスを吸収するには十分のように感じます。
実務家能力、謎めいていますね苦笑
昨日のガイダンスで配られた教材の抜粋の感じだと、どうやら、旧試の短めの問題や新試を要約した問題を利用して、主張の双方向性を訓練していくようです。
ストリーミングで、柏谷先生を拝聴しました。エネルギーもあるし、分かりやすいですね。講座はかなりハードなものになるようですが、まだまだ知識の穴がある自分(短答も頑張らなければ・・)にとっては、こちらをペースメーカーに基礎力を確実に上げていくのも有益だと考えました。短答・論文と考えると、コスパもいいかなとw私も、どちらにせよ体験受講の予定です!
色々と有難う御座います。
またコメントさせて頂くかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
もっとも録画されていることもあり、講義中の質問は少なかったですね。もし受講されるのであれば、是非積極的に質問してみてください。
旧試の短めの問題や新試を要約した問題を利用して、主張の双方向性を訓練していくという話を聞くと、ちょっと受けたくなってきました。先生には「散々去年のゼミでやったんだからいらないでしょ?」とか言われそうな気もしますが。
では、“柏谷ワールド”を体験することになりましたら、その時はよろしくお願いします。