今月も歌舞伎座に観劇に行ってきた、今月は珍しく夜の部を観た、昼の部には新作の「木挽町のあだ討ち」があった、これは私も読んだ直木町受賞作の永井沙弥子の同名の小説(こちら)を歌舞伎にしたものだが、今回は見送って夜の部の彦山権現や春興鏡獅子に期待した

座席はいつもの通り3階のA席、場内はほぼ満員だった
+++++
一、彦山権現誓助剱
杉坂墓所
毛谷村
毛谷村六助/幸四郎
お園/ 孝太郎
微塵弾正実は京極内匠/東蔵
一味斎孫弥三松/ 秀乃介
家人佐五平/ 松之助
杣斧右衛門/ /歌昇
お幸/ 歌六
もとは文楽の作品で「敵討ち狂言」、主人公の毛谷村六助は豊前の国の彦山に実在した男
(あらすじ)
豊前国毛谷村に住む六助は、百姓ながらも剣術の達人として知られ、偶然出会った微塵弾正の「親孝行をしたい」という願いを聞き入れ、仕官の剣術の試合にわざと敗れる、さらに、山賊に追われた幼い弥三松を助け、自分の家に連れて帰る、ここまでが「杉坂墓所」
ある日、六助の家に一人の虚無僧が訪ねてくるが、実はその正体は許嫁のお園、お園は父を殺し、さらに妹のお菊も殺した仇の京極内匠を追っている、その仇は六助をだました微塵弾正だったことを知り、六助が仇討ちに向かうまでを描くのが「毛谷村」、真実を知った男が奮起する義太夫狂言の名作との宣伝文句
(感想)
- 見取り狂言なので仕方ないが、毛谷村の終わり方が仇討に向かう決意を固めたところで幕となりすっきりしなかった、仇討を果たすまで見せてくれないと欲求不満となると感じた
- 幸四郎は久しぶりに観たが、演技はまあまあだと思った、あえて言えば、六助が弾正からだまされていたのだと分かった時の怒りの表現がもうちょっと迫力が欲しいと思った

+++++
二、新歌舞伎十八番の内春興鏡獅子
(配役)
小姓弥生、獅子の精/尾上右近
胡蝶の精/亀三郎
胡蝶の精/眞秀
用人関口十太夫/青虎
老女飛鳥井/梅花
家老渋井五左衛門/橘太郎
(あらすじなど)
明治26年3月に歌舞伎座で初演し、後に九世市川團十郎が選定した「新歌舞伎十八番」の一つで所作(舞踊)、獅子が長い毛をぐるぐる振る踊りで、獅子が2体出るのは「連獅子」だが、「鏡獅子」は1体で勇壮に踊る
江戸城の大奥、初春吉例のお鏡曵きが行われ、余興として踊りを所望された小姓弥生が可憐に踊り始める、やがて、弥生が祭壇に祀られた獅子頭を手にすると・・・
豪華な飾りが付いた「獅子の座」、幻想世界に舞台が変わると、胡蝶の精が出て来て踊り、その胡蝶の精に引かれるように獅子の精が登場し踊る、可憐な小姓弥生と、獅子の精のダイナミックな踊りが魅力の格調高く華やかな歌舞伎舞踊の大作というのがうたい文句、能の「石橋(しゃっきょう)」を基にした演目
(感想)
- この日の演目で一番良かった、右近がこんなにきれいな女方だとは知らなかった、顔も仕草もよかったし、着ていた振袖もきれいでよかった、そして前半の踊りも後半の獅子舞もよかった、右近の良さが十分に出ていたと思った
- イヤホンガイドの解説によれば、右近は清元節宗家の家に生まれ七代目清元栄樹太夫を襲名しているが、幼少の頃、名優と謳われた曽祖父の映像『春興鏡獅子』に魅せられ、役者を志望したという、今回はその初舞台となる記念すべき公演とのこと、そのような舞台を観られてよかったと思った
- この演目の右近の務めた小姓弥生と獅子の精の演技は非常にきついものであろう、この演目を演じた九代目団十郎は複数回演じただけでその後は演じず、「きつい演目だ」との言葉を残している、そしてその演技は六代目菊五郎が引き継ぎ、以後、音羽屋の俳優が演じているとのこと、確かに獅子の精の首振りの演技などは体力がないとできないと思う
- 右近が務めた前半の小姓弥生と後半の獅子の精とは物語の脈絡では直接的な関連はないとのこと、前半に獅子頭が出てくるので、後半には獅子の精が出た程度の関連かと思った
- 右近と同時に胡蝶を務めた12歳の眞秀と亀三郎の二人が右近に負けず劣らずの可愛さであった、踊りがうまいと思った
- この公演の音楽は長唄連中であった、イヤホンガイドによれば歌は杵屋勝四郎が、立三味線は杵屋巳太郎が務めていたが3階の私の席からはこの二人の姿が見えず残念だった

+++++
新作歌舞伎
三、無筆の出世(むひつのしゅっせ)
(配役)
中間治助後に松山伊予守治助/松緑
大徳寺同宿日念/ 青虎
大徳寺住職日栄/吉之丞
夏目左内/ 中車
左内妻藤//笑三郎
佐々与左衛門/ 鴈治郎
紺屋職人久蔵/ 坂東亀蔵
伊予守一子治一郎/ 左近
講談/神田松鯉
(あらすじ)
無筆の治助がひたむきな姿勢で文字を学び、中間から出世をしていく物語を丹念に描いた人間国宝の講談師・神田松鯉の講談から生まれる新作歌舞伎
ある夏の日、中間の治助は、主人である旗本の佐々与左衛門から預かった手紙を届けるため大川の渡し船に乗り込むが、慌てた治助が手紙を落としてしまうと、その場に居合わせた老僧から手紙には「この者を斬ってよい」と書いてあると教えられたため主人の元を去り老僧の寺の小僧となる、老僧の碁の対戦相手の夏目左内にその実朴さを気に入られ、左内の元で働くようになる、左内は読み書き算盤、さらには全ての学問一通りを教え、もとより利発で真面目な治助は次々とこれらを習得し、そのうちに左内は勘定奉行添えになり、やがて松山伊予守治助と名乗り勘定奉行まで出世した、与左衛門の元を出奔してから二十数年後、元の主人の与左衛門は伊予守から茶会に招かれると・・・
(感想)
- 神田松鯉の講談も聞きながらの新作歌舞伎であり、その点で貴重な機会であったが、全体としてみるとそんなに面白く感じなかった
- なぜかというと、仇を恩で返すという治助の人間の良さがあまりに現実離れしているからではないかと思った、こういう立派な人はまずいないでしょうから、現実離れして感動の程度も低くなったのではないか

+++++
さて、この日の幕間の食事は三越銀座の地下の弁当売り場で買い求めた地雷也の天むすであった

楽しめた夜だった










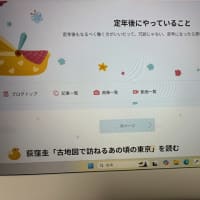









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます