前二回(7/25、8/1)で、「虫証」(人身中に住む「虫」が引き起す病症のこと)の原因と考えられていた「異虫」について、近世の医書から具体的な例を見てきましたが、ここで注意したいことは、「これらは創作ではなく。確信をもって語られた医学的「実話」にほかならない」し、「しかも、その著者たちはいずれも、実力派の先端的医学者であった」(長谷川雅雄ほか『「腹の虫」の研究』名古屋大学出版会 二〇一二 六六頁)ということです。「異虫」という用語は、体内から体外へと排出され人前に姿を現したさまざま奇怪な虫に対して、近世の医者たちが使った呼称です。第1章で学んだ「応声虫」が特殊で稀な病気であったのに比べ、当時人々に広く見られた「虫」の病がありましたが、そのよく知られた方の「虫」を指します。「応声虫」とはこれまで何度もでてきましたが、江戸時代に知られていた、「人が声を出すと、それに反応して体内の「虫」が言葉を発するという、不思議な病気」のことです。さて前二回では、消化器官から出て来るという「異虫」、生殖器官から出て来るという「異虫」、そして「皮下走虫」とさまざまな「異虫」がありましたが、この書物の著者は、近世の実力派医師がこれらの「異虫」をどう扱ったのか、三つ挙げています。今回はここを追ってみます。
≪・・・〔前出の『内科秘録』を書いた本間〕棗軒(ソウケン)は、いわゆる漢蘭折衷派の医師であるが、その経歴は特異である。漢方を原南陽に、蘭方を杉田立卿(りゅうけい)に学んだ後、長崎ではシーボルトに接し、また紀州では華岡青州門で外科術を体得し、後にわが国初の大腿切断術を成功させたという、広い見識と手腕を兼ね備えた臨床家であった、先に引用した箇所に、「和蘭ノ医書ニモ、・・・」とあるように、西洋医学にも通じていた棗軒(ソウケン)が、堂々とかつ詳細に「異虫」の事例を多く挙げて論じている点が重要である。しかも、一方では、皮下を遊走する「異虫」を認めず、それを「心気病」すなわち「脳病」であるとして、近代医学的な理解をしているにもかかわらずである。≫(前掲書 六六頁)
≪・・・皮下を走り回る「虫」が、「小児の啼(なく)がごとくなる」音声を出すという記載は、「応声虫」との関連を考える上で、興味深い問題をはらんでいる。小児の泣き声は、むろん言葉ではないが、言葉に劣らぬ強いメッセージ性を持ったものである。実際、乳幼児が泣き声をあげれば、親たちは強いメッセージを嗅ぎ取り、何らかの対処行動を取るだろう。J・ボウルビィ(J.Bowlby)が、有名なアタッチメント理論のなかで、乳幼児の「微笑」と「泣く行為」は、母親を乳児に接近させて母性行動を誘発する「信号行動」(signal behavior)であり、アタッチメント(愛着)の成立に不可欠なものであると指摘している通りである。皮下を走り回る「虫」が、子供の泣き声のような音声を発するというのは、原初的もしくは未分化なレヴェルの「悲痛な叫び」が信号として、自身または他者に向って発せられているということかもしれないのである。何らかのメッセージを発するこの意思体を、「虫」と見なしているのであり、この点では「応声虫」とも共通していて、両者の連続性を感じさせるものである。「異虫」のなかに、「応声虫」との接点を持つものがあることを留意しておきたい。≫(前掲書 六六~七頁)
≪最後に、「虫」に関して独自の見解を表明している、山下玄門(宥範)の『医事叢談』(一八四九刊)を取り上げておこう。玄門は、「虫」病に対して懐疑的な態度を取っており、第5章で詳しく述べる「疳」(疳の虫)や「労」〔肺結核〕について、それらの病を引き起こすとされていた「虫」(「疳虫」や「労虫」)を認めず、これらの病因は「有形ノ虫ニアラズ」と断じている。しかしながらその一方で、具体的な形状については触れていないものの、「異形ノ虫、四、五種」を「見タ」と明言している(巻之三)。このように玄門は、「疳虫」や「労虫」の存在を否定しているにもかかわらず、「異形ノ虫」を単に受容するだけではなく、実際に見たとまで述べているのである。玄門のように、「虫」病への疑念を持ちながらも、「異虫」は実在すると確信した医家もいたのであり、「異虫」がいかに圧倒的な力で医師たちをとらえていたかを示していよう。(以下略)≫(前掲書 六七頁)
以上を整理してみると、
① 当時の先端的医学者の一人は、「異虫」を取り上げ詳細に論じているが、「皮下走虫」という異虫は認めず、これを近代医学的な「心気病」(「脳病」)と理解を示している。
② 皮下を走り回る「虫」が子供の泣き声のような音声を発するという「皮下走虫」について、この泣き声を何らかのメッセージと捉え直すと、それを発する意思体を「虫」と見なしていることになる。この点では「応声虫」とも共通している。
③ 「疳の虫」や「労」〔肺結核〕の原因を「異虫」にもとめることへ疑念を持ちながらも「異虫」は実在すると確信した医家もいた。
以上から著者が書くように、一つは、「異虫」がいかに圧倒的な力で医師たちをとらえていたかがわかります。しかしもう一つ付け加えておくと、精神的な原因も察せられる虫病(「皮下走虫」や「疳の虫」)については、一部の医者からは、その原因としての「異虫」は否定されていることがわかります。もっと言うと、近世医学において病気は心身一元的な段階から、少しずつ身体と心のそれぞれの領域に分裂しつつあったらしい、ということが言えると思います。














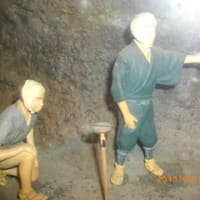




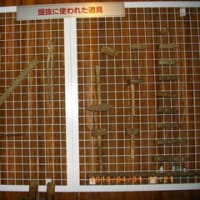
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます