前回(7/31)は、平賀源内が小説『風流志道軒伝』(一七六三)において、主人公深井浅之進が次々と体験してゆくお伽話の国々が担っている意味について考えました。日野龍夫「近世文学に現われた異国像」によると、実はこれらの「お伽話の国々」は「西洋の国々」を代行しており、源内は「西洋の国々」を当時の蘭学者流の説明で描くのではなく、「わざと曖昧な誤解につつまれた形で」提出することによって、当時の民衆の見方を揶揄したのだと説かれていました。「民衆の見方」とは、自分と異なる文化を奇妙だとかお伽話みたい(あるいは馬鹿にするなど)とか言ってそれで済ませてしまう視点のことです。私はこの揶揄を「目糞鼻糞を笑う」というコトワザをとりあげることで、相手を笑い・けなす自分の立場を自覚することの難しさ、相手をけなした点は自分にも当てはまるものだと自覚するうえで、このコトワザが優れていることに触れました。そしてこの難しさを理解するうえで、両者の立場を体験することが手っ取り早いなどと書きました。ここで少し補足しておきたい。それは、互いにちがった立場にあることを理解するに効果的な方法はなにか、という問題です。このためには立場の異なる人物の生き方を追体験すること。もっと言えば、互いの立場を次々と交換できるような追体験が効果的ではないか、と考えます。このような追体験が実際に不可能なことを踏まえると、源内が敢えて小説という領域を選び、主人公の深井浅之進が「仙人から飛行自在の羽扇を授けられ、諸外国を遍歴して見聞を広めるという遍歴譚」(前掲日野論文)の形式であったことの意義がしみじみと伝わってきます。さて、今回は、本論文第四節「平賀源内のいいたかったこと」の最後「源内の体得した思想」を読んでみます。
≪・・・源内がもっともいいたかったことは、作品の最後、浅之進に羽扇を授けた仙人がふたたび登場して長々と述べる説教のなかに要約されている。
・・・唐(中国)の法が皆あしきにはあらず。されども風俗に応じて教えざれば、また却(かえ)って害あり。日本人は小人島を虫のごとく思えば、また〔大人国の〕大人は日本人を見世物にし、穿胸国では全き人(五体満足な人)をかたわと心得、手長・足長の不釣合なること。皆これ土地の風俗なり。天竺の右肩合掌(右肩を脱いで手を合わせる礼法)、日本の小笠原(小笠原流。武家の礼法)、其しうちは替われども、礼といえば皆礼なり。
つまり、文化とは相対的なもので、普遍的な人間性も文化によって現われ方はさまざまであるから、たまたま自分がそのなかに生まれついたというだけの理由で所与の文化を絶対化することなく、海外の異種の文化にも柔軟に接しなければならないという主張であり、それこそが蘭学に親近するなかで源内の体得した思想であった。≫(日野前掲論文 中央公論社版『日本の近世』第一巻 二九六~八頁)
ここで「風俗」が何を意味しているかは明白です。その国を、その国たらしめている地理的・文化的環境(風土)のことだと受けとめますと、異文化に接するときには、自国の「風俗」や「文化」を絶対化しない柔軟な対応が必要だという平賀源内の思想は、当時(十八世紀中頃)日本人を一歩も二歩も賢くさせようとした、たいへん優れた認識だと思います。彼が小説形式を選んで主張しようとした具体的な手続き・方法もまた、異文化理解へのヒントになりそうです。と同時に、このような思想が十八世紀中ごろに誕生しながら、およそ百年後に展開される近代日本の対外政策、特に朝鮮や中国に対して生かされなかったことを残念に思います。この間(十九世紀)における日本人の海外認識のついてもっと研鑚を積みたいところです。














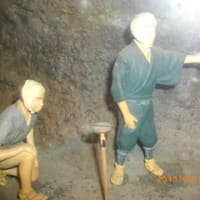




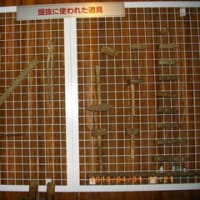
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます