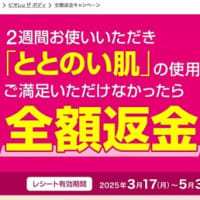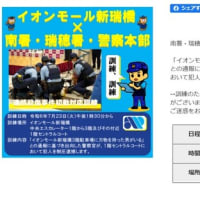受動喫煙が野放し
ビジネスジャーナルの記事より 一部改編
危険な「たばこ」受動喫煙が野放し
…国民のがんリスク助長、海外と比べ異常な対応の遅れ
Business Journal 1月28日(木)8時0分配信
国際オリンピック委員会(IOC)は「スモークフリー五輪」を掲げ、
開催国・開催都市は、禁煙や分煙を義務づける法を制定している。
昨年末までは自民党の議連が中心となって
「罰則規定を盛り込まない受動喫煙防止対策法案」の
骨子がつくられ今国会で提出する、といわれていたからだ。
「タバコ農家は自民党の支持基盤のひとつで、公明支持者も
小規模飲食店の経営者が多い。そこで、罰則規定を盛り込まず、
努力目標を掲げるスローガンのような法案を整備してお茶を濁す
というシナリオだった。本当に政府主導で罰則規定をもうけるとなると、
与党内の『親たばこ派』が総力をあげて潰しにかかるはずだ」(全国紙記者)
実際に潰された前例もある。東京都の舛添要一都知事が
「受動喫煙防止条例」の検討を口にしたところ、
自民党都議団から猛反発をくらって、わずか数カ月で引っ込めた。
条例制定の是非を議論する「東京都受動喫煙防止対策検討会」も
ほとんどの委員が何かしらの法的規制が必要という認識だったが、
わずか数人の反対派が強固に踏ん張って「見送り」となった。
政府が「罰則規定」というタブーに切り込んだのは、
「五輪標準に合わせる」ということが大きい。08年の北京でさえ、法律で罰則規定をもうけ、
公共施設の禁煙を義務化している。
都市環境面において中国より遅れた国とみられたくない、という
安倍官邸の強い意志が感じられる。
東京五輪の「レガシー」
東京五輪の「レガシー」(正の遺産)という観点でみても大きな意義があると
指摘するのは、日本禁煙推進医師歯科医師連盟の会長に1月に就任した、
齊藤麗子・十文字学園女子大学教授・健康管理センター長だ。
「たばこ推進派の人たちは、日本の喫煙率が下がっているにもかかわらず、
肺がん患者が減っていないから因果関係はないなどと主張しますが、
それは吸い始めてからがんで死亡するまで年月がかかるからです。
さらに日本が他の先進国と比較して、際立って受動喫煙防止対策が
遅れているため、非喫煙者が受動喫煙の被害にあっているので、
がんの発症率も減らないでしょう。分煙では非喫煙者を守ることはできません。
他の開催地で規制をしているからではなく、東京五輪を契機に、
罰則規定のある有効性の高い受動喫煙防止対策をレガシーとして、
次世代のがんリスクを減らしていくという発想が必要です」
1964年の東京五輪では、そのようなレガシーによって多くの人々の命が救われたという。
これは日本の水道普及率と、赤痢やコレラ等の水系伝染病の患者数、
そして乳児死亡率は60年頃を境に、それまでは3%ほどあった
乳児死亡率が1%以下まで下がり、伝染病患者数にいたっては急激に減っている。
「東京五輪のレガシーというと新幹線や首都高速などの交通インフラが有名ですが、
実は『水の整備』というきわめて重要なレガシーを残すことで多くの人を救っています。
今度のオリンピックでは、箱物ではなく、目に見えない『受動喫煙のない空気』
というレガシーを子どもたちの世代のために残すべきです」(齊藤教授)
2歳の息子に喫煙をさせた父親が「虐待」で逮捕された事件も記憶に新しいが、
たばこの煙を子どもに吸わせることは「健康や発育を阻害する虐待」ととられることが多い。
「子どもが受動喫煙をすると、気管支炎、中耳炎などの疾患はもちろん、
ADHD(注意欠如・多動症)や集中力不足の影響がみられるという研究があります。
子どもたちが将来、各種のがんが発生するリスクが高まること。
欧米の先進国では常識となっていますが、日本では大きく遅れています」
子どもが同乗している自動車内で親が喫煙することは、米カリフォルニア
、オーストラリア、カナダなどの自治体では「虐待」と
されて明確に法律で禁止されている。しかし、日本では子どもがいる車内で
父親や母親が喫煙しながらハンドルを握る光景も珍しくはない。
「個人の自由」「家庭内の問題」と片づけられてしまっているのだ。
●「美しい空気」の整備
そんな「受動喫煙防止対策後進国」である日本をもっとも象徴する場所が、
「公園」だ。齊藤教授が2013年に全国の政令都市、特別区、都内市町村の
215カ所に調査を依頼し149カ所から回答を得たところによると、
「禁煙表示をしている公園・遊園がある」との回答は1割にとどまり、
子どもの受動喫煙への取り組みが「進んでいない」と
回答をした自治体が過半数を占めたという。
「公園という公共の場所が喫煙場になっていることで、子どもたちが
煙を吸い込むおそれがあるほか、砂場に捨てられた吸い殻に触れてしまう
などの危険があります。東京五輪を契機に
空気のバリアフリー化をすすめていければ、これほど有意義なことはありません」
東京五輪では、外国人観光客への案内のためにピクトグラム(絵文字)が開発され、
空港や鉄道、競技施設に掲示された。このコミュニケーションのバリアフリー化は
、国際社会でも高く評価され、今や世界中に広まっている。
20年へ向けて、新国立競技場などの箱物施設、東京の緑化、自動運転自動車や
水素タウンなどさまざまものがレガシーの候補として名が挙がっている。だが、
その前に年齢、性別、そして人種を問わず、あらゆる人々にかかわる
「美しい空気」を整備することに、まず手をつけるべきではないだろうか。
ビジネスジャーナルの記事より 一部改編
危険な「たばこ」受動喫煙が野放し
…国民のがんリスク助長、海外と比べ異常な対応の遅れ
Business Journal 1月28日(木)8時0分配信
国際オリンピック委員会(IOC)は「スモークフリー五輪」を掲げ、
開催国・開催都市は、禁煙や分煙を義務づける法を制定している。
昨年末までは自民党の議連が中心となって
「罰則規定を盛り込まない受動喫煙防止対策法案」の
骨子がつくられ今国会で提出する、といわれていたからだ。
「タバコ農家は自民党の支持基盤のひとつで、公明支持者も
小規模飲食店の経営者が多い。そこで、罰則規定を盛り込まず、
努力目標を掲げるスローガンのような法案を整備してお茶を濁す
というシナリオだった。本当に政府主導で罰則規定をもうけるとなると、
与党内の『親たばこ派』が総力をあげて潰しにかかるはずだ」(全国紙記者)
実際に潰された前例もある。東京都の舛添要一都知事が
「受動喫煙防止条例」の検討を口にしたところ、
自民党都議団から猛反発をくらって、わずか数カ月で引っ込めた。
条例制定の是非を議論する「東京都受動喫煙防止対策検討会」も
ほとんどの委員が何かしらの法的規制が必要という認識だったが、
わずか数人の反対派が強固に踏ん張って「見送り」となった。
政府が「罰則規定」というタブーに切り込んだのは、
「五輪標準に合わせる」ということが大きい。08年の北京でさえ、法律で罰則規定をもうけ、
公共施設の禁煙を義務化している。
都市環境面において中国より遅れた国とみられたくない、という
安倍官邸の強い意志が感じられる。
東京五輪の「レガシー」
東京五輪の「レガシー」(正の遺産)という観点でみても大きな意義があると
指摘するのは、日本禁煙推進医師歯科医師連盟の会長に1月に就任した、
齊藤麗子・十文字学園女子大学教授・健康管理センター長だ。
「たばこ推進派の人たちは、日本の喫煙率が下がっているにもかかわらず、
肺がん患者が減っていないから因果関係はないなどと主張しますが、
それは吸い始めてからがんで死亡するまで年月がかかるからです。
さらに日本が他の先進国と比較して、際立って受動喫煙防止対策が
遅れているため、非喫煙者が受動喫煙の被害にあっているので、
がんの発症率も減らないでしょう。分煙では非喫煙者を守ることはできません。
他の開催地で規制をしているからではなく、東京五輪を契機に、
罰則規定のある有効性の高い受動喫煙防止対策をレガシーとして、
次世代のがんリスクを減らしていくという発想が必要です」
1964年の東京五輪では、そのようなレガシーによって多くの人々の命が救われたという。
これは日本の水道普及率と、赤痢やコレラ等の水系伝染病の患者数、
そして乳児死亡率は60年頃を境に、それまでは3%ほどあった
乳児死亡率が1%以下まで下がり、伝染病患者数にいたっては急激に減っている。
「東京五輪のレガシーというと新幹線や首都高速などの交通インフラが有名ですが、
実は『水の整備』というきわめて重要なレガシーを残すことで多くの人を救っています。
今度のオリンピックでは、箱物ではなく、目に見えない『受動喫煙のない空気』
というレガシーを子どもたちの世代のために残すべきです」(齊藤教授)
2歳の息子に喫煙をさせた父親が「虐待」で逮捕された事件も記憶に新しいが、
たばこの煙を子どもに吸わせることは「健康や発育を阻害する虐待」ととられることが多い。
「子どもが受動喫煙をすると、気管支炎、中耳炎などの疾患はもちろん、
ADHD(注意欠如・多動症)や集中力不足の影響がみられるという研究があります。
子どもたちが将来、各種のがんが発生するリスクが高まること。
欧米の先進国では常識となっていますが、日本では大きく遅れています」
子どもが同乗している自動車内で親が喫煙することは、米カリフォルニア
、オーストラリア、カナダなどの自治体では「虐待」と
されて明確に法律で禁止されている。しかし、日本では子どもがいる車内で
父親や母親が喫煙しながらハンドルを握る光景も珍しくはない。
「個人の自由」「家庭内の問題」と片づけられてしまっているのだ。
●「美しい空気」の整備
そんな「受動喫煙防止対策後進国」である日本をもっとも象徴する場所が、
「公園」だ。齊藤教授が2013年に全国の政令都市、特別区、都内市町村の
215カ所に調査を依頼し149カ所から回答を得たところによると、
「禁煙表示をしている公園・遊園がある」との回答は1割にとどまり、
子どもの受動喫煙への取り組みが「進んでいない」と
回答をした自治体が過半数を占めたという。
「公園という公共の場所が喫煙場になっていることで、子どもたちが
煙を吸い込むおそれがあるほか、砂場に捨てられた吸い殻に触れてしまう
などの危険があります。東京五輪を契機に
空気のバリアフリー化をすすめていければ、これほど有意義なことはありません」
東京五輪では、外国人観光客への案内のためにピクトグラム(絵文字)が開発され、
空港や鉄道、競技施設に掲示された。このコミュニケーションのバリアフリー化は
、国際社会でも高く評価され、今や世界中に広まっている。
20年へ向けて、新国立競技場などの箱物施設、東京の緑化、自動運転自動車や
水素タウンなどさまざまものがレガシーの候補として名が挙がっている。だが、
その前に年齢、性別、そして人種を問わず、あらゆる人々にかかわる
「美しい空気」を整備することに、まず手をつけるべきではないだろうか。