
2010/05/04 OnAir - 1st. Week
01.Erykah Badu:Window Seat
02.佐野元春 with The Heartland:99ブルース
03.佐野元春:夜のスウィンガー
04.佐野元春:光 (Final Version)
05.The Beatles:Rock and Roll Music
06.佐野元春 and The Hobo King Band:希望 (Live Version)
---------------------------------------------------
■内容の一部を抜粋
・トーク・セッション「ALTERNATIVE 80's」
Motoharu Radio Show 一周年を記念して4週に渡って特別番組を届ける。題してトーク・セッション「ALTERNATIVE 80's」。東京、恵比寿で開催された元春の30周年キック・オフ・イベント「アンジェリーナの日」の中で、元春がキャリアをスタートした'80年代のことを語るトーク・セッションが行われた。ミュージシャンの伊藤銀次、片寄明人、グラフィック・デザイナーの駿東宏、ジャーナリストの長谷川博一の4人との対談を4週に渡って特集する。第四回目は3月27日に行われた長谷川博一とのトーク・セッション。
・3PICKS!
「Motoharu Radio Show」では毎月番組推薦盤3枚のCDをピックアップしている。今月5月の「3PICKS!」はエリカ・バドゥ『New Amerykah Part Two: Return of the Ankh
・エリカ・バドゥ
エリカ・バドゥのニュー・アルバム、タイトルは『New Amerykah Part Two: Return of the Ankh
・ミュージック・クリップ「Window Seat」
エリカ・バドゥの公式サイトで公開されている。
http://www.erykahbadu.com/
・雑誌「This」
元春が1980年代の中盤、雑誌「This」を編集していたときに、そのアソシエイト・ライターとして長谷川さんが参加してくれたのが最初の出会いだったとか。長谷川さんが参加したのは再開した「This」の第二号となる「スタイル・オブ・クール」特集号の頃だそうだ。元春は「This」の全てのコーナーのリード文を自分で書いていたという。ポエトリーと上質な写真、元春が影響を受けてきたものを更に掘り下げた記事を一冊の雑誌化にしようというのが、元春の目的だったとか。限りなく個人雑誌だったと元春。ちょうどニューヨークから帰ってきて新しい音楽と、新しい時代の新しいアーティストの姿勢をファンに見せたいという意気込みがあったそうだ。それまでのシンガーは素敵な曲を作ってよいライヴをするだけでOKだったが、これからはアーティストが表現者なんだということをみんなに示していこうということで、自らライヴを作ったり、自らラジオ番組を制作したり、雑誌の編集をしたり、そういう新しい気があった最初の頃だったと元春。
・99ブルース
雑誌「This」の編集会議があったとある土曜日の夜。次の日、みんな休みだったが、元春には「99ブルース」のビデオ撮影があった。「何にも考えてない」という元春だったが、「監督を信じてるし、何かできると思う」と話していたのが印象に残っていると長谷川さん。
・そば
雑誌「This」の「スタイル・オブ・クール」の撮影で富士五湖へ行ったそうだ。長谷川さんは富士五湖の食堂でそばを食べる元春を見て「佐野元春だ」と思ったという。普通はどんぶりをテーブルに置いて食べるが、元春は背筋を伸ばしどんぶりを手に持って食べていたという。日本男児のそばの食べ方に見えたとか。そばというのは朝昼晩に食べるものではなくて、ちょっと小腹が空いたときに食べるものだと元春。
・そうだろ?
元春のステージ・マナーで特筆すべきは「ここに嫌なやつは一人もいないんだ、そうだろ?」とお客さんの同意を取りにいくことだと長谷川さん。「いかしたビートがなけりゃ意味がないのさ、そうだろ?」とか、そんなことを言う人は今までいなかったんだと。つまりそれだけお客さんと分かち合いたいという気持ちを真正面から出せる人だったということ。元春は一人称が主語のロックンロールのフォーマットが好きだったものの、曲はソウル・ミュージックの「私たちはこう思う」といったふうに、主語を「私たち」にして曲を書いていた節があるという。
・夜のスウィンガー
プロテスト・ソングは世の中の毒素を言い当ててほしいという聴き手側の要求があるものだが、佐野元春は世の中の問題点を指摘するのが目的ではなくて、「ストリート」という別世界を作って、こちらのほうがもっと素敵だぜと提示していたのではないかと長谷川さん。元春は「ストリート」は若い世代の出会いの場という意味合いを持たせていたと話す。
・あの日からろっくんろーるは日本語になった
長谷川さんが考えた元春のコピーは「あの日からろっくんろーるは日本語になった」。それまでもロック的な歌詞はあったけれど、自分の意見や自分の持ってる世界をこんなにヴィヴィッドに書いてくれる人はいなかったと長谷川さん。
・光 (Final Version)
9.11の直後、インターネットで無料ダウンロードした曲のフル・ヴァージョン。即席で作ったヴァージョンは一週間で8万ダウンロードを記録した。アーティストも聴き手も「僕はこう思うんだ」と思ったらそれを形にして誰かと共有してゆく、あるいは共感を積極的に取り付けてゆく、芸術とはこうあるべきだ、コンテンポラリーなアーティストの姿はこうあるべきなんじゃないかなと元春は思ったそうだ。それを実現してくれるインターネットの良さをそのとき実感したのだという。
・『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』
過去の何かを塗り替える力を持った革新性といったものが元春の言う「新しさ」。何か物事を変えてゆく力がないと物足りないのだとか。「自分の内なるレボリューションを常に活性化させてゆくというかっこうですね」と元春。元春がデビューする前のロック音楽は下半身より上半身に訴えかける曲が多かった。元春が表現したかったのは「フォーク&ロック」。いわゆる知性と肉体性がほどよく共存している音楽。そうした音楽を作りたいという要求がアルバム『SOMEDAY』であったり、特に『VISITORS』であったり、その方法論が上手くまとめられた『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』であったりした。元春が個人的に追及していたのはそれだった。『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』は怒りの感情をポップな形にしてロックンロール化したいという目論見があったそうだ。
・Rock and Roll Music
元春がライヴで演奏する曲のテンポはすばしっこいと長谷川さん。オン・ビートで、スピーディーで、さっさと大事なことを言ってしまいたいという感じがある。「言いたいことがたくさんあるので言葉を詰めてしまうという傾向があるんですよね。ゆったりとできないというかね」と元春。言いたい事を書きなぐって、そのエッセンスを三分間に濃縮するのが元春のスタイルなんだとか。
・希望 (Live Version)
1990年代の元春はステージ上で温和な表情になり笑うようになったと長谷川さん。こんなご時勢で自分の音楽を選んで見に来てる人たちに感謝とか敬意を含めてにこやかな表情と演奏自体を楽しもうという態度が見えると。それまでの1980年代はすごいものを見せてやるという引き締まった気持ちがあり、その雰囲気は会場にもあったんだと。今自分がやってることを楽しめるようになったのは『The Barn』のコンサートからだと元春。それは仲間のホーボーキングバンドがもたらしてくれた余裕だと思うそうだ。ホーボーキングバンドの絆が更に深まったライヴ・ツアーだったと元春。アルバム『The Sun』はホーボーキングバンドと一緒に作った二枚目のアルバム。「希望」は元春の生活の変化、経験の蓄積が出た曲。元春の中のフォーキーな部分が出た曲なんだとか。元春は「アノニマス(無名性)」を素敵なものだと捉えいて、そこには本当の真実や本当の輝きがあるかもしれないと常に思っているそうだ。主人公を「アノニマス(無名の誰か)」に据えて意識して書いた曲を自分の中のフォーキーなジャンルと呼んでいるとか。「君を連れてゆく」、「すべてうまくはいかなくても」、「希望」がそんな曲だという。
・セルフ・カヴァー・アルバム
元春の過去の楽曲一曲、一曲にゲストをフィーチャーして制作する予定だとか。シンガーが変わったり、プレイヤーが変わったりすると楽曲が違う意味を発すると思うと元春。
・番組ウェブサイト
「番組ではウェブサイトを用意しています。是非ご覧になって曲のリクエスト、番組へのメッセージを送ってください。待ってます」と元春。
http://www.moto.co.jp/MRS/












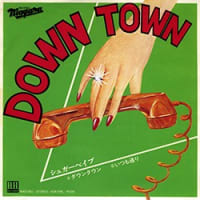


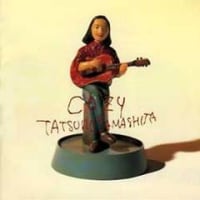
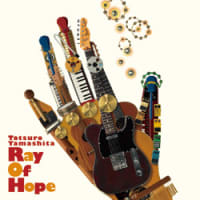

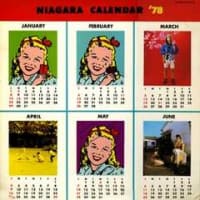

「その胸にサムエ」聞くために(笑)
また寄らせていただきます(^^)
コメントありがとうございます。
杉さんのヤマイダレ教授、初めて聞きました。
コント聞くだけでもアロハ・ブラザースのCDを
買う価値があると思います。(^^)