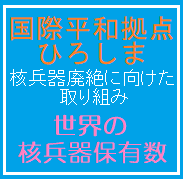再放送も終わってしまったけど。
アンコールでやってくれるかな。
Eテレ ハートネットTV
【特集】変わり始めた精神医療 (3)“オープンダイアローグ”の可能性
”オープンダイアローグ”
もしわたしだったら、あの人数(5~6人?)でさえも対話するってなったら、
委縮してしまいそうだけど・・・
でも興味深い試み。
番組の最後の、斉藤環先生の言葉、長いですが印象に残ったので。
↓↓↓↓↓
ということは・・・
精神医療の現場にもっともっとさくさんの人の手が必要、ってことだよね?
アンコールでやってくれるかな。
Eテレ ハートネットTV
【特集】変わり始めた精神医療 (3)“オープンダイアローグ”の可能性
”オープンダイアローグ”
もしわたしだったら、あの人数(5~6人?)でさえも対話するってなったら、
委縮してしまいそうだけど・・・
でも興味深い試み。
番組の最後の、斉藤環先生の言葉、長いですが印象に残ったので。
| 日本の臨床現場では ネットワーク以前に”ケースワーク”の発想が弱い 患者さんに関係した人に介入して環境を整えたり そういうことは 医師の仕事ではないという認識がまだ主流 まずケースワークの大事さから気づいていってもらう必要がある 疾患と言うのは非常に複合的な現象で もちろん個人の脳とか心の中にも原因があったりするが それを症状に発現させるかどうかには 家族の関係とか職場での人間関係 地域との関連性とかがすごく関連している ところが薬が変えられるのは脳の状態だけ カウンセリングで帰ることができるのは心理状態だけ ケースワークというのは環境調整 その人が暮らしている家庭に介入したりとか 職場に介入したりとか いろんな場面に介入する形で環境を整える そうすると 脳や心に直接タッチしていなくても 関係がよくなるだけで症状が消えることが起こりうる せっかくそういう近道があるのに あえてそれを使わないのはもったいない |
| 私はよく 人間主義の復権と言っているんですけども 人の精神のありようを 脳とか心理に分解するんじゃなくて 丸ごと1個の人間として捉えることの価値が オープンダイアローグを通じて再発見できたような気がしている 1個のバラバラにできない 人間存在の尊厳 自由は権利を 大事にしていくことこそが 治療上 大きな意味を持つ 入院治療とか薬物療法は ある種の保険として必要なもの そこまで否定するつもりは全く無いが ちょっと過剰に使われすぎていると 患者管理と言う名目で 使われ過ぎの傾向は否定できない でなければ「30万人近く入院病床に入っている」ということは起こらない 患者さんの安全とか社会防衛とかいろんな名目はあるでしょうけれども それを理由として 過度に 管理的になりすぎてしまったということが 日本の精神医療の 最大の問題ではないかと感じています |
↓↓↓↓↓
ということは・・・
精神医療の現場にもっともっとさくさんの人の手が必要、ってことだよね?