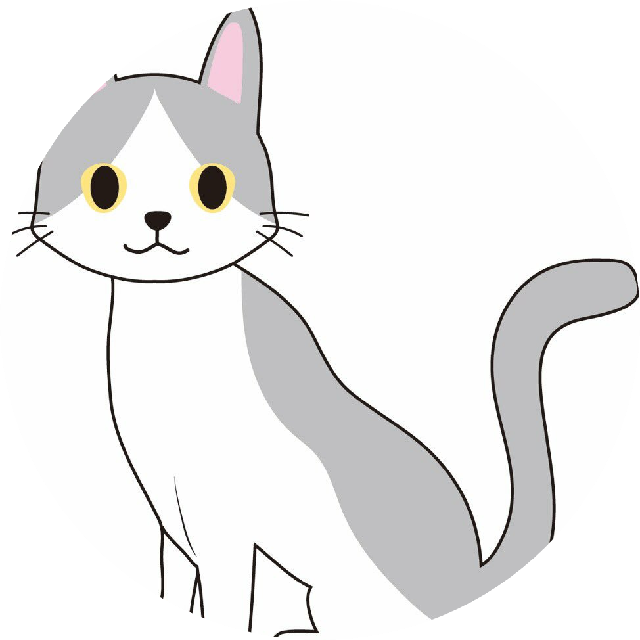私が担当する案件の中には、家庭裁判所での調停案件というものがあります。
典型的には離婚調停とか遺産分割調停ですが、調停に依頼者の方と同席して調停委員と対峙していて、調停委員さんというのは司会者の役割だなと思います。
「調停は話し合い」とはよく言われます。しかし、話し合いをしてきたけれども当事者同士では話し合いがつかなかったので、調停を申立てるわけですから、そう簡単に話し合いがつくわけはありません。
双方の主張がかなり対立している案件が裁判所に持ち込まれるのであって、それをほぐして一定の方向性を出していかなければならない。何かの会の司会とはまた違ったところがあり、”司会”という役割の中でもかなりの難しさです。離婚の調停でも遺産分割の調停でも話が拡散しがちなので、ポイントを絞っていかないといけませんし、なぜ対立しているのかの核心を聞き出さなければならないのです。
日本の調停は「別席調停」といって、当事者が同じテーブルに着くということは基本的にはありません。それぞれ別々に調停委員が話しを聞き、「相手はこう話しているよ」という話しをしていきます。そうすると、うまく要約して相手に伝えなければならない。これに失敗すると、当事者同士が話すのであればうまくいく話も、調停委員が入ると対立をあおるようなことにもなりかねません。
ただ単に相手の話を伝えるだけということでは、伝言ゲームになってしまって意味はないですから、難しいです。調停委員が良いと思う方向性を見定めて、説得するというスタンスが必要になってきます。つまりは有能な司会者が務まる人が調停委員となるべきだし、そうでないと調停は混乱していきます。
実際そういう混乱した調停を見て来ているので、そのような調停委員相手だと当事者が対応するのはかなり困難です。
調停委員は、「普通こうだよ」「法律ではこうだよ」という話しをして説得してくるのですが、それが当事者には正しいかどうかがわからない。
弁護士が同席していれば、おかしければツッコミを入れますから、調停委員も確実なところでしか言わなくなりますが、当事者相手だとそんなことまで言っているのかな、言っていいのかなということまで言っている。まあこれは相談でお聞きするだけで、また聞きなので正確ではないかもしれないけれども、そのように当事者が意味をとってしまったという点では調停委員の説得としては成功していないということにはなってきます。
離婚や遺産分割では必ず家裁の調停を通らなければならないので、調停委員への対応というのは一種の関門です。
調停委員がこちらの見方に同意してくれれば良いですが、そうでない場合も多々あるので。
調停委員は個性的で、裁判官よりも人柄の幅も大きく、弁護士としてもどう持っていくか苦慮することもありますので、やりがいという点ではある意味訴訟(裁判)よりもあるかもしれないなと感じております。
(写真は本文と関係ありません)
典型的には離婚調停とか遺産分割調停ですが、調停に依頼者の方と同席して調停委員と対峙していて、調停委員さんというのは司会者の役割だなと思います。
「調停は話し合い」とはよく言われます。しかし、話し合いをしてきたけれども当事者同士では話し合いがつかなかったので、調停を申立てるわけですから、そう簡単に話し合いがつくわけはありません。
双方の主張がかなり対立している案件が裁判所に持ち込まれるのであって、それをほぐして一定の方向性を出していかなければならない。何かの会の司会とはまた違ったところがあり、”司会”という役割の中でもかなりの難しさです。離婚の調停でも遺産分割の調停でも話が拡散しがちなので、ポイントを絞っていかないといけませんし、なぜ対立しているのかの核心を聞き出さなければならないのです。
日本の調停は「別席調停」といって、当事者が同じテーブルに着くということは基本的にはありません。それぞれ別々に調停委員が話しを聞き、「相手はこう話しているよ」という話しをしていきます。そうすると、うまく要約して相手に伝えなければならない。これに失敗すると、当事者同士が話すのであればうまくいく話も、調停委員が入ると対立をあおるようなことにもなりかねません。
ただ単に相手の話を伝えるだけということでは、伝言ゲームになってしまって意味はないですから、難しいです。調停委員が良いと思う方向性を見定めて、説得するというスタンスが必要になってきます。つまりは有能な司会者が務まる人が調停委員となるべきだし、そうでないと調停は混乱していきます。
実際そういう混乱した調停を見て来ているので、そのような調停委員相手だと当事者が対応するのはかなり困難です。
調停委員は、「普通こうだよ」「法律ではこうだよ」という話しをして説得してくるのですが、それが当事者には正しいかどうかがわからない。
弁護士が同席していれば、おかしければツッコミを入れますから、調停委員も確実なところでしか言わなくなりますが、当事者相手だとそんなことまで言っているのかな、言っていいのかなということまで言っている。まあこれは相談でお聞きするだけで、また聞きなので正確ではないかもしれないけれども、そのように当事者が意味をとってしまったという点では調停委員の説得としては成功していないということにはなってきます。
離婚や遺産分割では必ず家裁の調停を通らなければならないので、調停委員への対応というのは一種の関門です。
調停委員がこちらの見方に同意してくれれば良いですが、そうでない場合も多々あるので。
調停委員は個性的で、裁判官よりも人柄の幅も大きく、弁護士としてもどう持っていくか苦慮することもありますので、やりがいという点ではある意味訴訟(裁判)よりもあるかもしれないなと感じております。
(写真は本文と関係ありません)