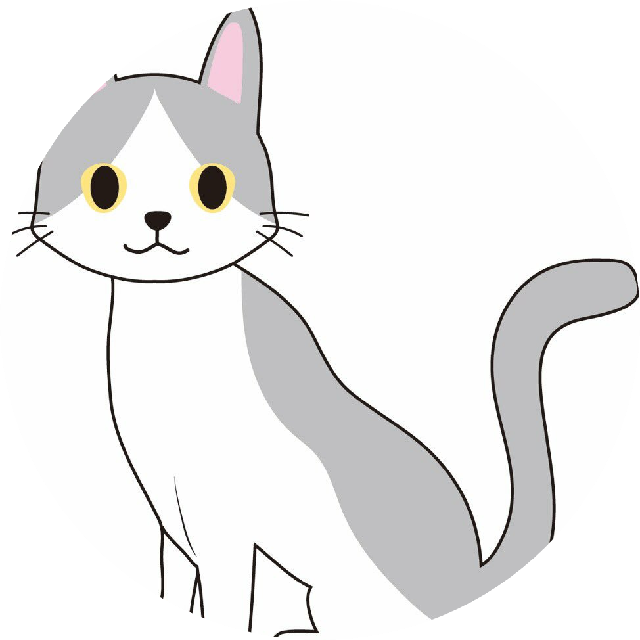平成29年9月に、原賠審は「地方公共団体における不動産の賠償について」を公表した。ここでの原賠審の考え方は次のとおりである。
①公有財産の特徴からすると、民間財産とは賠償における取り扱いを異なるものとすることが適当である。
②公有財産の不動産の賠償については、事故による一定期間の利用阻害により、行政的な利用による利益を享受ないし提供することができなかったことを損害とみなして、一律の基準による賠償を行うことが適当である。
③ただし、利用が阻害されている不動産について、将来的な利用再開の見通しが当面立たず、現時点において、減少した行政的な利用価値の回復が見込まれない場合は、必要かつ合理的な範囲の損害(ただし、「財物損害」の性質上、「全損」を超えることはない)の適切な賠償について、当事者間で円滑な話し合いと合意形成が図られることを期待する。
④不動産の種類や使用目的等に応じた個別の損害により、上記②に基づく一律の基準による賠償が適当ではない損害については、必要かつ合理的な範囲で賠償が認められる。
この原賠審の考え方は、自治体所有の不動産賠償に大きな影響を与えるものである。
すなわち、自治体所有の財物が賠償の対象となることは中間指針(平成23年8月)において定められていたが、具体的な賠償基準・算定方法については定められていなかった。「地方公共団体における不動産の賠償について」は、具体的な賠償基準・算定方法まで提示してはいないが、賠償基準・算定方法を定めるにあたっての考え方を示したと位置づけられる。
出発点は、公有財産は民間所有の財物とは異なる扱いとすべきという認識である(上記①)。その理由としては次のようなものが挙げられている。
ア 公有財産は、行政財産であれ、普通財産であれ、主として公用・公共用に供する行政的な価値を有し、売却等の譲渡を想定しない財産であり、商業的な価値を有する民間財物とは、本質的に異なる性質を有する。
イ 公有財産は、利用可能な状態になれば、住民に対する行政サービスの提供など、避難指示以前と同様に公用・公共用に供されることが期待される。
ウ 地方公共団体には、国の様々な支援がなされていることを踏まえれば、少なくとも利用の再開された公有財産については、民間の被害者と同様の取り扱いとする必要性・合理性があるとまではいえない。
公有財産は、民間財産とは違う考え方で賠償するとして、それではどのように公有財産の不動産の賠償額を算定するのかという点が次に問題となる。
これに応えたのが上記の②であり、「事故による一定期間の利用阻害により、行政的な利用による利益を享受ないし提供することができなかったことを損害とみなす」という原則を原賠審は採用した。
この考え方の背景には、民間財物は、貸付けや売払い等が可能であり、取引可能な評価額を設定しやすい交換価値を有する財産と解することができるが、公共財物の多くを占める行政財産は、地方自治法に基づき貸し付けや売払い等の制限があるため、取引可能な評価額の設定が困難である使用価値のみを有する財産と解することができるとの認識がある(45回原賠審における資料1-2)。
交換価値や使用価値については、45回原賠審における資料1-2でもマルクスを引用して説明している。
“マルクスの「資本論」によれば、「使用価値とは、商品等を使ってそれが役に立つ場合に有する価値」であり、「交換価値とは、商品等を交換する場合に交換される量(通常は価格)によってあらわすことができる価値」であるとの考え方が示されている。”
これだけでは、何のことかわかりにくいが、次の中田委員の発言が理解の助けになると思われる。
【中田委員】 公有財産の特殊性ということですが、先ほど会長がおっしゃいましたように、売却するかしないかということと交換価値の賠償額とは必ずしも直結しないというのはおっしゃるとおりだと思います。その上で、ほかにどういう特殊性があるかと考えてみたんですけれども、今回の案の中でもありますけれども、利用阻害についていうと、「行政的な利用による利益を享受ないし提供することができなかった」ということです。ということは誰の損害かというと、公共団体の損害でもあり地域住民の損害でもあると。そこにいろいろなものが入っているので、民間の財産の場合には自分のためのものである、その損害であるというのとちょっと違いがあるということかなと感じております。