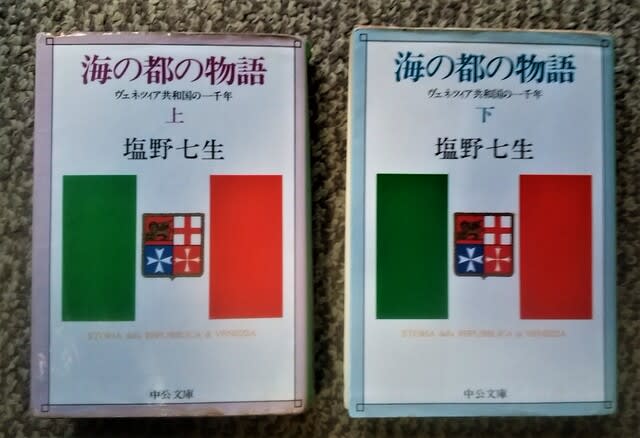<雪のヴェネツィア>
2010年3月10日。
今日はヴェネツィアから特急列車でフィレンツェへ移動する。フィレンツェでは2泊し、今日の午後と明日1日を見学にあてている。
昨夜、夜半、眠りながら窓を打つ突風の音を聞いた。
朝、ホテルをチェック・アウトし、玄関を出て、驚いた。雪!! 積雪だ。
10センチ以上も雪が積もっていた。
雪道をスーツケースを引いて歩く。とりあえず水上バスの「カ・ドーロ」駅へ。水上バスは動いているだろうか??
見上げると、雪はまだ降り続け、無数の雪片が建物の間の空から舞い降りてくる。寒い。
水上バスが乗客を乗せて霧の中から現れ、ほっとした。… しかし安心はできない。フィレンツェ行きの特急列車は、大幅に遅れるかも …。
水上バスのテラスに出て、寒風の吹く中、写真を撮った。


(水上バスから雪の大運河を撮影)
風は冷たく、雪が舞い、手が凍えた。欧米人の乗客は誰も写真を撮ろうとしない。だが、ヴェネツィアの大運河と雪の組合せは、めったにないシャッターチャンスだ。
大運河に臨む「サンタ・ルチア」駅の前も、一面の雪景色だった。

(雪の「サンタ・ルチア」駅前)
ヨーロッパの鉄道駅はホームが横にずらっと並び、自由に入ることができる。改札は車内で行われる。
終着駅「サンタ・ルチア」駅のホームは10列近くもあるだろうか。何本かの列車が雪に濡れて停まっていた。
フィレンツェ、ローマ方面に行く特急はどのホームから出発するのだろう??
電光掲示板の表示に注意した。
フィレンツェ行きはなかなか表示されない。雪のため遅れているのだろう。気になって、ホームを歩き、停車している列車の行き先を確認して回った。
時間になっても、何の表示も出ない。飛行機なら「delay」の表示ぐらい出るところだ。
切符売り場に行って聞くと、もう出発したと言う。ええっ!!
日本で購入した電子チケットを見せると、これは正規料金だから、少しの手数料で1時間後の列車に乗ることができると言う。
旅は、いろいろ起きる。それでも、時間どおりに出発しているなら、何よりだ。最低、今日中にフィレンツェの宿に着ければいい。
1時間後の列車でフィレンツェに向かった。イタリア鉄道の誇る特急は、2時間でフィレンツェに着く。
★ ★ ★
「早春のイタリア紀行」と題しながら、ここまでずっと「ヴェネツィア紀行」だった。今思えば、「ヴェネツィア紀行」としてまとめるべきだった。しかし、書いているなかで、話が広がっていくこともある。
最後に、ヴェネツィアを愛した3人の文学者・作家の文章を紹介して、この拙いヴェネツィア紀行の掉尾としたい。

<饗庭孝男 … 空と水の間に>
「かつてこの町に来たクロード・モネはもっと早く来るべきだと嘆いたという。反映と動き、空と水の間にあるこの「印象派」そのもののような町にいれば、モネならずとも、この美しい幻惑と影深い魅力に心を奪われるに違いない」(『ヨーロッパの四季』東京書籍)。
★
<須賀敦子 … 街自体が「劇場」>
「年月とともに、私は、ヴェネツィアという島=町が、それまで私が訪れたヨーロッパの他のどの都市とも基本的に異質であると思うようになっていた。そして、その原因の一つとして私が確信するようになったのが、この都市自体に組み込まれた演劇性だったのである。ヴェネツィアという島全体が、絶えず興行中の一つの大きな演劇空間に他ならないのだ。16世紀に生きたコルナーロはヴェネツィアに大劇場を設置することを夢見たが、近代にいたって外に向かって成長することをしなくなったヴェネツィアは、自分自身を劇場化し、虚構化してしまったのではないだろうか。サン・マルコ寺院のきらびやかなモザイク、夕陽に輝く潟のさざ波、橋のたもとで囀るようにしゃべる女たち、リアルト橋の上で澱んだ水を眺める若い男女たち、これらはみな世界劇場の舞台装置なのではないか。ヴェネツィアを訪れる観光客は、サンタ・ルチアの終着駅に着いたとたんに、この芝居に組み込まれてしまう。自分たちは見物しているつもりでも、実は彼らはヴェネツィアに見られているのかもしれない。かつて、私がヴェネツィアのほんとうの顔を求めたのは、誤りだった。仮面こそ、この町にふさわしい、ほんとうの顔なのだ」(『ミラノ 霧の風景』白水社から)。
ヴェネツィアはそれ自体が「劇場」だとはよく言われる。
ヴェネツィアが本格的に妖艶な美女に変身していったのは、16世紀以後である。
それまでのヴェネツィアは … やはり、勇壮な海洋都市国家だったと言っていい。フィレンツェなどと違って、共同体としてのまとまり、「意思」があった。
しかし、大航海時代が始まると、地中海貿易では食っていけなくなる。ポルトガルやスペインが、続いてオランダやイギリスが、新大陸へと帆船を乗り出して行ったのだ。
元老院はヴェネツィアの将来について、知恵をしぼった。例えば、技術と技術者を呼び込み、ものづくりをはじめてみた。今も土産物として売られるヴェネツィアン・グラスはその名残りである。織物業などにも取り組んだが、結局、ヨーロッパの他の地方の安い労働力に勝てなかった。有り余る労働力があるわけではない。
ヴェネツィアで培われたヴェネツィアの資源、魅力・売りは何か??
貴族、市民が一体となって取り組んだのが観光業だった。
所有する商船や軍船、それに船乗りとしてやってきた経験・知識・技術を活用して、警護付きの聖地エルサレム巡礼ツアーを企画したのだ。これは相当にヒットした。ヨーロッパ世界も少し裕福になっていたから、異なる世界を見たいという旅への欲求があった。それに加えて、12世紀以来の巡礼願望 …… 教皇庁はエルサレムに巡礼すればこれまでの全ての罪が免罪されるとしていた(それ以後の罪は、また、別ですぞ!! )。イスラム圏も、十字軍ではなく、カネを落としてくれる観光客なら一応の安全は保障してくれる。旅行業の元祖はヴェネツィアなのだ。ツアーに参加するために、多くのヨーロッパ人がヴェネツィアを訪れるようになった。とりわけ多かったのは英国人だったようだ。
当然のことながら、お客さまに、もっと長くヴェネツィアに滞在し、もっとヴェネツィアにおカネを落としてもらいたい。
幸いなことに、教皇庁の免罪条件には「対象」(聖地・聖遺物)ごとのランク付けがあって、免罪の点数が決められていた。現代のミシュランのランク付けのようなものだ。サン・マルコ寺院の聖マルコの遺骸への参拝は相当に点数が高く、参拝すれば何年分かの罪が帳消しになる。自分の死後、天国に近づくのだ。その他にも、ヴェネツィアの街角ごとに建つ古いキリスト教聖堂には、海外雄飛の過程で集められた聖遺物がある。ペテロが処刑されたときの十字架の木材の破片とか、マグダラのマリアのドレスの切れ端とか … 。それらを巡れば、こつこつと免罪点を稼ぐことができる。それに、たいていの聖堂にはルネッサンス以後の巨匠の描いた素晴らしい宗教画もある。
ヴェネツィアは、ヴェネツィアの街巡りの魅力をアピールしたのだ。例えば観光客・巡礼の中で貴族やお金持ちと見るや、ヴェネツィア貴族や豪商たちが私邸を宿舎として提供し、接待し、自ら街をガイドするというふうに、街を挙げて取り組んだ。
建築家を招いて、改めて都市美を造りだしていった。街そのものを華麗にドラマティックに装っていったのだ。
それに加え、種々のカーニバル、仮面舞踏会、カジノ、オペラ、そして高級コールガールも生み出していった。こうしてヴェネツィアは、仮面の似合う、どこか謎めいた、耽美的で、妖艶な美女に変貌していったのだ。(この項は塩野七生『海の都の物語』を参照した)。
★
<饗庭孝男 … 「仮面」の街>
「夜、サン・マルコ広場の、たとえばカフェ『クァードリ』にすわり、陽気に盛り上がるバンドの音楽を聴いているとき、私の脳裡をかすめるのは、ヴェネツィアのこのような歴史である。かつて中世の頃、この壮麗な古代的広場で、遠く黒海沿岸から連れられてきた奴隷市が開かれていたのであった。ビザンチンの禁欲的な書割りの中で、嘆かわしい売買が公然と行われていたのである。この町はローマ教皇の命に背いてキリスト教徒の奴隷も売り、禁じられていたイスラムとの交易にも精を出した。ヴェネツィア自身が「仮面」だったのである。しかも街角によく見かける聖母マリア像への崇拝とそれは決して矛盾することもなく存在していた」(『ヨーロッパの四季』から)。
饗庭孝男氏はここで、現代の価値観でヴェネツィアの歴史を裁いているわけではない。背徳的なものも含んだヴェネツィアという街の耽美的な世界に思いをめぐらせているのだ。
ヴェネツィアにまだ活力があったころ、彼らが運ぶ商品の一つに奴隷もいた。西ヨーロッパ世界では、スラブ系の若い女性の美しさは神秘的だった。
ローマ教皇は、キリスト教徒を奴隷売買してはいけないと言い、また、ヴェネツィアがイスラム教徒と交易することを非難した。
そして、西ヨーロッパ世界に十字軍の結成を呼びかけた。聖地エルサレムを奪還せよ、かの地に行き異教徒を殺し、異教徒から奪い、異教徒を犯せ。そう神は望んでおられる。
啓蒙的な皇帝フリードリッヒ2世は、やはり啓蒙的なスルタンと交渉し握手して、1滴の血も流さずエルサレムを(平和裏に)「奪還」し凱旋した。現代でもできないことをやってのけたのだが、ローマ教皇はフリードリッヒ2世をキリスト教から破門した。なぜ異教徒の血を1滴も流さず帰って来たのかと。
巨悪は、仮面など必要とせず、「正義」を振りかざす。
7つの海に乗り出した英国商人は、部族抗争を繰り返すアフリカに武器を運んで売り、部族戦争の結果生じた大量の捕虜を買い取った。大量の奴隷たちが新大陸へ運ばれて売られ、奴隷たちの過酷な労働によって綿花畑が経営された。彼らの過酷な労働なくして、今のアメリカ合衆国の繁栄はなかったとも言える。
人は誰しも罪深い存在だから「仮面」なしでは生きられない。だが、巨悪は、仮面など必要としない。
★
<須賀敦子 … 冬のヴェネツィアの女たち>
先のブログに、12月の終わりのヴェネツィアの旅のことを書いた。
時差で眠れず早く目が覚め、朝食には早すぎ、小さなホテルの1階の窓から、カーテン越しにホテルの前の小さな広場を眺めていた。すると、高い所に鳩が巣を作る向かいの古い教会の壁の横から、1人、2人と、人が出てきた。あんな所に路地があるんだと初めて気づいた。男も女も一様に急ぎ足で、観光客とは違う雰囲気があった。その光景が不思議に今も脳裏に残っている。
次は、ヴェネツィアを描いた須賀敦子の文章の中でも、いちばん好きな文章である。
「ある年の12月、もう年の暮れも近いころにある会合があって、ヴェネツィアを訪れた。観光客のいない季節のヴェネツィアははじめてだった。参加者は朝8時半に会場に着くように指示されていた。8時すぎ、ホテルを出たところで、私は不思議な光景に出くわした。それはとりわけ底冷えのする朝で、凍りつくような空気の中に濃い霧がしっとりと立ち込め、つい目の前の家具店のショーウィンドウが、霧の中で見え隠れしていた。だが、私を驚かせたのは霧ではなかった。
ホテルと隣の建物の間には、人と人がやっと擦れ違うことのできるくらいの狭い路地があって、それを通り抜けると、大運河の水上バスの船着場に出るはずだった。その路地に入ろうとしたとき、向こうから誰か人が出てきた。一人、また一人、それは、出勤途上の男女らしく、みな、せわしげにホテルの前の広場を過ぎていった。私を驚かせたのは、その一群の中の女たちが、一様に口を閉ざして、視線を石畳に落として、足早に歩いていたことだ。夏の日に耳をくすぐったあの甲高い笑いさざめきは、もう、どこにもなかった。そして、その服装。大半が、黒、あるいは濃い緑色の裾の長いマントを着て、膝までのブーツを履いていた。私は数年前のルチッラ(須賀の女友だち。ヴェネツィア出身)の服装を思い出した。あのとき、少々芝居がかっていると思った彼女の服装は、ヴェネツィアの女たちが、この冷たい冬の気候から身を守るために考え出した武装だったのだ。芝居の季節はとっくに過ぎていたが、彼女たちは、登場人物であることを忘れず、しゃんと背筋をのばして、ひとりひとりが、それぞれ振り当たられた舞台の場所をめざすかのように、黙々と足早に歩き去っていった。それは、なぜか心を打たれる光景だった。冬のヴェネツィアの女たちに魅せられて、私は立ちつくした」(『ミラノ 霧の風景』から)。
★
<塩野七生 … ヴェネツィア共和国の終焉>
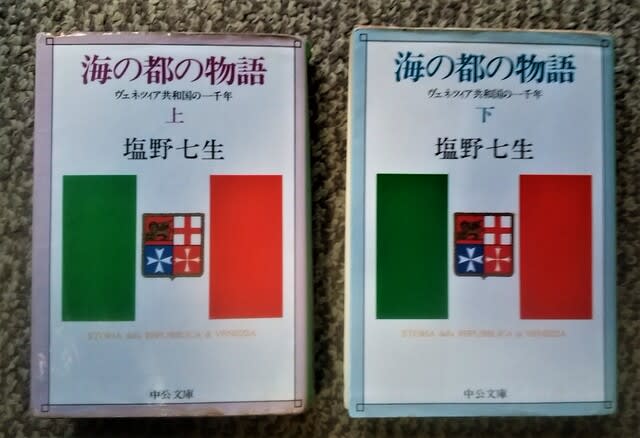
最後に、わが愛するヴェネツィア共和国の終焉についても書いておきたい。
国民一人一人が国家というものを軽んじていると、国家といえども次第に衰えていき、ある日、突然、終焉がやって来る。その結果、自分が「世界市民」などという美しいものになれるわけではない、ということをぜひ知っておきたい。
国力衰えた末期のヴェネツィア共和国は、かつての経済力のみか、貴族も市民も気概を失って、陸軍を維持することができず、非武装・非同盟政策を取っていた。それでも、海賊対策として、海軍は残していた。(海賊はこの時代にも活躍していた。英国海軍の源が海賊だったとはよく言われることである。)。
フランスの若い将軍であったナポレオンが大軍を率いて、ヴェネツィアの本土側領土を横切って敗走するオーストリア軍を追ってやってきた。
だが、「自国内でのオーストリア、フランス両軍の勝手な振舞いに対するに、ヴェネツィアは、言葉しか持っていなかった」。
ヴェネツィアの元老院は、老練な貴族外交官を使者としてナポレオンのもとに送ったが、年下のナポレオンによって鼻で冷淡にあしらわれただけだった。
「彼の説明する非武装中立は、法を尊重してくれる相手とでなくては成り立たない」のだった。
それは、今も、南シナ海において、フィリピンやヴェトナムの海域を力で占拠していく中国の振舞いを見ればわかることだ。かねてからオーストラリアにも浸透して行っている。オバマは言葉で非難しただけだった。軍事費を膨張させる中国に対して、オバマの8年間はひたすら軍事予算を削る8年間だった。中国の防衛線は、台湾の東の太平洋上である。その意思は固い。
ヴェネツィア議会は右往左往しながら、一度は再軍備を決議したのだ。
「だが、遅すぎたのである。金も兵も集めることができても、それを駆使するに足る数の人間が不足していた。100年の平安は、ヴェネツィア共和国から、そのようなことのできる人間を、知らず知らずの間に、駆逐していたのである」。
徴税をし、徴兵をして、さて、どこを防衛線として断固、戦い抜くのか?? もちろん、大軍を相手にこちらから挑む必要はない。ここは守り抜くぞという戦略と態度が大切なのだ。古来、潟がヴェネツィアの自然の城壁だった。茫々と広がる潟の中の本島に閉じこもれば、フランス海軍に対して、ヴェネツィアはまだ死闘を繰り広げることができる。その覚悟を示すことが必要だった。
だが、この時代、ヴェネツィアは本土側にも領土を広げ、元老院議員(貴族)たちは本土に農園をもつ領主になっていた。
どこを死守するのか、ヴェネツィアはその防衛線すら一致点を見いだせなかった。
果敢に決断し、断固とした戦略を立て、全軍を団結させて戦い抜く、肝のすわった層としてのリーダーたちが、この時代のヴェネツィアにはいなかったのだ。
ヴェネツィアが右往左往しているうちに、遂にナポレオンは宣戦布告を発してきた。
慌てふためきただ追い詰められた共和国評議会は降伏する。降伏を決定するため、最後の議会がドゥカーレ宮殿で開かれた。
塩野七生の『海の都の物語』は、そのときの一つのエピソードを紹介している。
「聖マルコの船着場では、抗戦するなら給料なしでも参加すると申し出たにもかかわらず、故国へ帰るように言い渡されたスキアヴォーニたち(ヴェネツィア船に雇われていたアドリア海沿岸の船乗りたち)が、用意された船に乗り始めていた。
会議場では、無抵抗で降伏するヴェネツィア共和国の、自国の市民に対する布告文の是非が評決中であった。その時、時ならぬ銃砲の音がひびいた。議員たちは肝をつぶし、われ先にと逃げようとした。フランス軍の来襲かと思ったのである。数名の議員の、『惨めな振舞いは、いい加減にされたがよかろう!!』の声に、やむをえず自席にもどったものの、鉄砲の音が、去り行く船上に整列したスキアヴォーニたちが、別名をスキアヴォーニの岸とも呼ばれる聖マルコの船着場にひるがえるヴェネツィア共和国の国旗に向かって、最後の礼砲を撃ったものであるとわかるまでは、安心しきれなかったのである。
投票の結果は、賛成512、反対20、不明5である。
ヴェネツィア共和国は、これで死んだ」。
「1797年5月16日、4千のフランス兵、ヴェネツィアに進駐。一度たりとも武装した外国兵を入れたことのなかったヴェネツィア(本島)に上陸したフランス軍は、聖マルコ広場の中央に、『自由、平等、博愛』と記した札を立てることを命じた。フランス占領のはじまりである。
同1797年10月18日、カンポ・フォルミオの条約によって、ヴェネツィア共和国領は、オーストリアとフランスの間で分割され、本土の大部分とギリシアの島々はフランスに、本土の一部とヴェネツィアの町、そして、イストリア、ダルマツィア地方は、オーストリア帝国領下に入る。
翌19日、去るフランス軍に代わって、オーストリア軍進駐。
1805年12月26日、皇帝ナポレオン、ヴぅネツィアを、自分の支配下のイタリア王国の一部に編入。
1814年5月30日、ナポレオンの失脚により、ヴェネツィア、再びオーストリアの占領下に入る。
1866年8月26日、オーストリア、ヴェネツィアをフランスに譲渡。
同1866年10月4日、統一されたイタリアに編入」。(『海の都の物語』から)。
「非武装・非同盟」などというと美しく聞こえるが、いざというとき、それがいかに醜く悲惨なものであるかを、塩野七生のヴェネツィア800年の物語は、最後に教えてくれる。
※ 以上で、ヴェネツィアの話は終わりとします。
 。
。



 で新しい年を迎えましょう。不安→怒り→攻撃
で新しい年を迎えましょう。不安→怒り→攻撃 ではなく、笑顔
ではなく、笑顔 です。
です。 。
。












 」。そもそもは旧制三高のボート部の歌。
」。そもそもは旧制三高のボート部の歌。






 。
。

 。
。 。
。
 。
。 !!
!!