

▲ 今週のみけちゃん
■ 今週のよその猫
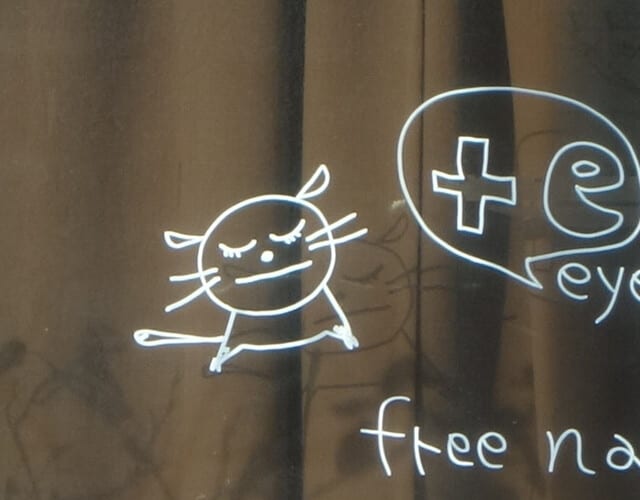
▼ 新しい街でもぶどう記録;第377週

■ 今週の武相境斜面




■ 今週の草木花実





■ 今週の壁画/壁オブジェクト

JR十日市場駅
■ 今週の三昧
■ 今週の聖護院

寒ぶりと聖護院かぶらの押し寿司:『日本海産』天然寒ぶりと『聖護院かぶら』を使用し店内で押し寿司に
■ 今週の和製英語の進化
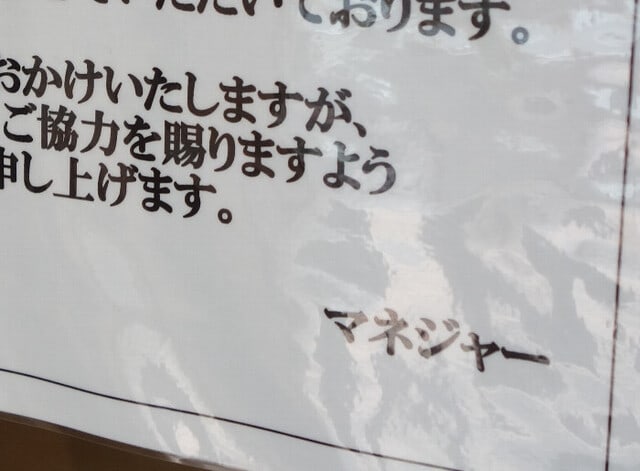
managerは、日本で従来、マネージャーとされてきた。長母音が2つも。 managerの発音は「まにじゃ」。シラブルとして似ているのは、(時代劇で出てくる)「兄じゃ」。「兄じゃ」のあをまに変えれば、発音が似ている。古来のマネージャーが、マネジャーに進化している。
■ 今週の広告

横浜市営バスにて。「原点回帰」らしい。
■ 今週の購書
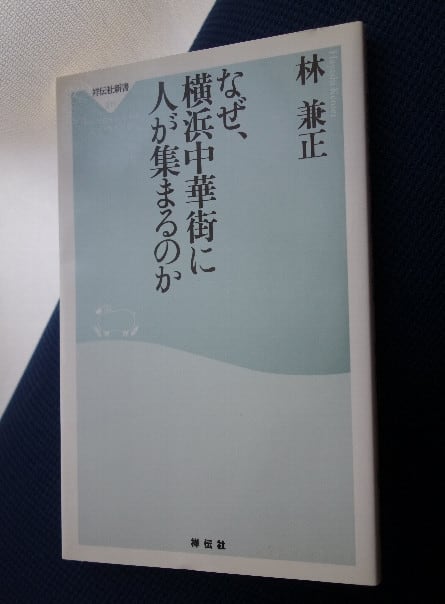
ブックオフで100円。2010年の本。林兼正(はやし けんせい)、『なぜ、横浜中華街に人が集まるのか』(Amazon)。中華街"コミュニティ"代表の中華街事情説明の本。2月の正月、6月の関帝誕生日に祭りをやって中華街"コミュニティ"の結束を高めるという、日本の村社会のような共同体運営を誇る。
中華街の歴史が簡潔に説明されている。「中華街」の呼称は1960年代以降で、それまでは南京町。チャイニーズ当人たちは唐人街と呼んでいた。唐人街は横浜開港とともにできて、横浜開港時最も多い外国人は、欧米人ではなく、チャイニーズの1000人であった。彼らは「買弁」であった。その後の歴史で5万人いた時もあるらしい。現在は、3000人とのこと。
林兼正は、中華街の将来について心を砕き、孫の世代にどのように残して、発展させるかを考えている。これもまた昔の日本の村社会のような共同体運営のようである。むしろ、現在の日本社会の各コミュニティは孫の時代にどうするとか考えてなさそうではないか。逃げ切るばかりを考えている権力者が多いのではないか。
■ 今週のリバイバル:3位、有吉佐和子、『非色』

Amazonの本のトップページをみると、ランキングに有吉佐和子、『非色』(Amazon)があった。1963年の小説だ。何事か?と思った。どうやら、NHKの朝ドラの影響らしい。
有吉佐和子は1959年にロックフェラー財団の金[1]でアメリカに滞在している。滞在したのニューヨーク近くのサラ・ローレンス・カレッジ。学校はともかく、ニューヨークに通い詰めたらしい。そのニューヨークで日本からの戦争花嫁に取材して創作したのが『非色』。おいらは、去年の夏に図書館から借りて読んだ。ブログには書いていない。主人公は黒人兵と結婚し東京で子供を産む。のち、渡米。渡米するときの船の中(三等客室)で複数の戦争花嫁仲間ができる。その船では留学生も出てくるのだが、有吉がかれらを醜く描いているのは興味深かった。なぜなら、渡米した有吉は留学生だったのだから。なお、有吉佐和子の実際の渡米は飛行機であった。登場する戦争花嫁たちの夫は黒人、プエルトリコ人、そしてユダヤ人とwaspがいない。『非色』は現実の戦争花嫁たちの実体験談をもとにして、一般的情勢を組み合わせて話をつくっているので、できすぎ、つくりものくさいと思わなくてはいけないのだが、面白さを感じるのを禁じえなかった。敗戦直後は戦争花嫁たちの金銭・物資調達力に依存していた戦争花嫁の家族たちも黒人の子供を産むと疎遠になっていく話とが、実話なんだろうなと思う。でも、ちゃんと米兵と結婚して渡米するというのが稀だったのではなかろうか。実際生まれた米兵との子供の運命は苛酷なものであったとのこと。
[1] ロックフェラー財団の金=ロックフェラー財団研究員
いずれにしても、小島氏や私のような、あるいは安岡章太郎や庄野潤三氏や有吉佐和子氏のような、ロックフェラー財団研究員とは、いったい何だったのだろうか?これらは後世の批評家や文学史家が、解き明かさなければならない一つの興味深い宿題である。(江藤淳、『自由と禁忌』、1984年、Amazon)
後世の批評家や文学史家が、解き明かさなければならない一つの興味深い宿題への応答として、『日本文学の〈戦後〉と変奏される〈アメリカ〉』(金志映、2019年、Amazon)、文士たちのアメリカ留学 一九五三‐一九六三(斎藤 禎、2018年、Amazon)などがある。
■











