生きている 藤本トシ
おおげさに言えば、数えきれないほど落としては拾い、拾ってはまた落としてしまい、そのたびに部屋中を這いまわり撫ぜまわりながら、わたしの手はようやく一粒の栗を拾った。瞬間、凱歌にも似た太息が唇をついて出る。心に小鳥も海も躍動する朝の風景が開けて、相好をくずした私が、そのさわやかさの中にとける。額は苦闘のなごりの汗を吹いているが、そんなことは苦にならない。
このように物をさがす場合、家人がいればすぐに見てくれるし、今日のように留守であっても、インターホンで頼めば補導員さんがすぐ来て、苦もなく用を足してくれるのだが、しかしそのときには、喜びと感謝の思いがあるだけなのである。ときによると、その思いのなかに、
「こんなことさえ出来なくなってしまったのか」なぞと愚痴が貌を出すことさえあるのだ。
骨が折れたにせよ、暇がかかったにもせよ、小さいものほど始末に困る麻痺ぶかい手が、自力で栗を拾い得たこの感動は、言いようもなく深いものである。そこからは生のあかしが生まれるからだ。
先日、私の部屋に七十になる盲友があそびに来られた。秋季大掃除の前日であった。友はくつろいだ口調で話しはじめたのである。
「うちは、きのう押入れの掃除を全部してしまったぜ。拭き掃除は補導員さんにしてもらったが、夏冬の道具の入れかえは、脚立をつかって三階まで一人でちゃんとすませてしまった。むろん蒲団もやってのけたよ」
私はびっくりしてしまった。三階とは一間の押入れの上にもう一段天井までの押入れがあって、さしあたり不用のものを入れておく倉庫がわりのところである。わたしは問うた。
「あんな高いところから、重い蒲団をどうやって下ろしたり上げたりするんです」と。
「頭さ、頭を使うんだ。まず脚立にのぼって、一ばん上のをそっと頭にのせるとしずかに下りて、それを畳の上におく。このくり返しをやって下ろし終わったら、今度は上げるばんや。
やっぱり一枚頭にのせると、脚立にのぼって、三階に首が出たら、そこでぐっとおじぎをするんだ。すると蒲団がぱっと押入れの中に入るやろ。これを二、三回やったら終わりや」
友は呵々と笑った。おそらくその一瞬、この盲友も生の実感を得たのであろう。誇らかに眉をあげたであろう。足にまだある感覚を、こよない宝と思いながら・・・。
けさは鵙(もず)がたいへんよく鳴く。すばらしい晴であろう。窓をいっぱいに開けてふかぶかと呼吸する。そのとき遠くで池野のお婆ちゃんらしい声がした。久しく会わない人である。確かめようと身をのりだしたとき、過ぎた日のひとこまが胸をよぎった。
「あんたよう、なにまごまごしてるんや・・・」
これが、わたしの耳がとらえた池野のお婆ちゃんの第一声である。
あの日も快晴であった。ひとまわり散歩をして、楓陰亭にゆく坂下まできたとき、私はなんとかして一人で亭まで行ってみようという気をおこしたのである。これまでにも何度そう思ったことかしれない。理由は、内海の風景はもはや見るよしもないが、そこにある四季それぞれの長閑(のどか)さに私は心をひかれていて、人手を借りずに行けたなら、おりおりそこに坐して、松風や笹生の香や、草をけるキチキチバッタなどの中にいたいという、切な望みがあったからだ。
しかしいざとなると、無感覚のうえに数回の手術で、すっかり変形した足には自信がもてず、杖は突くたび両手の中でぐらぐらする頼りなさに、つい気勢をそがれて思いはいつも立消えになっていたのである。
だがその日はちがった。どうしてもという気であった。私は杖を右に向け、左に向けして、恐ろしい崖ぶちを確かめると、一歩を踏みだす地をたたいた。この時である、見知らぬお婆ちゃんが私に声をかけたのは。わたしは心の一部をかくして、
「亭まで行こうと思うのです」
とだけ答えた。
「そうか・・・。わてもあそこへ行くんよ、ちょうどいい、連れになろうや」
お婆ちゃんは、ぽんと私の背をうった。
やがて二人は手に手をとって坂を登りはじめたのである。
意に反したが私は楽しくなっていた。
が、そのうちにお婆ちゃんの歩みは私よりもさらに頼りないのに気がついた。私は組んでいた手に力をこめるとお婆ちゃんの体を支えはじめたのである。よいしょー、よいしょー、坂はだんだん急になり、歩行はいよいよ千鳥になったが、お婆ちゃんのかけ声だけは威勢がよかった。
「ほーら着いたぜ、あとはコンクリートの段を六つ七つ登るだけや」
どうにか目的場所に来て、お婆ちゃんは明るく言ったが、私は当惑してしまった。段がもんだいなのである。もうお婆ちゃんの足は頼れない。杖はなおさら駄目である。どうしようか・・・と思いまどっている耳もとで、声がした。
「早う這わんかい。わてはな、いつも這うて登るのや、らくだぜ」
私は杖をぐっと帯にさしこんだ。突くほうを空にむけて。ふたりは一心に、陽光のなかを、うごめくような蟇(がま)の歩みをつづけたのである。
ようやく亭に腰をおろしたとき、お婆ちゃんはあたりかまわぬ声で笑った。その、けろりとしたひびきが真下の海にころげていった。
このとき私は、この新患者のお婆ちゃんから、わが手で生の歓びをかちとるために、残された可能を、えぐりだすことを学んだのである。










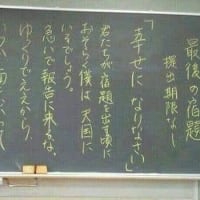

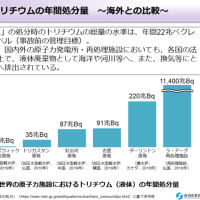
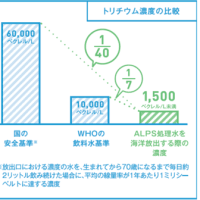
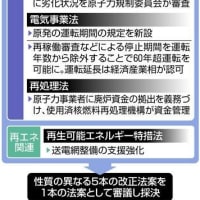


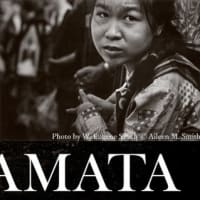








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます