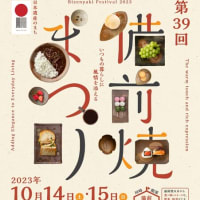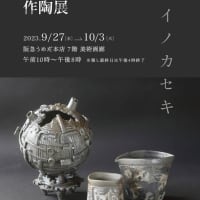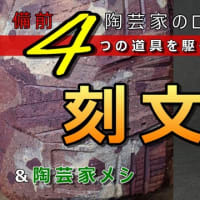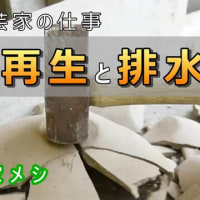過日、『好適環境水』について学ぶ機会に恵まれました。
「何処から書けばいいのかな?」と思えるぐらい将来性ある技術でした。全世界的食料危機、国内食料自給率、過疎、安全性など様々な方面の解決が望まれます。
好適環境水は、要約すると『淡水使用で海水魚を育てる技術』です。
使う水は、淡水にナトリウムやその他ミネラルを溶かし込んだ水です。塩分濃度は海水3.5%に対して、好適環境水は1.5%です。
これで、海水魚が生きる理由は、海水魚の体内塩分濃度が1%程度という点にあります。
海水魚は摂取してしまう濃い塩分を常に体外に排出する努力をしているという。この為、塩分濃度を抑えた好適環境水なら排出に関するストレスがない。つまり魚自体の無理のない環境。しかも、その余った排出エネルギーを個体の成長に使える為に成長が早くなるのも特徴となっています。
淡水があればよいので、井戸水、河川、雨水でも作ることが出来ます。汎用性広し。
メリット
・成長率アップ
・卵から成体までの一貫養殖(通常は稚魚から)
・代替飼料の可能性(ブラックバス、ブルーギルなどの外来魚利用)
・海洋汚染がない
・生産性アップ(機械化による労働コストダウン)
デメリット
・エネルギーコスト(光熱費)
魚種別の成長段階に応じた温度管理が重要とのこと。その為のエネルギーは、温泉、焼却炉などの排熱利用の熱交換でも検討されている。
水を循環させて排水せず再利用して使える為に、人工海水に比べてもコストダウン。更には濾過した有機物やチッソ・リン・カリウムは野菜工場併設で肥料としても使えるなど展開が期待されている。有機肥料栽培が労なくして出来ます。
循環型で工業化したシステムが出来上がれば、食物自給率は格段に上がり。工業国が農業国にもなれるという切り札になりうるだろう。
デメリット解消が今後の問題。
その解決策付きで海外産油国からのオファーもあるそうですが、先生の意向としては「日本発の技術にしたい」との事。
今こそ日本の底力で実現してほしいなぁ。淡水養殖分野(マス・サケ)では、諸外国から遅れている日本。よりはるかに難しい海水魚の完全陸上養殖で世界トップになり得るチャンスですぞ。
今は、トラフグ、ヒラメなど高級魚対象に研究中。市場価格的観点。加えて生産量に対するエサの量も重要で「トラフグ1kg=エサ1.2kg。マグロ1kg=13k」でもあるとか。
個人的には、アマゴをサツキマスにとか、鮭児・サワラ・クロマグロあたりを期待したいな。品種改良により更に美味しく大きなブランド魚が作れるかも。
で、ここからが我々の大事なところ。「百聞は一食にしかず」のトラフグ実食~~。
「一般の方で好適環境水育ちのトラフグを食した人はいませんよ」とのこと。「おぉ~~、 \(◎o◎)/」
さてさて、トラフグコースのはじまり。刺身(テッサ)は柔らかくもあり、途中から鍋でシャブシャブ~っとして頂きました。あとは、鍋、雑炊。開発秘話や研究室のこぼれ話なども伺いつつ……。
肝はエサをコントロールしているので「毒はないだろう」との推測ですが、今回のフグは天然天草産のF1世代なので万全を期して出ませんでした。肝は先生が研究室で解析中。無毒となれば、いずれ肝も食べられるようになります。毒見の機会があればいつでもお伺いしま~~す。人柱候補やる気マンマン。
最後に料理長が挨拶に来られる。いきなり料理長の「水の温度は何度でしたか?」との問いから、料理人と学者の臨時対談が始まりました。非常に興味深い意見交換を目の当たりにしました。実際の市場に出れば更なるご批評もあるでしょうから、商品価値は大事なところ。
我々、ヤキモノ屋は食べて呑んで……先生の役に立ったのかは不明。
8月頃(フグシーズンの始まるちょっと前)から実際に市場に流れるそうです。皆で食べて、この技術を支えて参りましょう!
唐揚げとか美味しいと思います。(食べてないけど)
ちなみに「好適環境水育ちトラフグのお名前募集中」だそうです。
参考:Youtube
その1 ・ その2
「何処から書けばいいのかな?」と思えるぐらい将来性ある技術でした。全世界的食料危機、国内食料自給率、過疎、安全性など様々な方面の解決が望まれます。
好適環境水は、要約すると『淡水使用で海水魚を育てる技術』です。
使う水は、淡水にナトリウムやその他ミネラルを溶かし込んだ水です。塩分濃度は海水3.5%に対して、好適環境水は1.5%です。
これで、海水魚が生きる理由は、海水魚の体内塩分濃度が1%程度という点にあります。
海水魚は摂取してしまう濃い塩分を常に体外に排出する努力をしているという。この為、塩分濃度を抑えた好適環境水なら排出に関するストレスがない。つまり魚自体の無理のない環境。しかも、その余った排出エネルギーを個体の成長に使える為に成長が早くなるのも特徴となっています。
淡水があればよいので、井戸水、河川、雨水でも作ることが出来ます。汎用性広し。
メリット
・成長率アップ
・卵から成体までの一貫養殖(通常は稚魚から)
・代替飼料の可能性(ブラックバス、ブルーギルなどの外来魚利用)
・海洋汚染がない
・生産性アップ(機械化による労働コストダウン)
デメリット
・エネルギーコスト(光熱費)
魚種別の成長段階に応じた温度管理が重要とのこと。その為のエネルギーは、温泉、焼却炉などの排熱利用の熱交換でも検討されている。
水を循環させて排水せず再利用して使える為に、人工海水に比べてもコストダウン。更には濾過した有機物やチッソ・リン・カリウムは野菜工場併設で肥料としても使えるなど展開が期待されている。有機肥料栽培が労なくして出来ます。
循環型で工業化したシステムが出来上がれば、食物自給率は格段に上がり。工業国が農業国にもなれるという切り札になりうるだろう。
デメリット解消が今後の問題。
その解決策付きで海外産油国からのオファーもあるそうですが、先生の意向としては「日本発の技術にしたい」との事。
今こそ日本の底力で実現してほしいなぁ。淡水養殖分野(マス・サケ)では、諸外国から遅れている日本。よりはるかに難しい海水魚の完全陸上養殖で世界トップになり得るチャンスですぞ。
今は、トラフグ、ヒラメなど高級魚対象に研究中。市場価格的観点。加えて生産量に対するエサの量も重要で「トラフグ1kg=エサ1.2kg。マグロ1kg=13k」でもあるとか。
個人的には、アマゴをサツキマスにとか、鮭児・サワラ・クロマグロあたりを期待したいな。品種改良により更に美味しく大きなブランド魚が作れるかも。
で、ここからが我々の大事なところ。「百聞は一食にしかず」のトラフグ実食~~。
「一般の方で好適環境水育ちのトラフグを食した人はいませんよ」とのこと。「おぉ~~、 \(◎o◎)/」
さてさて、トラフグコースのはじまり。刺身(テッサ)は柔らかくもあり、途中から鍋でシャブシャブ~っとして頂きました。あとは、鍋、雑炊。開発秘話や研究室のこぼれ話なども伺いつつ……。
肝はエサをコントロールしているので「毒はないだろう」との推測ですが、今回のフグは天然天草産のF1世代なので万全を期して出ませんでした。肝は先生が研究室で解析中。無毒となれば、いずれ肝も食べられるようになります。毒見の機会があればいつでもお伺いしま~~す。人柱候補やる気マンマン。
最後に料理長が挨拶に来られる。いきなり料理長の「水の温度は何度でしたか?」との問いから、料理人と学者の臨時対談が始まりました。非常に興味深い意見交換を目の当たりにしました。実際の市場に出れば更なるご批評もあるでしょうから、商品価値は大事なところ。
我々、ヤキモノ屋は食べて呑んで……先生の役に立ったのかは不明。
8月頃(フグシーズンの始まるちょっと前)から実際に市場に流れるそうです。皆で食べて、この技術を支えて参りましょう!
唐揚げとか美味しいと思います。(食べてないけど)
ちなみに「好適環境水育ちトラフグのお名前募集中」だそうです。
参考:Youtube
その1 ・ その2