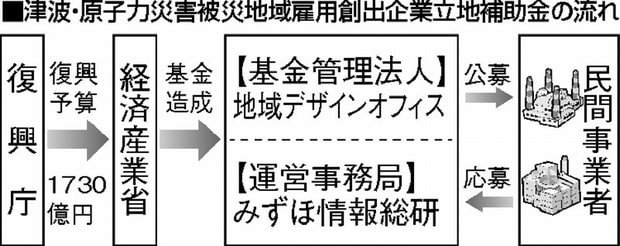岩手日報より転載
復興願うサウンド5千人魅了 ケセンロックフェス「ケセンロックフェスティバル(KRF)’14」(同実行委主催)は19、20日の両日、住田町世田米の種山ケ原イベント広場で開かれた。復活3年目の今回は計18組のアーティストが熱演を繰り広げ、約5千人の観客を魅了した。20日は被災地でのライブ経験もあり、復興への願いが強い「THE BACK HORN」など10組が出演。出店には地元の特産品や海産物が並んだ。両日とも悪天候だったが、地元有志が手作りの温かさで歓迎。情熱のビートに泥まみれになりながら全力で跳び、叫び、熱狂する観客たち。前へと歩む古里を奮い立たせるロックが会場に響き渡った。
KRFでは、復興への願いも多く集まった。19日初出演したロックバンド、サンボマスターのボーカルギター山口隆さん(福島県出身)は東日本大震災後、音楽を通じて力強いメッセージを発信し続けている。音楽やロックの力、東北への思いを聞いた。 東日本大震災後、自分の考え方は大きく変わった。それまで、自分の古里や東北に対して、これだけ自覚的に活動することはなかった。震災があったからこそ、東北の一つ一つのまちに行って「このまちが好きだ」と言いたい。それが、震災で変わったことだ。 でも、被災したことがライブに行く理由ではない。そのまちが好きだから行くということが最初。(ライブ経験がある)宮古も大船渡もとても居心地がよく、もっと長くいたいと感じる魅力がある。好きなまちだから、また来たいし、力になれたらと思う。(談) 【写真(左)=圧巻のパフォーマンスで観客を魅了する「THE BACK HORN」=20日、住田町】 【写真(右)=アーティストの熱演に、盛り上がる観客】 (2014/07/21)
[PR]
|