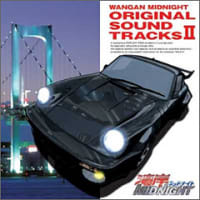ナチス・ドイツのポーランド侵攻以後、ワルシャワの廃墟の中を生き抜いたユダヤ系ポーランド人のピアニスト「ウワディスワフ・シュピルマン」の体験記が、幼少期、ゲットーを体験したユダヤ系映画監督ポランスキーの下、フランス・ドイツ・イギリス・ポーランドの合作で、スクリーンに描かれる!
第二次世界大戦のヨーロッパの歴史に触れるにはもってこいの感動作、と言ってしまえば簡単だが・・
「戦場のピアニスト・シュピルマン」は、食べるものもピアノもないまま、どうやって生き延びたのか?
一瞬たりとも目を覆ったり、顔を背けたり、気持ちを逸らしたりしてはいけない―
紛れもない「歴史」がそこにある・・
【ストーリー】
1940年、ナチス・ドイツがポーランドへ侵攻した翌年、ユダヤ系ポーランド人で、ピアニストとして活躍していたウワディスラフ・シュピルマンは家族と共にゲットーへ移住する。ゲットー内のカフェでピアニストとしてわずかな生活費を稼ぐも42年にはシュピルマン一家を含む大勢のユダヤ人が収容所行きの列車に乗せられるときがやってきた。だがそのとき、一人の男が、列車に乗り込もうとする彼を引き止めた―
しかし彼にも、生きるも地獄、捕まるも地獄の日々が始まるのだった―
【主人公・原作執筆者のウワディスラフ・シュピルマンについて】
ウワディスラフ・シュピルマンは、1911年、ポーランド南部の町、ソスノヴェッツで生まれた。10代の時に、ワルシャワのショパン音楽院で、かのフランツ=リストの弟子だった、ヨゼフ・スミドヴィッチにピアノを学び、後には、アレキサンドル・ミハウォフスキにも師事する。1931年、ドイツのベルリンに留学し、音楽アカデミーで、レオニード・クロイツァーについて、ピアノの腕を磨く。この間、「ヴァイオリン協奏曲」、ピアノ組曲「機械の一生」をはじめ、数多くのピアノ曲、管弦楽、ポピュラーソングを作曲し、母国での人気を高めていった。
1935年、ワルシャワにあるポーランド国営ラジオ局での仕事を得る。1939年9月、放送局がドイツ空軍の爆撃を受けたとき、彼はショパンの夜想曲を生演奏しているときだった。その後の6年間、強制移住や大量殺戮といった戦争の恐怖を体験した末に、彼はドイツ軍将校ヴィルム・ホーゼンフェルトによって奇跡的に命を救われる(ホーゼンフェルトは、1952年、ソ連の戦犯捕虜収容所で死亡した)。
1946年に、戦争中の体験の回想録を「ある都市の死」というタイトルで出版。ただし、戦争直後のポーランドは、ドイツ人がユダヤ系ポーランド人の命を救った内容の本を出版する状況になかったため、彼は、ホーゼンフェルトをオーストリア人として書かざるを得なかった。だがそれでも、ゲットーでの生活と、第二次世界大戦における犠牲者・加害者の姿を公平な筆致で描いたこの真実の記録は、共産党当局により、発禁措置を受ける。
1945年の放送局再開後、再びラジオの生演奏の仕事を始めた彼は、やがて同局の音楽部主任に任命され、欧米での演奏活動も行うようになった。国際的ヴァイオリン奏者ブロニスワフ・ギンベルとのデュオで、世界中で2500回を越えるコンサートを開催。また、作曲活動も続け、彼の書いた歌の多くは、ポーランドの人気スタンダードナンバーとなっている。1950年代には子供向けの歌を数々作曲し、その功績により、1955年、ポーランド作曲家協会から賞を授与された。その後も若い聴衆向けに作曲活動を続けた。
1961年、ソボト国際音楽祭を創設。1964年、ポーランド作曲家アカデミーの会員に選出される。
1998年、息子アンジェイが、父の回想録の草稿を発見。ドイツで出版されるや、同書はたちまち評判となり、海外でも翻訳が出版されるようになった。日本でも2000年に春秋社より刊行された。
ポーランドの著名音楽家として生涯活躍し、2000年7月6日、88歳で亡くなった。
【詳細情報】
監督:ロマン・ポランスキー
原作:ウワディスワフ・シュピルマン
脚本:ロマン・ポランスキー、ロナルド・ハーウッド
音楽:ヴォイチェフ・キラール
上映時間:150分
受賞:カンヌ映画祭「パルムドール」受賞、アカデミー賞「監督賞」「脚本賞」「主演男優賞」受賞、他
【登場人物・キャスト】
ウワディスワフ・シュピルマン:エイドリアン・ブロディ
ヴィルム・ホーゼンフェルト陸軍大尉:トーマス・クレッチマン
シュピルマンの父:フランク・フィンレー
シュピルマンの母:モーリン・リップマン
ヘンリク(シュピルマンの弟):エド・ストッパード
ドロタ:エミリア・フォックス
ミルカ(ドロタの夫):ヴァレンタイン・ペルカ
ヤニナ(ゲットーの外で出会った反ナチス地下組織の一員):ルース・プラット
アンジェイ(ヤニナの夫):ロナン・ヴィバート
マヨレク:ダニエル・カルタジローン
イーツァク・ヘラー(ユダヤ人警察)ロイ・スマイルズ
【使用ピアノ曲】
○夜想曲第20番嬰ハ短調「遺作」 - オープニング
○バラード第1番ト短調作品23 - クライマックス 使用ピアノは「Perzina」
○アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ変ホ長調作品22 - エンディング 「華麗なる大ポロネーズ」の部分をオーケストラ伴奏で演奏している。使用ピアノは「スタインウェイ」。
演奏はいずれもヤーヌシュ・オレイニチャク(ピアノ)、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団(指揮:タデウシュ・ストゥルガラ)。
【コメント・感想】
第二次大戦中のユダヤ人の悲劇やホロコーストに関しては、これまでも本当にたくさんの映画が作られてきました。戦時中のドキュメントだけでなく、実在のドラマは、万が一虚偽の事実があったにしても、オーバーに描かれているとしても、「映画」というカタチで残しておかなくてはならない―現代を生きる私たちの中で、映画人であるならばそれはひとつの「責任」なのだ、と監督や俳優さんがこの映画全体を通して訴えかけてくるような、そんな作品です。
恐らく、加害者であるドイツ人達でさえ、大抵の人は集団流れに身を置くしかなかった・・自分の身を守るために、大きな流れに身を任せていただけなのかもしれないです。
「いつ殺されるか分からない」とか「明日、食べるものがない」とかいう状況は、現代日本にいたら考えること自体できないけれど、それがどれだけ幸せなことであり、悲しいことでもあるか、と思います。観終わった後、率直に「平和な時代、平和な国に生まれたこと」を感謝したい気持ちになりました。
演出面は、今までにない厳かで怖いくらいの静寂と美しさがあり、そこに素晴らしさを感じました。命からがら乗り越えた塀の向こうに永遠と続く瓦礫の街並みに、ひとりよろめきながら歩くシュピルマンの後ろ姿。心にあるのは殆どすべてが絶望でしかなかったはずです。
この映画は、途中からぱたりとセリフがなくなります。ラスト30分前からクライマックスへの展開は、ブラボー!の一言です。私は、主人公に気持ちを重ね、ワルシャワの街を逃げ惑い、つらい逃亡生活を胸が痛くなるのを必死で押さえて見ていました。
やはり最高潮は、敵の将校に見つかってしまうシーンです。ピアニストだというシュピルマンに対して「何か弾け」と言う将校。
私は、とにかく上手く弾けますように、どうか気に入ってもらえますようにと祈っていました。
今の今まで勇気ある行動もとらず、人の善意のおかげではありながらひたすら逃げるばかりだったシュピルマン。逃亡生活の中で、ピアノの鍵盤にも楽譜にもロクに触れていない・・・でも、こうなったからにはやるしかない―そう決心したその演奏には、一瞬の曇りもなく、彼は一心にピアノに向かい、美しい旋律が流れているそこは、まるで別世界のようでした。
戦時中という悲惨な状況でも、綺麗な音を綺麗と感じる心が残されているという不思議な空間―
シュピルマンはあの時、ナチから逃げ隠れる生活の中で身も心もボロボロになっていて、髪も髭も伸ばしっぱなし、ボロボロで歩くことすらままならない。
でも本当の意味で「ピアノに命を捧げて」いたのだと思います。
自分のできる最高のことをしたからこそ、将校は彼を救ったのだと思います。
「逃げのびるだけの主人公の生き方」と表現すれば、これには賛否両論はあるかとは思いますが、監督のポランスキー氏もナチス・ドイツのゲットー生活の経験者であり、生き残りであるからこそ描ける作品であるとも思えます。
生き延びてしまったことへの罪悪感。戦わなかったことへの悔恨。戦争への憎しみ・・・。
そういった物を映画化しようとしたときに、真正面からこのピアニストのエピソードに取り組んだ監督の心意気と、キャストの演技にただただ感動する、そんな映画です。
「芸は身を助ける」というカンタンなことわざでは片付けられない物語だと思います。
第二次世界大戦のヨーロッパの歴史に触れるにはもってこいの感動作、と言ってしまえば簡単だが・・
「戦場のピアニスト・シュピルマン」は、食べるものもピアノもないまま、どうやって生き延びたのか?
一瞬たりとも目を覆ったり、顔を背けたり、気持ちを逸らしたりしてはいけない―
紛れもない「歴史」がそこにある・・
【ストーリー】
1940年、ナチス・ドイツがポーランドへ侵攻した翌年、ユダヤ系ポーランド人で、ピアニストとして活躍していたウワディスラフ・シュピルマンは家族と共にゲットーへ移住する。ゲットー内のカフェでピアニストとしてわずかな生活費を稼ぐも42年にはシュピルマン一家を含む大勢のユダヤ人が収容所行きの列車に乗せられるときがやってきた。だがそのとき、一人の男が、列車に乗り込もうとする彼を引き止めた―
しかし彼にも、生きるも地獄、捕まるも地獄の日々が始まるのだった―
【主人公・原作執筆者のウワディスラフ・シュピルマンについて】
ウワディスラフ・シュピルマンは、1911年、ポーランド南部の町、ソスノヴェッツで生まれた。10代の時に、ワルシャワのショパン音楽院で、かのフランツ=リストの弟子だった、ヨゼフ・スミドヴィッチにピアノを学び、後には、アレキサンドル・ミハウォフスキにも師事する。1931年、ドイツのベルリンに留学し、音楽アカデミーで、レオニード・クロイツァーについて、ピアノの腕を磨く。この間、「ヴァイオリン協奏曲」、ピアノ組曲「機械の一生」をはじめ、数多くのピアノ曲、管弦楽、ポピュラーソングを作曲し、母国での人気を高めていった。
1935年、ワルシャワにあるポーランド国営ラジオ局での仕事を得る。1939年9月、放送局がドイツ空軍の爆撃を受けたとき、彼はショパンの夜想曲を生演奏しているときだった。その後の6年間、強制移住や大量殺戮といった戦争の恐怖を体験した末に、彼はドイツ軍将校ヴィルム・ホーゼンフェルトによって奇跡的に命を救われる(ホーゼンフェルトは、1952年、ソ連の戦犯捕虜収容所で死亡した)。
1946年に、戦争中の体験の回想録を「ある都市の死」というタイトルで出版。ただし、戦争直後のポーランドは、ドイツ人がユダヤ系ポーランド人の命を救った内容の本を出版する状況になかったため、彼は、ホーゼンフェルトをオーストリア人として書かざるを得なかった。だがそれでも、ゲットーでの生活と、第二次世界大戦における犠牲者・加害者の姿を公平な筆致で描いたこの真実の記録は、共産党当局により、発禁措置を受ける。
1945年の放送局再開後、再びラジオの生演奏の仕事を始めた彼は、やがて同局の音楽部主任に任命され、欧米での演奏活動も行うようになった。国際的ヴァイオリン奏者ブロニスワフ・ギンベルとのデュオで、世界中で2500回を越えるコンサートを開催。また、作曲活動も続け、彼の書いた歌の多くは、ポーランドの人気スタンダードナンバーとなっている。1950年代には子供向けの歌を数々作曲し、その功績により、1955年、ポーランド作曲家協会から賞を授与された。その後も若い聴衆向けに作曲活動を続けた。
1961年、ソボト国際音楽祭を創設。1964年、ポーランド作曲家アカデミーの会員に選出される。
1998年、息子アンジェイが、父の回想録の草稿を発見。ドイツで出版されるや、同書はたちまち評判となり、海外でも翻訳が出版されるようになった。日本でも2000年に春秋社より刊行された。
ポーランドの著名音楽家として生涯活躍し、2000年7月6日、88歳で亡くなった。
【詳細情報】
監督:ロマン・ポランスキー
原作:ウワディスワフ・シュピルマン
脚本:ロマン・ポランスキー、ロナルド・ハーウッド
音楽:ヴォイチェフ・キラール
上映時間:150分
受賞:カンヌ映画祭「パルムドール」受賞、アカデミー賞「監督賞」「脚本賞」「主演男優賞」受賞、他
【登場人物・キャスト】
ウワディスワフ・シュピルマン:エイドリアン・ブロディ
ヴィルム・ホーゼンフェルト陸軍大尉:トーマス・クレッチマン
シュピルマンの父:フランク・フィンレー
シュピルマンの母:モーリン・リップマン
ヘンリク(シュピルマンの弟):エド・ストッパード
ドロタ:エミリア・フォックス
ミルカ(ドロタの夫):ヴァレンタイン・ペルカ
ヤニナ(ゲットーの外で出会った反ナチス地下組織の一員):ルース・プラット
アンジェイ(ヤニナの夫):ロナン・ヴィバート
マヨレク:ダニエル・カルタジローン
イーツァク・ヘラー(ユダヤ人警察)ロイ・スマイルズ
【使用ピアノ曲】
○夜想曲第20番嬰ハ短調「遺作」 - オープニング
○バラード第1番ト短調作品23 - クライマックス 使用ピアノは「Perzina」
○アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ変ホ長調作品22 - エンディング 「華麗なる大ポロネーズ」の部分をオーケストラ伴奏で演奏している。使用ピアノは「スタインウェイ」。
演奏はいずれもヤーヌシュ・オレイニチャク(ピアノ)、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団(指揮:タデウシュ・ストゥルガラ)。
【コメント・感想】
第二次大戦中のユダヤ人の悲劇やホロコーストに関しては、これまでも本当にたくさんの映画が作られてきました。戦時中のドキュメントだけでなく、実在のドラマは、万が一虚偽の事実があったにしても、オーバーに描かれているとしても、「映画」というカタチで残しておかなくてはならない―現代を生きる私たちの中で、映画人であるならばそれはひとつの「責任」なのだ、と監督や俳優さんがこの映画全体を通して訴えかけてくるような、そんな作品です。
恐らく、加害者であるドイツ人達でさえ、大抵の人は集団流れに身を置くしかなかった・・自分の身を守るために、大きな流れに身を任せていただけなのかもしれないです。
「いつ殺されるか分からない」とか「明日、食べるものがない」とかいう状況は、現代日本にいたら考えること自体できないけれど、それがどれだけ幸せなことであり、悲しいことでもあるか、と思います。観終わった後、率直に「平和な時代、平和な国に生まれたこと」を感謝したい気持ちになりました。
演出面は、今までにない厳かで怖いくらいの静寂と美しさがあり、そこに素晴らしさを感じました。命からがら乗り越えた塀の向こうに永遠と続く瓦礫の街並みに、ひとりよろめきながら歩くシュピルマンの後ろ姿。心にあるのは殆どすべてが絶望でしかなかったはずです。
この映画は、途中からぱたりとセリフがなくなります。ラスト30分前からクライマックスへの展開は、ブラボー!の一言です。私は、主人公に気持ちを重ね、ワルシャワの街を逃げ惑い、つらい逃亡生活を胸が痛くなるのを必死で押さえて見ていました。
やはり最高潮は、敵の将校に見つかってしまうシーンです。ピアニストだというシュピルマンに対して「何か弾け」と言う将校。
私は、とにかく上手く弾けますように、どうか気に入ってもらえますようにと祈っていました。
今の今まで勇気ある行動もとらず、人の善意のおかげではありながらひたすら逃げるばかりだったシュピルマン。逃亡生活の中で、ピアノの鍵盤にも楽譜にもロクに触れていない・・・でも、こうなったからにはやるしかない―そう決心したその演奏には、一瞬の曇りもなく、彼は一心にピアノに向かい、美しい旋律が流れているそこは、まるで別世界のようでした。
戦時中という悲惨な状況でも、綺麗な音を綺麗と感じる心が残されているという不思議な空間―
シュピルマンはあの時、ナチから逃げ隠れる生活の中で身も心もボロボロになっていて、髪も髭も伸ばしっぱなし、ボロボロで歩くことすらままならない。
でも本当の意味で「ピアノに命を捧げて」いたのだと思います。
自分のできる最高のことをしたからこそ、将校は彼を救ったのだと思います。
「逃げのびるだけの主人公の生き方」と表現すれば、これには賛否両論はあるかとは思いますが、監督のポランスキー氏もナチス・ドイツのゲットー生活の経験者であり、生き残りであるからこそ描ける作品であるとも思えます。
生き延びてしまったことへの罪悪感。戦わなかったことへの悔恨。戦争への憎しみ・・・。
そういった物を映画化しようとしたときに、真正面からこのピアニストのエピソードに取り組んだ監督の心意気と、キャストの演技にただただ感動する、そんな映画です。
「芸は身を助ける」というカンタンなことわざでは片付けられない物語だと思います。