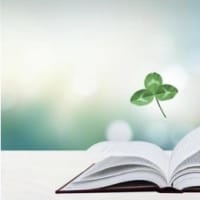就職氷河期世代の私の社会人生活のスタートは非正規職でした。
その後30歳間近にしてやっと念願の職種での正社員職にありつけますが、そこはかなりの激務で安月給。家庭の事情で引越しし、それからもいろいろあって、職場を転々とし、個人事業主にもなりながら、現在は会社員との兼業で生きています。
正社員に戻れてとてもありがたいのは。
完全固定月給制なので、月の所定勤務日数に関わらず給与が大幅に減らないことです。
派遣社員でシフト勤務だったときは、一箇月の勤務日数をめぐって同僚とイザコザがあり、人間関係が最悪でした。また景気が悪くなると、すぐ一匹狼の人間が濡れ衣を着せられて追い出されます。どんなに業務能力があっても、その部署には5年以上契約更新できないようにされますし。派遣先が契約終了したら、すぐに派遣元から希望の条件で仕事を貰えるかわからないのです。そのあいだに、下手な職種で働いたりするとそれが前職のキャリアになるので、次の転職活動では不利に働くことがあります。中高年になるほど、不安定な雇用で働くのはリスクが大きいのです。求人の年齢制限がありますので。
正社員でよかったことのもうひとつは。
自分の机がきちんと与えられること。責任ある仕事ができること、その会社の社員です、と堂々と名乗れることですね。まれに派遣勤務なのに市役所職員だの、大手マスコミのウェブディレクター(ただのコーディング屋ぐらいのITスキルしかない)だのと嘘のキャリアを言う方に出会いますが。健康保険証を見せてもらったら勤務先がバレます。会社のネームバリュー問わず正社員で長くいる人ほど、多くの取引先と折衝するし組織内の調を学んでいるので、自分に謙虚な方が多いです。
会社の業績次第ですが、夏冬のボーナスもありますし、各種の手当てもありますね。
私は経営幹部層に近い位置にいますので、日々、会社の取引の数字や社員の勤怠管理がわかるのです。そのため会社の中心にいて業務を担っているという自信が湧きます。
ただそれだけに責任は重く、休憩時間も削っていますし、早出サビ残もしばしばです。
代わりのいない職種なので、有休も連続で何日もとれるはずがありません。
現在、正社員で勤める会社は、けっしてお給料がいいほうではありません。
私が若い頃派遣社員で残業や休日出勤で稼いだ額からしたら。過去の士業事務所での正社員での給与からしたら。
それでも、私からしたら。電車や車やらで通わずにすむので朝はゆったり過ごせますし。私とほぼ同年代ぐらいの方が中途採用で多く雇用されていますし、定年年齢も高いので、中年で入社しても長く働けます。とてもありがたいことです。
個人事業主としての経験が10年ある私からしたら、毎月かならずお金が振り込まれるサラリーマンという働き方はとても天国です。
なんぼ自由だといいましても、取引先が経営難になったら入金されない、勝手に契約変更されてしまう。病気や怪我になって働けなくなっても保障が薄い。家族を健康保険の被扶養に入らせられない。そんな個人事業上だけの働き方はリスクが大きいのです。自分の名前だけで働けて、自分だけの成果にできるかわりに、失うもの、背負わねばならないものはかなり重いわけです。
若いうちならば、今の勤め先を選んだでしょうか。
たぶん見劣りがして拒んでいたでしょう。けれども40歳を過ぎて、あちこち渡り歩き、結局どこの会社も大なり小なりのトラブルがある。そればらば、もう一箇所で腰を落ち着けて長く働いた方がいいに決まっています。履歴書や職務経歴書にこれ以上経歴が増えるのは御免でした。
私が過去に企画編集職で勤めていた職場のエリート営業マンは癖があって。
後に同業界で起業したようですが、その会社は1円資本の会社なので、その後どうなったのかわかりかねます。起業で失敗すると莫大な負債を背負いかねないですし。契約をとってくるだけではなく、経費の精算などの数字の管理などの細かい業務も発生します。会社で営業成績をあげているのは、個人の能力ではなく、その会社のネームバリューもあるのだということを、会社員個々人は忘れがちですね。
若いうちは大言壮語して自分の能力を過信し、起業で儲けるだの、自由を謳歌するだの思いがちですが。年をとればとるほど労働生産性が下がることに気づいてしまいます。給料が少々低くても、定年退職年齢が長い職場に細々と働き続ける方がトータルに見てお得なのではないでしょうか。もちろん、どんな勤め先も倒産や廃業リスクがありますので、絶対安定とは言い難いのですけども。
毎月貰える、というか私が作成している給与明細をみながら、つくづく有難みを実感してやまないのです。就職氷河期には喉が手が出る程欲しいのが安定した仕事だったのですから。
企業経営者の皆さんにも、働く意欲に飢えている、誠実な中高年社員を積極的に安定雇用で雇っていただきたく思います。無駄なプライドなんて棄ててしまえばいい。置かれた場所で咲き続けなければ、わ私たちは生き残ってはいけないのです。
(2022/07/30)