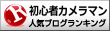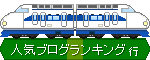今朝も気温が12度で初夏を思わせる気温で
したが、南の風が強く、時折頭の帽子に手を
当てながら風と格闘してきました。
一昨日、市内の工場での火災事故があって又
不安な夜となりました。
今から300年程前の江戸は、人口100万人を超
える世界最大級の都市で当時の家屋は木材と
紙(襖や障子)で出来ていたため、ちょっと
した火の粉が元で大火となることもしばしば
「火事と喧嘩は江戸の華」と言われましたよ
うに火事は日常茶飯事でしたが、1657年の明暦
の大火(振袖火事)は死者数10万を超えると言
われ、震災戦禍を除けば日本史上最大の火災と
なっています。そんな時代ですから火付(放火)
は特に重罪で、火罪(火あぶり)をもって罰せ
られました。「八百屋お七」はその頃の悲しい
恋の物語です。お七は火事の非難場所で偶然出
会った人が忘れられずにいました。火事になれ
ばまた会えると思ったお七は放火をしてしまい
そして捕らえられます。火付けは重罪で、お七
はまだ16歳であったことを哀れみ、奉行は「そ
の方、歳は15であろう」(当時は15歳以下は
罪を減じられました)と尋ねるのですが、そん
な配慮に気づかなかったお七は16歳であること
を正直に答えてしまいます。お七は市中引き回
しの上、火刑に処せられてしまいます。
井原西鶴がこの事件を取り上げて以降、浄瑠璃
や歌舞伎の題材にもなり評判となったそうです。
諸説あるものの、お七は丙午(ひのえうま)生
まれだったことから、丙午生まれの女は思いつ
めたら何をしでかすか分からない、丙午の女は
嫁にもらうなとの風聞が広まっていきました。
丙午の迷信は古代の中国にも求めることができ
馬という字面(気性の激しいじゃじゃ馬等)と
相まって、長い間、丙午生まれの女性が疎まれ
てきたという歴史があります。
日本の人口ピラミッドを見てみますと、戦争の
影響で出生率が著しく低下した1945年、1946年
生まれの人口の割合がガクンと少なくなってい
ます、その次の世代が第一次ベビーブームで
人口が急増。そして1カ年だけ人口の割合が
極端に少なくなっているところがあります。
それが丙午(1966年)生まれです。
その後も、丙午の迷信が少なくとも今日まで
囁かれている事に驚かされます。
火事の夜は、いつもそんなことを思い出して
しまいます。そして昨夜から今朝のように強風
の日も不安になる私です。





なんか 不思議な花です・・チューリップ
ではないようです・・さて ??





したが、南の風が強く、時折頭の帽子に手を
当てながら風と格闘してきました。
一昨日、市内の工場での火災事故があって又
不安な夜となりました。
今から300年程前の江戸は、人口100万人を超
える世界最大級の都市で当時の家屋は木材と
紙(襖や障子)で出来ていたため、ちょっと
した火の粉が元で大火となることもしばしば
「火事と喧嘩は江戸の華」と言われましたよ
うに火事は日常茶飯事でしたが、1657年の明暦
の大火(振袖火事)は死者数10万を超えると言
われ、震災戦禍を除けば日本史上最大の火災と
なっています。そんな時代ですから火付(放火)
は特に重罪で、火罪(火あぶり)をもって罰せ
られました。「八百屋お七」はその頃の悲しい
恋の物語です。お七は火事の非難場所で偶然出
会った人が忘れられずにいました。火事になれ
ばまた会えると思ったお七は放火をしてしまい
そして捕らえられます。火付けは重罪で、お七
はまだ16歳であったことを哀れみ、奉行は「そ
の方、歳は15であろう」(当時は15歳以下は
罪を減じられました)と尋ねるのですが、そん
な配慮に気づかなかったお七は16歳であること
を正直に答えてしまいます。お七は市中引き回
しの上、火刑に処せられてしまいます。
井原西鶴がこの事件を取り上げて以降、浄瑠璃
や歌舞伎の題材にもなり評判となったそうです。
諸説あるものの、お七は丙午(ひのえうま)生
まれだったことから、丙午生まれの女は思いつ
めたら何をしでかすか分からない、丙午の女は
嫁にもらうなとの風聞が広まっていきました。
丙午の迷信は古代の中国にも求めることができ
馬という字面(気性の激しいじゃじゃ馬等)と
相まって、長い間、丙午生まれの女性が疎まれ
てきたという歴史があります。
日本の人口ピラミッドを見てみますと、戦争の
影響で出生率が著しく低下した1945年、1946年
生まれの人口の割合がガクンと少なくなってい
ます、その次の世代が第一次ベビーブームで
人口が急増。そして1カ年だけ人口の割合が
極端に少なくなっているところがあります。
それが丙午(1966年)生まれです。
その後も、丙午の迷信が少なくとも今日まで
囁かれている事に驚かされます。
火事の夜は、いつもそんなことを思い出して
しまいます。そして昨夜から今朝のように強風
の日も不安になる私です。





なんか 不思議な花です・・チューリップ
ではないようです・・さて ??