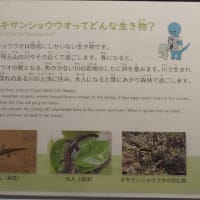【 2025年3月16日 】
もう10日前に読み終えたが、ブログを書く時間がなかった。
それと、先に読み終えた『日銀の限界』と順序が逆になってしまった。『日銀の限界』は第二次トランプ政権が成立した後の著書だが、『アメリカはなぜ日本より~』の方は昨年の8月末の「トランプが返り咲くかどうか」が不確かな状況の時に出版されたものだった。だから、昨年のこの著書では《杞憂と思われていた事》が、後の本では《現実となってしまった》という「世界政治地図の大転換」という大きな違いはあるが、大筋において書かれていることは一貫している。
〇 〇 〇
日本の低賃金はもう30年以上変わりがなく続いている。しかも長時間労働は北欧の比ではない。GDPはドイツに抜かれるし、その内にインドにはもちろん、韓国や台湾にも抜かされそうな状況である。

【 実質GDP推移 】
この本の構成は次のようになっている。
第1章 日米給与のあまりの格差
第2章 先端分野はアメリカが独占、日本の産業は古いまま
第3章 円安に安住して衰退した日本
第4章 春闘では解決できない。金融正常化が必要
第5章 アメリカの強さの源泉は「異質」の容認
第6章 強権化を強める中国
第7章 トランプはアメリカの強さを捨て去ろうとしている
となっている。

1章と2章で、日米の経済格差がどのように開いてしまったかが、産業構造の違いや双方の「経営理念」「社会政策」の違いから解き明かされている。
3章と4章では、それらを経済・金融政策の違い裏付けされている。
5章から7章は、第2次トランプ政権が成立することによって変わるであろう《アメリカの立ち位置》や《世界の政治地図の展望》が述べられている。
この本には、初学者に配慮して丁寧に、各章の終わりに《章のまとめ》なる文書が添えられている。わたしが要約しぃて紹介するより、それを提示する方が手っ取り早いし、的確だと思うので以下に提示し、若干補足してみることにする。
本な内容を一度に紹介するのは、内容が多すぎるので、今回は第1章と第2章にしぼって扱うことにする。
【 第1章のまとめ 】
1.アメリカは日本より豊かな国だ。これは、誰でも知っている。では、どの程度豊かなのか?「2倍程度」ということがよく言われる。
しかし、専門家の給与格差は、これよりずっと大きい。金融専門家の初任給では、7.5倍もの差がある。
2.アメリアでは、コロナ禍からの回復で需要が急拡大し、供給が追いつかないためにインフレが発生した。しかし、その後の金融引き締
めで、インフレを克服しつつある。一方、日本では、長期にわたる金融緩和の継続で生産性が低下し、実質賃金が下落した。
3.アメリカでは、IT企業を中心として技術革新が起こったので、賃金が上昇した。
日本ではそうした革新が起きず、産業構造が古いままなので、賃金が上がらない。
【 第2章のまとめ 】
1.アメリカでは、IT産業やAIを利用した新しい経済活動が拡大している。それに対して、日本の産業構造は古いままだ。
2.アメリカは、IT産業やAIなど、先端分野になるほど強くなる。これを支えるのは、大学の水準の高さだ。これに対して
日本は、専門教育をOJTに頼る仕組みから脱却していない。高度人材育成という最も重要な分野において、日本は間違っ
た資源配分を行っている。
3.世界的な半導体ブームが起きている。重要なのは、半導体そのものでなく、AIの目覚ましい発展と、それが引き起こす変化だ。
4.世界では半導体関連企業の株価上昇が著しい。日本は残念ながら、その流れから取り残されている。日本が強いのは、半導
体製造装置や原材料であり、半導体の製造は振るわない。この状況は、政府がいくら補助金を出しても、変るものではない。
5.半導体事業支援のため、巨額の補助金が出されている。しかし、これによって日本の半導体産業が復活するかどうか、極め
て疑問だ。必要なのは補助ではない。経済学の教科書に書いてあるとおり、「技術・投資・人材」だ。
6.日本のサービス収支のうち「デジタル赤字」は、5兆円を超え、原油輸入額の半分程度になる。「通信・コンピュータ・情報
サービス」で、日本は世界最大の赤字国だ。日本がデジタル化を進めれば、この赤字が増える。
7.デジタル庁が発足して2年以上経つが、脱印鑑は、進んでいない。それどころか、アナログとデジタルの手段が入り乱れて、
事態は悪化している。デジタル庁の存在意義を見直すべきではないか?
8.日本がGDPでドイツに抜かれるのも、株価が急騰したのも、円安という共通の要因によるものだ。ただし、前者は長期的
なトレンドであるのに対して、後者は円高になれば崩壊する一時的な現象だ。
9.日経平均株価が、バブル後の最高値を更新した。日本は「失われた30年」からやっと抜けだし、そして、新しい目標に向か
ってスタートを切ったと言われる。しかし、新しい産業で発展しているアメリカと比較してみると、とてもそうは言えない。
となる。

図表-2.3 GDP推移
若干、補足しておこう。
〇【 給与格差 】について
アメリカの給与はドルで支払われ、日本では円だ。だから当然、その時の為替レートによって変わってくる。
例:同じような仕事をしているシステム・エンジニアが、〔日本でのSEが:月給45万円で アメリカでのSEが5000ドルを受け取っている]場合を考えると、
【為替レート】が
1ドル=150円の場合 → 日本のSEの45万円=3000ドル アメリカのSEの5000$=75万円
従って、給与の格差は 日本:アメリカ=45万円:75万円=3000$:5000$=3:5=日本はアメリカの6割
1ドル=100円の場合 → 日本のSEの45万円=4500ドル アメリカのSEの5000$=50万円
従って、この時の格差は 日本:アメリカ=45万円:50万円=4500$:5000$=9:10=日本はアメリカの9割
となって、円高の場合、円安の場合に比べ、格差は狭まっている。だから、アメリカの給料が日本の7.5倍とは一概に言えないが、日本の一般的職員の給与が低すぎるのは事実である。
( だからと言って、私は《日本のエリートも、アメリカの一部のエリートや起業家、経営者・CEO等が
受け取っているのと同じような高給(月給を年俸と思い違えるような破格の)を受け取るべきだ》とは思わない。
幅広い中間層や非正規雇用の職員が、その仕事にふさわしく、より豊かな生活が出来るような、もっと多くの給与を受け取るべきだと考える。 )


為替レート推移 購買力平価
*どのくらいの【為替レート】が適切なのかという判断は、【購買力平価】という値を参照する必要がある
かつての日本が東南アジアの諸国に対し、経済的優位な状況のもとでの円高で、ベトナムやらフィリピンから多くの出稼ぎ労働者が日本に押し寄せたが、彼らが日本で稼いだ賃金を故国に送金すると、数年分で家が建てられると言われた。故国での月給はというと、数千円と言われるのを聞いて、それで1ヶ月の生計を営んでいたというから信じられなかったが、当時の東南アジア諸国と日本との為替レートが、不当に日本の円が高く評価されていたとも考えられる。
逆の事が近年、日本とオーストラリアの間で起こっている。日本の学生がオーストラリアでアルバイトをすると、1ケ月で50万円を稼げるという。日本は一流国でも豊かな国でもなく、貧しい国に成り下がってしまった。
〇【 金融緩和 】が、どうして【 実質賃金の低下 】を招くか?
金融緩和には、政策金利を下げる質的緩和と、日銀が市中の国債を買って(日銀の当座預金残高を増やすことで)、市中に円を潤沢に供給させようとする量的緩和の、2つの方法があるが、いずれにしても円安を招く。
金利が下がれば、より金利の高いドルに資金は流れ、さらに円安が進み、事態は悪化する。
〇【 産業構造が古いまま 】なのはどうしてか?
著者によれば、経営者の怠慢(将来を見る目がない、金融取引の利益を追って有効な設備投資をしない=【 今だけ、金だけ、自分だけ】)ということになる。
これらの問題は、第4章で再考する。
〇【 IT 】・【 AI】・【 半導体 】の用語について
最近、横文字の略語が多くて紛らわしい。
IT=インフォメーション・テクノロジー、つまり「情報技術」のこと
AI=アーティフィシャル・インテリジェンス、つまり「人工知能」のこと
ところで、紛らわしいのは「半導体」という言葉である。
むかし、学校で習った「半導体」とは、条件によって電気を通したり、通さなかったりする《物質》、つまりゲルマニウムやケイ素などの、《導体と絶縁体の中間の
電気伝導率を持った物質》ということだったが、そう解すると《世界では半導体関連企業の株価上昇が著しい》とか《日本では半導体の製造は振るわない》という表現はどこかおかしいし、違和感がある。
《半導体》は単なる《物質》を表す言葉ではなく、半導体を材料として使った様々な《集積回路》《チップ》《モジュール》等を意味している、そう理解した方が良いとわかる。
(というより、現在ではその意味でつかわれていることが多い。)
具体的に《半導体》を意味するものとして、
・パソコンやスマホのCPU(中央処理演算装置)やGPU、デジカメのイメージ・センサ(CMOS)、エアコンの温度センサー、自動車に組み込まれている制御装置や自動運転技術を支える回路等、
挙げればきりがない。そう理解すれば、この分野の《遅れ》は致命的だと理解できる。(私個人の意見として、このような意味合いで《半導体》という用語は不適当だと思うのだが。)
〇【 デジタル赤字 】について


【 デジタル赤字の新聞記事 】 【 図表-2・4 サービス状況推移(本書より)】
新聞を見ていたら、タイミングよく『デジタル赤字』に関する記事が出ていた。現在では、SNSにしてもスマホやパソコンを使うにしてもGAFAなどのアメリカの巨大企業のサービスを抜きに利用することなど考えられない。クラウドサービスや映画やスポーツの視聴・閲覧にも欠かせない。日本はこの面でもアメリカに完全に依存している。
長くなってしまった。続きはまた改めて書くとしよう。 【 続く 】
【 『アメリカはなぜ日本より豊かなのか?』(その2)】へジャンプ
【 日銀の限界』(野口悠紀雄著、幻冬舎新書、2025年刊)-タイムリーでわかりやすい解説!】のマイブログへジャンプ