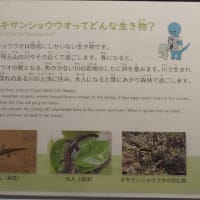【 京都総評の「最低賃金・時給1700円に!」のチラシ(署名用紙)から 】
【 2025年3月19日~27日 記 】
この本の構成は次のようになっている。( 再掲 )
第1章 日米給与のあまりの格差
第2章 先端分野はアメリカが独占、日本の産業は古いまま
第3章 円安に安住して衰退した日本
第4章 春闘では解決できない。金融正常化が必要
第5章 アメリカの強さの源泉は「異質」の容認
第6章 強権化を強める中国
第7章 トランプはアメリカの強さを捨て去ろうとしている
〇 〇 〇
今回は、このうち第3章と第4章について書くことにするが、前回、第2章の【8.と9.のまとめ】についての記事が抜けてしまったので、補足しておく。
【 第2章のまとめ 】
8.日本がGDPでドイツに抜かれるのも、株価が急騰したのも、円安という共通の要因によるものだ。ただし、前者は長期的
なトレンドであるのに対して、後者は円高になれば崩壊する一時的な現象だ。
9.日経平均株価が、バブル後の最高値を更新した。日本は「失われた30年」からやっと抜けだし、そして、新しい目標に向か
ってスタートを切ったと言われる。しかし、新しい産業で発展しているアメリカと比較してみると、とてもそうは言えない。

【 消費者物価上昇率と実質賃金上昇率 】
【 第3章のまとめ 】
1.2022年から急激な円安が進んだ。アメリカが金利を引き上げ、日本は引き上げなかったためだ。日本人は大幅に貧しくなった。
「円安の是非」など問題にするのはおかしい。
2.円安になると、日本円に換算した売り上げ額は増加する。原材料価格の上昇分は販売価格に転稼されるため、企業の利益が増加する。
このため株価が上がり、政治的に歓迎される。
3.ユーロやポンドの減価は2022年9月で止まり、為替レートはコロナ以前の水準に戻った。しかし、円はコロナ前より大幅に減価
したままだ。これは、日銀が、金融正常化宣言をしたにもかかわらず、金融緩和を継続するとしているためだ。
4.2024年の購買力平価は1ドル=90円程度なので、市場レート150円は、これより大幅に円安だ。両者の差がこれほど開いた
のは、1980年代前半以来のことだ。円安が日本経済に与える弊害を直視し、長期金利を市場の実勢に委ねる必要がある。

【 IMF購買力平価と市場レートの比較 】
【 第4章のまとめ 】
1.「賃金と物価の好循環」が日本でも実現しつつあるとの見方が広まっている。しかし、2023年以降の高い賃上げ率は、物価上昇に
よりもたらされたものであり、労働に対する需要増の結果ではない。なお、春闘値上げ率のうち経済全体の賃上げ率をもたらすのは
「ベア」だけだ。また、春闘参加企業は全企業の一部でしかないことに留意する必要がある。
2.2024年春闘で、高額回答が続いた。しかし、賃金上昇分が販売価格に転嫁されると、スタグフレーションを誘発する危険がある。
3.金融緩和で金利が低下し、収益性の低い投資が正当化されることとなった。このため、生産性が低下した。また、財政資金の調達コス
トが低下したため、財政放漫化がもたらされた。
4.20年以上にわたる過剰な金融緩和の継続によって、日本の経済が衰退した。ここから脱却して金融正常化を進めることは、焦眉の課題だ。
5.日本経済は「スタグフレーション」に落ち込んでいる。賃金上昇分が物価に転嫁されるという動きが生じているのかもしれない。
6.実質家計消費支出が減少している。これを補うために、財政支出が膨張している。
7.生産性向上による賃金上昇を実現するために、金融緩和の正常化が必要だ。日銀は、2024年3月に金融正常化の開始を決定した。
これによって、日本経済が大きく変わることが期待される。金融正常化は、財政や企業にとっても、本来は望ましいことだ。
8. 実質経済成長率、消費者物価上昇率、長期金利の間には密接な関係があり、この関係を無視して金利政策を決めることはできない。
日本では、物価上昇率を2%にするとしながら、長期金利を0%に抑えるという矛盾した経済を求めてきた。物価上昇率が2%を超え
れば、長期金利は現在より大幅に高くならなければならない。
等々。
前回と同様に[ 補足 ]しておこう。
〇【 『円安』ということ 】
前回、どうして日本の給与水準が低いのかという話で、為替レートが1ドル=100円の場合と、1ドル=150円の場合を比べて、
後者の場合(1ドル=150円)は、前者の時より【 円安 】で、アメリカとの給与格差が広まるという話をした。
つまり、円安とは他国の通貨(ここの場合はアメリカ)に対し、円の価値が下がることを意味している。(同じ1ドルの物を得るのに、1.5倍の円を払わねばならない)
【 円安が日本のGDPの評価額を下げる 】というのは、
今、仮に日本が年間150億円の物を生産したとする。これをドル換算で表すと、
【 為替レート 】が
1ドル=150円の場合 アメリカでの評価は → 1億ドル
1ドル=100円の場合 ” → 1.5億ドル
となって、日本の名目GDPは1.5倍となる。つまり、円安のときは円高のときと比べて(上の例だと)、3分の2の評価しか得られないとわかる。

【 為替レートの変遷 】
〇【 失われた30年 】について
『失われた30年』とは1990年のバブル崩壊後に日本経済が陥った長期の不景気状態を指すが、特徴として、
・ 賃金が上がらず、物価も上がらないデフレ状態が続いた
・ 企業はそれなりに稼いだが、利益を設備投資や給与アップに回さなかった
・ 金利が低く抑えられた(庶民の金利所得が名目減りした)
・ 一人当たりのGDPが1990年以降、全く増えていない
・ 株価が上がらず停滞した 等々

【 一人当たりGDPの推移(日・米・独の比較) 】
これらの特徴に対し、世間一般では【 超金利緩和政策の出口 】が見えたとか、【 物価と賃金の好循環 】の始まりの兆しとか、【 株価が最高値を更新した 】とか言って、
【 日本経済復活への明るい兆し 】が見えたとかいう風潮がささやかれているが《 そう甘くは無い 》と、本書では厳しく批判している。
〇【 円安の是非 】について → 【 金融緩和政策 】がどうして【 円安 】につながるのか
ヨーロッパも含め、他の国々が【 金融緩和政策 】を止めて2022年以降、【 金利を上げる】方向に舵を切ったのに対し、日本では日銀総裁も、他の経済学者も、政府関係者も、
さも訳ありそうに《なんだかんだ》言って理屈をこねわして、円安を導ている【超金融緩和政策】を止めようとしていないことに著者もあきれているが、私も全く同感である。
円安でも円高でも、ある者(ある面)にとっては有利に、別のある者(ある面)にとっては不利になるという両面があって、一国全体を取れば差し引きゼロになると思うのだが、
強者は自分の都合に合わせ、それを許さないで【利益を独占している】という現実を見ていない。
( 円安は、自動車などの輸出産業や、インバウンドを迎える観光業界などには有利に働くが、食料や原材料・燃料を輸入に頼る産業・企業にとっては不利となる。)
しかし、下にも書いたが、大企業は、円安によって値上がりした燃料費や原材料費を価格に転嫁し、自分の利益をしっかり確保している。
そもそも、【 金融緩和 】(質的金融緩和)での(ゼロ・パーセント金利という時代も含め)超低金利の元では、アメリカとの金利差が大きく開いて、
円が売られドルが買われるのは必然であった。その結果、当然円は安くなる。
 ←前回のデジタル赤字を参照
←前回のデジタル赤字を参照
【 日本のサービス収支の内訳 】
〇【 円安になると、企業の儲けが増大する 】について
『円安になれば、円ベースでの輸出企業の売り上げが増える。一方、企業は原価上昇分を製品価格に転嫁する。したがって、利益が自動的に増える』(第2章、P-92)
『為替レートが円安になったとすると、アメリカのドル建て販売価格は不変だが、日本円に換算した売上高は増加する。』(第3章、Pー115)
『円安は、企業の収益を見かけ上、増加させる。なぜなら、ドル建ての輸出価格が変わらなくても、円建ての輸入価格が上昇し輸出企業の収入を増加させるからだ。』(第4章、Pー154)
この問題に対しての著者のこの説明は物足りない、というか分かりづらい。
アメリカで1台1万ドルの車が売れた時、この車が生産された日本では、
【 1ドル=100円のとき 】 → 1台100万円に相当する売価の車のはず
【 1ドル=150円のとき 】 → 1台150万円に相当する売価の車のはず
である。だから輸出台数(生産台数)が変わらなくても、売上高は増えることになる。
(円安のときは、輸入する原材料の高騰もあるから、そのぶん利益が減るが、それは価格に転嫁していると筆者は説明している。)
常識的に考えると、円安のときは、輸出をメインとする大企業に有利であることは間違いない。
同じ性能の車は、円高のときより定価を下げるか、あるいは、性能を上げた車を生産して、より多く売れたはずである。(ただ現実は、企業の怠慢でそうにはなっていなかったようである。)
逆に、原材料や燃料をもっぱら輸入に頼っているエネルギー企業や食品・農産物を扱っている企業や中小・零細企業は、円安で大きな負担を強いられている。
それと合わせて、著者は【 円安 】のデメリットとして、
『円安になれば、日本は、外国のものを買いにくくなる。また、労働力不足を緩和する手助けになる外国人労働力を得にくくなる。さらに、日本人の学生が
外国に留学できなくなる。こうした意味で、円安は、日本人を貧しくする。』(Pー93)
これはもっともな意見だ。
それでは、為替レートとして【どのくらいが 適正か】という問題が出てくるが、【 購買力平価 】という指標がある。
〇【 購買力平価 】について
【 購買力平価 (PPP)】というのは、『ある国で、ある価格で買える商品が他国ならいくらで買えるかを示す交換レート。』(ウィキペディアより)
ということです。わかりやすく説明するために、この本でも取り上げている(Pー126)【 ビッグマック指数 】で説明すると、こういう事だ。
『日本でのビッグマックの価格は450円。アメリカでは5.69ドル。これを等しくする為替レートh、1ドル=約79円。ところが、実際の市場為替レートは、
約148円。したがって、円は46%ほど過小評価されている』となる。
その国に、豊富にある物や希少価値のある物の分布も異なるし、そもそもその物に対する価値観も異なる環境で、ビッグマックだけを取りだして評価するのは乱暴に見えるが、世界共通のモノを基準の尺度にするのは
わかりやすい。前回の記事で述べたが、《日本に出稼ぎにきた賃金数が月分》で、《年間の生活費が賄える》とか、《家が建つ》というのは、それだけ為替レートがゆがめられていることを示していると思われる。
自己の体験で話をすると、バルト3国を旅行している時だった。エストニアのタリンからフィンランドのオスロにフェリーで渡った時、タリンでは500mlの水が1本1ユーロくらいだったのが、
オスロでは1本10ユーロ近くもしたのには驚いた。同じEUの国なのに、お金の価値が《どうしてこうも違うのか》と思ったが、前段の歴史が、まだ変わり切っていないのかとも思った。
ラウンジの軽食にもべらぼうな値が付いていて、思わず何も食べないで我慢したのを覚えている。
そうして、あれこれ考えると《日米の為替レートは、1ドル=90円くらいが妥当ではないか、それに対し1ドル=140でもかなり円安に思われる?》というのが、筆者の感想でもある。
ちなみに、購買力平価で修正した為替レートでGDPを比べると、日本は、2009年にインドに抜かれて以降、中国、アメリカ、インドに次いで世界第4位になっている、という報告もある。
第4章では、賃金と物価の関係と金融政策に述べられている
〇【 賃金と物価の好循環 】が始まった、とか【2024年春闘は、2023春闘を上回る歴史的高額回答】だとかいう見解、について
今年の春闘で、【 賃金と物価の好循環 】が始まったというのは、全くのまやかしで、筆者の意見に同感である。
【 賃金が5%を超えた 】とか【 歴史的高額回答 】というのは、その後の物価上昇を見れば、霞んでしまう。そもそも春闘は大手企業の一部の組合しか参加していないし、
圧倒的多数を占めている中小零細企業の実態を反映していないものであると。それに、【賃上げ】というが、ベア(ベースアップ)と定期昇給は別物で、ベア自体の賃上げ率を見ないと
意味がないと、筆者は指摘する。(定期昇給は、個人を追ったもので順送りとなり、高齢者は退職するか、非常勤並みの低賃金となり、全体を見れば意味をなさない-ごもっとも!)

【 消費者物価上昇率と実質賃金上昇率 】
昨年夏以来の米価を見よ。野菜の価格を見てみれば、5%の賃上げなどかすんでしまう。
〇【 家計消費支出の減少 】について
物の生産は、最終的に一般消費者の生活を豊かにするためのものであり、一方、生産された商品は消費され回転して貨幣に戻らなければ資本主義は成り立たない。
全生産量の6割を占めると言われる家計消費が落ち込めば、経済も萎縮するに決まっている。
〇【 スタグフレーション 】
物価が上昇する中でも、低賃金や高失業率に陥って、景気が後退している状態。スタグネーション(停滞)とインフレーション(物価上昇)の合成語。
賃金が上がらないもとで、生活必需品(エネルギーや食料・米など)の値段が上がる悪いインフレと言える。(今の日本の状態)
それに対し、著者の言う《望ましいインフレ》は、生産力が上昇した結果、給与が上昇し、それに伴い物価も上昇し、金利も上昇する状態といえる。
〇【 賃金上昇分が物価に転嫁される 】という、「鶏が先か卵が先か」と似たような《堂々巡り》を回避するにはどう考えたらいいのだろう
最近の春闘は「物価高に負けない賃上げを!」と政府までが《応援》しているように見えるが、賃金は商品の原材料・経費の一部を成すものだから、それが値上がりすれば販売価格に跳ね返ってきて、
物価が上がるように思われる。だからこの本の著者は「賃金上昇には生産性(生産力)を高める必要がある」と力説する。
それもその通りだが、もうひとつ抑えておくべきポイントがある。円安によって、輸入される原材料費の値上が分を企業主は、販売価格に転嫁して自分の利益はしっかり確保するのだが、
逆に輸出する場合、円安によってより多くの利益を受けた場合、労働者に利益を還元したりはしない。
もうひとつ。 大企業はなんだかんだ言いながら、この間も着実に儲けていて、内部留保のお金も増え続けている。
野口さんの言うように、持続的な賃金上昇は、【 生産性の向上 】がなければ長続きはしないというのはごもっともだが、それまで労働者は待ってはいられない。
【 粗利益 】は、株主への配当と、経営者の利益が優先され、あるいは【 理由を付けて内部留保 】に回されるかのいずれかに分配されるて、労働者の賃上げは後回しか、無視され続けている。
どう配分されるかは、それぞれの力関係にかかっているが、【賃上げ】こそが今、最優先されるべき課題だ。
最賃が50円値上がりしたと言って、、高々1000円をようやく超えたところで、春闘同様《過去最高の上げ幅》だとお茶を濁して騒いでいるが、
【 最低賃金1500円以上 】を掲げてもう、何年がたつのだろうか。
いつまで1500円なのかと、思っていたところ、ようやくでた【 今こそ、最低賃金・時給1700円! 必要です】の文字に感激!
そう!、労働者は、《経営者の温情や、経営改善がなされる事や、生産性の向上が効果を表すまで 》待っていられない。

【 見出しチラシの下半分 】
【 『アメリカはなぜ日本より豊かなのか?』(その1)】のマイブログ記事へ戻る
【 2025年3月19日~27日 記 】
この本の構成は次のようになっている。( 再掲 )
第1章 日米給与のあまりの格差
第2章 先端分野はアメリカが独占、日本の産業は古いまま
第3章 円安に安住して衰退した日本
第4章 春闘では解決できない。金融正常化が必要
第5章 アメリカの強さの源泉は「異質」の容認
第6章 強権化を強める中国
第7章 トランプはアメリカの強さを捨て去ろうとしている
〇 〇 〇
今回は、このうち第3章と第4章について書くことにするが、前回、第2章の【8.と9.のまとめ】についての記事が抜けてしまったので、補足しておく。
【 第2章のまとめ 】
8.日本がGDPでドイツに抜かれるのも、株価が急騰したのも、円安という共通の要因によるものだ。ただし、前者は長期的
なトレンドであるのに対して、後者は円高になれば崩壊する一時的な現象だ。
9.日経平均株価が、バブル後の最高値を更新した。日本は「失われた30年」からやっと抜けだし、そして、新しい目標に向か
ってスタートを切ったと言われる。しかし、新しい産業で発展しているアメリカと比較してみると、とてもそうは言えない。

【 消費者物価上昇率と実質賃金上昇率 】
【 第3章のまとめ 】
1.2022年から急激な円安が進んだ。アメリカが金利を引き上げ、日本は引き上げなかったためだ。日本人は大幅に貧しくなった。
「円安の是非」など問題にするのはおかしい。
2.円安になると、日本円に換算した売り上げ額は増加する。原材料価格の上昇分は販売価格に転稼されるため、企業の利益が増加する。
このため株価が上がり、政治的に歓迎される。
3.ユーロやポンドの減価は2022年9月で止まり、為替レートはコロナ以前の水準に戻った。しかし、円はコロナ前より大幅に減価
したままだ。これは、日銀が、金融正常化宣言をしたにもかかわらず、金融緩和を継続するとしているためだ。
4.2024年の購買力平価は1ドル=90円程度なので、市場レート150円は、これより大幅に円安だ。両者の差がこれほど開いた
のは、1980年代前半以来のことだ。円安が日本経済に与える弊害を直視し、長期金利を市場の実勢に委ねる必要がある。

【 IMF購買力平価と市場レートの比較 】
【 第4章のまとめ 】
1.「賃金と物価の好循環」が日本でも実現しつつあるとの見方が広まっている。しかし、2023年以降の高い賃上げ率は、物価上昇に
よりもたらされたものであり、労働に対する需要増の結果ではない。なお、春闘値上げ率のうち経済全体の賃上げ率をもたらすのは
「ベア」だけだ。また、春闘参加企業は全企業の一部でしかないことに留意する必要がある。
2.2024年春闘で、高額回答が続いた。しかし、賃金上昇分が販売価格に転嫁されると、スタグフレーションを誘発する危険がある。
3.金融緩和で金利が低下し、収益性の低い投資が正当化されることとなった。このため、生産性が低下した。また、財政資金の調達コス
トが低下したため、財政放漫化がもたらされた。
4.20年以上にわたる過剰な金融緩和の継続によって、日本の経済が衰退した。ここから脱却して金融正常化を進めることは、焦眉の課題だ。
5.日本経済は「スタグフレーション」に落ち込んでいる。賃金上昇分が物価に転嫁されるという動きが生じているのかもしれない。
6.実質家計消費支出が減少している。これを補うために、財政支出が膨張している。
7.生産性向上による賃金上昇を実現するために、金融緩和の正常化が必要だ。日銀は、2024年3月に金融正常化の開始を決定した。
これによって、日本経済が大きく変わることが期待される。金融正常化は、財政や企業にとっても、本来は望ましいことだ。
8. 実質経済成長率、消費者物価上昇率、長期金利の間には密接な関係があり、この関係を無視して金利政策を決めることはできない。
日本では、物価上昇率を2%にするとしながら、長期金利を0%に抑えるという矛盾した経済を求めてきた。物価上昇率が2%を超え
れば、長期金利は現在より大幅に高くならなければならない。
等々。
前回と同様に[ 補足 ]しておこう。
〇【 『円安』ということ 】
前回、どうして日本の給与水準が低いのかという話で、為替レートが1ドル=100円の場合と、1ドル=150円の場合を比べて、
後者の場合(1ドル=150円)は、前者の時より【 円安 】で、アメリカとの給与格差が広まるという話をした。
つまり、円安とは他国の通貨(ここの場合はアメリカ)に対し、円の価値が下がることを意味している。(同じ1ドルの物を得るのに、1.5倍の円を払わねばならない)
【 円安が日本のGDPの評価額を下げる 】というのは、
今、仮に日本が年間150億円の物を生産したとする。これをドル換算で表すと、
【 為替レート 】が
1ドル=150円の場合 アメリカでの評価は → 1億ドル
1ドル=100円の場合 ” → 1.5億ドル
となって、日本の名目GDPは1.5倍となる。つまり、円安のときは円高のときと比べて(上の例だと)、3分の2の評価しか得られないとわかる。

【 為替レートの変遷 】
〇【 失われた30年 】について
『失われた30年』とは1990年のバブル崩壊後に日本経済が陥った長期の不景気状態を指すが、特徴として、
・ 賃金が上がらず、物価も上がらないデフレ状態が続いた
・ 企業はそれなりに稼いだが、利益を設備投資や給与アップに回さなかった
・ 金利が低く抑えられた(庶民の金利所得が名目減りした)
・ 一人当たりのGDPが1990年以降、全く増えていない
・ 株価が上がらず停滞した 等々

【 一人当たりGDPの推移(日・米・独の比較) 】
これらの特徴に対し、世間一般では【 超金利緩和政策の出口 】が見えたとか、【 物価と賃金の好循環 】の始まりの兆しとか、【 株価が最高値を更新した 】とか言って、
【 日本経済復活への明るい兆し 】が見えたとかいう風潮がささやかれているが《 そう甘くは無い 》と、本書では厳しく批判している。
〇【 円安の是非 】について → 【 金融緩和政策 】がどうして【 円安 】につながるのか
ヨーロッパも含め、他の国々が【 金融緩和政策 】を止めて2022年以降、【 金利を上げる】方向に舵を切ったのに対し、日本では日銀総裁も、他の経済学者も、政府関係者も、
さも訳ありそうに《なんだかんだ》言って理屈をこねわして、円安を導ている【超金融緩和政策】を止めようとしていないことに著者もあきれているが、私も全く同感である。
円安でも円高でも、ある者(ある面)にとっては有利に、別のある者(ある面)にとっては不利になるという両面があって、一国全体を取れば差し引きゼロになると思うのだが、
強者は自分の都合に合わせ、それを許さないで【利益を独占している】という現実を見ていない。
( 円安は、自動車などの輸出産業や、インバウンドを迎える観光業界などには有利に働くが、食料や原材料・燃料を輸入に頼る産業・企業にとっては不利となる。)
しかし、下にも書いたが、大企業は、円安によって値上がりした燃料費や原材料費を価格に転嫁し、自分の利益をしっかり確保している。
そもそも、【 金融緩和 】(質的金融緩和)での(ゼロ・パーセント金利という時代も含め)超低金利の元では、アメリカとの金利差が大きく開いて、
円が売られドルが買われるのは必然であった。その結果、当然円は安くなる。
 ←前回のデジタル赤字を参照
←前回のデジタル赤字を参照【 日本のサービス収支の内訳 】
〇【 円安になると、企業の儲けが増大する 】について
『円安になれば、円ベースでの輸出企業の売り上げが増える。一方、企業は原価上昇分を製品価格に転嫁する。したがって、利益が自動的に増える』(第2章、P-92)
『為替レートが円安になったとすると、アメリカのドル建て販売価格は不変だが、日本円に換算した売上高は増加する。』(第3章、Pー115)
『円安は、企業の収益を見かけ上、増加させる。なぜなら、ドル建ての輸出価格が変わらなくても、円建ての輸入価格が上昇し輸出企業の収入を増加させるからだ。』(第4章、Pー154)
この問題に対しての著者のこの説明は物足りない、というか分かりづらい。
アメリカで1台1万ドルの車が売れた時、この車が生産された日本では、
【 1ドル=100円のとき 】 → 1台100万円に相当する売価の車のはず
【 1ドル=150円のとき 】 → 1台150万円に相当する売価の車のはず
である。だから輸出台数(生産台数)が変わらなくても、売上高は増えることになる。
(円安のときは、輸入する原材料の高騰もあるから、そのぶん利益が減るが、それは価格に転嫁していると筆者は説明している。)
常識的に考えると、円安のときは、輸出をメインとする大企業に有利であることは間違いない。
同じ性能の車は、円高のときより定価を下げるか、あるいは、性能を上げた車を生産して、より多く売れたはずである。(ただ現実は、企業の怠慢でそうにはなっていなかったようである。)
逆に、原材料や燃料をもっぱら輸入に頼っているエネルギー企業や食品・農産物を扱っている企業や中小・零細企業は、円安で大きな負担を強いられている。
それと合わせて、著者は【 円安 】のデメリットとして、
『円安になれば、日本は、外国のものを買いにくくなる。また、労働力不足を緩和する手助けになる外国人労働力を得にくくなる。さらに、日本人の学生が
外国に留学できなくなる。こうした意味で、円安は、日本人を貧しくする。』(Pー93)
これはもっともな意見だ。
それでは、為替レートとして【どのくらいが 適正か】という問題が出てくるが、【 購買力平価 】という指標がある。
〇【 購買力平価 】について
【 購買力平価 (PPP)】というのは、『ある国で、ある価格で買える商品が他国ならいくらで買えるかを示す交換レート。』(ウィキペディアより)
ということです。わかりやすく説明するために、この本でも取り上げている(Pー126)【 ビッグマック指数 】で説明すると、こういう事だ。
『日本でのビッグマックの価格は450円。アメリカでは5.69ドル。これを等しくする為替レートh、1ドル=約79円。ところが、実際の市場為替レートは、
約148円。したがって、円は46%ほど過小評価されている』となる。
その国に、豊富にある物や希少価値のある物の分布も異なるし、そもそもその物に対する価値観も異なる環境で、ビッグマックだけを取りだして評価するのは乱暴に見えるが、世界共通のモノを基準の尺度にするのは
わかりやすい。前回の記事で述べたが、《日本に出稼ぎにきた賃金数が月分》で、《年間の生活費が賄える》とか、《家が建つ》というのは、それだけ為替レートがゆがめられていることを示していると思われる。
自己の体験で話をすると、バルト3国を旅行している時だった。エストニアのタリンからフィンランドのオスロにフェリーで渡った時、タリンでは500mlの水が1本1ユーロくらいだったのが、
オスロでは1本10ユーロ近くもしたのには驚いた。同じEUの国なのに、お金の価値が《どうしてこうも違うのか》と思ったが、前段の歴史が、まだ変わり切っていないのかとも思った。
ラウンジの軽食にもべらぼうな値が付いていて、思わず何も食べないで我慢したのを覚えている。
そうして、あれこれ考えると《日米の為替レートは、1ドル=90円くらいが妥当ではないか、それに対し1ドル=140でもかなり円安に思われる?》というのが、筆者の感想でもある。
ちなみに、購買力平価で修正した為替レートでGDPを比べると、日本は、2009年にインドに抜かれて以降、中国、アメリカ、インドに次いで世界第4位になっている、という報告もある。
第4章では、賃金と物価の関係と金融政策に述べられている
〇【 賃金と物価の好循環 】が始まった、とか【2024年春闘は、2023春闘を上回る歴史的高額回答】だとかいう見解、について
今年の春闘で、【 賃金と物価の好循環 】が始まったというのは、全くのまやかしで、筆者の意見に同感である。
【 賃金が5%を超えた 】とか【 歴史的高額回答 】というのは、その後の物価上昇を見れば、霞んでしまう。そもそも春闘は大手企業の一部の組合しか参加していないし、
圧倒的多数を占めている中小零細企業の実態を反映していないものであると。それに、【賃上げ】というが、ベア(ベースアップ)と定期昇給は別物で、ベア自体の賃上げ率を見ないと
意味がないと、筆者は指摘する。(定期昇給は、個人を追ったもので順送りとなり、高齢者は退職するか、非常勤並みの低賃金となり、全体を見れば意味をなさない-ごもっとも!)

【 消費者物価上昇率と実質賃金上昇率 】
昨年夏以来の米価を見よ。野菜の価格を見てみれば、5%の賃上げなどかすんでしまう。
〇【 家計消費支出の減少 】について
物の生産は、最終的に一般消費者の生活を豊かにするためのものであり、一方、生産された商品は消費され回転して貨幣に戻らなければ資本主義は成り立たない。
全生産量の6割を占めると言われる家計消費が落ち込めば、経済も萎縮するに決まっている。
〇【 スタグフレーション 】
物価が上昇する中でも、低賃金や高失業率に陥って、景気が後退している状態。スタグネーション(停滞)とインフレーション(物価上昇)の合成語。
賃金が上がらないもとで、生活必需品(エネルギーや食料・米など)の値段が上がる悪いインフレと言える。(今の日本の状態)
それに対し、著者の言う《望ましいインフレ》は、生産力が上昇した結果、給与が上昇し、それに伴い物価も上昇し、金利も上昇する状態といえる。
〇【 賃金上昇分が物価に転嫁される 】という、「鶏が先か卵が先か」と似たような《堂々巡り》を回避するにはどう考えたらいいのだろう
最近の春闘は「物価高に負けない賃上げを!」と政府までが《応援》しているように見えるが、賃金は商品の原材料・経費の一部を成すものだから、それが値上がりすれば販売価格に跳ね返ってきて、
物価が上がるように思われる。だからこの本の著者は「賃金上昇には生産性(生産力)を高める必要がある」と力説する。
それもその通りだが、もうひとつ抑えておくべきポイントがある。円安によって、輸入される原材料費の値上が分を企業主は、販売価格に転嫁して自分の利益はしっかり確保するのだが、
逆に輸出する場合、円安によってより多くの利益を受けた場合、労働者に利益を還元したりはしない。
もうひとつ。 大企業はなんだかんだ言いながら、この間も着実に儲けていて、内部留保のお金も増え続けている。
野口さんの言うように、持続的な賃金上昇は、【 生産性の向上 】がなければ長続きはしないというのはごもっともだが、それまで労働者は待ってはいられない。
【 粗利益 】は、株主への配当と、経営者の利益が優先され、あるいは【 理由を付けて内部留保 】に回されるかのいずれかに分配されるて、労働者の賃上げは後回しか、無視され続けている。
どう配分されるかは、それぞれの力関係にかかっているが、【賃上げ】こそが今、最優先されるべき課題だ。
最賃が50円値上がりしたと言って、、高々1000円をようやく超えたところで、春闘同様《過去最高の上げ幅》だとお茶を濁して騒いでいるが、
【 最低賃金1500円以上 】を掲げてもう、何年がたつのだろうか。
いつまで1500円なのかと、思っていたところ、ようやくでた【 今こそ、最低賃金・時給1700円! 必要です】の文字に感激!
そう!、労働者は、《経営者の温情や、経営改善がなされる事や、生産性の向上が効果を表すまで 》待っていられない。

【 見出しチラシの下半分 】
【 『アメリカはなぜ日本より豊かなのか?』(その1)】のマイブログ記事へ戻る