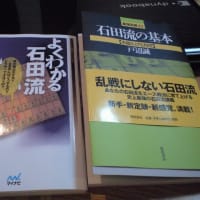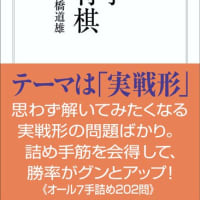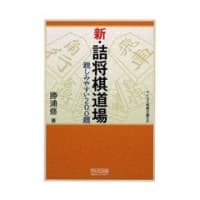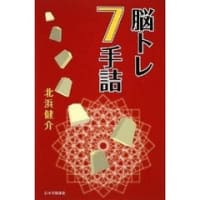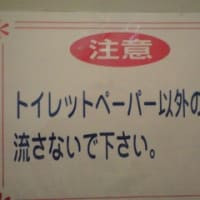少子高齢化とは、
「若者が減りお年寄りが増える」社会構造と定義して話をすすめますね。
その「少子高齢化」という社会構造が「経済」に対してどういった影響を与えるのかを簡潔に考えてみましょう。
少子高齢化 =「若者が減り・お年寄りが増える」
まずは、少子高齢化の中における「若者が減る」という部分から分析してみましょう。
■若者
「若者」とは社会の中で主に労働をになう存在であり、
若者は何らかの「モノ」や「サービス」を社会の中で生産・供給(作って売る)する存在です。
それと同時に若者は――
先ほどから若者、若者とまくしたてていますが、
ここでいう若者のターゲットは約15歳~約60歳と非常に幅広く、
そこいらのガタがきてるズラったおっさんでもここでは立派に若者。俺、超若者。
それと同時に若者は―
「モノ」や「サービス」を社会の中で消費・需要(買って使う)する存在でもあります。
つまり若者は、
生産者として 「モノ」を作って売る(供給する)と同時に、
消費者として 「モノ」を買って使う(需要する)存在です。
生産 = 供給 = モノを作って売ること
消費 = 需要 = モノを買って使うこと
――――――――――――――――――――――――――――――――
図1 よくわかる若者の生産消費・需要供給バランス
生産 ■■■■
消費 ■■
↓若者が減ると↓
生産 ■■
消費 ■
――――――――――――――――――――――――――――――――
図1のようになりますね。
例えば農家の人であれば、
田んぼで米作して、ご飯食べて寝ると。
ただし、若者は将来のために貯蓄・貯金するため、消費は生産で得たお金(所得)よりも控えめになります。
少子高齢化 =「若者が減り・お年寄りが増える」
次に、少子高齢化の中における「お年寄りが増える」という部分から分析してみましょう。
■お年寄り・ご隠居
お年寄りは若者の進化形態。
労働から解放され悠々自適な生活を送る存在。
若者が、
生産者として 「モノ」を作って売る(供給する)と同時に、
消費者として 「モノ」を買って使う(需要する)存在だったのに対して、
お年寄りは、
生産から解放された存在とも書けるでしょう。
つまり、
お年寄りは世の中で、
生産側から解放され、
消費者として 「モノ」を買って使う存在。
生産 = 供給 = モノを作って売ること
消費 = 需要 = モノを買って使うこと
――――――――――――――――――――――――――――――――
図2 よくわかるお年寄りの生産消費・需要供給バランス
生産
消費 ■■
↓お年寄りがふえると↓
生産
消費 ■■■■
――――――――――――――――――――――――――――――――
図2のようになりますね。
悠々自適な毎日。
ここまで観てみた―少子化と高齢化が同時に進む
少子高齢化 =「若者が減り・お年寄りが増える」社会構造における経済を考えてみましょう。
■少子高齢化という社会構造がどのような経済を形作るか
生産 = 供給 = モノを作って売ること
消費 = 需要 = モノを買って使うこと
――――――――――――――――――――――――――――――――
図1 よくわかる若者の生産消費・需要供給バランス
生産 ■■■■
消費 ■■
↓若者が減ると↓
生産 ■■
消費 ■
――――――――――――――――――――――――――――――――
図2 よくわかるお年寄りの生産消費・需要供給バランス
生産
消費 ■■
↓お年寄りがふえると↓
生産
消費 ■■■■
――――――――――――――――――――――――――――――――
まず、少子高齢化になる前の状況、
つまり、
図1の上側と図2の上側を合成して若者とお年寄りが共生している経済状況をみてみましょう。
――――――――――――――――――――――――――――――――
図3 よくわかる少子高齢化前の社会における生産消費・需要供給バランス
生産 ■■■■
消費 ■■■■
――――――――――――――――――――――――――――――――
あたかも狙っていたかのように生産と消費が均衡していますね。海江田のようだ。
次に、少子高齢化【若者が減り・お年寄りが増える】が進行した状況
つまり図1の下側と図2の下側を合成して若者とお年寄りが共生している経済状況をみてみましょう。
――――――――――――――――――――――――――――――――
図1 よくわかる若者の生産消費・需要供給バランス
生産 ■■■■
消費 ■■
↓若者が減ると↓
生産 ■■
消費 ■
――――――――――――――――――――――――――――――――
図2 よくわかるお年寄りの生産消費・需要供給バランス
生産
消費 ■■
↓お年寄りがふえると↓
生産
消費 ■■■■
――――――――――――――――――――――――――――――――
図1の下側と図2の下側を合成
――――――――――――――――――――――――――――――――
図4 よくわかる少子高齢化社会における生産消費・需要供給バランス
生産 ■■
消費 ■■■■■
――――――――――――――――――――――――――――――――
少子高齢化が進むと、
生産よりも消費が多い経済構造となる。
生産<消費 供給<需要 作って売る<買って使う
これを経済の概念でいえば、「モノ不足」「継続的な物価の上昇」「継続的な貨幣価値の下落」 「インフレ」
というものになります。
少子高齢化はインフレを招くのではないか、
ということです。
まとめますと、
非常に世の中を簡便化した形で分析したわけですが。
若者が減り・お年寄りが増える、いわいる「少子高齢化」社会におきましては―
生産主体である若者が減り、生産から解放されたお年寄りが増える。
そういった社会構造・社会状況を、
経済における需要と供給の考え方を使って考察すると、
『少子高齢化』社会がもたらす経済の姿は、
「インフレーション」つまり物価上昇圧力がかかり続ける世の中ではないかと考える次第です。