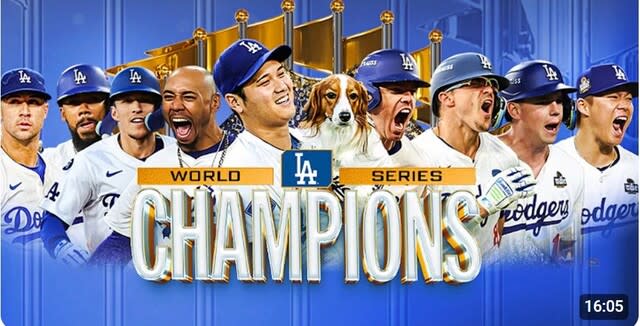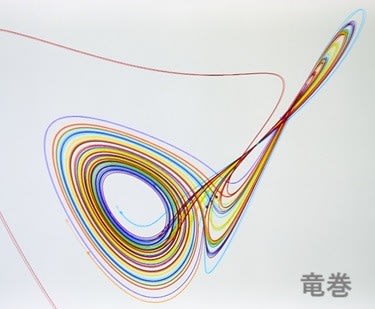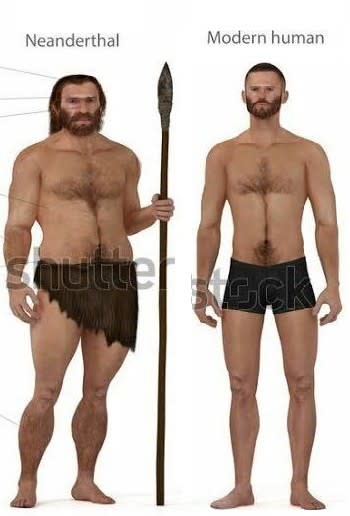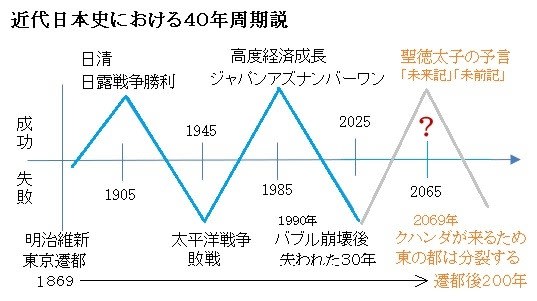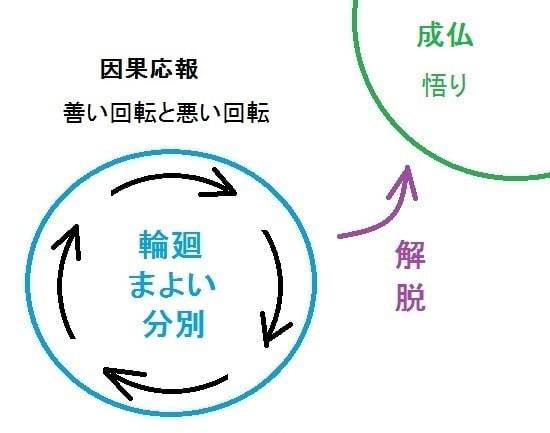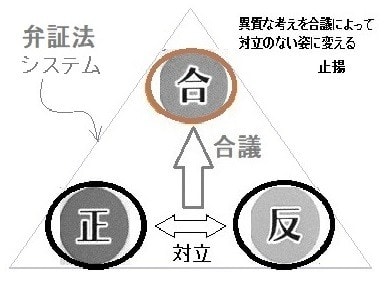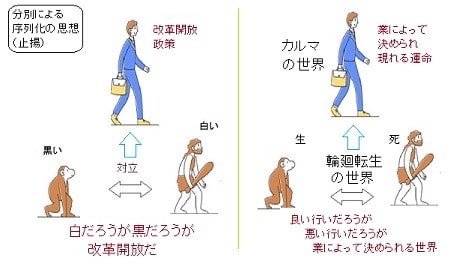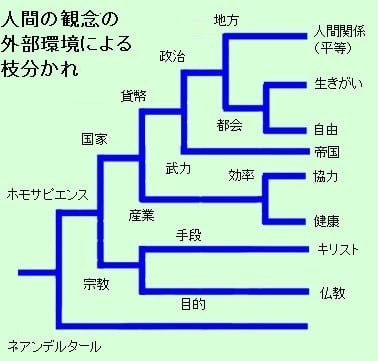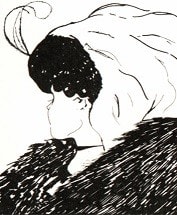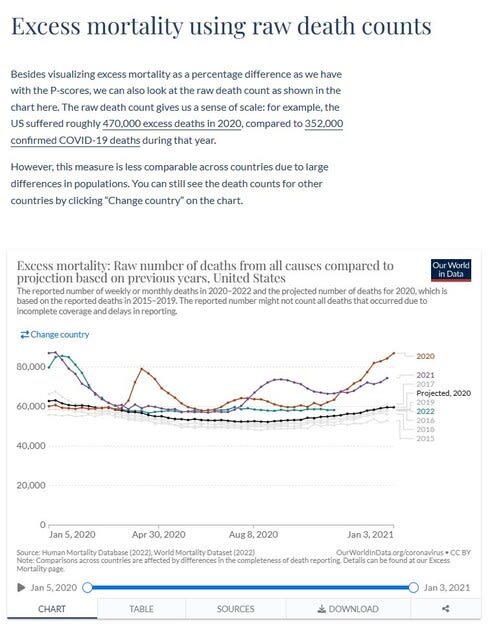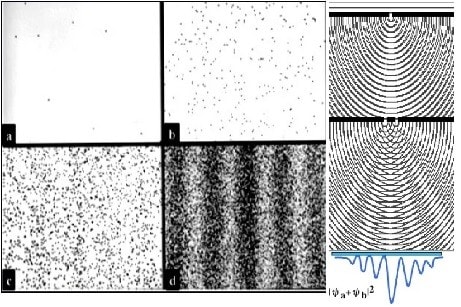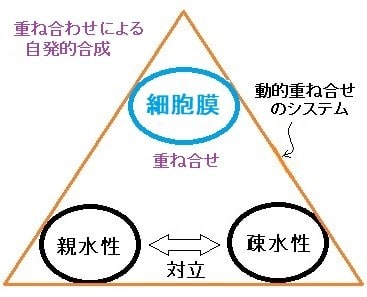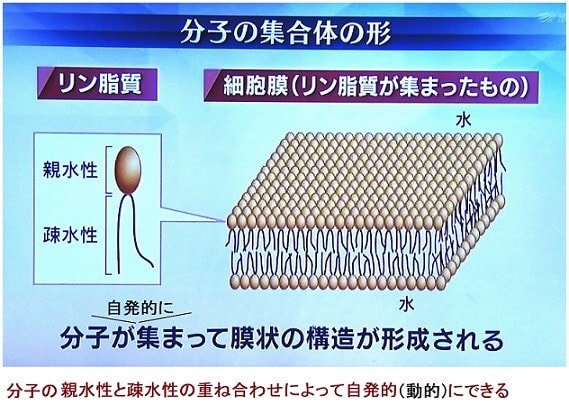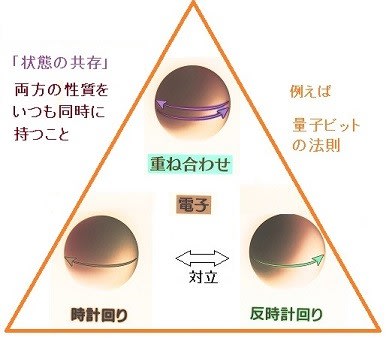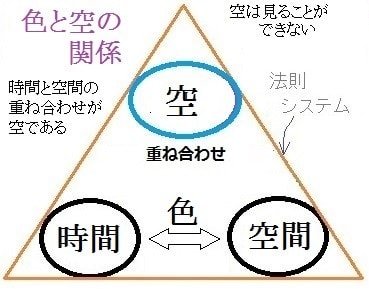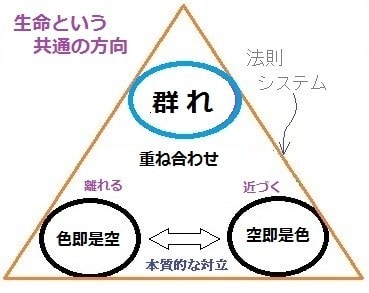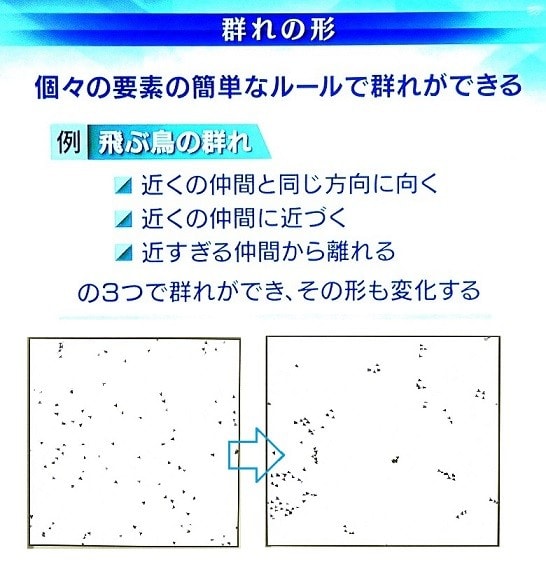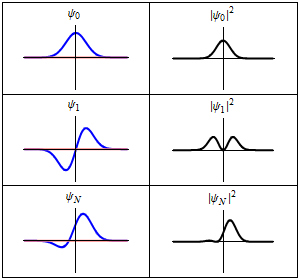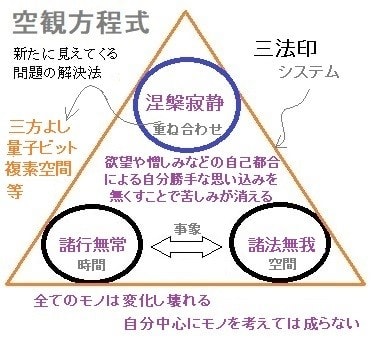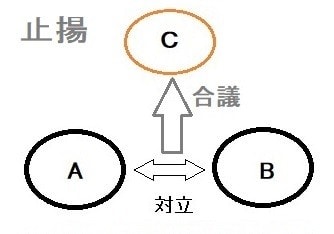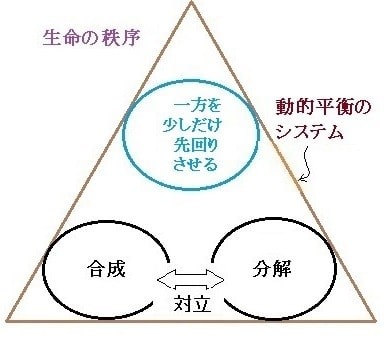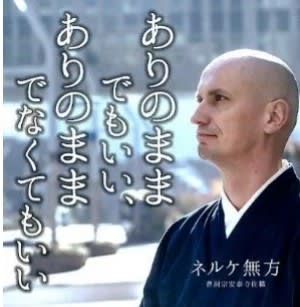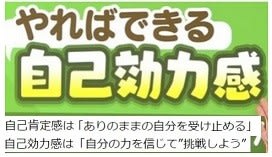人間の脳の機能によれば
「今」が楽しくなければ、過去の優雅でリッチな生活もどこかに吹っ飛び、
逆に「今」が楽しければ、過去の苦痛は消し飛び幸福感で満たされるそうです。
確かに、登山でどんなに苦しい思いをしたとしても
頂上に達した「今」の達成感があれば 全てが幸福に包まれて
また登ってみようと思うものです。
従って、これを人生に置き換えてみれば、
避けることのできない「死」を受け入れない限り
幸福は得られないということになります。
最近接した記事に哲学者の言葉がありましたので紹介します。
「未来のことで悩み続ける魂(意識)ほど不幸な魂(意識)である」
とモンテーニュは言ったそうです。
将来確実に訪れる「死」を受け入れなければどんなに贅沢しようが
どんなに至福に浸ろうが「今」が幸福になれないからです。
「死」を受け入れるとは、
常に足りないものばかりを求め、不満を抱えているようでは不幸になってしまう。
「未来のことを心配するのでなく、今この瞬間をしっかりと生きることが
幸せへの道である」とモンテーニュはさらに言いいます。
私が意図できるものは「私自身」である。他人ではない
私という「今」を変えられない限り、
そしてまた、私が決めない限り幸せは訪れない。
日常の幸福と、「今」という自分に与えられた時間に感謝し満足して生きることで、
これこそ老人ホームを選ぶ前に必要な事であり、
かつ自分で選ぶことができるものです。
そこから「死」を受け入れることにつながってゆく。
幸せだと思えば幸せであり、不幸だと思えば不幸になる。
酒好きの人にとって大吟醸の一滴は至福の極みであるが、
酒の飲めない人や嫌いな人にとってはただの水滴となるように。



「今」が楽しくなければ、過去の優雅でリッチな生活もどこかに吹っ飛び、
逆に「今」が楽しければ、過去の苦痛は消し飛び幸福感で満たされるそうです。
確かに、登山でどんなに苦しい思いをしたとしても
頂上に達した「今」の達成感があれば 全てが幸福に包まれて
また登ってみようと思うものです。
従って、これを人生に置き換えてみれば、
避けることのできない「死」を受け入れない限り
幸福は得られないということになります。
最近接した記事に哲学者の言葉がありましたので紹介します。
「未来のことで悩み続ける魂(意識)ほど不幸な魂(意識)である」
とモンテーニュは言ったそうです。
将来確実に訪れる「死」を受け入れなければどんなに贅沢しようが
どんなに至福に浸ろうが「今」が幸福になれないからです。
「死」を受け入れるとは、
常に足りないものばかりを求め、不満を抱えているようでは不幸になってしまう。
「未来のことを心配するのでなく、今この瞬間をしっかりと生きることが
幸せへの道である」とモンテーニュはさらに言いいます。
私が意図できるものは「私自身」である。他人ではない
私という「今」を変えられない限り、
そしてまた、私が決めない限り幸せは訪れない。
日常の幸福と、「今」という自分に与えられた時間に感謝し満足して生きることで、
これこそ老人ホームを選ぶ前に必要な事であり、
かつ自分で選ぶことができるものです。
そこから「死」を受け入れることにつながってゆく。
幸せだと思えば幸せであり、不幸だと思えば不幸になる。
酒好きの人にとって大吟醸の一滴は至福の極みであるが、
酒の飲めない人や嫌いな人にとってはただの水滴となるように。