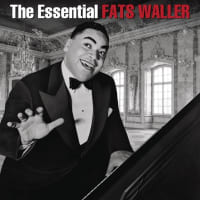最近、あるきっかけから江戸後期の浮世絵師・歌川国芳についての本を読んでみて、ずいぶん面白い思いをした。今回はその感想文。
このブログで映画や音楽の話をする時、僕はなるたけ、どんな結論になるのか自分でも謎なまま、考えた順番に書くようにしている。そのほうが、書く前は自分でも予想もしていなかった発見に辿り着けた時の喜びが大きい。ブログで好き勝手に書ける良さだ。
その代わり、自分だけの発見に辿り着けない時は、方向が決まっていて原稿料をもらえる文章を書く時の窮屈さよりも苦しい。
シロウトゆえ美術・絵画の話をするのは滅多にないので、今回はどうなることやら。
(作品画像は、パブリックドメインで無料ダウンロードが可能なサイトからもらいました)
さて、歌川国芳。
さすがに、今まで存在を知らなかったわけではない。何度かは美術館で見ている。以前、父の友人の美術コレクターに所有品を見せてもらったのが新鮮で、それからは浮世絵展があればちょくちょく出かけるようになった。
葛飾北斎は何を描いてもすごいなあ、と毎度のように唸るし、歌川広重の風景画/名所絵は特に魅かれる。広重の『東海道五拾三次』のひとつ「蒲原 夜之雪」は、古今東西の美術品のなかでもブリューゲル「雪中の狩人」と一、二を争うほどに好きだ。
ところが国芳に、北斎や広重ほどの感銘を受けたことがない。
見た展を記録しておく習慣を持たなかったため厳密には言えないけれど、国芳を何度か見たといっても人気絵師の代表作を集めた特別展のたぐいで、国芳だけの展は行ったことがないはずだ。
特別展での国芳は確かに面白い。豪快な武者絵や、物語の一場面を描いたエンタテインメント感たっぷりのもの、打って変わってネコや金魚を擬人化した可愛いものを見て、まるで漫画家やアニメーターの先輩みたいな人だなあ、と思ったことは一度や二度ではない。
描かれたものが躍動する、その一瞬を捉えることに貪欲なさまが、江戸中期までの浮世絵の平板さ、立体感の乏しさと比べるとケタ違いで、遥かに映像的なのだ。
でも、その感慨はいつも他の絵師、北斎や広重、喜多川歌麿や東洲斎写楽らの代表作を見た嬉しさの次に回ってしまうのである。僕のなかでは常に浮世絵界のナンバー2(ナンバーワンはそのつど変わる)という感じ。
これはどうも、国芳の面白がりどころを絞り込めない僕の理解度の問題だ、と薄々は気付いていた。
北斎なら富士山、広重なら江戸の風景、歌麿なら美人画……みたいにパチーンと、これぞ国芳、というイメージが自分の中で定まらないままでいた。
そのことが、橋本治、悳俊彦、林美一の連名の本『幕末の修羅絵師 国芳』(1995 新潮社)を読んでみてようやく整理できた。これぞ国芳、と絞り込めないほどに幅広いから国芳だった。
新潮社のとんぼの本は、これまでも仏教美術や伊藤若沖などを知るために何度かお世話になってきた、案内書シリーズの名門。『幕末の修羅絵師 国芳』も、豊富なカラーページの図版とビギナーを意識した解説で国芳の多彩さを教えてくれる。
それによくよく眺めていれば、僕がこれまで、いかにも江戸後期の浮世絵らしい浮世絵と典型的に思っていたイメージは、かなりの部分で国芳に拠っていたことにも気付かされる。
北斎や広重となるともう屹立した固有名詞というか、浮世絵の範疇からはみ出した存在になるので、“浮世絵らしい浮世絵”を見たことにはならなくなる。
映画で例えればこういうことだ。もしも外国の研究者に、いかにも昔の日本映画らしい典型的な日本映画をリストアップしてほしい、とリクエストされたら、僕はまず小津安二郎、黒澤明、溝口健二の作品を外すだろう。オズ、クロサワ、ミゾグチはすでに世界的な存在で、日本映画の枠を越えているから。
『幕末の修羅絵師 国芳』のなかで、国芳が生きて活動した時代を、戦後の日本映画黄金期と重ね合わせた考察をしているのは橋本治。
各社の撮影所で量産されていた頃の日本映画、いわゆるプログラム・ピクチャーは、題材がどんなに多種多様であろうと、自ずといかにも日本映画らしいものになった。型とそれを作る技術がしっかり決まってさえいれば、注ぎ込む題材のヴァリエーションは幾ら違ってもよいからだ。浮世絵もまたそうで、どちらもマニエリスムの最盛期に通じるのだという。
マニエリスムとは(美術検定の本などを参考に大まかに言えば)、ルネサンス最盛期のミケランジェロ、ダ・ヴィンチらの影響を受け継いだ16世紀美術のこと。ルネサンスの手法を重んじるなかで様々な誇張や大胆な表現が試みられたが、影響そのものから脱しようとはしないことに対して様式的で創造性がない、という批判が次第に生まれ、もっと強烈なバロック美術にとって代わられた。マンネリズムの語源と言われる。
橋本治は、このマニエリスムの傾向のひとつとして江戸後期の浮世絵人気を捉え、国芳の手掛けた題材の幅広さは江戸の職人としては当然のことであって、それ自体が国芳の特性・個性なわけではないと言い切っている。
そのうえで、構図や描写の細部にある、国芳の絵にはあるが他の絵師では見られないものはどんな点かを解いていき、認識をもう少し奥に導いてくれる。
例えば『椿説弓張月』の場面をモチーフにした、巨大ワニザメと鳥天狗が登場する「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」。画面の半分を想像上の大魚が占める、かなり奇天烈なものなのに、品があって破綻がなく、スンナリと“絵になる”ところまで達しているところが「国芳の本当のすごさだろう」と橋本治は説く。
「『変だから面白い』を、変なままにしてしまったら、それは素人のすることになる。変なものが、『ちゃんとドラマになっている』というところまで持っていくのがプロで、国芳は勿論プロ。『変になっても、おれは平気だよ。力があるから』というのが、国芳だ」
流れるようにナットクさせていく橋本治の名調子、久々に味わえた。この人がそういうんだから、そうなんだろうと思わせる。戦後のプログラム・ピクチャーを支えた娯楽映画の監督論としても読める。
『幕末の修羅絵師 国芳』では、枕絵研究で有名な林美一の論も読みごたえがある。主には枕絵師の側面についてなのだが、水滸伝の豪傑を描いたシリーズが国芳の出世作となったことの重要性についても触れている。
それで、ずいぶん前に読んだ林美一の単著『江戸の枕絵師』(1987 河出文庫)を本棚の奥から出してみたら、やはり(枕絵の切り口から人気絵師達を紹介していく本なのに)、国芳の章では水滸伝の武者絵への評価に字数が費やされていた。
そのおかげで、ずいぶん理解が進んだのである。実は僕、国芳の武者絵はこれまで苦手だった。今でいうとヤンキー/不良が暴れる漫画のようなギトギトしたところが受け入れにくく、それが、常に浮世絵界のナンバー2という僕の中の序列の要因になっていた。
ところが『江戸の枕絵師』を久々に開いて、菱川師宣の時代からのおっとりした図柄を順に見ていったうえで、水滸伝ものの一枚「花和尚魯知深初名魯達」に行き着くと、アッとなる。突然、何かが爆発しているのだ。
人物も風景の一部のような平板な浮世絵は、江戸の町民の生活の向上にそぐわなくなっていた。それと国芳の売出しとのタイミングが、ピッタリ合ったのだと思われる。
西洋絵画の遠近法が当時どれだけ江戸に入っていたか、は分からないのだが、ここでは、人物を思い切り描きたいように描けば周囲は自ずと後景になるのだと言わんばかりの、理論よりも先のものが漲っている。

しかもストップモーションのような、砕け散る松の木片。ヨーロッパではちょうど写真技術が発達し始めたばかりの頃だと考えると、国芳のレンズのような目と、フィルムの一コマのように動きを捉えるセンスは、まさに天賦の才だ。あまりに早く生まれ過ぎて映像作家になれなかったビジュアリストとさえ言える。
こうして橋本治、林美一の論に導かれて国芳理解が進むと嬉しい。満足しているうち、気になることが生まれてきた。連名の著者のひとり、悳俊彦(いさお・としひこ)の存在だ。
洋画家で、画業の一方で国芳らの浮世絵研究を続けているという。他のふたりに比べたらネームバリューは格段に落ちる。僕もまるで存じ上げていなかった。
ところが。『幕末の修羅絵師 国芳』をよくめくれば、国芳の生涯のコンパクトな紹介も含めた総論は悳俊彦が担当しているし、個々の作品の解説文や年譜も悳が校閲している。何より、多くの図版の出典は〈悳コレクション〉ときた。
実質は悳が編集者とともにベースを作っていて、橋本治と林美一はゲストに近い本だった。
そう分かってみると、悳俊彦だけネームバリューが落ちるぞ、なんて思っていて……おみそれしました、もいいところである。
せっかく国芳が今までになく身近になってきたし、この人の単著も読んでおかねばと、『もっと知りたい歌川国芳 生涯と作品』(2008 東京美術)を続けて手に入れた。美術館のミュージアムショップによく置いてあるのでおなじみのシリーズだ。タイトルが、今の僕のレベルに実におあつらえ向き。
まえがきにあたる冒頭の「私の親分・国芳師匠」を読んで、いきなり、ジーンときてしまった。
「特に国芳の人間性には強く惹かれるものがあり、(中略)彼は他人とは思えない」
「だから私は、酸いも甘いも知り尽くした苦労人の彼に、すっかり気を許している」
「そのようなわけで、私は読者の皆さんに、最も身近な人を紹介するような気持ちで、本文を進めてゆくことにしたいと思う」
カラッと爽やか。心意気がなんてよく伝わるのでしょう。
僕は以前、ある映画監督の作家論を書き、序文にあたる部分をどう始めるかで少し苦労した。その実感から言うのだが、こういうまえがきは、なかなか書けないものだ。
生臭い気持ちがあると、どうしても「○○は今こそ再評価されるべき存在である」「○○の真価と世間の評価との間の落差に怒りを禁じえなかったことしばしばであった」云々と、義憤と私憤がゴッチャになる。この作家と一緒に、この作家を評価してきた自分にも利益が欲しい、という心根がどうしても出てしまう。
逆に、すでに問答無用の評価が定まった作家を紹介する場合なら、「私のごとき若輩が諸先輩の論に論を重ねる愚行に恥じ入りつつ……」など、殊勝なようで予防線を張っておくのに懸命な、処世臭が出てしまいがち。どっちにしても書くのは難しい。
ここでの悳俊彦のように、いやーボクが昔から好きな人をぜひ紹介したくてね、と明るくはにかんで温かいのみ、というまえがきは一体、それこそどんな心根から出てきたのだろう。
「酸いも甘いも知り尽くした苦労人の彼」とあるように、国芳は、技量は若いうちから認められながら、なかなか世に出られなかった。長い間、赤貧だったという。しかし水滸伝の武者絵で一躍ブレイクした後も気取ることはなく、ギャラは弟子と分配した。「先生」と呼ばれるのをひどく恥ずかしがった逸話も本の中で紹介されている。
悳俊彦は、そういう国芳の人柄を慕っている。
まず多彩な絵に共通する着想の豊かさ、健康的な力強さに魅かれ、その後で軌跡やエピソードを知ると、作品のなかから窺える精神が、道理で!……と納得され、ますます惹き込まれるようになった。こういう順番のようだ。
僕は、とても国芳の絵から人柄を類推するまではできない。ただでさえ浮世絵のように大枠のスタイルが決まっているものから作家性を読み取るのは、高度な作業だ。
だからなおさら、悳さん自身はどういう人で、どんな人生だったのかな……と興味が湧く。同じ画描きとして、国芳に対して親しみや憧れ以上の、骨まで沁みるような共感があったのだろうか。
いずれにせよ、国芳の絵から不遇のなかでもクサらない人間性を感じ取った悳さん(いつのまにかさん付け)も若々しい精神の持ち主のようだ。
「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」の解説で、
「この作品を見ているといつの間にか宮崎駿作品の一場面を観ているような錯覚にとらわれてしまう」
と書いている。1935年生まれで1970年代から国芳の研究を続けてきた人が、宮崎アニメを見て刺激を受けているなんて、微笑ましくもその柔軟さに頭が下がる。
しかし。ちょっと待てよ……となる。
「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」は海上の一大ファンタジー絵巻なので、僕はすぐに、悳さんのいう宮崎駿作品とは当時の最新作『崖の上のポニョ』のことだろうな、と認識したのだが。確認してみて驚いた。
ポニョは2008年7月の公開。『もっと知りたい~』は、2008年3月の刊行。悳さんは、ポニョをまだ見ているはずがないのに「宮崎駿作品の一場面を観ているような」と書いているのだ。
これには唸った。要するに悳さんは、海と怪魚の浮世絵→ポニョという、直接に描かれたものからの単純な連想ではなく、小さな人間と大きな怪異を同じ画面に同居させるダイナミズムや、この世ならぬ生き物が生々しい息使いとともに人間を守る、霊界と現実が侵食し合った世界を具象にしていくイマジネーションにおいて、国芳と、『もののけ姫』(1997)、『千と千尋と神隠し』(2001)の頃の宮崎アニメとの間に通じるものを見ている。
いや、悳さんはもっと前、風の谷の姫ナウシカが王蟲の群れを止める姿にすでにいち早く、国芳を見ていたのかもしれない。
ともかく目が覚めるような指摘だ。確かに宮崎アニメのほうにだって、国芳の浮世絵を見ているような錯覚を起こさせるところがあるもの。
この見識に感心していると僕の中でも、もともと国芳のことを、まるで漫画家やアニメーターの先輩みたいな人だと直感的に思っていたことが活き活きと蘇ってきて、他にも連想が湧き出てくる。
例えば、混み合う人が一杯に描かれた「本朝名橋之内 江戸日本橋略図」。
ひとりひとり違う表情にする手間を明らかに楽しんでいるさまは、手塚治虫の初期の漫画の見開きページや、監督兼アニメーターとして乗りに乗っていた頃の宮崎駿作品でもおなじみのものだ。『風の谷のナウシカ』(1984)の併映だった『劇場版名探偵ホームズ 海底の財宝の巻』の、船上一杯にひしめく水兵達みんなが違う動きをするカットの、バカバカしいほどの凝りようを初めて見た時の震えを思い出す。
とはいえ、十代の頃の僕にとって宮崎駿はほとんど信仰の対象だったが、『もののけ姫』以降、先に書いたような異世界のイマジネーションがどんどん前に出てくるのには、どうもしっくりこないでいた。これは『君たちはどう生きるか』(2023)でも同様で、擬人化されたインコや、カエル、ペリカンの群れをなぜあれほどたくさん登場させ、グニョグニョと動かしたがるのか?……と戸惑ったままにしていた。
しかし、国芳のほうにも「里すヽずめねぐらの仮宿」のような浮世絵があると知れば、これは『君たちはどう生きるか』のインコの群れや、『名探偵ホームズ』で全てのキャラクターをイヌの擬人化にしたアイデアに通じるではないかと気付く。「竜宮玉姫之図」も、これこそもろに『崖の上のポニョ』ではないか……などと連想していくと、近年の宮崎アニメの苦手に感じて戸惑っていた部分が、どんどん理解できる気がしてくる。
そういう絵にするための目的(風刺やテーマ)はもちろん大事でありつつ、内面から出てくるイメージの欲求がまず大きくあり、でも似た絵はこの世にはないから絵筆をとって自分で描いたのだろう。その点できっと、国芳と宮崎駿はよく似ている。
それに今回読んだ国芳の2冊に少しずつ紹介されている、スケッチにあたる下絵が、奮い立つほどにいいのである。宮崎駿の絵コンテみたい! と目や頭より先に細胞が喜ぶ。
「風俗大雑書」の一部も、町人のようすの数パターンが描かれているページなんか、アニメのキャラクター設定書みたい。サラッとした線が、生活の一部を活き活きと浮かび上がらせる。
ここまで粘ってみると、どうも国芳の幅広さには、2つの側面があると認識しておく必要がありそうだ。
1・武者絵から物語に材をとった絵、名所絵、戯画、枕絵までの、題材の幅広さ
2・「宮崎駿の絵コンテみたい」と思わせる下絵・スケッチの、実に現代的な筆の感覚をもとに、当時の江戸庶民の流行、ニーズに絵柄を合わせ、完成させていく幅広さ
1はすでに触れているとして、問題は2だ。
僕はさっき、国芳の武者絵は、ヤンキー/不良漫画のようなギトギトしたところが苦手だった、と書いた。しかしこれが国芳にとって最初の大ヒットとなり、絵師を続けていく基盤となる。
つまり、ギトギトは国芳の生来の絵柄というより、多分にマーケットに合わせたものだ。ここがますます面白い。
日本人の精神には、あはれ、わびさび、季節の微かな変化や虫の音を愛でる繊細な感覚と、過剰な装飾性や暴力的なほど奇抜な表現に血が騒ぐ、歌舞伎の語源である傾く(かぶく)感覚の両方がある。
どっちの感覚が濃いかで一般人とヤンキー系に分かれる、とさえ言ってしまっていいだろうが、多くの人の場合は、両者が実にフシギに同居している。ふだんはみんなと歩調を合わせて暮らしているが、地元のお祭りやハロウィンの仮装の時は思う存分はっちゃける―そんな風にバランスをとっている。
国芳はその、日本人の二重の感性をよく知ることで、どちらにも対応できる先駆者だった。そんな仮説を立てられるのではないだろうか。
ギトギトした武者絵はあくまで当時の江戸庶民の、歌舞伎を支持して一大芸能に作り上げていった感覚に合わせていったもの。国芳の一部に過ぎないとは思いつつ。
悳さんが自画像に近いものだと指摘している「国芳もやう 正札附現金男 唐犬権兵衛」で、本人が、自ら考案した閻魔大王や鬼が揃い踏みする地獄図の柄のどてらを愛用していた、と知ってしまうと、ああ……となるのだ。なにそのデザインの好み。国芳先生、めちゃヤンキーの御先祖ですやん。
『もっと知りたい歌川国芳 生涯と作品』の、悳さんのまえがきを再び読むと、1972年、銀座三越で開かれた国芳展が国芳に強烈に打たれた最初で、それ以前は多くの若い画家と同様に海外のモダンアートに夢中で、浮世絵への興味は薄かったと打ち明けている。
林美一も『江戸の枕絵師』で、この1972年の展が国芳の世評を大きく高めるきっかけとなったと書いている。
逆に捉えれば、国芳の見直しにはそこまで時間が要されたわけだ。原因の少なからずはやはり、国芳の絵が持つ過剰さ、どぎつさ、にあったと思う。
大正から昭和にかけて活動した漫画家・細木原青起が、平安時代の鳥羽僧正に始まる戯画の流れを漫画の先駆として捉えた『日本漫画史』(1924)という本がある。2019年になって『日本漫画史 鳥獣戯画から岡本一平まで』というタイトルで岩波文庫に入った時、すぐに買って読んだ。
国芳も当然のように紹介されている。だが、改めてその項を開いてみると、評価はかんばしくないのだ。「低級」「醜感を先ず招いて」とさえある。国芳が無学だったことがその原因かのように、遠回しに強調されている。
近代以降の美術のハイカルチャー指向にとって、国芳の今でいうヤンキー感覚は受け入れ難いもの。これは時代が下ってもそうだったらしい。
林美一の『江戸の枕絵師』の国芳の章が、水滸伝の武者絵への評価に字数が費やされていることは先に書いたが、ここで林は、国内有数の浮世絵コレクター・研究家だった高橋誠一郎(僕も高橋コレクションの展を見に行ったことがある)が、国芳の武者絵に関しては「藝術味の稀薄なもの」「不愉快千万」として冷遇しているのを、かなり厳しく批判している。
高橋は、慶應義塾長で日本芸術院長で……と日本の文化人のトップにいた存在。そんな人が自分の好みで国芳の評価を下げた弊害への批判は、国芳のヤンキー漫画みたいなところが苦手だった、とつい書いてしまった僕も甘受せねばならない……と思う。
同時に、宮崎駿の場合は評価のベクトルが逆になったことも改めて。
アニメファンに熱狂的に支持されていた頃の宮崎アニメは、スマートなユーモアとモダンな魅力に満ち溢れていた。
しかし宮崎アニメがその支持の枠を越え、それこそヤンキー系にも愛される国民的な存在となったのは、怪異なものを登場させて過剰なほど動かす怪奇性を高めてからなのだ。
そう考えると……しつこいようだが、もう一度おさらいしておこう。
1995年の『幕末の修羅絵師 国芳』で橋本治は、国芳をマニエリスムの範疇で捉え、映画でいうとプログラム・ピクチャーと重ね合わせた。
2008年の『もっと知りたい歌川国芳 生涯と作品』で悳さんは、国芳を浮世絵におけるバロック(マニエリスムを打破する形で生まれた過剰さ)と捉え、日本のアニメーションの商業体制の中から登場しつつ、1990年代以降はケタ違いに特異で突出した存在となった宮崎駿と重ね合わせてみせた。その違いが、ますます興味深い。
映画や漫画がどんどん発達し、人々の視覚を通してものを考える回路が飛躍的に拡大したことが、国芳の正当な評価を準備し、また変化させているのだとすれば。
今後、別のサブカルチャーが隆盛すれば、それが、僕らに今までとは全く違うアングルで歌川国芳を発見させる可能性は大きい。
現にもう、「国芳といえばネコですよね~」と笑顔になる人は少なからずいる。その観点から言えば国芳はすっかり〈動物もふもふ動画〉の大先輩ですからね。
浮世絵自体がメディアアートでありコンテンポラリーアートであり……だったんだから、未来に対してもどうとでも対応できるわけだ。
オーケー、国芳。次はとりあえずVRアートをやってくれ。