2024年に見た最初の映画は、『博奕打ち』(1967)。鶴田浩二主演で、小沢茂弘が監督。当時の東映京都のドル箱だった任侠映画路線の1本だ。評判になってシリーズ化され、路線の一角を担うことになった。
これがまあ、良かった。パチーンと琴線に触れるものがあって、CS放送の録画を2回続けて見た。
主人公である博徒・銀次郎(鶴田浩二)は、大阪の賭場で、大阪一の腕と言われる桜井(小池朝雄)を相手に勝ち、たちまち注目されるが、桜井の師匠にあたる市岡(河野秋武)には完敗する。
ところが市岡は、銀次郎のことがすっかり気に入り、桜井にも引き合わせるなど温かく目をかけてくれるようになる。銀次郎の、札と命を一緒に賭けるような「負けっぷり」がいい、そこに本物を見て、嬉しいというのである。流れ者の銀次郎も、市岡と桜井にすっかり心を許すようになる。
腕の立つ者同士の、すぐさま意気が通じ合う居酒屋の場面が実に爽やか。やっと話が通じる相手と出会えた。そういう喜びが、しみじみと伝わってくる。僕が映画を見るのは、時々はこういう情景に出会えるからなのかな、という気にさえなる。
『博奕打ち』シリーズは、山下耕作による『博奕打ち 総長賭博』(1968)と『博奕打ち いのち札』(1971)が、やくざ映画ファン以外にも知られるほど評価が高い。僕もこの2本を見て満足していて、1本目にあたる本作など他の映画をずっとスルーしていた。
監督が小沢茂弘だから、あまり食指が湧かなかった……が正直な理由。東映のやくざ映画をよく見ている人なら多少は理解していただけると思うが、マキノ雅弘、加藤泰や山下耕作の情の濃い演出のあいだに小沢茂弘の監督作を見ると、どうしても大味というか、艶のない感じがしてしまうのだ。
しかし、男と男が勝負を介して渡り合い信頼を寄せあう、まっすぐな組み立てのものだと、大味と感じられていたものが骨太な魅力となって映えてくる。アメリカ映画の監督で言えばヘンリー・ハサウェイやジョン・スタージェスのセン。
そう、『博奕打ち』はタイトル通り、博徒の賭場での勝負がメインになるのがいい。
東映のやくざ映画は多くの場合、博徒が主人公であっても違うところ(組織の内紛や復讐、恋愛など)にドラマの重点が移るのだが、『博奕打ち』は、銀次郎の博才が物語を動かし、それを軸にしてドラマは回る。
賭場の場面は意識的に音楽を減らし、胴師(親)の脇にいる助手役の合力が、旦那衆が掛け金を張ったかどうか確認する声だけが響く音の現実味や、低く下げた裸電球の光が盆茣蓙とそれを囲む男達の顔だけを浮かび上がらせるコントラストの、雰囲気の良さ。『現金に体を張れ』(1956-1957公開)の謀議シーンや『ハスラー』(1961-1962公開)を、ずいぶん参考にしていると思う。
そこまで賭場の場面が本格的だと、どうしても、銀次郎達がやっているのがサイコロや花札ではなく、手本引であることに唸らざるを得なくなってくる。
手本引。すごく簡単にまとめると、胴師が一から六までのカルタ札のうち1枚を隠したまま選ぶ。それが何かを推理して賭けるのがルールだ。
『博奕打ち』では、札を選ぶ桜井のポーカーフェイスと、その桜井の顔をじっと観察する銀次郎の厳しい表情のカットバックが何度も強調されるが、あれは、勝負に挑む男の決意の顔、みたいなイメージのためのクローズアップではなくて、カットバック自体が勝負の描写として無駄なく成立しているのだ。『博奕打ち』の演出と編集の引き締まった印象は、手本引というゲームを選択した効果によるところが大きい。
手本引は、花札よりも覚えるのが簡単。しかし奥が深くて、博奕のなかの博奕と言われる。
実は僕、この手本引を若い頃に教えてもらい、一時期熱中しかけたことがある。
とはいえ、メンバーは専門の札を持つ年長者の家に来られる人達に限られていたし、他に遊戯施設があるわけでもない。当時すでに、本職の人達の賭場でも手本引きはほとんど扱われていないと聞いていた。上記で書いたように大まかなルール自体は簡単なのだが、張り方と配当のほうはぐんと複雑になる。僕もせっせとノートに書き写し、自分の部屋でやろうとしたものの、乗ってくれる相手もまた限られるので、自然と遠ざかった。
ただ、「手本引きを覚えると他のギャンブルがつまらなくなるぞ」と言われたのは本当だった。当時、パチンコやパチスロでも遊んでいたのだが、たしなみ程度止まり。それほどの熱中にはついには至らなかったのだ(それほどの手持ちがない……というのが一番の理由だが)。
『博奕打ち』を見た後、手本引と他のギャンブルとの違いとは何かを初めて考えてみて、それなりの仮説が出た。
おそらく、射幸心の多寡だと思われる。
ギャンブルは基本(くじも含めて)、丁か半かなど、偶然がもたらす結果に従う遊びだ。パチンコも、1980年代に電気による仕掛けが入った特別電役台がメインになってから、飛躍的に射幸性があがる娯楽になった。
もちろん、現在のデジパチの世界でも、本気でやるとなれば台選びや釘読みに訓練や習熟は必要だろう。ただ相対的には確実に、誰でも気楽に遊べるものになり、偶然性が味方さえすれば初めて座った人であろうと大勝ちできるものになった。
一方の手本引も、一から六までの札のどれかを当てるのだから、当てずっぽうで勝てることはできる。
しかし、そうした射幸性は、自分も一時期凝ってみた経験からだけでも分かるのだが、かなり低い。胴師(親)は、張る相手の気配をよく感じ取り、心理を読む。その上で裏を、裏の裏をかいて札を選ぶからだ。張り子はその胴師(親)をさらによく観察して、札を選ぶ。
自分の記憶でいうと、親をやらせてもらった時は震えるような思いだった。二を出したら、その場にいた人達みなが二を選んでいなかった時の痛快さ。でも、その後が怖いのである。
(若木は気が小さいから、続けて二は出せねえだろ)
(いや、気が小さい奴は考え過ぎる。同じ二、隣の一、三は出せない……となった挙句、大きく六と離れてくるぞ)
などの声が、みんな黙っていても聞こえてくる。自分がそう読まれているに違いない、と思うからだ。そうなると、四か五か、それこそ思う壺か……と本当にかなり考え込むことになる。
つまり、どれだけ人の心のひだを読めるか、の勝負になる。思考がシンプルな人は向いていない。それがハッキリ分かって恥をかいてしまうことになりかねない。
プロ野球のバッテリーと打者の配球の読み合い、サッカーのPK戦に近い、とも言えるだろう。
伝統的なカードゲームということなら、eスポーツの源流の一つと捉えてもいいかも。
だから、銀次郎と桜井、市岡は、大金を取った取られたの勝負をしたのに深い友情を結ぶことになる。(俺の次の手を、よくぞここまで読んだな……!)という感嘆は、(俺という人間を、よくここまで分かってくれたなあ)という喜びと同義になるからだ。
『博奕打ち』は、桜井役の小池朝雄と、市岡役の河野秋武がベテラン俳優の長いキャリアのなかでも屈指の魅力を見せてくれる映画だが、やはり主演スターの鶴田浩二が、銀次郎役にはまったことありきだと思われる。
ここでの鶴田は流れ者の勝負師らしく、常にむっつりとしているのだが、同じむっつりでも、勝負に挑む時の覇気、桜井や市岡の知遇を得た時のはにかみ、舎弟(待田京介)がしくじった時のきびしさ、その舎弟を叱りながら許す時の情、ではまるで表現されているものが違う。
プライベートで鶴田と親交があった経営者・杉井輝応による回想録『鶴田浩二』(1997 扶桑社)には、鶴田は「本当に凄くうまい役者」だったが、美男子過ぎたために抜群の演技力を認められにくかったという山城新伍の証言が紹介されている。『博奕打ち』は、その証言を納得させるうちの1本だ。
さて、手本引は、他よりもその人間の質が試される賭博であり、鶴田浩二がそのマスターを演じるにふさわしい貫禄を示している映画が『博奕打ち』なのだ―とまとめて気持ちよく締めくくりたいところだが、そうもいかない。
eスポーツの源流の一つと捉えてもいいほど精神性が高いゲームだといっても、実地で大金が賭けられたのは同じだからだ。むしろ格上の者や、それなりの旦那衆がやる賭博なので、張られる金額はそれだけ大きかったという。
去年(2023年)、田中紀子『ギャンブル依存症』(2015 角川新書)という本を読んだ。著者は、一般社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の代表で、自分の関わっていたネット番組にも出演していただき、お話を聞いた。
そのうえで『博奕打ち』を見ると、ズルズルと手本引にはまって銀次郎に助けを求め、それが銀次郎に迷惑をかけることになり、妻が自殺しても、まだやめられない遊郭の主人(山城新伍)ののめりこみ方には、かなり陰惨なリアリティがある、と分かる。
田中さんの本とお話に照らせば、遊郭の主人は完全なギャンブル依存症の状態。本人はもう賭場を楽しんではいない。やめたくてもやめられず、苦しみながら続けてしまっている。
これはれっきとした精神疾患のひとつで、「病的賭博」の名称でWHOも正式に病気と認定している。意志や努力だけで治るというのは間違いで、その考え方がやめられない人をかえって苦しめ、ますますギャンブルに走らせてしまうことになる。治療が必要な病気であるという正しい認識のもとに、周囲が病院や施設など、回復できる場所に早期に導くことが大切になる。
だから銀次郎のように、博奕の目的がアスリートにおける競技に近くなっている(自己肯定できている)者はあくまで特殊な例だ。
また、そういう銀次郎が、借金返済のために博奕にのめり込む遊郭の主人に「もう博奕はやめなはれ」と忠告するほど、かえって逆効果になってしまっている。そこのリアリティが『博奕打ち』の隠れたリサーチの凄み。
そこで興味深くなってくるのが、冷血な悪役・憎まれ役に思い切り徹している大関(若山富三郎)の言動。
主人の身ぐるみを剥いだ大関が「あんた、もう二度と博奕に手を出したらあかん」と淡々と声をかける時、その言葉はむしろ銀次郎よりも親切に聞こえるのがミソだ。
国や社会がギャンブル依存症対策を進めるようになったのは、たかだか数年前。『博奕打ち』の舞台設定は昭和初期。
やめようと思えばいつでもやめられる。だから、最後にもう一度……と執着し続ける人間を止めるには、今の暮らしを破滅させるよりない。当時の認識としては最善かもしれないのだ。
この大関、遊郭にお気に入りの女郎(桜町弘子)がいるのだが、借金のカタに手に入れた遊郭の支配人に収まった後、子分達が遠慮してその女郎を店に出さずにいると烈火のごとく怒る。
商売物を店に出さずにしまっておいて、なんてムダなことをするのだ、と経営者として子分を叱責するのだ。そこにも、冷血な人間なりの理屈が通っているので、かえって怖い。
その怖さは、手本引と競技のように向き合うことで人格形成できている、という奇跡を起こしている銀次郎と、一対。どちらが人間的か。いや、どちらも非人間的なのは同じではないか……とまで考えさせる。
この文の前半に、東映のやくざ映画は多くの場合、博徒が主人公であってもドラマの重点は違うところ(組織の内紛や復讐、恋愛など)に移る、と書いたが、それは必然だったのかもしれない。博徒の世界はとことん描こうとするほど、いずれ観客にとっても苦しい、楽しくないものになるのが目に見えているからだ。
この後はいったん保留。『博奕打ち』シリーズの他も見てみてから考えたい。
それに近年の『カイジ』や『ライアーゲーム』のシリーズはことごとく未見なので、気になる。
















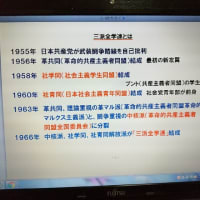
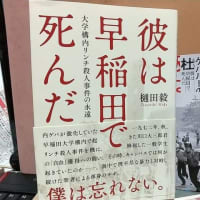

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます