今回は(今回も)、まとまらないことのメモになる。
バンドサウンドとはなにか、について最近よく考えるのである。レッド・ホット・チリ・ペッパーズが今年(2022年)春に出したニューアルバム『アンリミテッド・ラヴ』。これがいつまでたっても聴き飽きないからだ。今年ここまでspotifyで仕込んだ数十枚のなかでも断トツによく聴いていると思う。いや、もしかしたらこのまま行くと『母乳』(89)や『ブラッド・シュガー・セックス・マジック』(91)を超えるかもしれない。
これは大変なことだ。なにしろ僕は前期の2枚を愛聴盤にしてきた通り、レッチリがミクスチャー界の雄、明るい暴れん坊だった時期をピークと考えていた。なんだか落ち着いちゃってスカッとしないなあ、いかにも王道で面白くなくなったなあ……とガッカリした最初が『カリフォルニケイション』(99)なんだから、レッチリがニューアルバムを出すと聞いたところで別にワクワクしなくなってからだけでも、もう20年以上!も経っている(今書いていて、気が遠くなりかけた……)。
『アンリミテッド・ラヴ』ももうハッチャけたところはほとんどないし、ミディアム・スローな、じっくり下に沈んでいくような曲ばかり。前作『ザ・ゲッタウェイ』(16)の「シック・ラヴ」のように単体ですぐ身体の中に入ってくる、飛び抜けた名曲もない。しばらくは全ナンバーおなじに聴こえた。
なのに、飽きない。それどころか、他のバンドやミュージシャンを聴いていても、ある程度時間が経つとこの『アンリミテッド・ラヴ』でしか聴けないものが欲しくなって定期的に戻ってくるようになった。過去のいわゆる名盤と同じ事態が起きている。何があったのだろう。
音楽に関しては「ミュージック・マガジン」と「レコード・コレクターズ」の定期購読が切れて以来、情報を仕入れる習慣が本当になくなってしまった。
理由A―両誌の内容が悪いわけではなくて、駅前の書店が約十年前にたたんでしまってからだんだん毎月買いにくくなった。
理由B―識者のレビューを読み、評判なのを知ってから聴く、という順番がだんだん自分でイヤになってきていた。これは音楽に関わらず、なんでも。
理由C―仕事で演歌・歌謡番組の台本を書くことになり、そちらを他の音楽より優先する期間が長かった。仕事にするからには演歌ファンにならなければならなかった。その間の参考資料にしていた雑誌「カラオケファン」や「歌の手帖」は毎月、電車に乗って別の町の書店に買いに行っていたのだから、理由Aはあまり言い訳にはならない。
なので、しばらく聴いた後で『アンリミテッド・ラヴ』がジョン・フルシアンテ(ギター)の復帰作だったのを知った時には、ワッと声が出た。しかもプロデューサーも久しぶりのリック・ルービン。黄金メンバーが揃っていたのだった。
そりゃあいいわけだよ、と嬉しく納得しかけたが、自分で自分自身に対して、それもヘンな話だろう? と思った。初めてレッチリを退屈だと感じた『カリフォルニケイション』以来の、じっくり落ち着いた曲ばっかりなのは変わらないし、年齢的にも本当に落ち着いた大人のバンドになっている。メロウな雰囲気がますますサマになっている。やつらが『ブラッド・シュガー・セックス・マジック』の頃のイケイケであぶなっかしいほど攻めたサウンドに戻ってきてくれた! みたいな単純な話にはなっていないのだ。
ウニウニと考えてきて、ようやく分かってきた。このアルバムの主役は、その演奏そのもの。アンソニー・キーディス(ヴォーカル)、フリー(ベース)、チャド・スミス(ドラムス)にジョン・フルシアンテ。この4人じゃなければ成立しない音がある。楽器を演奏できないからうまく説明できないが、確実にそれ―4人だけの音がある。で、その4人がもう30年以上キャリアを積んでいるのだから、いい感じで枯れてきているのも当然なのだ。
『オレたちひょうきん族』で、ビートたけしと明石家さんまが、カメラの前で楽屋ネタみたいな話をマイクで拾い切れないほど小声でコソコソ言っては、クスクスと笑いあう。その姿がなぜか猛烈に面白いというありかたは、当時けっこう衝撃的だった。
今は、たけしは明らかに気持ちの面でも現役からおりているし、さんまはまだ現役だが仰ぎ見られるポジションになり、周りの空気のほうが全く変わって久しい。ところがこのふたりがたまの特番などで顔を合わせ、コソコソ、クスクスとひょうきん族の頃の話をし出すと、やはり、なぜか猛烈に面白い。そこだけは変わらない。レッチリにも似たところがある。
「不動のメンバー」、「バンドの黄金期」。そんな言葉がどんどん古くなっていったのと、僕が音楽情報を仕入れなくなった時期は重なる。いつの間にか、突出したパフォーマーと音作りの責任者が注目される時代になり、バンドやグループの離合集散や欠員などはそれほど耳目を集める話題にならない時代になっていた。
そんな、ロックも優秀なサポートミュージシャンをそのつどオーディションで集めるプロデュース公演に近くなっている時代に、フルシアンテが戻ってきて、ベストメンバーが揃ったことが話題になり、新作の充実に即つながっているのは、魔法のような話だ。
今年出た宇多田ヒカル、藤井風、チャーリーXCXなどのニューアルバムも僕はそれぞれ楽しんでいる。それらよりレッチリの新作のほうがいい、と言いたいわけではなくて。
このメンバーじゃなければ出せない音を聴く。そんな、いったんは凄まじく古くなった楽しみ方の稀少価値に、僕だけでなく多くの人も気付きつつあるのだと思う。
それは脱退などがあればたちまちに変わってしまう、幾らサウンドプロダクションが高度になっても取り換えが効かないものだ。
まさにその、取り換えの効かなさをテーマにした古い映画素材のリニューアル版が昨年の晩秋、世界的な話題になったばかり。二大天才のジョンとポールが揃っていようが、ジョージがいなくては困るし、リンゴがいなくても困る。それでいろいろとスケジュールが滞ってしまう、ある有名バンドの姿を描いたものだった。
そのこと自体はメンバーが一番よく分かっていて、『アンリミテッド・ラヴ』のセールスに合わせた公式コメントには、こんな言葉がある。
「僕たちのゴールは音楽の中で迷走すること。僕たちは最高のアルバムを作るために計り知れないほど多くの時間を使って、全員、または個人で作品を磨きながらお互いを支えてきた。バンドが同じ場所で共に時間を過ごし、そして更に成長できるための機会を与えられて、本当に感謝しているよ。何日も、何週間も、何ヶ月も、お互いの音を聴き、曲作りをし、自由にジャムり、慎重かつ意図的なアレンジで曲を肉付けしてきた」
フリーののた打つベースと、抑えているのに肉感的なフルシアンテのギター。それぞれソロを勝手に弾いているような音が、チャドのドラムが入ると途端に仲良くなる。
また、別のところではアンソニーがじっくり歌いたいんだから、ここでは俺達リズムに徹しようか、うん、そうしよう、となっている。
さらに別のところでは、えッお前そんな鳴らし方するの、へえ。じゃあ俺も思い切り大きな音出すよ、と追いかけっこのようなことをしている。
聞き役になったり、議論になったり、意見を求めたり。4人が歌唱と演奏を通して、いろんなおしゃべりを楽しんでいる姿を、こっちも楽しむ。『アンリミテッド・ラヴ』はそういうアルバムだ。もはやジャズのそれに近いのかも。
僕は今まるで、クローズアップやアクションつなぎ、俯瞰、またはモノローグやアフレコなどという用語を全く知らないまま映画評を書いているような真似をしている。
なるほど、音楽に通じている方はこう書くのか、と久々に感心したのが、4月にリアルサウンドにアップされた、ライターのノイ村さんによる、「Red Hot Chili Peppersが辿り着いた開放的なバンドマジック ジョン・フルシアンテ復帰作『Unlimited Love』徹底解説」という記事。
https://realsound.jp/2022/04/post-1006670_2.html
例えば、淡々としていてアルバム中で一番地味な気がするんだけど、そこがまた良かったりする、としか僕には書けない「ホワイト・ブレイズ・アンド・ピロー・チェアー」の場合、ここでのノイ村さんは「どこか捻れたサーフロック調」と端的に評している。
そう書いてもらうと、ああそういえば! と気づくところがあるし、カリフォルニア出身ミクスチャー育ちのバンドの背景の奥をもう一段、垣間見えた気になってありがたい。勉強になりました。
ただ、ここまで僕は、フルシアンテが戻るとレッチリ最強、の前提で書いてきたが、実はもう少し話は複雑かもしれない。
フルシアンテ以前のギタリストに、ヒレル・スロヴァクがいたからだ(88年に薬物のオーバードーズで死去)。ヒレルがもともとアンソニーとフリーを「バンドやろうぜ」と引き込んだのがレッチリの始まりだから、結成者、リーダーに近かった。フルシアンテはヒレルの追っかけで、「ヒレルのリフを全部完コピできる」ことがバンド入りの大きな理由となった。アンソニーはかつて「レッチリのギタリストはあくまでヒレル」という主旨の発言をしていたと記憶している。
ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースが大成功していた80年代、「FMステーション」でルイスのこんな内容の発言をインタビュー記事で読んだ。
「ニューヨークのバンドは、テクニックでメンバーを選ぶ。自分達サンフランシスコのバンドは、気が合うかどうかを大事をするんだ。だから一度メンバーが固まれば、なかなか解散しない」
読んだ当時はこっちも高校生なので、なんだかユルい印象を持ったものだが、今となっては人柄優先・相性優先の大切さは、いろんな仕事のいろんな座組みにおいて、痛いほど分かる。
ストーンズはビル・ワイマン脱退以来、ダリル・ジョーンズが不動のサポートメンバーとして30年近くいるが、いまだにベーシストは欠員状態にしている。チャーリー・ワッツの死去から後はスティーヴ・ジョーダンがドラムスを叩いているが、やはりサポートメンバー扱いで、今後も正式なドラマーと発表されることはないだろう。
これからやるぞ、売れるぞ、という時代を共有した者だけが正式メンバーであって、抜けた者がいた後は永久欠番。
これもバンドのひとつの形なのだろう。ギター、ベース、ドラムス(場合によってはキーボードやサックス)によって形作られたものがバンドサウンドという、字義通りの話とは別の価値観がそこにはある。
つまりアンソニーやフリーにとっては、フルシアンテも実はまだ正式メンバーではない。そういう気持ちが最近まで残っていたかもしれないのだ。
先に引用したバンドの正式コメントを、もう一度読んでみよう。
「バンドが同じ場所で共に時間を過ごし、そして更に成長できるための機会を与えられて、本当に感謝しているよ」
よく考えてみれば、結成が80年代の超ベテラン・バンドが一体何を今さら、と驚くほど初々しいコメントだ。
しかし、もしかしたら。
脱けたり戻ったりが続いたがその間もずっと仲間だったフルシアンテが、今回のセッション、レコーディングで、いよいよレッチリにとって欠かせない存在なのが分かったのかもしれない。
先のコメントが初々しいのは、やっとフルシアンテこそが正式のギタリスト、と4人で確認しあえた喜びを語っているからなのかもしれない。そう想像してみると、ずいぶん納得はできるのである。
いろいろ想像させる人間関係が、個別の神話的ストーリーにまでなるのが一流のロックバンド。
そういう意味では、レッチリはまさにアメリカン・ロックの王道なのだ。
これはどのバンドにも当てはまる話なので(もっと言えば、大衆芸能のトリオやコンビもみんなそう)、あれもこれもと思い浮かべだすとキリがなくなる……というところで話をそろそろ終わらせようと思う。
やはり春に出たムーンライダーズの『it's the moooonriders』が、僕にとっては今回のレッチリとは好対照で、なかなかの問題作だったりする。
昔ッからバンドらしくなくて、「俺達」という言葉が一番似合わない、たまに集まる醒めた不定期ユニットという印象のあったライダーズが、久々のニューアルバムでもやっぱりそう。ふだんはお互いのケータイ番号も知らないんじゃないかぐらいのバンドらしくなさ。なのにある旋律になると、ああ、ライダーズだ、となる。バラバラのコーラスでも、この人達らしいなーとなる。
バンドの数だけ人間関係があり、音も違ってくる。結論は実はそんな、いたってシンプルなことかもしれない。
ここまで書いて「フルシアンテまたレッチリ脱退。アンビエイト・ミュージックに専念したくなったのが理由」なんてニュースがもしもあったら、今度はちょっと笑える気がする。










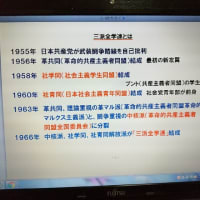
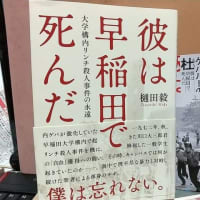






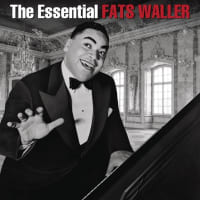

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます