
プログ内連載「試写で見た映画」の更新。
今をときめく人気監督・濱口竜介の新作を見せていただいた。
『悪は存在しない』
2024年 NEOPA/fictive
監督・脚本 濱口竜介
配給 Incine
https://aku.incline.life/

この映画を見てからつらつらと頭に浮かんだことを書いていきたいのだが、長くなるだろう割にはたいした感想文にならないことは前もってお断りしておきます。
謙遜や予防線ではなくて、単純に僕が、これまで濱口竜介の映画をろくに見ていないから。作家主義の観点からの解析が特に求められる人なので、その時点でアウトなのだ。
劇場公開されている主な長編作品(カッコは製作年)を、自分でも確認してみると―
『PASSION』(2008) 見ていません
『親密さ』(2011) 見ていません
『なみのおと』(2011) 見ていません
『なみのこえ 気仙沼』(2013) 見ていません
『なみのこえ 新地町』(2013) 見ている
『うたうひと』(2013) 見ていません
『不気味なものの肌に触れる』(2013) 見ていません
『ハッピーアワー』(2015) 見ている
『寝ても覚めても』(2018) 見ている
『偶然と想像』(2021) 見ていません
『ドライブ・マイ・カー』(2021) 見ている
ひどいもんだ。
しかも、〈東北記録三部作(計4作)〉のうち1本は見ていたものの、それがどれか、フィルモグラフィを確認した今の今まであやふやだった。
藤原智史監督・加藤孝信撮影の『無人地帯』(2011-2014公開)はまず際立った筆頭として、東日本大震災の被災地を取材したドキュメンタリー映画はどれも真摯に拝見したい心境の時期だったのに。
なんとか思い出してみると、あまり好い印象は持たなかったことまで思い出してしまった。
被災者に話を聞く時の、聞き手の相槌がうるさいのだ。
今の日本の頭のいい人って子どもの頃から、答案回答や課題理解のスピードを競わされる場でなまじ勝者になり続けてきちゃったので、どうしても「うんうん、ハイハイ」の相槌がやたらと早くて多くなりがちだが、その早呑み込みをずっと聞かされる。聞き手が監督なのか誰なのかは分からないけれど。
それでなんとなく、他のも見ておこうという気持ちが消極的なままになった。独創的な撮影が話題になったのは、僕が見たものではないらしい。
『ハッピーアワー』にしても、2017年にCSで放送された時の録画を、去年(2023年)の年末に見るまでほったらかしにしていた。濱口竜介監督作品をろくに見ていないというより、興味がなかった、のほうが正しい。
急に『ハッピーアワー』を見ることにしたのは、昨秋、『マリの話』(2023)を監督した高野徹さんとご挨拶する機会があり、その高野さんが『ハッピーアワー』の助監督だったと初めて知ったから。
『フィルムメーカーズ24 ホン・サンス』(2023 オムロ)に僕が寄稿した文を高野さんは読んでくれていて、なのに僕が『ハッピーアワー』をスルーしたままなのは申し訳ない……と思ってだった。もちろん、現在も上映中の『マリの話』を見て、掌編がつながっていくうち話法まで変わっていく作りのユニークさに感心したのもある。
その『ハッピーアワー』がずいぶん面白くて。才人なのがようやく分かってきた。
才人といっても、持って生まれた才気やセンスを活かせる場に恵まれているうち、枯れてしまわないうちにワッと出す、というタイプではなく。方法論などをいろいろ慎重に検討し、実践することで、なぜ自分が選んだのが映画なのかまで毎度一緒に問い直していくタイプ。その手間を惜しまない粘りに恵まれたろう人、という意味だ。ここには、早呑み込みで済ませているところがまるでない。
こういうタイプの人なら先述のような、僕にはどうも……となってしまったドキュメンタリーがあるのも理解できる。ふつうに粛々と撮って粛々とつないでくれさえすれば、自ずと見応えのあるものになるはずの題材・テーマで外すのは、それなりのスケールがないと逆に難しい。
これまで興味がなかった反動で、1冊まるごと作品論になっている三浦哲哉『『ハッピーアワー』論』(2018 羽鳥書店)も読んだら、見事な構造・細部の分析が、映画の持っている魅力をどんどん発見させてくれるもので、ますます楽しい思いをさせてもらった。
最近、寺本郁夫さんが講師をつとめる映画講座を受講して、自分がいかに美学的に映画を見ることに興味が薄いか、がよく分かったのもあって(大まかに言うと、僕は佐藤忠男さんが基本になっている人間でして、蓮實重彥先生が何を言っているのか常によく分かっていないのです)、ああ、そういう風に映画を見るのも面白いんだなー、とずいぶんタメになった。
そんなわけで、三浦哲哉さんの本のおかげで『悪は存在しない』に臨む心構えがちょうどできた状態になり。
さあ、話題の新作で、人物とストーリーを密接にしているものは何か? どんなところで、映画が「心理」を描くためにしばしば因果関係にこだわり描写を鈍重にしてしまう欠点を、「運動」や「変化」が「心理」に先んじることで乗り越える瞬間が訪れるのか? などと、身構えるような気持で試写室に入れてもらった。
結果的には、特に難しいことはなかった。拍子抜けするほどだった。
ストーリーも、事前に予習しておかなくても別にいいでしょう。あらすじに書いてあるようなことは、誰でも分かるように画面上で起きて、途中でややこしくなったりせず明瞭に進行する。
濱口竜介の新作なのだから、海外で大きな賞を獲った作品なのだから……と細部に仕掛けられた暗喩や徴候をがんばって探しながら見なくてもよい。だるまさんころんだのカットも、あれはまあ、ファンサービスみたいなもので、だるまさんころんだ以上の意味はない。
おそらくかなりの人を戸惑わせる終盤の展開も、むしろ、ふつうに見ていたほうがそんなに驚かなくて済む気がする。
『偶然と想像』などを見ていないうえで言うが、僕は『ハッピーアワー』の姉妹編、或いは後日譚のような気持ちで『悪は存在しない』を見た。
『ハッピーアワー』は、出てくる男達が揃いも揃って虫の好かない奴等なところが、妙に痛快な映画だった。溝口健二のように。
溝口健二の映画は、旧弊な社会に虐げられる女性をリアリズムで描いたことで名高いが、よくよく考えればその要素の多くは、日本の男達がどれだけ弱くてずるくて女に甘えているか、その無様さのほうを容赦なく執拗に描くことで間接的に成り立っている面があった。
なんというか、台所でネギを切る音を僕らが聴覚で捉え、ネギが台所で切られているな、と認識する時、その実体は、ネギの繊維が包丁の刃によって寸断されるそのものの音でなく、刃がまな板にトントントンと当たる音のことだったりするのに近い。
4人の女性が主人公の『ハッピーアワー』にも、男達がことごとく俗物的か「空っぽ」だから、その反射として彼女達が活き活きとならざるを得ない、というところがあった。
そんな、俗物的か「空っぽ」な男達ばかりが『悪は存在しない』には出てきて、しかも女性による反射をほぼ許されない(初期のホン・サンスの映画のように「男ってしかたない生き物ね」と苦笑まじりに許される逃げ道が与えられない)と、どうなるか、を見ていくのが僕には面白かった。
誰が俗物的で、誰が「空っぽ」なのかは、見る人の解釈次第。そういうポイントで見ていくのもありだと思います。
ここからは、終盤の展開を具体的にあかすのは避けつつ、あくまで僕なりに考えたことを書いていく。見る前にあんまり仕込みたくない方は、また後ほど覗いてくださいませ。
……といっても、今まで明かしたように、僕にはまともな濱口竜介作品の評は書けない。
むしろ、『悪は存在しない』について書かれる評のなかで、一番あさっての方向を向いて一番映画評らしくない、トンチンカンなものでありたい希望さえある。
このブログで先日書いた『PERFECT DAYS』(2023)の時と同じように、他の人の感想や評を目にしないうちにこれを書いてしまいたいのだが、「静謐な自然と人の物語のはてに神話的世界が現れる」式の短評がオーソドックスなものになるだろうことは、大よそ想像がつく。
それはそれで結構なことだ。「神話的世界」って高尚な雰囲気の言葉は確かに似合うし。ただ、もしも似た角度の声ばかりになったら、なんかさ、寒い山のなかでロケした作り手に対して悪いじゃないですか。
濱口竜介の映画について、高尚なクリティックの感じでなく書き、しかも作り手の意図とはかなり離れた解釈もしていく、何の役にも立たない作業は、誰かがやっといたほうがよいのです。
で、『悪は存在しない』の観賞ポイントになるのではないか、とさっき書いた、『ハッピーアワー』の俗物的で「空っぽ」な男達は、ここでは誰になるのか、という話の続き。
僕は、静かな高原の町にレジャー開発の話を持ち込んで波紋を呼ぶ、いかにも俗物代表の役回りを演じる高橋(小坂竜士)が、「空っぽ」だとは感じなかった。
そこはこの映画がゲーム的に仕掛けた、都会の男=軽薄、自然に生きる男=中身がある、の図式に揺さぶりをかける初歩的なミスリードだと思う。
なぜなら高橋は、自分の俗っぽさに日頃からイヤになるほど自覚があり、同僚の女性(渋谷采郁)の言葉にいちいち真っ当に反射して動揺し、人生まで考え出しちゃうからだ。すこぶる善い部類の人間じゃないですか。
では『悪は存在しない』で、「空っぽ」に該当するのは誰なのか。
僕が、『ハッピーアワー』の鵜飼に該当するな、と思ったのは、あの人です。
鵜飼は、名字のように鵜飼いのごとく、女性達を挑発し、変化のきっかけを与え続ける側にいることで自身の「空っぽ」さ=成長のできなさを隠ぺいし続ける。妙に、若いうちから講師やコンサルタントの立場になりたがる人っているが、ああ、こういうことね、という感じ。
『悪は存在しない』のその人は、自然と一体となったような静かな生活と寡黙さで、重みと内実を感じさせるような雰囲気を周囲に与えながら、自身の「空っぽ」さ=成長のできなさを隠ぺいし続けている。若いうちからスローライフに凝っているのになぜか逆に面白みのない人っているが、ああ、そういうことね、という感じ。
鵜飼は、ワークショップの講師から本格的な教育者・文化人としての役回りを求められるようになった時、その場その場で適当なことを言って逃げる。なにしろ「空っぽ」なので、メフィストフェレス的な謎めいた余韻を残し、かえって自分の印象を上げているところがうまい。
森の生活をよく知る者と遇されてきたその人は、都会からやってきた連中との折衝役を望まれ、語ることの辻褄が微妙に合わなくなり、それが都会人に露見しかけた時に、唐突な行動に出る。唐突と思わせるほど巧みに「空っぽ」なのを隠しおおせていた、とも言える。
やはり「空っぽ」なので、そこにまるで中上健次の小説のような、自然の大きさに人間が直面した時の摩擦として奔出する暴力……などと一席ぶちたくなる後味を残すことができる。
それにしても、いい場所でロケしているなあ、と思う。見ていて目が懐かしい。
実家の母が祖父の土地を相続し、叔母らと一緒に管理している山が、湧き水のまわりにワサビが生え、鹿もよく出没する、よく似た条件の土地だからだ。中学高校の頃は、やはりこの映画と同じようによく薪割りをさせられた。
山を舞台にした母と鹿の戦いは、どこか漫画的だ。母は、植えた苗木を鹿に夜中に食べられないようネットを張り巡らせ、鹿は工夫してネットの隙間をかいくぐる。その攻防を昔からトムとジェリーのように繰り返している。
「食べられたらもうアッタマに来て、見つけたら石投げてやるんだけど、鹿はぜんぜん動かないでねえ、こっちジローッと見てるんだ。このバアさんが石を投げてもここまで届かないぞって、見抜かれてるんだわ!」
なので、もしも施設が出来たとして鹿対策はどうするかを巡るディスカッションは、見通しの甘さが僕にも察せられるのも含めて面白かったし、また、夏場に撮られたなら内容も雰囲気も全く違っただろうな……とも感じた。
『悪は存在しない』が夏場に撮られたら、非常に魅力的なファーストカットは生まれなかった。
細やかな放射線状の黒い模様が幾重も重なりながら、手前は大きく、奥は小さく動いていく。次第に、冬の山を見上げながら歩き、枯れた枝々を見ている視点なのだと分かる。数枚の絵を密着させて少しずつ動かす、昔のセルアニメーションのマルチ撮影のようだ。これだけで映像作品になるほど美しい。
作り手はこれをオープニングに据え、物事は幾重もの事情が重なっているもので、数歩歩いて視点をずらしただけでも変わっていく。そういうものだ(村上春樹調)、とあらかじめ映画の中で起きることを予告している。夏の山で同じ枝々を同じアングルで撮ったら、繁った葉の生命力が画面を圧倒して、テーマさえ変えてしまう。
山は、夏と冬ではまるで表情が変わる。『悪は存在しない』の山も、夏はきっと素晴らしいでしょうねえ。濃い緑、淡い緑がずっと折り重なり、鳥の鳴き声があちこちで響き、清涼さにそれこそ心が洗われるような思いがするだろう。そしてその分、僕がこの映画で「空っぽ」の役回りだと感じた人の隠ぺいは、冬よりも苦しくなるだろう。
ここでちょっと話題を変える。
これまで僕は、三浦哲哉『『ハッピーアワー』論』の他にはしっかりした濵口竜介の作品論・監督論を読んでいないのだが(そこは不勉強で恐縮)、それでもSNSなどで、濵口竜介の映画は意外と難しくなく、構えずに見ることができるものではないか、という声を幾つか見てきた。僕もそう思うし、そこにこの人の大器を感じている。
現代の若手・中堅監督のなかでもとび抜けた国際的評価を得ている人なのだから、さぞかし作品も芸術的で難解だったりするのだろう……という予断を、あっさり裏切るからだ。見やすいからかえって戸惑う。
ここでさらに違う話を。
『『ハッピーアワー』論』の幾つもある読みどころのなかで、いやあ著者の三浦さんは凄い見識の人だ、読ませてもらえてよかったな、と僕が特に感じ入ったのは後半の、現代日本映画の先端をいく数本の映画にまで論が及んでいくあたりだった。
『ハッピーアワー』やそれらの映画は、「映画作りの方法論を一から吟味し直すことを自らに課し」、そのために「おそらく、そのとき作品は、表面的には貧しくなるだろう。ジャンルの伝統に根差すことで得られる充実には、あえて背を向けられるからだ」。
この一文には唸った。
メジャー会社が自分のスタジオと社員、契約スターで作った時代の旧作邦画、いわゆるプログラム・ピクチャーを見る時の楽しさ、マニエリスムの成熟した技術を隅々まで楽しむ喜びに浸かっている間は、現代の日本のインディーズ映画は確かに安っぽく見えてしまう。
しかし、現代の日本のインディーズ映画の意欲的な部分に触れ、刺激されている間は、昔のプログラム・ピクチャーの決まりきった物語や演出のパターンはどこか他人事でまだるっこしく感じられてしまう。
映画好きな方の多くが、一度ならず感じたことのあるジレンマだろう。しかしその断絶にも意味があるのだ、とこんなに見事に説いてくれる文は、僕は初めて読んだ。
そうなると、企業によるマニエリスムの成熟が始まる寸前の時代の映画が与えてくれる、ソワソワさせる魅力―例えば『浪人街 第一話 美しき獲物』(1928)の、DVDで8分の残存部分を見られるだけでも、まるで今のインディーズ映画の尖ったやつみたい! とダイレクトに感覚がつながってしまうロケの生々しさ―にも、ちゃんと理由が付くのだ、と分かってくる。
(『『ハッピーアワー』論』でどんな映画が挙げられているのかは、ぜひ本をお読みください)
そんな、一からの取り組みを続けている現代日本映画最前線の監督のなかで、濱口竜介は、既成の映画のフォーマットの解体ではなく、語り方、文体の洗い直しを指向している。
「どう語るか」を自分の納得いくようにアップデートしたいのだから、「なにを語るか」自体はむしろこれまで人々が馴染んできたドラマの作劇に則ったほうがよい。それで、濵口竜介の映画は意外と難しくない、という印象になり、自ずとかつてのプログラム・ピクチャーに似てくる。(そこはクリント・イーストウッドがそのつど多彩な「ジャンル映画」を作り続けてきたのに近い)
そして、にも関わらず似ていない、はみ出すところこそが、今、濱口が作り、撮る必然として鮮やかに浮き出てくる。
つまり、こんな言い方もできてしまえる。
『ハッピーアワー』は、実は『ニッポン無責任時代』(1962)のリメイクだ。万事調子よいが内容のない平均(たいら・ひとし)の無責任男振りは、鵜飼の「空っぽ」さに受け継がれている。
『悪は存在しない』は、実は『花咲く港』(1943)のリメイクだ。その後のローカル喜劇のロールモデルになった、詐欺師のコンビが地方の島にやってくる筋立ては、いい加減なレジャー開発計画を携えてやってくる芸能事務所コンビに受け継がれている。
日本映画の伝統が、過去のメジャーと現在のインディーズとの間ではほぼ断絶した後のリメイクだから、リブートのほうが適切かもしれない。
(『寝ても覚めても』で僕が驚いたのは、仲本工事が震災の被災者の役で登場することだった。ザ・ドリフターズの映画でのパターンを固めた『やればやれるぜ 全員集合! !』(1968)は、東北から上京してきた若者達の奮闘劇だった。それを強烈に思い出させたからだ)
もっと言うと、実は僕が『悪は存在しない』を見ていて特に連想した映画は、『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』(1967)だった。
今ちゃんと見比べたら、画面上はまるで共通点はないだろうが、この映画も前半、高速道路工事を進める公団側と、立ち退きを拒絶する山村の人々の間の対立が描かれる。
それがそうスパンと割り切れたものでなく、公団側にも善人がいたり、村のなかにも賠償金を吊り上げる目的で表面上は反対する者がいたりと、子ども向けの怪獣映画としては少し異例なほど、綾のあるローカル喜劇が展開されるのだ。(そして後半は、村の周囲ごとガメラとギャオスの戦いの舞台となる)
そう、昔のよくできた怪獣映画やパニック映画は、怪獣が本格的に現れたり大災害が起きたりする前の、日常描写も細やかな場合が多かった。そのほうが、こんなにいい人が、あんなに仲のよかった家族が……!とスリルとサスペンスを増幅させるので、工夫としては当然だ。
その手のジャンルの映画がよくテレビ放送されていた小学生の頃、片ッ端から見ているうちにだんだん、大きな「前振り」としての序盤の日常ドラマのほうが好きになってきた。異変がジワジワと迫るようになってくると、ああ、もう終わりか……とガッカリするようになった。そういうかたちで僕は自然と、その手のジャンル映画一辺倒から卒業している。
ここまで連想を広げてみてようやく、僕は『悪は存在しない』を、〈怪獣の出ない怪獣映画〉、もしくは〈怪獣が出る前の怪獣映画〉としても見ていて、それが、こうして粘って書いておきたくなる理由になっていたことに気付く。
昔のよくできた怪獣映画は、序盤の日常のなか、異変にいち早く気付くのは子どもである場合が多かった。そして、その子どもが怪獣と感応し合ったり、怪異の秘密に触れたりする。
『悪は存在しない』の少女は、『ハッピーアワー』の女性達のように男達と反射し合うことはせず、学童保育を出た後は、もっぱらひとりで山の中を歩く。彼女は、周囲の大人達、それに僕ら観客よりずっと前に、すでに何かの予兆に触れているのだ。
以前、『祭の馬』(2013)という、元競走馬を主人公にしたドキュメンタリー映画があった。
この元競走馬は、福島県南相馬市で引退後の余生を送っていたのだが、震災の影響で住処を次々と変えざるを得なくなる。この馬の流転の日々を通して、国や行政の混乱などを浮き彫りにしていくものだった。『バルタザールどこへ行く』(1966)の、震災後の日本版という切り口で見直してもらってもいいだろう。
この『祭の馬』の画面の端々で、湯気を出した馬糞が映る。
馬糞は、牧草地で虫に分解されれば土の栄養になって土地を肥やし、自然のサイクルの一端を担えるのだが、アスファルトの上に集められると分解もしてもらえない。ただ臭いだけの、嫌われものとして邪険に扱われる。
この馬糞の湯気が、元祖・産業廃棄物として、福島第一原発が水蒸気爆発を起こした直後の煙を連想させるところが、『祭の馬』の細部の見どころとなっていた。
どうして急に、10年前に公開されたドキュメンタリー映画に映る馬糞を思い出したかというと。
『悪は存在しない』に牛糞が出てきたからだ。一ヶ所に集められた牛糞の山を、少女はひとりでじっと見て、鼻を押さえる。牛糞の山は、もうもうたる湯気を立てている。土中の虫に分解してもらえず、元祖・産業廃棄物として嫌われる牛糞の湯気と臭気は、いつその怨念を実体化させ、怪獣になってもおかしくないのだ!―『悪は存在しない』が、〈怪獣が出る前の怪獣映画〉ならば。
「戦後の怪獣映画には、人類の未来に対する不安が影を落としている」
『新映画事典』(1980 美術出版社)のなかで石崎浩一郎が書いている一文が、僕が怪獣映画を捉える時の基本になっている。(といってもこの、レベルが異常に高い映画論・映像論が高密度に詰まった事典を僕はつまみ読みしかできていない。ちゃんと全部読んだら、僕も映画批評家になれるのではないか……と思うほどの本だ)
この「人類の未来に対する不安」は、時々、さまざまな形を伴って的中する。
冒頭で、東日本大震災の被災地を取材したドキュメンタリー映画のなかでも突出した作品として触れた『無人地帯』。
ここで見せられる津波の後の光景には、レンズが捉えた以上のものがあった。僕のなかには〈怪獣の出ない怪獣映画〉、もしくは〈怪獣が出た後の怪獣映画〉をドキュメンタリーで見ることになってしまった……という恐怖に近い感動があったのだが、当時はそのままを文字にはできなかった。決してスペクタクル映像として楽しんだわけではない、もっと霊的経験に近いことなんだ、と説明するとかえって誤解を招きそうで。
『悪は存在しない』について書いていくうち、自分でも、思いがけないタイトルが次々と出てくることになった。
でも、こうして自分のなかで(怪獣映画というジャンル映画の概念を通した、自分だけの納得ではあるけれども)、『無人地帯』と濱口竜介がつながったのは感慨がある。
濱口竜介の新作は、ドキュメンタリーから離れ、まるで違う題材を描いても、それでも「震災後の映画」(『『ハッピーアワー』論』)だった。
そして今後もおそらく、どんな映画を作ったとしても「人類の未来に対する不安」を無視・軽視したものにはならないだろう。
さらに言えば。僕はいずれ、濱口竜介という人は「映画監督としても知られる思想家」になるのではないか、と予想している。
自分の頭のよさに飽きがきている人、という印象を持つからだ。
言葉が乱暴だとすれば、自分の頭のよさに常に満足できず、検討や叩き直しを重ねていないと落ち着かない人、と言い換えてもいいかな。
かつてのプログラム・ピクチャーの担い手となった監督は、高学歴で高い教養を持つ人が多かった。鎌倉アカデミア出身の鈴木清順、東大文学部在籍中はギリシャ悲劇研究会を主宰していた中島貞夫……などなど例を挙げ出したらきりがないが、ともかくそういう人達が、量産される娯楽映画のために持てるものを注いだ時代が、確実にあった。
濱口竜介はその道をある程度は踏まえながら、いつかはそこに留まらなくなるだろう、と考えるのだ。
映画をたくさん見て、語り、作る側になるのは、今までのように一流の映画監督・映画人や論者となり、そうであり続けるため、ではなく、映画をたくさん見て、語り、作る営みを通じて、より善く生きる人になるため。
そんな、僕が理想とする価値観の時代をつくる先行ランナーになってほしい……という願望込みである。
映画監督なんかにしておくのは勿体ないよ! と言っているのと同じなので、本人にとっても関係者にとっても、映画好きな方々にとっても迷惑な、まさにトンチンカンな結論です。










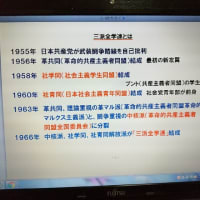
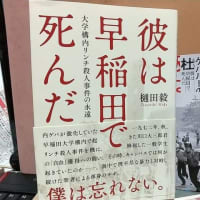






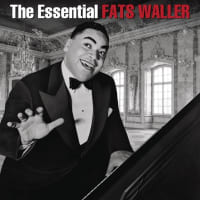

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます