『ストーミー・ウェザー』という、1943年製作のアメリカ映画をご存知ですか。
当時人気の黒人エンターテイナーが多数出演した音楽映画で、すこぶる付き!の楽しさ。僕が今まで見てきた音楽映画、ミュージカル映画のなかでも上位に入るだろう。
ただ、黒人兵の慰問のために作られた映画であり、その楽しさの大部分は有事国家の要請に基づいていることが端々で分かる。甘い/からいの味わいが二重構造になっている。
メモしておきたいことがいろいろ出てくる映画で、SNSでは長くなるのでブログに。
(「黒人」ではなく「アフリカ系アメリカ人」と書いたほうが適切かと考えましたが、「白人」と「黒人」の社会的な差がはっきりしていた時代の音楽と映画の話なのもあり、「黒人」で通しておきます)
見ることになったきっかけから書いていこう。
去年(2023年)の秋に出版された、娯楽映画研究家・佐藤利明の『笠置シヅ子 ブギウギ伝説 ウキウキワクワク生きる』(興陽館)を最近になって読んだ。
SNSでいつも楽しそうに発信している佐藤さんらしく、惜し気なく情報を盛り込んだ本。笠置シヅ子の評伝でありつつ、笠置と服部良一のコンビがいかにアメリカの最新サウンドを咀嚼し、国産化させてきたかの記録にもなっている。
この本によると、笠置シヅ子は戦前、本格的にレコードデビューする前からステージで「セントルイス・ブルース」やファッツ・ウォーラーの「浮気はやめた」などをバリバリ歌い、客席にいた若い頃の瀬川昌久や双葉十三郎をコーフンさせていた。
それにアンドリュー・シスターズ、ライオネル・ハンプトン、デューク・エリントンらのレコードや譜面がどれだけ服部良一の血肉になったか、という話も次々と出てくる。
僕は、他の全てのジャンルと同様、ジャズもとにかく半可通だ。それでも、ちょうど去年はミルドレット・ベイリーやホーギー・カーマイケルの中古LPを手に入れたり、spotifyでビックス・バイダーベックにしばらく凝ったりして、戦前の白人ジャズにある程度は気が行くようになった。この流れで、なぞる程度だった戦前の黒人ジャズにももうちょい親しみたいと思っていた。
そんな時に先述の本を読んで、これは良いガイドをしてもらえたと、さっそくファッツ・ウォーラーなどをspotifyで聴き始めていた。
そうするうちにファッツの動く姿も見たくなり、出演している映画『ストーミー・ウェザー』の配信に行き着いたのだ。
『ストーミー・ウェザー』の主演はタップ・ダンサーのビル・ロビンソンで、自身をモデルにした人気ダンサー・ビルを演じている。
彼が、近所の子ども達に自分の芸能人生を話して聞かせるなかに、レナ・ホーン演じる歌手とのロマンス、ファッツ・ウォーラーやキャブ・キャロウェイ(どちらも本人自身の役)らとの交流が描かれる。筋立てはシンプルにして、とにかく歌と芸をみっちり詰め込んでいる。
これが、どれも見事で貴重なパフォーマンスの記録になっていて、かなりの厚みなのだ。ショービジネスを舞台にしたドラマで、歌や芸の披露=ほぼ本人達のステージの再現である効果が大きいだろう。
1988年に日本で劇場初公開された時は、今とはケタ違いにマメに映画館に足を向けていた頃なのに、スルーしていた。ハタチ前後にとってはセールスポイントが渋過ぎた。
面白みが色々と分かるようになってからの初見で良かったなー、と思うが、予備知識なしでいきなり見てガツンとくる体験だって良かっただろうな、とも思う。映画もレコードも本も出会いのタイミングは運命。人と同じだから、なんとも言えない。
なにしろ多士済々の映画なので、一人ずつメモしておきたいことを。レナ・ホーンについては名前を知っていただけで、魅力的な人だと今回初めて知った程度なので割愛させてもらうとして。
〈ビル・ロビンソン〉
並み居るビッグネームを押しのけて主役になっているのは誰だ? と事前に検索してみて、アッとなった。通称、ミスター・ボージャングルス。「タップの神様」。
ジェリー・ジェフ・ウォーカーが作り、ニッティー・グリッティー・ダート・バンドがヒットさせた「ミスター・ボージャングルス」。ジャズの数倍はカントリーロックに胸を焦がせてきた僕にとって、世界でいちばんステキな曲(のひとつ)。この曲のモチーフになった人の映画なのだ。望外のことですっかり嬉しくなった。
ただし、ロビンソンのダンサーとしての全盛期は、ニューヨークのコットン・クラブに出ていた1920年代らしく、この映画に主演した時は還暦を過ぎている。
キレキレのタップを存分に見られる……わけではないのは、しかたない。それでも〈自分の芸能人生がモデルの映画〉が作られるのだから、当時の格は察せられる。
〈ファッツ・ウォーラー〉
古いジャズのガイド本を何冊かめくると、「ジャズ・ピアノの基本を作った偉人のひとりだが、コメディアンとして遇されるほうが多かった」と、ほぼ異口同音に、真価が認められなかった人生を惜しむように書かれている。
戦前の才能ある黒人パフォーマーは、白人が安心できるよう笑顔で道化を演じていないと仕事の場が広がらなかった―もはや常識に近いことだ。戦後デビューのマイルス・デイヴィスは、オレがつっぱった態度を通したのは、先輩達の時代の反動なんだよ、という話を自伝で打ち明けている。
ファッツ・ウォーラーも、とぼけた笑顔で愛されることで白人社会で多少評判になっても許されたひとりなのだろう。サッチモ=ルイ・アームストロングやルイ・ジョーダンのように。
ただ『ストーミー・ウェザー』での、「浮気はやめた」をしみじみ歌いながら自分のバンドをだんだん乗せていく名場面を見ると、落語の師匠のような貫禄はたっぷりだが、卑屈な雰囲気は全くない。
「ジャズマンは見せるのも、客を笑わせるのも商売」だと言われるまでもなく分かっているし、それと人種の問題は別という、根っからの芸人気質を感じる。
むしろ、キャリアからしたら日本のフランキー堺やハナ肇の先輩という感じだし。
大柄な体格のキャラクターとピアノのストライド奏法(右手でメロディを弾き、左手はベース音となるコードを往復する)はそのままR&B世代のファッツ・ドミノに受け継がれたと考えれば、ロックンロール世代のおじいちゃんとも言える人だ。
ずいぶん前、仕事で会ったエド山口さんが「僕らは難しいフレーズほど、ついでみたいに笑って弾くんだ」と言うのを聞いて、(これがクレージーキャッツからつながる、東京の音楽の笑いの精神か)と感心させられたことがある。
僕は、ロックやジャズ=シリアスの価値観で生きてきた時間が長いので、まだどうしても、笑いながら弾く=コミックバンドと連想するクセが抜けきらない。
『ストーミー・ウェザー』での、ファッツ・ウォーラーと彼のバンドの小粋なかっこよさには、求道者みたいな顔をして深刻に吹くマイルスやコルトレーンのほうが実はユーモアのセンスがなくてダサいのだ、とまで思わせるところがある。なかなか楽しい戦慄だ。
〈キャブ・キャロウェイ〉
初登場の場面。子ども達がすぐに気付いて「あッ、キャブ・キャロウェイだ!」と叫ぶ。すると本人も「ハイ・デ・ハイ・デ・ホー!」と応える。
名刺代わりの人気フレーズをすぐにやって、紹介の手間はおしまい。なんつう話の早さ。この映画の中で特におかしくてハッピーな場面だ。
キャブの当時の人気は本当に凄かったんだな、と随所で分かる。仲間のビルを盛り立てる役どころなんだけど、盛り立てる姿のほうがどうしても目立つ。それだけのオーラがある。
派手なステージ・パフォーマンスの元祖みたいな人だから、「ジャズマンは見せるのも商売」に関しては、ファッツ・ウォーラーよりもよく分かっている人だろう。
なので映画への進出も早く、1930年代のうちから、パラマウントを創設したアドルフ・ズーカーの指揮下で複数の短編が撮られたり、クネクネした踊りをセル画にトレースされてベティ・ブープの短編アニメで使われたりと、ルイ・アームストロングに次ぐ成功を収めてきた。
ちなみに、キャブのダンスをベティさんがフィーチャーしたうちの1本で、幽霊がブルージーに歌い踊る「ベティの白雪姫」は、あんまりのブキミなかわいさで、世界のアニメーションの歴史に残る作品になっている。僕も初めて上映会で見た時は電撃的ショックを受け、しばらくフライシャー兄弟のアニメに凝ることになった。
〈ニコラス・ブラザーズ〉
ここまでレジェンドのことを書いてきたが、彼等をまとめて食ってしまうのが、終盤のこの二人によるダンスだ。
タップが基本だが、そこにもう留まってはいられない、という感じで跳び回り、アクロバットなダンスを披露する。今の目で見ると、ステップや動きのあちこちがヒップホップダンス。
僕が今までよく知らなかっただけで、ダンスの世界では別格の存在なのだった。晩年になってからは、ジャネット・ジャクソンに乞われてPVに特別出演している。
他にも、キャサリン・ダナム率いるモダンダンスのチームが幻想的な場面で踊る(ミュージカル映画のなかに芸術的なダンスが織り込まれることでは『巴里のアメリカ人』より早い)など、見どころは本当に満載だ。
『ストーミー・ウェザー』は、第一次世界大戦が終わって除隊したビルが、ミシシッピーの遊覧船でジャグ・バンド(洗濯板などで演奏する)と出会ったり、メンフィスのビール・ストリートで職を得たりしていく展開が、実にうまいことジャズの発展史をなぞっている。
ジャズの最初のメッカだったニューオリンズは、アメリカの第一次世界大戦参戦によって軍港に指定されてから風紀取り締まりが厳しくなり、演奏者の多くがメンフィスやシカゴ、ニューヨークへ移り住むことになったからだ。つまり、戦争がジャズを各地に広めたのだ。
そうするうちにビルは、主要なジャズ流出地のひとつ、ニューヨークで頭角を現したキャブ・キャロウェイと仲間になる。
キャブは映画のなかで当時の最新サウンド、スイングやブキウギをもっとうねりのある、ビートを強烈にしたもの―ジャンプ・ミュージックとも、R&Bの元祖ともいえるもの―を披露している。そして(これは映画の創作だろうが)息子が第二次大戦に応召され、凛々しい新兵さんになったことを喜んでいる。
1本の映画のなかで、南部のジャグ・バンドからニューヨークのジャンプ・ミュージックまでの道のりを駆け足で見せる趣向。
スムーズにまとめるのは、作り手にかなりの音楽的素養がなければ難しいと思う。映画を作るたびにその題材への深い理解を求めるのが酷なのだとすれば、センス、カンどころを掴む才能、と言い換えてもいい。いいのだが、そっちのほうがコツコツ勉強するよりもずっと厳しいかも。
時系列に合わせて、演出のタッチを微妙に変えているのがうまいのだ。映画の前半はゆったり引いたサイズで演奏を撮り、それこそ古い時代の映画風。
しかし後半、キャブが髪を振り乱して当時の最新サウンドで踊る後半では、シャープな構図を挟み、早いカット割りをまぜ、まさに現代の映画にする。
監督のアンドリュー・ストーンは、かなりの才人ではないだろうか。IMDbのバイオグラフィを読むと、この『ストーミー・ウェザー』が出世作であり、いちばん評価された映画らしいのだが。
さて、こうして『ストーミー・ウェザー』を楽しく見ているうちに、さすがに僕も、白人がほとんど出てこないことに気付いた。
この理由については公開当時に書かれた、野口久光の文章がある。
知らないシネフィルの方も多くなったかもしれませんが、僕が中学生の頃は、野口久光さんといえば、戦前から戦後にかけて映画を作る/宣伝する/語るの三刀流を極めた、神話上の人物みたいな人だった。
「シネマライズフィルムアーカイヴス」というサイトに転載されているなかから、該当する部分を少し長く引用させていただく。http://www.cinemarise.com/theater/archives/films/1988010.html#pagetop
「『ストーミー・ウェザー』は第2次世界大戦中の1944年(昭和18年)、20世紀フォックス社が製作したオール・ブラック・キャストの異色のミュージカル映画で、ファンの間では長年話題となっていた幻の映画である。
敗戦後間もなく、日本でもアメリカ映画が続々と公開されはじめたが、この映画は公開中止になったままこんにちに至っている。
それもその筈、第2次世界大戦とともに応召したアメリカの黒人兵に対する慰問映画を兼ねて作られたこの映画は、アメリカが舞台でありながら白人がひとりも出てこないといういささか不自然な映画であるため、当時の占領政策に相応しくないと判断され上映中止となったようである」
「第2次世界大戦という総力戦に直面したアメリカは兵隊としての黒人を平等に待遇せざるを得なくなっていた。戦時下のハリウッドでは、戦地や基地などの米兵慰問を兼ねた作品が数多く作られていたが、『ストーミー・ウェザー』は、とくに黒人兵へのサービスを目的に作られた数少ない作品としてまことに貴重なものといえよう。またこれほど黒人の超一流エンタテイナーが作品で顔を合わせたハリウッド映画は同年のMGMが製作した『キャビン・イン・ザ・スカイ』の他には前にもその後にも作られていない」
そういうわけで『ストーミー・ウェザー』は、第一次大戦では軍楽隊にいたビルがショービズの世界に入り、先輩のいじめを受けながらも奮闘し、功なり名を遂げた後、第二次大戦で応召された兵隊の慰問ショーでカムバックする……というストーリーになっている。
序盤、ビルは、兵隊になった理由を聞かれて「三度の飯に困らないからさ」と、サラッと答える。
ここで僕はジーンときた。ほだされるというか。そういう理由が聞けたなら、もう、複雑な設定とかドラマとかはなくてもいいのです。
除隊した後も何かと協力してくれる気のいい戦友(ドリー・ウィルソン。『カサブランカ』のサムだ)がいて、別の戦友が、美しい妹(レナ・ホーン)との縁をつなげてくれた。
ジムにとって軍隊はあくまでいいところ、いい思い出の場所なのだ。その記憶に、わざわざ白人が混ざってくる必要はない。
学園内バトルを描く漫画や映画に、教師や親はほとんど出てこないものが多いのも、そういうことだろう。
でも。
メジャー製作の映画に出てくる黒人といえばもっぱら屋敷の使用人かメイド、という慣習を破り、しっかり働いてしっかりいい家に住む黒人を描く先例を作った意義と、当時のトップスターのパフォーマンスをたっぷりと撮影した価値が、戦時中のプロパガンダと取引したことで成立している皮肉は、やはり素通りはできない。
好きな映画だけど、手放しで推薦はしにくい。その難渋さがまた好ましい……という心境。
野口さんは指摘していないが、この映画が一度は輸入されながら公開が見送られたのには、日本の戦時中の映画と雰囲気が似ていたからではないか。それが、敗戦からまだ数年後では生々しく感じられ、配給・公開する人達からバツの悪い感情を呼び起こし、敬遠されたのではないか……? という予想も、僕のなかにはある。
大陸か南方かから帰ってきた復員兵が、職場や家庭など自分のコミュニティの問題点を率先して改善し、お国のための生産に貢献するが、彼が戦地でどんな体験をしてきたかは巧妙に伏せる。
そういうタイプの市民もの、音楽ものは、新体制運動下の日本映画に少なくなかった気がする。具体的に例を次々と挙げて検証していくことは、僕の勉強量ではとてもムリで、あくまで予想に留まる話なのだが。
ここからは蛇足。黒人兵慰撫のPRならばメジャーでもオール・アフリカンアメリカンな映画が作れるし、見られる、という時代に生まれた『ストーミー・ウェザー』のその後を、つらつら考えておきたい。
『サッチモは世界を廻る』(SATCHMO THE GREAT)という1時間強の中編がある。1957年に製作され、日本では1959年に短編映画の扱いで上映された。
今、これを見られる機会はなかなかない。せっかくなので、以前に都合2度見てクレジット等を書き取っておいたメモをここに出しておく。
製作はCBS「See It Now」のフレッド・W・フレンドリーとエドワード・R・マローで、ユナイトが配給した。
つまり、高名な硬派ニュース番組の枠内でのドキュメンタリーが劇場公開に至ったものなので、通常の映画のような監督クレジットはない。その代わり、複数の編集クレジットのなかに『真夏の夜のジャズ』の共同監督のひとり、アラム・アヴァキアンの名がある。
大きくは三部構成で、国務総省から親善大使として派遣されたルイ・アームストロングの1955年欧州ツアーから始まる。
モダン・ジャズの時代になってもサッチモは現役だった! とヨーロッパ各国の若者達が熱烈に歓迎し、聴き入るようすをヴィヴィッドに捉えている。ステージとインタビューの随所に、温かい人柄と年輪の厚みが滲み出ている。幕間の、ジャズの歴史を説明するパートのイラストはなんとベン・シャーン。
続いて1956年、サッチモ一行は独立前夜のガーナへ。10万の観客が集まる大歓迎。独立運動の父エンクルマの前で「ブラック・アンド・ブルー」を歌う。
帰国後には、レナード・バーンスタイン指揮のニューヨーク・フィルと共演。招待されたW.C.ハンディ翁が「セントルイス・ブルース」に落涙する場面がハイライトになる。
ここでのジャズ及びサッチモへの視点は、かつての映画での〈ガハハと笑うほんわかトランペットおじさん〉扱いとはまるで逆。完全にアメリカを代表する文化であり、文化人として遇している。
時代が変わればこんなにも違ってくるのか……と呆れてしまうほどだ。もちろん、ハリウッドの映画業界人とニューヨークのジャーナリストとの意識の違いも大きいだろう。
で、どうして『ストーミー・ウェザー』からの連想でこの映画についても書いておきたいかと言うと。
サッチモがガーナで歌う「ブラック・アンド・ブルー」は、ファッツ・ウォーラーの曲だからだ。しかも「俺は黒くて気分はブルー」と抉るように嘆く、ファッツの自作のなかでも異例に物哀しいと言われている曲なのだ。(正確には作曲だけだが、作詞者はファッツとコンビを組んでいた相棒なので、ファッツの曲だと考えていい)
さっき僕は、『ストーミー・ウェザー』のファッツには、白人に媚を売ってイヤイヤ道化を演じるような屈折は感じられないと書いた。矛盾しているようだが、だからといって苦い思いを味わったことがない、はずもないのだ。
ここでの「ブラック・アンド・ブルー」のサッチモの演奏と歌唱は、ドロッとしていて鬼気迫るものがある。
見た後は慌てて山野楽器に行き、同時期に吹き込まれたトリビュート盤『サッチ・プレイズ・ファッツ』のCDを買った。ここでの「ブラック・アンド・ブルー」も確かにいい。でも、『サッチモは世界を廻る』でのそれとは比較しようがなかった。後者には別次元の念がこもっているからだ。
トリビュートといっても、1901年生のサッチモのほうが、1904年生のファッツより年上。同時代の人気も評価も、サッチモのほうが高かっただろう。
それでもサッチモは、円熟期に入ってから「ブラック・アンド・ブルー」をレパートリーにした。
黒人芸人の、顔に一切出さなかった長年の鬱屈を、後輩達のシリアスなモダン・ジャズのおかげでようやく表現できるようになった、ということかもしれない。
それに、コメディアンの顔のほうが知られるまま早逝した(ファッツは『ストーミー・ウェザー』撮影から数ヶ月後に病死している)仲間への、黒人ジャズメンが白人から尊敬される時代まで生き残った者による鎮魂なのかもしれない。










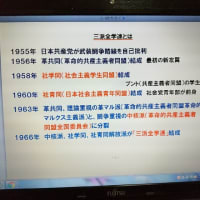
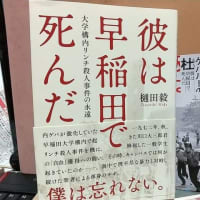
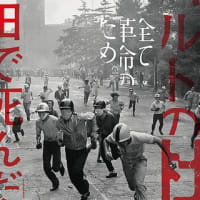



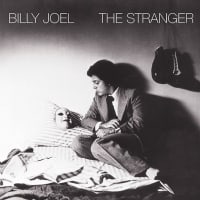

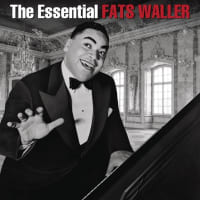

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます