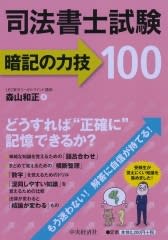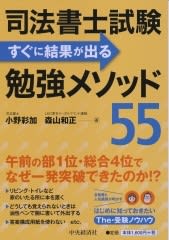論語です。
吾れ日に吾が身を三省す。
書き下すとこんな感じ。
漢文も英語と同じで5文型があり,これはSVOですね。
吾がS
日が副詞
三省がV
吾身がOですね。
大学受験生のときに「ガッツ漢文」で仕入れた古い知識ですので,間違っていないかな?
自分の行動を振り返って一日三回は反省するということです。
僕自身,三省どころか,「こう説明したほうがよかったな」「今の相談ベストな回答だったかな」とか反省することばかりです。
情けないですが,傲慢に生きるよりはいいかなと思ったりはします。
この言葉,続きがあります。
為人謀而不忠乎
與朋友交而不信乎
傳不習乎
人の為に謀りて忠ならざるか
朋友と交わりて信ならざるか
習はざるを伝へしか
人の言葉に誘われて信義に反することをしなかったか
人を惑わせることはしなかったか
うーん,心にとめておかなければいけないですね。
さて,この論語を社名にしている出版社がありました。

暑い中,三省堂で,次回作の打合せ。
写真は三省堂の社版。
そして,
写真手前にあるのは,羽生名人の揮毫扇子。
これも「三省」と揮毫しています。
達筆で読みにくいですが,「名人 羽生善治」と署名してありますね。
右から読んで「三省」。
「省三」ではありません。十津川省三警部じゃないんですから。
しかし,外に出ると本当に暑い。
皆さま,熱中症などにご注意くださいね。
吾れ日に吾が身を三省す。
書き下すとこんな感じ。
漢文も英語と同じで5文型があり,これはSVOですね。
吾がS
日が副詞
三省がV
吾身がOですね。
大学受験生のときに「ガッツ漢文」で仕入れた古い知識ですので,間違っていないかな?
自分の行動を振り返って一日三回は反省するということです。
僕自身,三省どころか,「こう説明したほうがよかったな」「今の相談ベストな回答だったかな」とか反省することばかりです。
情けないですが,傲慢に生きるよりはいいかなと思ったりはします。
この言葉,続きがあります。
為人謀而不忠乎
與朋友交而不信乎
傳不習乎
人の為に謀りて忠ならざるか
朋友と交わりて信ならざるか
習はざるを伝へしか
人の言葉に誘われて信義に反することをしなかったか
人を惑わせることはしなかったか
うーん,心にとめておかなければいけないですね。
さて,この論語を社名にしている出版社がありました。

暑い中,三省堂で,次回作の打合せ。
写真は三省堂の社版。
そして,
写真手前にあるのは,羽生名人の揮毫扇子。
これも「三省」と揮毫しています。
達筆で読みにくいですが,「名人 羽生善治」と署名してありますね。
右から読んで「三省」。
「省三」ではありません。十津川省三警部じゃないんですから。
しかし,外に出ると本当に暑い。
皆さま,熱中症などにご注意くださいね。