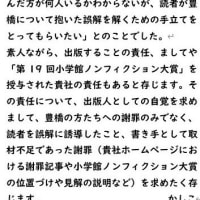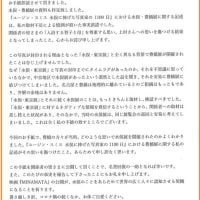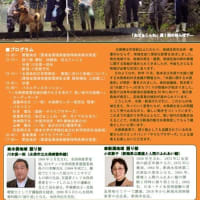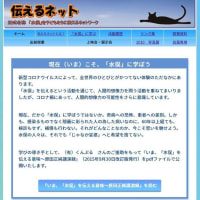第8回 水俣病事件研究交流集会に参加して
知ったこと 思ったこと 考えたこと
 原田先生と宮澤さんの気配を感じながらの研究会
原田先生と宮澤さんの気配を感じながらの研究会
行ってきました。久々に。
このところ、地域活動と音声サポート部会の活動をもっぱらにしてきたので、3学期の出前活動を前に、「水俣」に触れなおし、感じなおしたくて、参加を決めました。
水俣のことは、水俣のひとたちにしかわからない。だからこそ、不断に想像しつづける意志が必要だと考えています。
人間的想像力は、実際に当事者の気持ちをわかるということではなく、わからないだろうその気持ちに近づこうとする意志のありようであり、その営みのことだと思っているからです。
それに、この事件交流集会は、とても大切なキー・パーソンをふたり、昨年、彼岸におくりました。
原田正純先生と宮澤信雄さんです。そのおふたりの追悼の機会ともなるはずです。
原田先生は、私たちを第15回田尻賞に推薦してくださいました。
大きな賞にしり込みする思いを訴えたとき、先生は「あんたたちのような、名もない市民にあげる賞なんだ」とあの独特の笑顔で言われました。
その言葉は、私たちの立ち位置となりました。
子どもたちの前に立つとき、私たちは「名もない市民」です。
専門的に何かを知っているわけでもなく、何かの肩書きによって立つのではなく、「市民」として「生活者」として子どもたちに「水俣」を伝える意思で話しかける――そう位置を再び確かめる機会としての参加でした。
当日の朝に羽田をたって、集会の終わりも待てずに帰路につくという強行スケジュールでの参加でした。
そんな参加を可能にしてくれたのは、水俣現地の友人の全面的なヘルプがあったおかげです。
空港の送迎から宿泊提供まで、また親しく懐かしい夜なべの語らい・・・本当に嬉しかったし、深謝であります。
伝えるネットの活動を重ねる10年を超える年月のなかで、地縁も血縁もなかった水俣が、心通う友がくらす水俣、となりました。
 「うして水俣病」は終わらない
「うして水俣病」は終わらない
久々の参加で、研究者の成果報告という様相は、スムーズに入り込めない感覚も、正直ありました。
もちろん、十分刺激的で、新しく知ったこと、改めて知りなおしたこと、考えずにやり過ごしていたことを改めて考えていかなければならない課題を教えられる機会となりました。
たとえば、水銀を含んだ農薬が日本で広域で大量に使用されていたこと。水銀使用が全地球的に問題となって国際的に規制をかけようとしている条約を、「水俣条約」と名づけて事件の落とし前にしたい国と、そうしたごまかしを許すまいとする患者さんの気持ちがあること。
また、頭の下がる思いで新潟木戸病院の斉藤先生の発表と、その都度の発言を聞きました。

お元気な斎藤先生には、励みをいただきます
これまでも親しくさせてもらってきた元・チッソ労働組合の山下善寛さんが、昨年7月18日に水俣病の認定申請を出されたこと。
特措法の受付期限である7月末日に熊本市内の街路で突然、ひとりがのぼり旗を立ててマイクで手続きするように呼びかけるということが目撃されたそうです。
それが、「広く」救済を呼びかけるという内実であったというエピソード。
(こんなの、その情景を想像してみると、余りにもお粗末で、「普通」の市民感覚でお口がアングリ。
あとで聞いたら、当時の細野環境相が水俣の協立病院の前で街宣したんだって・・・
これが、広報の実態だったんだ・・・!」
そして、そこで知った「うして水俣病」という言い方。
潜在患者でもなく、潜伏患者でもなく、「うして=つまり、捨てられた」患者とするのが、いちばん的を射た表現ではないだろうかという議論。
本当は「遅発性」という言い方も、ふさわしくはありません。水俣病は、連綿とつづく事象、病いなのですから。
国は被害の実態を一度も調べたことはないのです。
汚染魚は、行商ルートにのってどこまで行ったのか。
特措法で発生時期や発生地域を限定していながら、その根拠となる調査は、一度もきちんと行われていないのです。
遅発性だからでもなく、潜んでいたのでもなく、「うして水俣病」なのでした。
 懐かしい出会いと 新しい出会いと
懐かしい出会いと 新しい出会いと
貴重な機会となったのは、研究会の場だけでなく、初日の懇談会でもそうでした。
いつもツイッターで水俣病のことから放射能のことまで発信してくださる水俣協立クリニックの高岡先生に面識をいただくこともできました。
ツイッターで感じていたより、もっと活動的で戦闘的な方でした。
懇親会でも、また、研究会の締めくくりでも、原田正純先生と宮澤信雄さんへの感謝と敬意と、あとにつづく意思に満ちていました。
翌日のセッションで新潟の斎藤先生が心のこもった追悼文を読み上げられたとき、上村好男さんが智子さんと原田先生との思い出に触れ感謝をされたとき、こらえきれず涙がこみあげました。
ふと、振り返ると坂本しのぶさんが、やはり止められず、涙をぬぐっておられました。

智子さんが上京された折の原田先生とのエピソードを語る上村好男さん

懇親会の折に、坂本しのぶさんとツーショットを撮ってもらいました
知ったこと 思ったこと 考えたこと
2013年1月12日―13日
水俣市公民館(水俣市浜町2-10-26)にて
水俣市公民館(水俣市浜町2-10-26)にて
 原田先生と宮澤さんの気配を感じながらの研究会
原田先生と宮澤さんの気配を感じながらの研究会行ってきました。久々に。
このところ、地域活動と音声サポート部会の活動をもっぱらにしてきたので、3学期の出前活動を前に、「水俣」に触れなおし、感じなおしたくて、参加を決めました。
水俣のことは、水俣のひとたちにしかわからない。だからこそ、不断に想像しつづける意志が必要だと考えています。
人間的想像力は、実際に当事者の気持ちをわかるということではなく、わからないだろうその気持ちに近づこうとする意志のありようであり、その営みのことだと思っているからです。
それに、この事件交流集会は、とても大切なキー・パーソンをふたり、昨年、彼岸におくりました。
原田正純先生と宮澤信雄さんです。そのおふたりの追悼の機会ともなるはずです。
原田先生は、私たちを第15回田尻賞に推薦してくださいました。
大きな賞にしり込みする思いを訴えたとき、先生は「あんたたちのような、名もない市民にあげる賞なんだ」とあの独特の笑顔で言われました。
その言葉は、私たちの立ち位置となりました。
子どもたちの前に立つとき、私たちは「名もない市民」です。
専門的に何かを知っているわけでもなく、何かの肩書きによって立つのではなく、「市民」として「生活者」として子どもたちに「水俣」を伝える意思で話しかける――そう位置を再び確かめる機会としての参加でした。
当日の朝に羽田をたって、集会の終わりも待てずに帰路につくという強行スケジュールでの参加でした。
そんな参加を可能にしてくれたのは、水俣現地の友人の全面的なヘルプがあったおかげです。
空港の送迎から宿泊提供まで、また親しく懐かしい夜なべの語らい・・・本当に嬉しかったし、深謝であります。
伝えるネットの活動を重ねる10年を超える年月のなかで、地縁も血縁もなかった水俣が、心通う友がくらす水俣、となりました。
 「うして水俣病」は終わらない
「うして水俣病」は終わらない久々の参加で、研究者の成果報告という様相は、スムーズに入り込めない感覚も、正直ありました。
もちろん、十分刺激的で、新しく知ったこと、改めて知りなおしたこと、考えずにやり過ごしていたことを改めて考えていかなければならない課題を教えられる機会となりました。
たとえば、水銀を含んだ農薬が日本で広域で大量に使用されていたこと。水銀使用が全地球的に問題となって国際的に規制をかけようとしている条約を、「水俣条約」と名づけて事件の落とし前にしたい国と、そうしたごまかしを許すまいとする患者さんの気持ちがあること。
また、頭の下がる思いで新潟木戸病院の斉藤先生の発表と、その都度の発言を聞きました。

お元気な斎藤先生には、励みをいただきます
これまでも親しくさせてもらってきた元・チッソ労働組合の山下善寛さんが、昨年7月18日に水俣病の認定申請を出されたこと。
特措法の受付期限である7月末日に熊本市内の街路で突然、ひとりがのぼり旗を立ててマイクで手続きするように呼びかけるということが目撃されたそうです。
それが、「広く」救済を呼びかけるという内実であったというエピソード。
(こんなの、その情景を想像してみると、余りにもお粗末で、「普通」の市民感覚でお口がアングリ。
あとで聞いたら、当時の細野環境相が水俣の協立病院の前で街宣したんだって・・・
これが、広報の実態だったんだ・・・!」
そして、そこで知った「うして水俣病」という言い方。
潜在患者でもなく、潜伏患者でもなく、「うして=つまり、捨てられた」患者とするのが、いちばん的を射た表現ではないだろうかという議論。
本当は「遅発性」という言い方も、ふさわしくはありません。水俣病は、連綿とつづく事象、病いなのですから。
国は被害の実態を一度も調べたことはないのです。
汚染魚は、行商ルートにのってどこまで行ったのか。
特措法で発生時期や発生地域を限定していながら、その根拠となる調査は、一度もきちんと行われていないのです。
遅発性だからでもなく、潜んでいたのでもなく、「うして水俣病」なのでした。
 懐かしい出会いと 新しい出会いと
懐かしい出会いと 新しい出会いと貴重な機会となったのは、研究会の場だけでなく、初日の懇談会でもそうでした。
いつもツイッターで水俣病のことから放射能のことまで発信してくださる水俣協立クリニックの高岡先生に面識をいただくこともできました。
ツイッターで感じていたより、もっと活動的で戦闘的な方でした。
懇親会でも、また、研究会の締めくくりでも、原田正純先生と宮澤信雄さんへの感謝と敬意と、あとにつづく意思に満ちていました。
翌日のセッションで新潟の斎藤先生が心のこもった追悼文を読み上げられたとき、上村好男さんが智子さんと原田先生との思い出に触れ感謝をされたとき、こらえきれず涙がこみあげました。
ふと、振り返ると坂本しのぶさんが、やはり止められず、涙をぬぐっておられました。

智子さんが上京された折の原田先生とのエピソードを語る上村好男さん

懇親会の折に、坂本しのぶさんとツーショットを撮ってもらいました
報告は、その2 につづく