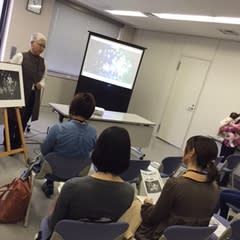ネット・インフォメーション 55号ができました。
ようやく、やっとです。
54号の発行日が2015年11月7日、55号の発行日は2018年1月20日になってしまいました。
いいかげん発行せねばと編集作業にはいったのが、正月2日ですので、12ページの編集に2週間。
印刷屋さんに入稿してホッとしていたら、発送作業に丸々1週間かかってしまいました。
簡単ではありませんでした。
どうして、こんなに間隔が空いてしまったかと振り返れば、いろいろと理由があります。
物理的な理由から精神的な理由まで、挙げれば両手の指だけでは足りません。
大きいのは、伝えるネット会計でもあった属さんを彼岸に見送ったことです。
親友でした。(いまもって、彼女を過去形で語るのは苦しいです。)
喪失はひとの世の常ながら、彼女のいない日々を日常をすることになかなか馴れることはできません。
しかし、さらに振り返れば、会報に取り掛かることのできなかったのは、「そんなはずがない」「であるわけがない」という思いだと思うのです。
はっきり言えば、世の中が正気に戻るのを待とう、という思いがあったのです。
伝えるネットの活動は、1998年の水俣・豊橋展、1999年の水俣・浜松展で出会った有志によって始まりました。
豊橋展のプレ・イベントとして行われた豊橋にある桜ヶ丘中学校での出前講座で、中学生の子どもたちと行った「水俣病は二度と起こらないか」というフリー・ディスカッションで、わたしはどんな発言をしたでしょうか。
「だから、時代は変わっていっている」と、そう発言したことを、わたし自身が記憶しております。
いま、社会は、情報をスミ塗りにすることが通例となり、発言すること、特に疑念を呈したり、異論を口にすることは排除され、ヘイト発言は大手を振ってまかり通るようになりました。
若くして彼岸に旅立った彼女に、この時代を見せずにすんだことが救いのようにも感じられるとは、なんということでしょう。
そして、何よりも――。
「水俣」を伝えていくことが、何よりもまちづくりであると信じて活動してきたこのまちで、津久井やまゆり園事件が起きてしまったことを、どう受け止めればいいのか。
自分たちの活動がいい気なもんだった。
何もできないのではないか。
いや、社会の根底にある賢明さは、こんな時代を許すはずはない。
賢明? どこが賢明であったのか。
見失っていたのは、何よりも、わたし自身ではないか。
思いに翻弄されるなか、とても会報は出せませんでした。
でも、日々は積み重なります。
いのちは生まれ、子どもたちは現れます。
伝えるネット設立以来、子どもたちの瞳の色は少しも変わりません。
そして、「ずっと、もっと、伝えて行ってください」と子どもたちは言うのです。
いま、わたしたちは、つづけることが大切だと考えています。
その気持ちを込めて、ブログトップの画像をリニュアルいたしました。
ブログ発信や、SNS発信も新規まき直しをはかりたいと存じます。
2年分の記事を詰め込んだ55号をどうぞ、お手元に。

ネット・インフォメーション 第55号
ご希望があれば、1部200円(送料込み)でお分けいたします。
内容は、1ページの左下にあります「目次」の欄にてお確かめください。
注文は、こちらのコメント欄でもお申し込みできます。
ようやく、やっとです。
54号の発行日が2015年11月7日、55号の発行日は2018年1月20日になってしまいました。
いいかげん発行せねばと編集作業にはいったのが、正月2日ですので、12ページの編集に2週間。
印刷屋さんに入稿してホッとしていたら、発送作業に丸々1週間かかってしまいました。
簡単ではありませんでした。
どうして、こんなに間隔が空いてしまったかと振り返れば、いろいろと理由があります。
物理的な理由から精神的な理由まで、挙げれば両手の指だけでは足りません。
大きいのは、伝えるネット会計でもあった属さんを彼岸に見送ったことです。
親友でした。(いまもって、彼女を過去形で語るのは苦しいです。)
喪失はひとの世の常ながら、彼女のいない日々を日常をすることになかなか馴れることはできません。
しかし、さらに振り返れば、会報に取り掛かることのできなかったのは、「そんなはずがない」「であるわけがない」という思いだと思うのです。
はっきり言えば、世の中が正気に戻るのを待とう、という思いがあったのです。
伝えるネットの活動は、1998年の水俣・豊橋展、1999年の水俣・浜松展で出会った有志によって始まりました。
豊橋展のプレ・イベントとして行われた豊橋にある桜ヶ丘中学校での出前講座で、中学生の子どもたちと行った「水俣病は二度と起こらないか」というフリー・ディスカッションで、わたしはどんな発言をしたでしょうか。
――わたしたちは、情報開示を求めることができる。事実を知ろうと思えば知ることができる。
――わたしたちは、発言することができる。決定に参加することができる。
――わたしたちは、発言することができる。決定に参加することができる。
「だから、時代は変わっていっている」と、そう発言したことを、わたし自身が記憶しております。
いま、社会は、情報をスミ塗りにすることが通例となり、発言すること、特に疑念を呈したり、異論を口にすることは排除され、ヘイト発言は大手を振ってまかり通るようになりました。
若くして彼岸に旅立った彼女に、この時代を見せずにすんだことが救いのようにも感じられるとは、なんということでしょう。
そして、何よりも――。
「水俣」を伝えていくことが、何よりもまちづくりであると信じて活動してきたこのまちで、津久井やまゆり園事件が起きてしまったことを、どう受け止めればいいのか。
自分たちの活動がいい気なもんだった。
何もできないのではないか。
いや、社会の根底にある賢明さは、こんな時代を許すはずはない。
賢明? どこが賢明であったのか。
見失っていたのは、何よりも、わたし自身ではないか。
思いに翻弄されるなか、とても会報は出せませんでした。
でも、日々は積み重なります。
いのちは生まれ、子どもたちは現れます。
伝えるネット設立以来、子どもたちの瞳の色は少しも変わりません。
そして、「ずっと、もっと、伝えて行ってください」と子どもたちは言うのです。
いま、わたしたちは、つづけることが大切だと考えています。
その気持ちを込めて、ブログトップの画像をリニュアルいたしました。
ブログ発信や、SNS発信も新規まき直しをはかりたいと存じます。
2年分の記事を詰め込んだ55号をどうぞ、お手元に。

ネット・インフォメーション 第55号
ご希望があれば、1部200円(送料込み)でお分けいたします。
内容は、1ページの左下にあります「目次」の欄にてお確かめください。
注文は、こちらのコメント欄でもお申し込みできます。











 写真パネルの同行なしの出前って!?
写真パネルの同行なしの出前って!?

 時代に揺さぶられながら、取り組む出前
時代に揺さぶられながら、取り組む出前






 子どもたちが親になるとき
子どもたちが親になるとき