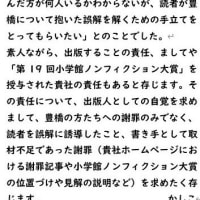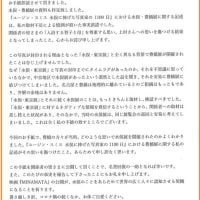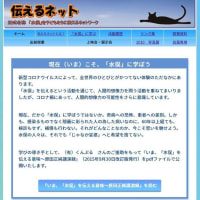今朝の新聞報道で石牟礼道子さんの『苦海浄土』の紛失原稿が見つかったという報道がなされています。→こちら
この機会に、この夏いただいた石牟礼道子さんとの出会い、珠玉の時間について、報告させていただくことにしました。
ホントは、なかなか更新できないHPを補うためのブログとして、タイムリーでスムーズな記事アップが必要なわけですけど、この石牟礼道子さんとの出会いは、内側で、それも精神の内側で、ためておきたい思いがありました。
ため過ぎて、時の経過のなかに折り込んでしまう危うさがありながら、どこまで、深いところまで醸成できるか課したいと思ってきたのです。
とは言え、自分たちの持つ感受性や思考のなかで、それが果たしてできるのか、自信があるわけではありません。
なので、今朝の記事を見つけて、きっかけをいただいた思いで、みなさまに報告することにします。
 花を奉る思いで 石牟礼さんに会いに行く
花を奉る思いで 石牟礼さんに会いに行く
さる方の伝手を得て(複数のみなさまに手助けいただけました。深謝)、石牟礼道子さんにこの夏、お会いすることができました。
原田正純先生が亡くなってから、石牟礼さんにお会いしたい気持ちが私たちのなかで募ってきておりました。
とくに『花を奉る』という文章を、筆にし、何度も何度も意味を探り、振り返るたびに、その解題をご本人に確かめたい思いが高まっていったのでした。

ここで咲く「花」とは何か。
「奉る」ということは、どういう営みなのか。
いま、振り返ると、石牟礼さんに思いを寄せ、言葉を求めていったわたしたちの在り方が、そのまま「花を奉る」ことだったのかも知れません。
 そのままの珠玉の言葉をいただく
そのままの珠玉の言葉をいただく
普通は、話す、聞く、と表現するのかな、と思います。
でも、石牟礼さんの言葉は、読む、という思いで聴きました。


石牟礼さんが語り始められたこと――。
「金肥」まみれの現代を振り返らせずにおかない、静かで、透明な石牟礼道子さんの声がつづきました。
そして、つたないながら、わかってきたように思ったのです。
そうか、山の民、いえ、お祖父さんやお父さんや、水俣のみなさんのひとりひとりが、「花」なのか。
ひとびとが、自然や、そこに為された道普請に、畏れるようにいただく姿が、「奉る」ことなのか、と。
 畏れながら ひとが営みをいただくとき、花を奉れ
畏れながら ひとが営みをいただくとき、花を奉れ
いま、「奉る」べきひとの暮らしはあるでしょうか?
「金肥」まみれで、畏れも祝いもない無機質な現代生活のなかに、思わず頭を垂れるような瞬間は、たぶん、失われて久しいでしょう。
石牟礼さんの精神のなかには、お祖父さんやお父さんの日々の暮らしぶりの記憶とともに、そのような畏れ、奉る気持ちが息づいているのでしょう。
石牟礼さんの優しい語り口のなかに、「花」は確かにあると感じられたのでした。
だとすれば――。
ひとがひとらしくあるとき、そのひと(いのちと言い換えていいのかも知れません)が、そのまんま、やはり「花」。
限りあるいのちならば、やはり「奉る」ように生きるのが、その本来なのではないか。
「花を奉る」とは、人間本来への回帰のことなのではないだろうか。
石牟礼さんは、長いお話のあと、「こちらは甘いのよ」とお茶菓子をすすめて、少女のように微笑まれました。
誘われて、わたしたちまでも、まるで清廉な花になったように、互いに微笑んだことでした。
この機会に、この夏いただいた石牟礼道子さんとの出会い、珠玉の時間について、報告させていただくことにしました。
ホントは、なかなか更新できないHPを補うためのブログとして、タイムリーでスムーズな記事アップが必要なわけですけど、この石牟礼道子さんとの出会いは、内側で、それも精神の内側で、ためておきたい思いがありました。
ため過ぎて、時の経過のなかに折り込んでしまう危うさがありながら、どこまで、深いところまで醸成できるか課したいと思ってきたのです。
とは言え、自分たちの持つ感受性や思考のなかで、それが果たしてできるのか、自信があるわけではありません。
なので、今朝の記事を見つけて、きっかけをいただいた思いで、みなさまに報告することにします。
 花を奉る思いで 石牟礼さんに会いに行く
花を奉る思いで 石牟礼さんに会いに行くさる方の伝手を得て(複数のみなさまに手助けいただけました。深謝)、石牟礼道子さんにこの夏、お会いすることができました。
原田正純先生が亡くなってから、石牟礼さんにお会いしたい気持ちが私たちのなかで募ってきておりました。
とくに『花を奉る』という文章を、筆にし、何度も何度も意味を探り、振り返るたびに、その解題をご本人に確かめたい思いが高まっていったのでした。

ここで咲く「花」とは何か。
「奉る」ということは、どういう営みなのか。
いま、振り返ると、石牟礼さんに思いを寄せ、言葉を求めていったわたしたちの在り方が、そのまま「花を奉る」ことだったのかも知れません。
 そのままの珠玉の言葉をいただく
そのままの珠玉の言葉をいただく普通は、話す、聞く、と表現するのかな、と思います。
でも、石牟礼さんの言葉は、読む、という思いで聴きました。


石牟礼さんが語り始められたこと――。
水俣に工場ができる、ということを聞いて、人が集まるならば道が必要だと、お祖父さんは道普請のために天草から水俣に渡ってきた。
チッソ工場は、チッソやリンなどの肥料をつくっていた。
それまで、畑には人糞を撒くことはあっても、チッソやリンなど肥料を施すことはなかった。
それは、人糞と違って、お金で買う肥料だったから。
いわば、「人肥」に対する「金肥(きんぴ)」だった。
「金肥」を施す畑は、3年もすればみみずはいなくなり、土は固くなります。
畑の雑草にだって、人格というものはあるのです。
人々は、2,3日目をはなすと茂ってしまう雑草にも「よく育ちならして」と言ったものです。
「金肥」は、雑草をも変えます。
球磨川の氾濫はおそろしいものだった。
実家は、川の河口にあるけれど、川がひとつになって海に注ぐ、その元をたどれば、源流へ、山へとつづく細い川筋、さらに木々のなか、幹を流れる水脈にたどりつく。
祖父と父は、性格は似ても似つかなかかったけれど、ひとつだけ共通するものがあった。
それは、ふたりとも、吝嗇を嫌うことだった。
家には30人もの道をつくる人たちが集まって、夕飯を食べていたものです。
山の川沿いに石積みをして道をつくります。
道というのは、世の中の始まりのこと。
その道づくりの土台となるのが「地石(じいし)」というものです。
「地石」をおろそかにしては、道にはなりません。
湯の鶴の川沿いに最初の道ができたとき、山の衆が道の見物に来られたそうです。
見に来られて、足を道にのせたとき、思わす怖ろしくなって、逃げて帰ったそうです。
それは、まるで、神様の頭を踏んづけたような心持ちになったそうなのです。
いまのようなコンクリートの道ではありませんよ。
コンクリートの道には神様はいません。
そして、山の衆は花になって出てきた、と祖父は言うのです。
どうして道をつくりたいか、と言えば、山の衆が花となって喜ぶから、と。
ひとりひとりが神様であり、花となって出てくる。
その花に会いたいくて、道をつくるのだと。
花を奉らねば、道に足をおろすことはできません。
どんな花でも構わないのです。雑草の花であれば、なおよいかもしれません。
花を奉り、焼酎をつくり、山の神を祀った、と。
そうやって、山に道を食わせた。
道は、あっちの山、こっちの山と食べていったと。
チッソ工場は、チッソやリンなどの肥料をつくっていた。
それまで、畑には人糞を撒くことはあっても、チッソやリンなど肥料を施すことはなかった。
それは、人糞と違って、お金で買う肥料だったから。
いわば、「人肥」に対する「金肥(きんぴ)」だった。
「金肥」を施す畑は、3年もすればみみずはいなくなり、土は固くなります。
畑の雑草にだって、人格というものはあるのです。
人々は、2,3日目をはなすと茂ってしまう雑草にも「よく育ちならして」と言ったものです。
「金肥」は、雑草をも変えます。
球磨川の氾濫はおそろしいものだった。
実家は、川の河口にあるけれど、川がひとつになって海に注ぐ、その元をたどれば、源流へ、山へとつづく細い川筋、さらに木々のなか、幹を流れる水脈にたどりつく。
祖父と父は、性格は似ても似つかなかかったけれど、ひとつだけ共通するものがあった。
それは、ふたりとも、吝嗇を嫌うことだった。
家には30人もの道をつくる人たちが集まって、夕飯を食べていたものです。
山の川沿いに石積みをして道をつくります。
道というのは、世の中の始まりのこと。
その道づくりの土台となるのが「地石(じいし)」というものです。
「地石」をおろそかにしては、道にはなりません。
湯の鶴の川沿いに最初の道ができたとき、山の衆が道の見物に来られたそうです。
見に来られて、足を道にのせたとき、思わす怖ろしくなって、逃げて帰ったそうです。
それは、まるで、神様の頭を踏んづけたような心持ちになったそうなのです。
いまのようなコンクリートの道ではありませんよ。
コンクリートの道には神様はいません。
そして、山の衆は花になって出てきた、と祖父は言うのです。
どうして道をつくりたいか、と言えば、山の衆が花となって喜ぶから、と。
ひとりひとりが神様であり、花となって出てくる。
その花に会いたいくて、道をつくるのだと。
花を奉らねば、道に足をおろすことはできません。
どんな花でも構わないのです。雑草の花であれば、なおよいかもしれません。
花を奉り、焼酎をつくり、山の神を祀った、と。
そうやって、山に道を食わせた。
道は、あっちの山、こっちの山と食べていったと。
「金肥」まみれの現代を振り返らせずにおかない、静かで、透明な石牟礼道子さんの声がつづきました。
そして、つたないながら、わかってきたように思ったのです。
そうか、山の民、いえ、お祖父さんやお父さんや、水俣のみなさんのひとりひとりが、「花」なのか。
ひとびとが、自然や、そこに為された道普請に、畏れるようにいただく姿が、「奉る」ことなのか、と。
 畏れながら ひとが営みをいただくとき、花を奉れ
畏れながら ひとが営みをいただくとき、花を奉れいま、「奉る」べきひとの暮らしはあるでしょうか?
「金肥」まみれで、畏れも祝いもない無機質な現代生活のなかに、思わず頭を垂れるような瞬間は、たぶん、失われて久しいでしょう。
石牟礼さんの精神のなかには、お祖父さんやお父さんの日々の暮らしぶりの記憶とともに、そのような畏れ、奉る気持ちが息づいているのでしょう。
石牟礼さんの優しい語り口のなかに、「花」は確かにあると感じられたのでした。
だとすれば――。
ひとがひとらしくあるとき、そのひと(いのちと言い換えていいのかも知れません)が、そのまんま、やはり「花」。
限りあるいのちならば、やはり「奉る」ように生きるのが、その本来なのではないか。
「花を奉る」とは、人間本来への回帰のことなのではないだろうか。
石牟礼さんは、長いお話のあと、「こちらは甘いのよ」とお茶菓子をすすめて、少女のように微笑まれました。
誘われて、わたしたちまでも、まるで清廉な花になったように、互いに微笑んだことでした。