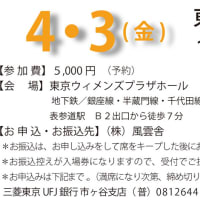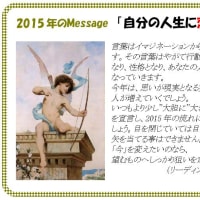『感情的になる事』と、『感情を表現する事』。
これはまったく『別』なものですよ。
とあるミーティングに参加したときの事。
意見が対立し、すっかり困っている二人。
近くのテーブルで別のミーティングをしていた私は口を出す事はなかったのですが、夜になって気になり、一人へメールをしてみました。
「大丈夫だった?だいぶ困っていたようだけど」
すると、「顔に出てた?感情的になるまいとしていたのだけど、ダメだね、私」と返信。
いやいや、感情的になっていたとは書いていないのだけど。
よく言われることですが、日本人は感情を表現するのが苦手とか。
それゆえ、「何を考えているのか分からない」と言われますね。
幼い頃から、「男の子は人前で泣くものじゃない」とか、「女の子はニコニコしていないと可愛がってもらえない」とか、どこかで聞いてきたセリフかと思います。
和を重んじる日本人は、結局のところ『対立』を恐れる人種なのであろうと思います。
こんなジョークがあります。
あなたが乗っていた豪華客船が沈没しそうになっています。
救命ボートにはあと一人しか乗れない。
順番を待っていたあなたが、今まさに乗り込もうとした瞬間、「先に乗せてほしい」と声を掛けられます。
そしてあなたは「どうぞ」と、言わざるを得ない状況に。
さて、なんと声を掛けられたのでしょう?
あなたがアメリカ人ならば、「先に乗らせてもらえたら、あなたは”ヒーロー”として称えられるでしょう」。
アメリカ人にとって、ヒーローになれる事は重要なようです。
そしてあなたがイギリス人ならば、「先に乗らせてくれるなんて、あなたはやっぱり”紳士”ですね」。
イギリス人、紳士である事に誇りを持っていますものね。
では日本人は、何と言われたら救助を譲るでしょうか?
答え。
↓
↓
「あなたは後です。 ”みんな”そうしていますから」。
対立を恐れる日本人は、”みんな”と同じ事に安心感を持つ、と思われているのですね。
昔から、「NOと言えない日本人」とか、「日本人はみんな同じ顔をしていて区別がつかない」とか、没個性が特徴とされてきた背景があります。
またハッキリ意思を表明しない分、『察する文化』が根付いています。
実は心理カウンセリングは、日本人には向かない、とも言われています。
悩みがあって、それを相談しに来たというのに、「これを言ったらカウンセラーにどう思われるのだろう」、等の気遣いから、本当に困っている事、思った事を言葉に出来ない相談者が多いのです。
ですから日本人のカウンセラーはちょっと大変(^^;)
相談者が言葉に出来ない部分を察しながら事実確認をし、感情を理解し、援助していく事となります。
そもそも自分の意見を言うことは、主張であっても我を通すことではありません。
活発に意見交換することを議論と言いますが、それはケンカとは違います。
つまるところ、私たち日本人の多くは意見交換する前から対立を恐れ、そして不慣れゆえにミスを犯し、そしてまた対立への恐れを深めてしまうのではないでしょうか?
よく見られるミス。
例えば、意見の違いを認めずに、相手の人格そのものを否定してしまうこと。
これをすると、会議室を出た後にも遺恨が残ってしまいます。
相手が異なる意見をぶつけてきたとしても、それはあなた自身を責めたり批判しているわけでは無い事を知っておいてほしいと思います。
また、こんなミスもよく見られます。
それはパワー争いとなること。
議論を、あたかも勝負のように誤解して、『どちらが勝つか』に終始する。
これもまた、意見と人格を混同しているから起こるのだろうと思います。
たとえ意見を取り下げる側になったとしても、それは『負け』でもなければ『妥協』ともなりません。
もしそう感じるのであれば、議論が十分でないだけのこと。
議論の本当の目的は、異なる者同士が、相手の”考え”や”思い”を理解するために行うのであって、1+1が2以上の結果を出す事だと思うのです。
ロボットvsロボットの関係ではあるまいし、私たちは感情を混じえずに議論をする事など不可能です。
いくら理性的に事を運ぼうとしたところで、『理性的に話し合いたい』という感情がそこにあるわけですから。
円滑なコミュニケーションを行う上で、感情を伝える事はとても重要です。
相手を『人』と見るか、『物』のように見るかで相手の反応が変わるのです。
特に言いにくい事を言わなければならない状況では、感情を伝える事はより重要です。
いつも締め切りを守らない人に仕事をお願いする時に、「いつもみたいに締め切りに遅れないでください」と言うよりも、「○月○日迄に私が見られるようやって貰えたら”助かります”」と言う事をおすすめします。
前者の言い方は、相手を尊重しない言い方です。
また、脳は否定後を理解しませんから「いつもみたいに締め切りに遅れなさい」とインプットされてしまう可能性があります。
後者の言い方の良いところは、第一に締切日を明示していること。
第二に、「私が見られるように」と言うことで、相手の潜在意識に、見ている人のイメージを植えつけることになります。
第三に、「助かります」と言うことで、その期待を裏切りたくないという気持ちを想起させることができます。
・・・と、種明かしすれば戦略的とも思われるかもしれませんが、こういう事を常日頃から無意識にやっていると確実にコミュニケーションがよくなるのです。
コミュニケーションは自分よがりのものではありません。
自分を大切にするように、相手もまたその人自身を大切にする権利があることを認めた上で成り立つ技術なのです。
赤ちゃんを見ていると癒されますね。
それはなぜかと言えば、安心しきっている赤ちゃんの波動を感じるからです。