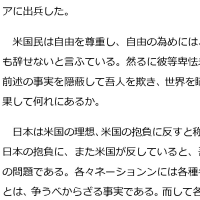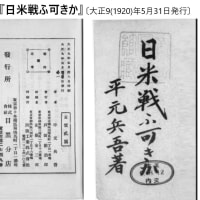菊池寛著『二千六百年史抄』
目次
序
神武天皇の御創業
皇威の海外発展と支那文化の伝来
氏族制度と祭政一致
聖徳太子と中大兄皇子
奈良時代の文化と仏教
平安時代
院政と武士の擡頭
鎌倉幕府と元寇
建武中興
吉野時代
足利時代と海外発展
戦国時代
信長、秀吉、家康
鎖国
江戸幕府の構成
尊皇思想の勃興
国学の興隆
江戸幕府の衰亡
勤皇思想の勃興
勤皇志士と薩長同盟
明治維新と国体観念
廃藩置県と征韓論
立憲政治
日露戦争以後
院政と武士の擡頭
この世をばわが世とぞ思ふ望月(もちづき)の
かけたる事もなしと思へば
と歌った摂政道長の権勢は、藤原氏の全盛を語ると共に、満つればかくる世の習ひをも示して、
以後藤原氏の頽勢は著るしかつた。
それは藤原氏に御縁故なき後三條天皇が即位ましますと共に、
藤原氏の権勢を抑へ、政治の革新に当られたからである。
天皇は、才学優れさせ給うた御英明の資を以て、記録所を新設され、
貴族の私有地たる荘園を調査され、その不当なるものを処分された。
その当時は、大化改新に於ける班田収授の制が廃れ、土地の兼併が行はれると共に、
開墾することに依つて私有を認められる墾田(こんでん)、功労に依って賜はつた功田(こうでん)などに依つて、
荘園は激増してゐたのである。
朝廷に租税を収めない荘園の激増は、北畠親房もその神皇正統記に於て、乱国の始めだと云つて慨嘆してゐる如く、
当時に於ける国家の大患であり、武士がその勢力を獲たのも、荘園が、その根拠を与へたからである。
後三條天皇は御在位わづか4年にして、御位を白河天皇に譲られたが、太上天皇となり給うた後、
猶ほ政治を親裁あらせられようとする思召(おぼしめし)があったが、御譲位後わづか5箇月にして崩ぜられた。
然し、これが院政の初めだと言はれてゐる。
白河天皇も、又英明の御資質で、藤原氏の権勢など顧慮せらるゝことなく、万機を決し給うてゐたが、
応徳三年、御位を堀河天皇に譲り給うた後、院庁を開いて、おん自から、万機を総攬し給ひ、
次の鳥羽天皇、崇徳(すとく)天皇まで御三代の間は、白河上皇の院政が続いたのである。
これは、従来の朝廷の高官は、藤原氏の人々で、
必ずしも練達堪能の士ではないので、新らしい人材を抜擢して、実際的な政治を行ふために、
院政と云った形式が案出されたのではなからうか。
このために、摂政関白の手中に在った政治上の実権が上皇に帰し、
藤原氏は全く雌伏するの外なくなってしまったが、
天皇御親政の理想から云へば、やはり変態であって、保元の乱の一つの原因になつたとも云はれてゐる。
藤原氏全盛時代から、この時代にかけて、重大なる社会的事実は諸国に於ける武士の擡頭である。
大化の改新に於ける軍団制度は、第49代光仁天皇の御世に、
東国辺要の地及び三関国(美濃、伊勢、越前)以外は、軍団の必要なしとして、
兵士の大都分を農に帰らしめられた時から、半ば崩解したのである。
その後、藤原氏が、中央に於ける権勢の維持、栄華の追及に専心して、
国司の遥任(ようにん)が盛んに行はれ、
遥任とは、国守に任ぜらるゝも、自らは任国に赴かず、
目代(もくだい)を差遣して政務に当らしめるものである)従つてその治績が挙るわけもなく、
軍団の廃止とともに諸国の治安は漸く乱れ、群盗所在に横行し、京畿にさへその姿を現はすに至った。
かうした紀綱の紊乱に連れて、貴族及び豪族の私有地なる荘園は、ます/\激増したが、
これ等の貴族豪族は、各自の荘園の治安を維持するため、各々の子弟もしくは臣従を武装せしめ、
武技を錬(ね)らしめたのである。これが、いはゆる武士の起源である。
しかも、これらの貴族豪族は、多くは前国司の位置にあつた守(かみ)とか、介(すけ)とか掾(じよう)などで、
その任国に土着したもので、人望も厚く、各地に強力なる武士団を形成したのである。
その強力なるものは、東国に於ける源氏であり、西国に於ける平家であつた。
而して、その統領と武士との関係は、官制上の関係でなく、人格的で情誼的であったから、
その団結力も強く、後年に於ける武家政治の基礎を築いてゐたわけである。
最初、これらの武士が、中央の政界に於ては、何等の勢力のなかったことは、
平将門(まさかど)(註)が、一検非違使たらんとする希望を拒まれたことが、
彼の後年の叛乱の遠因であると伝へられることに依つても分るが、
その後源氏第二代の源満仲などが藤原氏の股肱、爪牙(そうが)となることに依って、漸くその勢力を扶植し、
源頼義、義家は前九年、後三年の両役に、陸奥守、鎮守府将軍として武勲を輝かすと共に、
東北の武士と親炙(しんしや)し、次第にその統領たる位置を培(つちか)ったのである。
武士の擡頭と同時に、当時朝廷及び藤原氏等の尊信を得てゐた延暦寺、興福寺などは、
白河上皇の仏教御尊信に依って、いよ/\勢力を加へ、その広大なる寺領を自衛する必要上、武力を養ひ、
僧侶自身武装すると共に、浮浪の徒が之(これ)に加はり、宗門上の争ひにも武力を用ゐるばかりでなく、
朝廷に対する訴願などにも、延暦寺は日枝神社の神輿を、興福寺は春日明神の神木を奉じて、京都に乱入した。
之(これ)を嗷訴(がうそ)と称して、無理非道の振舞をしたのである。
朝廷は、これらの僧兵を防がしむるに、京都にある源平二氏の勢力を用ゐ給うたため、
武士は、いよ/\中央に於ても、その勢力を伸ばすに至ったのである。
しかも、白河上皇が、従来藤原氏の爪牙たる源氏に対抗せしめるため、
伊勢平氏たる平正盛(たひらのまさもり)、忠盛(ただもり)父子を御信任遊ばされたので、
忠盛は西海に於ける海賊討伐に功を立て、
瀬戸内海に平家の勢力を扶植すると共に、中央に進出して、鳥羽院の昇殿を許されるに至った。
かくの如くにして養はれて来た源平二氏を中心とする武士の勢力は、
保元の乱に於て、遂に中央の舞台に躍り出たのである。
保元の乱は、藤原氏に於ける父子兄弟間の権力争ひが、
皇室をまで、その渦中に引き入れ奉った戦乱であるが、
政権の争奪が、武力に依って左右さるべきものであることを、如実に示したことに依って、
今まで他の勢力の爪牙を以て甘んじてゐた武士をして、
遂に政権に対する野心を懐(いだ)かしむるに至ったのである。
されば、この戦ひに於ける殊勲者たる平清盛は、
相つゞく平治の乱に於て、その対抗勢力たりし源義朝を斃すと共に、
その官位はしきりに昇進して、太政大臣となり藤原氏に倣うて、
皇室の外戚となり、政治上の実権を握ったのである。
これは制度の上には、何の変革もなかったけれど、
その内容に於ては、平氏の武家政治であり、源頼朝の幕府政治に移る過渡期であつた。
が、幸運に依って栄達した人々が、その元(もと)を忘れるやうに、
平氏の一門も、殿上人(でんじやうびと)となつて、栄華に耽ると共に、武士たるの本領を忘れたのである。
武士が武士たるの本領を忘れたる以上、平家の武家政治が、崩解することは当然のことであった。
平将門は、桓武天皇の後裔平高望(たかもち)の孫に当り、父は陸奥鎮守府将軍平良将である。
初め、京都に出て、太政大臣藤原忠平に仕へてゐたが、
検非違使(けびゐし)になることを願つて許されなかったので、不平の余り、所領下総に帰つたと云はれる。