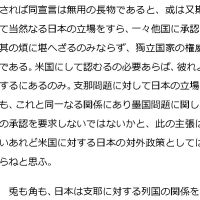第二篇 戦争史大観の序説
(別名・戦争史大観の由来記)
昭和15年12月31日於京都脱稿
昭和16年6月号「東亜連盟」に掲載
私が、やや軍事学の理解がつき始めてから、
殊に陸大入校後、最も頭を悩ました一問題は、日露戦争に対する疑惑であった。
日露戦争は、たしかに日本の大勝利であった。
しかし、いかに考究しても、その勝利が僥倖の上に立っていたように感ぜられる。
もしロシヤが、もう少し頑張って抗戦を持続したなら、
日本の勝利は危なかったのではなかろうか。
日本陸軍はドイツ陸軍に、その最も多くを学んだ。
そしてドイツのモルトケ将軍は日本陸軍の師表として仰がれるに至った。
日本陸軍は未だにドイツ流の直訳を脱し切っていない。
例えば兵営生活の一面に於ても、それが顕著に現われている。
服装が洋式になったのは、よいとしても、
兵営がなお純洋式となっているのは果して適当であろうか。
脱靴だけは日本式であるが、田舎出身の兵隊に、慣れない腰掛を強制し、
また窮屈な寝台に押し込んでいる。
兵の生活様式を急変することは、かれらの度胆を抜き、
不慣れの集団生活と絶対服従の規律の前に屈伏させる一手段であるかも知れないが、
しかし国民の兵役に対する自覚が次第に立派なものに向上して来た今日では、
その生活様式を国民生活に調和させることが必要である。
のみならず更にあらゆる点に、積極的考慮が払われるべきではないだろうか。
軍事学については、
戦術方面は体験的であるため自然に日本式となりつつあるものの、
大戦略即ち戦争指導については、いかに見てもモルトケ直訳である。
もちろん今日ではルーデンドルフを経てヒットラー流(?)に移ったが、
依然としてドイツ流の直訳を脱してはいない。
日露戦争はモルトケの戦略思想に従い
「主作戦を満州に導き、敵の主力を求めて遠くこれを北方に撃攘し、
艦隊は進んで敵の太平洋艦隊を撃破し以て極東の制海権を獲得する……」という
作戦方針の下に行なわれたのである。
武力を以て迅速に敵の屈伏を企図し得るドイツの対仏作戦ならば、
かくの如き要領で計画を立てて置けば充分である。
元来、作戦計画は第一会戦までしか立たないものである。
しかしながら日本のロシヤに対する立場はドイツのフランスに対するそれとは全く異なっている。
日本の対露戦争には単に作戦計画のみでなく、
戦争の全般につき明確な見通しを立てて置かねばならないのではないか。
これが私の青年時代からの大きな疑問であった。
日露戦争時代に日本が対露戦争につき真に深刻にその本質を突き止めていたなら、
あるいは却ってあのように蹶起する勇気を出し得なかったかも知れぬ。
それ故にモルトケ戦略の鵜呑みが国家を救ったとも言える。
しかし今日、世界列強が日本を嫉視している時代となっては、
正しくその真相を捉え根底ある計画の下に国防の大方針を確立せねばならぬ。
これは私の絶えざる苦悩であった。
陸大卒業後、
半年ばかり教育総監部に勤務した後、漢口の中支那派遣隊司令部付となった。
当時、漢口には一個大隊の日本軍が駐屯していたのである。
漢口の勤務二個年間、心ひそかに研究したことは右の疑問に対してであった。
しかし読書力に乏しい私は、殊に適当と思われる軍事学の書籍が無いため、
東亜の現状に即するわが国防を空想し、
戦争を決戦的と持続的との二つに分け、
日本は当然、後者に遭遇するものとして考察を進めて見た。
ロシヤ帝国の崩壊は日本の在来の対露中心の研究に大変化をもたらした。
それは実に日本陸軍に至大の影響を及ぼし、
様々に形を変えて今日まで、すこぶる大きな作用を為している。
ロシヤは崩壊したが同時に米国の東亜に対する関心は増大した。
日米抗争の重苦しい空気は日に月に甚だしくなり、
結局は東亜の問題を解決するためには対米戦争の準備が根底を為すべきなりとの判断の下に、
この持続的戦争に対する思索に漢口時代の大部分を費やしたのであった。
当時、日本の国防論として最高権威と目された
佐藤鉄太郎中将の『帝国国防史論』も一読した。
この史論は、
明治以後に日本人によって書かれた軍事学の中で最も価値あるものと信ぜられるが、
日本の国防と英国の国防を余りに同一視し、
両国の間に重大な差異のあることを見遁している点は、
遺憾ながら承服できなかった。
かくて私は当時の思索研究の結論として、
ナポレオンの対英戦争が、
われらの最も価値ある研究対象であるとの年来の考えを一層深くしたのであった。
明治43年頃、韓国守備中に、
箕作博士の『西洋史講話』を読んで植え付けられたこの点に関する興味が、
不断に私の思索に影響を与えつつあったのである。
ただ、箕作博士の所論もマハン鵜呑みの点がある。
後年、箕作博士が陸軍大学教官となって来られた際、
一度この点を抗議して博士から少しく傾聴せられ来訪をすすめられたが、
遂に訪ねる機会も無くそのままとなったのは、未だに心残りである。
大正十二年、ドイツに留学。
ある日、安田武雄中将(当時大尉)から、
ルーデンドルフ一党とベルリン大学のデルブリュック教授との論争に関する説明をきき、
年来の研究に対し光明を与えられしことの大なるを感知して、
この方面の図書を少々読んだのであるが、
語学力が不充分で、読書力に乏しい私は、
あるいは半解に終ったかとも思われるが、
ともかくデルブリュック教授の殲滅戦略、消耗戦略の大体を会得し得て盛んにこの言葉を使用し、
陸軍大学に於ける私の欧州古戦史の講義には、
戦争の二大性質としてこの名称を用いたのであった。
ドイツに赴く途中、
シンガポールに上陸の際、国柱会(こくちゅうかい)の人々から歓迎された席上に於て、
私はシンガポールの戦略的重要性を強調し、
英国はインドの不安を抑え、
豪州防衛のために戦略的側面陣地価値ある同地を、
近く要塞化すべきを断じたのであったが、
この後、間もなく実現したので、当時列席した人から感慨深い挨拶状を受けたことがあった。
ドイツ留学の二年間は、
主として欧州大戦が殲滅戦略から消耗戦略に変転するところに興味を持って研究したのであるが、
語学力の不充分と怠慢性のため充分に勉強したと言えず、誠にお恥ずかしい次第である。
欧州大戦につき少しく研究するとともに、
デルブリュックとドイツ参謀本部最初の論争戦であったフリードリヒ大王の研究を必要とし、
且つかねての宿望であったナポレオンを研究し、
大王の消耗戦略からナポレオンの殲滅戦略への変化は欧州大戦の変化とともに軍事上最も興味深い研究なるべしと信じ、
両名将の研究に要する若干の図書を買い集めたのであった。
明治の末から大正の初めにかけての会津若松歩兵第65連隊は、
日本の軍隊中に於ても最も緊張した活気に満ちた連隊であった。
この連隊は幹部を東北の各連隊の嫌われ者を集めて新設されたのであったが、
それが一致団結して訓練第一主義に徹底したのである。
明治42年末、少尉任官とともに山形の歩兵第32連隊から若松に転任した私は、
私の一生中で最も愉快な年月を、
大正4年の陸軍大学入校まで、この隊で過ごしたのである。
いな、陸軍大学卒業までも、
休みの日に第4中隊の下士室を根城として兵とともに過ごした日は、極めて幸福なものであった。
私自身は陸大に受験する希望がなかったのであるが、
余り私を好かぬ上官たちも、連隊創設以来一名も陸大に入学した者がないので、
連隊の名誉のためとて、
比較的に士官学枚卒業成績の良かった私を無理に受験させたのである。
私の希望通り陸大に入校しなかったならば、
私は自信ある部隊長として、真に一介の武人たる私の天職に従い、
恐らく今日は屍を馬革に包み得ていたであろう。
しかるに私は入学試験に合格した。
これには友人たちも驚いて
「石原は、いつ勉強したか、どうも不思議だ」とて、
多分、他人の寝静まった後にでも勉強したものと思っていたらしい。
余り大人気ないので私は、
それに対し何も言ったことはなかったが、
起床時刻には連隊に出ており、
消灯ラッパを通常は将校集会所の入浴場で聞いていた私は、
宿に帰れば疲れ切って軍服のまま寝込む日の方が多かったのである。
あのころは記憶力も多少よかったらしいが、
入学試験の通過はむしろ偶然であったろうと思う。
しかしこれは連隊や会津の人々には大きな不思議であったらしい。
山形時代も兵の教育には最大の興味を感じていたのであるが、
会津の数年間に於ける猛訓練、殊に銃剣術は今でも思い出の種である。
この猛訓練によって養われて来たものは兵に対する敬愛の念であり、
心を悩ますものは、この一身を真に君国に捧げている神の如き兵に、
いかにしてその精神の原動力たるべき国体に関する信念感激をたたき込むかであった。
私どもは幼年学校以来の教育によって、
国体に対する信念は断じて動揺することはないと確信し、
みずから安心しているものの、
兵に、世人に、更に外国人にまで納得させる自信を得るまでは安心できないのである。
一時は筧博士の「古神道大義」という
私には むずかしい本を熱心に読んだことも記憶にあるが、
遂に私は日蓮聖人に到達して真の安心を得、
大正9年、漢口に赴任する前、国柱会の信行員となったのであった。
殊に日蓮聖人の「前代未聞の大闘諍(とうじょう)一閻浮提(えんぶだい)に起るべし」は
私の軍事研究に不動の目標を与えたのである。
戦闘法が幾何学的正確さを以て今日まで進歩して来たこと、
即ち戦闘隊形が点から線に、
更に面になったことは陸軍大学在学当時の着想であった。
いな恐らくその前からであったらしい。
大正三年夏の 「偕行社記事別冊」 として発表された
恐らく曽田中将の執筆と考えられる 「兵力節約案」 は、
面の戦術への世界的先駆思想であると信ずるが、
私がこの案を見て至大の興味を感じたことは今日も記憶に明らかである。
教育総監部に勤務した頃、
当時わが陸軍では
散兵戦術から今日の戦闘群の戦法に進むことに極めて消極的であったのであるが、
私が自信を以て積極的意見を持っていたのは、この思想の結果であった。
私の最終戦争に対する考えはかくて、
1 日蓮聖人によって示された世界統一のための大戦争。
2 戦争性質の二傾向が交互作用をなすこと。
3 戦闘隊形は点から線に、更に面に進んだ。次に体となること。
の三つが重要な因子となって進み、ベルリン留学中には全く確信を得たのであった。
大正何年か忘れたが、
緒方大将一行が兵器視察のため欧州旅行の途中ベルリンに来られたとき、
大使館武官の招宴があり、
私ども駐在員も末席に連なったのであるが、
補佐官坂西少将(当時大尉)が五分間演説を提案し最初に私を指名したので私は立って、
「何のため大砲などをかれこれ見て歩かれるのか。
余り遠からず戦争は空軍により決せられ世界は統一するのだから、
国家の全力を挙げて最優秀の飛行機を製作し得るよう今日から準備することが第一」
というようなことを述べたのであるが、
これは緒方大将を少々驚かしたらしく数年後、
陸軍大臣官邸で同大将にお目にかかったとき、特に御挨拶があった。
大正十四年秋、シベリヤ経由でドイツから帰国の途中、
哈爾賓(ハルビン)で国柱会の同志に無理に公開演説に引出された。
席上で
「大震災により破壊した東京に十億の大金をかけることは愚の至りである。
世界統一のための最終戦争が近いのだから、
それまでの数十年はバラックの生活をし戦争終結後、
世界の人々の献金により世界の首都を再建すべきだ」といったようなことを言って、
あきれられたことも覚えている。
ドイツから帰国後、陸軍大学教官となったが、
大正十五年初夏、故筒井中将から、
来年の2年学生に欧州古戦史を受け持てとの話があり、
一時は躊躇したが再三の筒井中将の激励があり、
もともと私の最も興味をもっていた問題であったため、
遂に勇を鼓してお受けすることになった。
かくて同年夏、
会津の川上温泉に立て籠もり日本文の参考資料に熱心に目を通した。
もちろん泥縄式の甚だしいものであったが、
講義の中心をなす最終戦争を結論とする戦争史観は脳裡に大体まとまっていたので、
とりあえず何とか片付け、大正十五年暮から十五回にわたる講義を試みたのであった。
「近世戦争進化景況一覧表」(121頁参照)はそのときに作られたのである。
昭和二年の同二年学生に対する講義は35回であったが、
今度は少し余裕があったため、ドイツから持ち帰った資料を勉強し、
更にドイツにいた原田軍医少将(当時少佐)、
オーストリア駐在武官の山下中将をもわずらわして不足の資料を収集した。
昭和元年から2年への冬休みは、
安房あわの日蓮聖人の聖蹟で整頓した頭を以て、
とにかく概略の講義案を作成した。
もちろん、根本理論は前年度のものと変化はないのである。
当時、陸軍大学幹事坂部少将から熱心な印刷の要望があったが、
充分に検討したものでもないので、これに応ずる勇気も無く、
現在も私の手元に保存してある次第である。
昭和3年度のためには、
前年の講義録を再修正する前に、
私の年来最大の関心事であるナポレオンの対英戦争の大陸封鎖の項に当面し、
全力を挙げて資料を整理し、
昭和2年から3年への年末年始は、これを携えて伊豆の日蓮聖人の聖蹟に至り、
構想を整頓して正月中頃から起草を始めようとしたとき、流感にかかり中止。
その後、再び着手しようとすると今度は猛烈な中耳炎に冒されて約半歳の間、
陸軍軍医学校に入院し、遂に目的を達せずして終ったのであった。
その後もこの研究、
特に執筆を始めると不思議にも必ず病気にかかるので
「アメリカの神様が必死に邪魔をするんだろう」などと冗談を言うような有様であった。
昭和2年の晩秋、
伊勢神宮に参拝のとき、
国威西方に燦然として輝く霊威をうけて帰来。
私の最も尊敬する佐伯中佐にお話したところ余り良い顔をされなかったので、
こんなことは他言すべきでないと、誰にも語ったことも無く、そのままに秘して置いたのであるが、
当時の厳粛な気持は今日もなお私の脳裏に鞏固きょうこに焼き付いている。
昭和3年10十月、関東軍参謀に転補。
当時の関東軍参謀は今日考えられるように人々の喜ぶ地位ではなかった。
旅順で関東庁と関東軍幹部の集会をやる場合、
関東庁側は若い課長連が出るのに軍では高級参謀、高級副官が止まりで、
私ども作戦主任参謀などは列席の光栄に浴し得なかった。
満鉄の理事などにも同席は不可能なことで、
奉天の兵営問題で当時の満鉄の地方課長から散々に油をしぼられた経験は、
今日もなお記憶に残っている。
関東軍に転任の際も、
今後とも欧州古戦史の研究を必ず続ける意気込みで赴任した
特に万難を排しナポレオンの対英戦争を書き上げる決心であった。
しかし中耳炎病後の影響は相当にひどく、
何をやっても疲れ勝ちで遂に初志を貫きかねた。
漢口駐屯時代に徐州で木炭中毒にかかり、そ
れ以来、脈搏に結滞を見るようになり、
一時は相当に激しいこともあり、
また漢口から帰国後、マラリヤにかかったなどの関係上、
爾後の健康は昔日の如くでなく、
且つ中年の中耳炎は根本的に健康を破壊し、
殊に満州事変当時は大半、横臥して執務した有様であった。
かような関係で族順では遂に予定の計画を果し得なかったが、
しかし陸大教官2個年間の講義は未消化であり、
特にデルブリュックの影響強きに失し、
戦争指導の両方式即ち戦争の性質の両面を「殲滅戦略」「消耗戦略」と命名していたのは、
どうも適当でないとの考えを起し、
この頃から戦争の性質を「殲滅戦争」「消耗戦争」の名を用いて、
戦略に於ける「殲滅戦略」「消耗戦略」との間の区別を明らかにすることにした。
「殲滅戦争」「消耗戦争」の名称を
「決戦戦争」「持久戦争」に改めたのは満州事変以後のことである。
昭和四年五月一日、関東軍司令部で各地の特務機関長らを集め、
いわゆる情報会議が行なわれた。
当時の軍司令官は村岡中将で、
河本大佐はその直前転出し、
板垣征四郎大佐が着任したばかりであった。
奉天の秦少将、吉林の林大八大佐らがいたように覚えている。
この会議はすこぶる重大意義を持つに至った。
それは張作霖爆死以後の状況を見ると、
どうも満州問題もこのままでは納まりそうもなく今後、
何か一度、事が起ったなら結局、全面的軍事行動となる恐れが充分にあるから、
これに対する徹底せる研究が必要だとの結論に達したのであった。
その結果、昭和4年7月、
板垣大佐を総裁官とし、関東軍独立守備隊、駐箚(ちゅうさつ)師団の参謀らを以て、
哈爾賓、斉々哈爾(チチハル)、海拉爾(ハイラル)、満州里(マンチュウリ)方面に参謀演習旅行を行なった。
演習第1日は車中で研究を行ない長春に着いた。
車中で研究のため展望車の特別室を借用することについて、
満鉄嘱託将校に少なからぬ御迷惑をかけたことなど思い出される。
第2日の研究は私の「戦争史大観」であり、
その説明のための要旨を心覚えに書いてあったのが「戦争史大観」の第一版である。
第3日は吟爾賓に移り研究を続け、
夜中に便所に起きたところ北満ホテルの板垣大佐の室に電灯がともっている。
入って見ると、板垣大佐は昨日の私の講演の要点の筆記を整理しているのに驚いた。
板垣大佐の数字に明るいのは兵要地誌班出身のためとのみ思っていた私は、
この勉強があるのに感激した次第であった。
この頃から満蒙問題はますますむずかしくなり、
私も大連で二、三度、私の戦争観を講演し、
「今日は必要の場合、
日本が正しいと信ずる行動を断行するためには
世界の圧迫も断じて恐れる必要がない」旨を強調したのであった。
時勢の逼迫(ひっぱく)が私の主張に耳を藉かす人も生じさせていたが、
事変勃発後、私の「戦争史大観」が謄写刷りにされて若干の人々の手に配られた。
こんな事情で満州建国の同志には事変前から知られ、
特に事変勃発後は「太平洋決戦」が逐次問題となり、
事変前から唱導されていた伊東六十次郎(むそじろう)君の歴史観と一致する点があって、
特に人々の興味をひき爾来、満州建国、東亜連盟運動の世界観に若干の影響を与えつつ十年の歳月を経て、
遂に今日の東亜連盟協会の宣言にまで進んで来たのである。
昭和七年夏、私は満州国を去り、
暮には国際連盟の総会に派遣されてジュネーブに赴いた。
ジュネーブでは別にこれという仕事もなかったので、
フリードリヒ大王とナポレオンに関する研究資料を集め、
昭和八年の正月はベルリンに赴いて坂西武官室の一室を宿にし、
石井(正美)補佐官の協力により資料の収集につとめた。
帰国後も石井補佐官並びに宮本(忠孝)軍医少佐には、
資料収集について非常にお世話になった。
固より大したものでないが、
前に述べた人々の並々ならぬ御好意に依って、
フランス革命を動機とする持久・決戦両戦争の変転を研究するための、
即ち稀代の名将フリードリヒ大王並びにナポレオンに関する軍事研究の資料は、
日本では私の手許に最も良く集まっている結果となった。
私は先輩、友人の御好意に対し必ず研究を続ける決心であったが、
その後の健康の不充分と職務の関係上、遂に無為にして今日に及んでいる。
資料もまた未整理のままである。
今日は既に記憶力が甚だしく衰え且つドイツ語の読書力がほとんどゼロとなって、
一生私の義務を果しかねると考えられ、誠に申訳のない次第である。
有志の御研究を待望する。
支那事変勃発当時、
作戦部長の重職にあった私は、到底その重責に堪えず十月、関東軍に転任することとなった。
文官ならこのときに当然辞職するところであるが軍人にはその自由がない。
昭和13年、大同学院から国防に関する講演を依託されて
「戦争史大観」をテキストとすることとなり若干の修正を加えた。
「将来戦争の予想」については、
旧稿は日米戦争としてあったのを、
「東亜」と西洋文明の代表たる「米国」たるべきことを明らかにしたが、
「現在に於ける我が国防」は根本的に書き換えたのである。
昭和4年の分は次の如くであった。
1
欧州大戦に於けるドイツの敗戦を極端ならしめたるは、
ドイツ参謀本部が戦争の本質を理解せざりしこと、また有力なる一原因なり。
学者中には既に大戦前これに関する意見の一端を発表せるものあり、
デルブリュック氏の如きこれなり。
2
日露戦争に於ける日本の戦争計画は「モルトケ」戦略の直訳にて勝利は天運によりしもの多し。
目下われらが考えおる日本の消耗戦争は作戦地域の広大なるために来たるものにして、
欧州大戦のそれとは根本を異にし、
むしろナポレオンの対英戦争と相似たるものあり。
いわゆる国家総動員には重大なる誤断あり。
もし百万の軍を動かさざるべからずとせば日本は破産の外なく、
またもし勝利を得たりとするも戦後立つべからざる苦境に陥るべし。
3 露国の崩壊は天与の好機なり。
日本は目下の状態に於ては世界を相手とし東亜の天地に於て持久戦争を行ない、
戦争を以て戦争を養う主義により、長
年月の戦争により、良く工業の独立を完うし国力を充実して、
次いで来るべき殲滅戦争を迎うるを得べし。
昭和4年頃はソ連は未だ混沌たる状態であり、
日本の大陸経営を妨げるものは主として米国であった。
昭和6年 「満蒙問題解決のための戦争計画大綱」を起案している。
固より簡単至極のものであるが当時、
未だ「戦争計画」というような文字は使用されず、
作戦計画以外の戦争に関する計画としては、
いわゆる「総動員計画」なるものが企画せられつつあったが、
内容は戦争計画の真の一部分に過ぎず、
しかもその計画は第一次欧州大戦の経験による欧州諸国の方針の鵜呑みの傾向であったから、
多少戦争の全体につき思索を続けていた私には記念すべき思い出の作品である。
昭和13年には東亜の形勢が全く変化し、
ソ連は厖大なその東亜兵備を以て北満を圧しており、
米国は未だその鋒鋩(ほうぼう)を充分に現わしてはいなかったが、
満州事変以来努力しつつあったその軍備は、いつ態度を強化せしむるかも計り難い。
即ち日本は10年前の如く露国の崩壊に乗じ、
主として米国を相手とし、
戦争を以て戦争を養うような戦争を予期できない状態になっていたのである。
そこで持久戦争となるべきを予期して、
米・ソを中心とする総合的圧力に対する武力と経済力の建設を国防の目標とする如く書き改めた。
「若し百万の軍を動かさざるべからずとせば日本は破産の外なく……」というような古い考えは、
自由主義の清算とともに一掃されねばならないことは言うまでもない。
昭和10年8月、私は参謀本部課長を拝命した。
三宅坂の勤務は私には初めてのことであり、
いろいろ予想外の事に驚かされることが多かった。
満州事変から僅かに4年、
満州事変当初の東亜に於ける日・ソの戦争力は大体平衡がとれていたのに、
昭和11年には既に日本の在満兵力はソ連の数分の一に過ぎず、
殊に空軍や戦車では比較にならないことが世界の常識となりつつあった。
日本の対ソ兵備は次の2点については何人も異存のないことである。
1 ソ連の東亜に使用し得る兵力に対応する兵備。
2 ソ連の東亜兵備と同等の兵力を大陸に位置せしめる。
私はこの簡単明瞭な見地から在満兵備の大増加を要望した。
しかしそのときの考えは余りに消極的であったことが今となれば恥ずかしい極みである。
小胆ものだから自然に日本の現状即ち政治的関係に左右されたわけである。
しかし世間では石原はド偉い要求を出すとの評判であったらしい。
その頃ちょうど上京中であった星野直樹氏(私は未だ面識が無かった)から、
大蔵省の局長達が日本財政の実情につき私に説明したい希望だと伝えられたが、
私はその必要はない旨を返答したところ、
重ねて日本の国防につき、
できるだけのことを承りたいとのことであったので遂に承諾し、
山王ホテルの星野氏の室で会見した。
先方は星野氏の他に賀屋、石渡、青木の三氏がおられた。
賀屋氏が、まず日本財政につき説明された。
それは約束と違うと思ったが私も耐えて終るまで待っており、
私の国防上の見地を軍機上許す限り私としては赤誠を以て説明した積りである。
終ると先方から、
「現在の日本の財政では無理である」
「無い袖は振られない」というようないろいろの抗議的説明や質問があったが、
私は「私ども軍人には明治天皇から
『世論に惑わず政治に拘らず只一途に己が本分』を尽すべきお諭さとしがある。
財政がどうであろうと皆様がお困りであろうと、
国防上必要最少限度のことは断々固として要求する」旨お答えして辞去した。
私のこういう態度主張を、世の中には一種の駆引のように考える向きもあったらしいが、
断じてそんなことはあり得ない。
いやしくも軍人がお勅諭を駆引に用いることがあり得るだろうか。
世はいよいよ国防国家の必要を痛感して来た。
国防国家とは軍人の見地から言えば、
軍人が作戦以外のことに少しも心配しなくともよい状態であることで、
軍としては最も明確に国家に対して軍事上の要求を提示しなければならない。
私は世人の誤解に抗議するとともに、
私のこの態度だけは、わが同僚並びに後輩の諸君に私のようにせられることを、
おすすめするものである。
私は一試案を作ってそれに要する戦費を、
その道に明るい一友人に概算して貰った。
友人の私に示した案は私の立案の心理状態と同一で、
どうやら内輪に計算されているらしい。
私の考えでは軍は政府に軍の要求する兵備を明示する。
政府はこの兵備に要する国家の経済力を建設すべきである。
しかし当時の自由主義の政府は、
われらの軍費を鵜呑みにしてもこれに基づく経済力の建設は到底、
企図する見込みがないところから、
軍事予算は通過しても戦備はできない。
考え抜いた結果、
何とかして生産力拡充の一案を得て具体的に政府に迫るべきだと考え、
板垣関東軍参謀長と松岡満鉄総裁の了解を得て、
満州事変前から満鉄調査局勤務のため関東軍と密接な連絡があり
事変後は満鉄経済調査会を設立した宮崎正義氏に、
「日満経済財政研究会」を作ってもらい、
まず試みに前に述べた私案に基づき日本経済建設の立案をお願いしたのである。
誠に無理な要求であり、
立案の基礎条件は甚だ曖昧を極めていたにかかわらず、
宮崎氏の多年の経験と、そのすぐれた智能により、
遂に昭和11年夏には日満産業5個年計画の最初の案ができたのである。
真に宮崎氏の超人的活動の賜物である。
この案はもちろん宮崎氏の一試案に過ぎないし、
その後、軍備の大拡充が行なわれた結果、
日本の生産拡充計画も自然大きくなったことと信ずるが、
いずれにせよ宮崎氏の努力は永く歴史に止むべきものである。
宮崎氏は後に参謀本部嘱託となり幾多の有益な計画を立て、
国策の方向決定に偉大な功績を樹てられたことと信ずる。
この宮崎氏の研究の要領を聴き、
私も数年前自由主義時代・帝政ロシヤ崩壊時代に、
「百万の軍隊を動かさざるべからずとせば日本は破産の外なく……」と
日本の戦争力を消極的に見ていた見地を心から清算した。
即ち日本は断固として統制主義的建設により、
東亜防衛のため米・ソの合力に対抗し得る実力を養成することを絶対条件と信じ、
国家が真に自覚すればその達成は必ず可能なるを確信するに至ったのである。
経済力が極めて貧弱で、重要産業はほとんど英米依存の現状に在った日本は、
至急これを脱却して自給自足経済の基礎を確立することが第一の急務なるを痛感し、
外交・内政の総てをこの目的達成に集中すべく、
それが国防の根本であることを堅く信じて来たのであるが、
満州国は十二年から計画経済の第一歩を踏み出したものの、
日本は遂にこれに着手するに至らないで支那事変を迎えたのである。
国家は戦争・建設同時強行との、えらい意気込みであったが、
日本としてこの二大事業の同時遂行は残念ながら至難なことが、
戦争の経験によって明らかとなった。
しかし、いかなることが起るとも米・ソ両国の実力に対抗し得る力なき限り、
国防の安定せざることを明らかにしたのが昭和十三年の訂正である。
昭和14年、留守第16師団長中岡中将の命により、
京都衛戌講話に「戦争史大観」を試みたが、
その後、人々の希望により、昭和15年1月印刷するに当り、
既に第二次欧州大戦が勃発したため、若干の小修正を加えたのが現在のものである。
フランス革命から第一次欧州戦争の間が決戦戦争の時代であり、
この期間は125年である。
その前の持久戦争時代は大体三、四百年と見ることができる。
もちろんこの時代の区分や、その年数については、
簡単に断定することに無理はあるが、
大勢は推断することができると信ずる。
第一次欧州大戦から次の大変換即ち最終戦争までの持久戦争期間は、
この勢いで見れば、すこぶる短いように考えられる。
同時に私の信仰から言えば、
その決勝戦に信仰の統一が行なわれねばならぬ。
僅か数十年の短い年月で一天四海皆帰妙法は可能であろうか。
最終戦争までの年数予想は恐ろしくて発表の勇気なく、
ただ案外近しとのみ称していた。
昭和13年12月、舞鶴要塞司令官に転任。
舞鶴の冬は毎日雪か雨で晴天はほとんどない。
しかし旅館清和楼の一室に久し振りに余り来訪者もなく、
のどかに読書や空想に時間を過ごし得たのは誠に近頃にない幸福の日であった。
この静かな時間を利用して東洋史の大筋を一度復習して見たい気になり、
中学校の教科書程度のものを読んでいる中に突如、一大電撃を食らった。
私は大正8年以来、日蓮聖人の信者である。
それは日蓮聖人の国体観が私を心から満足せしめた結果であるが、
そのためには日蓮聖人が真に人類の思想信仰を統一すべき霊格者であることが絶対的に必要である。
仏の予言の適中の妙不可思議が私の日蓮聖人信仰の根底である。
難しい法門等は、とうてい私には分かりかねる。
しかるに東洋史を読んで知り得たことは、
日蓮聖人が末法の最初の五百年に生まれられたものとして信じられているのであるが、
実は末法以前の像法に生まれられたことが今日の歴史ではどうも正確らしい。
私はこれを知ったとき、真に生まれて余り経験のない大衝撃を受けた。
この年代の疑問に対する他の日蓮聖人の信者の解釈を見ても、どうも腑に落ちない。
そこで私は日蓮聖人を人格者・先哲として尊敬しても、
霊格として信仰することは断然止むべきだと考えたのである。
このことに悩んでいる間に私は、
本化上行(ほんげじょうぎょう)が二度出現せらるべき中の僧としての出現が、
教法上のことであり観念のことであり、
賢王としての出現は現実の問題であり、
仏は末法の五百年を神通力を以て二種に使い分けられたとの見解に到達した。
日蓮教学の先輩の御意見はどうもこれを肯定しないらしいが、
私の直感、私の信仰からは、これが仏の思召にかなっていると信ずるに至ったのである。
そして同時に世界の統一は仏滅後2500年までに完成するものとの推論に達した。
そうすると軍事上の判断と甚だ近い結論となるのである。
昭和14年3月10日、病気治療のため上京していた私は、
協和会東京事務所で若干の人々の集まりの席上で戦争論をやり、
右の見解からする最終戦争の年代につき私の見解を述べた。
この講演の要領が人々によって印刷され、
誰かが「世界戦争観」と命名している。
昭和15年5月29日の京都義方会に於ける講演筆記
(第二次欧州大戦の急進展により同年八月印刷に付する際その部分を少し追補した)の出版されたのが、
立命館版 『世界最終戦論』 である。
要するにこれは私の30年ばかりの軍人生活の中に考え続けて来たことの結論と言うべきである。
空想は長かったが、
前に述べた如く真に私が学問的に戦史を研究したのは、
主としてフリードリヒ大王とナポレオンだけであり、
しかもその期間も大正15年夏から昭和3年2月までの約一年半に過ぎないのである。
研究は大急ぎで素材を整理したくらいのところで、
まだまだ消化したものではなく、
殊に私の最も関心事であったナポレオンの対英戦争は、
その最重要点の研究がまとまらずにいるのである。
最終戦争論に論じてあるフリードリヒ大王以前のことは真に常識的なものに過ぎない。
私は常に人様の前で「軍事学については、いささか自信がある」と広言しているが、
このように真相を白状すれば誠に恥ずかしい次第である。
日本に於ける軍事学の研究がドイツやソ連の軍事研究に比し甚だ振わないことは、
遺憾ながら認めざるを得ない。
私は、戦友諸君はもちろんのこと、政治・経済等に関心を有する一般の人士も、
軍事につき研究されることを切望して止まないのである。
満州問題で国際連盟の総会に出張したときに、
ある日ジュネーブで伊藤述史公使が私に、
「日本には日本独特の軍事学があるでしょうか」と質問されたが、
私は
「いや、伊藤さん、どうも遺憾ながら明治以後には、
さようなものは未だできていない」と答えると伊藤氏は青くなって、
「それは大変だ。一つ東京に帰ったらお互に軍事研究所を作ろうではないか」と提案された。
なぜ、さようなことを伊藤氏が言ったかと聞いて見ると、
伊藤氏がフランス大使館の書記生の時代に、
田中義一大将がフランスに廻って来て盛んに外交官の無能を罵倒したらしい。
それで伊藤氏は大いに憤慨したが、
軍人はともかく政治・経済の若干を知っているのに、
外交官は軍事学を知っていないことに気がつき、
フランスの友人から軍事学の先生を探して貰った。
それが当時陸軍大学の教官であったフォッシュ少佐で、
同少佐から主としてナポレオン戦争の講義を聞いたのである。
第一次欧州大戦後、フォッシュ元帥から
「フランスを救ったものはフランス独特の軍事学であった。
独特の軍事学なき国民は永遠の生命なし」との意見を聞き、
伊藤公使の脳裡に深い印象を与えているらしい。
フランスが第二次欧州大戦によってこんなふうに打ちのめされた今日、
フォッシュ元帥のこの言葉は素人には恐らく大きな魅力を失ったであろうが、
この中に含むある真理はわれらも充分に玩味すべきである。
伊藤氏はそのときの講義録を私にくれるとてパリの御宅を再三探して下さったが遂に発見できなかった。
私はあきらめかねてなおも若し見付かったらと御願いして置いたが、
パリを引払われた後も何らの御通知がないから、
遂に発見されなかったのであろう。
世人は、軍が軍事上のことを秘密にするから軍事の研究ができないようなことを言うが、
それはとんでもないことである。
もちろん前述の通り軍人間の軍事学の研究も不振であるから、
日本語の軍事学の図書は残念ながら西洋列強諸国に比して余りに貧弱である。
しかし公刊の戦史その他の出版物が相当にあるのだから、
研究しようとするなら必ずできる。
私は少なくも政治・経済の大学には軍事学の講座を設くべしと多年唱導して来た。
配属将校は軍事学を講義すべきものではなく、
また多くの人はそんな力は持っていない。
西洋人の軍事学の常識に比し、日本知識人のそれはあまりに劣っている。
ドイツの中産以上の家庭には通常、ヒンデンブルグやルーデンドルフの回想録は所有されており、
広く読まれている。
これらの図書は立派な戦史書である。
一家の主婦すら相当に軍事的知識を持っていることは私の実見せるところである。
(昭和15年12月31日)
【続く】 石原莞爾 『戦争史大観』 第三篇 戦争史大観の説明 第一章 緒論