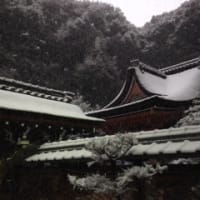25日が最終日のシャガール展に、駆け込みで行ってきた。前にも見たしもういいかっ・・・・なんて思ってたが、今回は大満足!だった。とっくに見に行ったhus.がよかったよかったと連呼していたのもうべなるかな・・・・だ。
大作ぞろいで、これぞシャガールと言う作品のオンパレード、さりながら多すぎてうんざりと言うことも無く、展観の流れが実にスムーズだった。大きく4つのパートに分けられていて、それぞれ
Ⅰ 故郷ロシア
Ⅱ 結婚ー幸福な日々
Ⅲ 悲しみの日々そして追憶・幻想へ
Ⅳ 版画シリーズ『ダフニスとクロエ』
スタートの《Ⅰ故郷ロシア》には、1910年ごろからの初期の作品群。試行錯誤の時代か、これはルオーに似てるとかブラックに似てるとか思いつつ、あっちょっとシャガールらしさの萌芽が・・・とそんな感じ。底辺に故郷の町や肉親への愛が漂い、しかし人はまだ空に浮遊していない。インクで書かれた白黒の数点(負傷した兵士ほか)が気にいった。
日本人tesyukeにはユダヤ人だから何? 別に?と、思うのだが、だんだんとシャガールにユダヤ人画家と言う側面があらわれて来る。1920年33歳のシャガールが依頼されて描いたモスクワのユダヤ劇場の壁画がⅠの最後を飾り圧巻。小劇場内部を模した小部屋に7点の壁画が配置され、観劇に来た人がこのように見たのか・・と、往時をしのぶ。ユダヤの習慣・比喩などがちりばめられた絵画に不思議を見る思い。
Ⅱは特別室で大作4点展示。30代のもの。でました彼と妻が空を浮遊している《街の上で》。そして《散歩》《結婚式》。多作の人の全作品の中で、シャガールの名を決定的にしたということで、これらに如くもの無しと特別扱いなのかも。もう一点は《ヴィテブスクの眺め》で彼の故郷の町を描いたもの。浮遊している恋人の下に描かれている街。
ところで、空に浮いているのが非現実と見る向きも多いが、ユダヤでは、うれしいときには天に昇る心地と言った比喩がある。恋人が浮遊しているのはシャガールには現実なんだという解説があった(うろおぼえだが)。英語にもin the seventh heavenと言う言い方があり何故だか知らないがうれしい時は第七天国にいるそうだ。そして、シャガールも言っている。《私を夢想家と呼ばないで欲しい。反対に私はレアリストなのだ。私は大地を愛している。》
Ⅲは晩年の作品群。ユダヤ人であるがゆえに戦火の中を転々とヨーロッパ・アメリカ・ヨーロッパと住み家を移し、最愛の妻を亡くし、再婚し、と長い98歳の生涯。
Ⅳは1961年制作の版画。多色刷りで画題とシャガールの作風がマッチして素敵だった。42点全てが日本の某会社の所有だ。