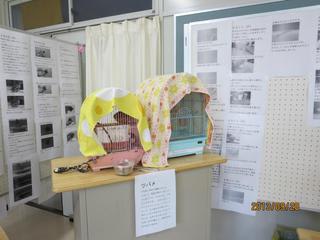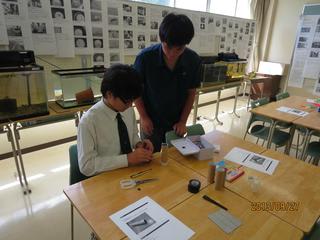今日は、硫黄の性質について実験をしました。
硫黄には3つの同素体が存在します。
同素体とは、ただ一種類の元素からできた物質で、同じ元素からできているのに、
見た目や性質が違うもののことをいいます。
有名なものは炭素の同素体です。
鉛筆の芯に使われるものはグラファイト(黒鉛)と呼ばれていて、
はがれやすいのが特徴です。
ダイヤモンドも炭素からできていますが、黒鉛と違って、
非常に硬い無色の結晶です。
そのほかにもフラーレン・カーボンナノチューブなどがあります。
硫黄の場合は、3つの同素体が有名で、
① 斜方硫黄 1気圧で一番安定している八面体の結晶です。
② 単斜硫黄 融解した硫黄をゆっくり冷やすとできる針状の結晶です。
③ ゴム状硫黄 融解した硫黄を急冷するとできる、ゴムのように伸びる
硫黄です。
硫黄には3つの同素体が存在します。
同素体とは、ただ一種類の元素からできた物質で、同じ元素からできているのに、
見た目や性質が違うもののことをいいます。
有名なものは炭素の同素体です。
鉛筆の芯に使われるものはグラファイト(黒鉛)と呼ばれていて、
はがれやすいのが特徴です。
ダイヤモンドも炭素からできていますが、黒鉛と違って、
非常に硬い無色の結晶です。
そのほかにもフラーレン・カーボンナノチューブなどがあります。
硫黄の場合は、3つの同素体が有名で、
① 斜方硫黄 1気圧で一番安定している八面体の結晶です。
② 単斜硫黄 融解した硫黄をゆっくり冷やすとできる針状の結晶です。
③ ゴム状硫黄 融解した硫黄を急冷するとできる、ゴムのように伸びる
硫黄です。