
《『宮沢賢治と法華経について』(田口昭典著、でくのぼう出版)の表紙》
ではここからは〝第四章 「雨ニモマケズ手帳」から臨終まで〟に移る。
この章はまず〝◎「雨ニモマケズ手帳」について〟という節で始まるのだが、この節には法華経と直接関連することは論じられていないので、次の節〝◎「雨ニモマケズ手帳」と法華経〟を見てみたい。それは、
賢治は大正十四年頃「法華堂建立勧進文」を記した後は、法華経についてや日蓮宗についての活動はしなかった。したくても出来なかったのである。羅須地人協会の活動、肥料設計のための農村巡回、過労による発病、病臥、東北砕石工場のための奔走、再発病という慌ただしい時間の中では、その余裕が無かったということである。
〈『宮沢賢治と法華経について』(田口昭典著、でくのぼう出版)190p~〉と始まっている。
そして、
賢治は最後まで法華経を信じ日蓮宗の信徒としてその一生を終えてということは疑う余地がない。そのひとつの証拠が、最晩年の「雨ニモマケズ手帳」の中に残されているのである。
〈同191p〉と田口氏は断じていた。
具体的にはまず「曼荼羅」そのものについて田口氏は説明をし、次に、同手帳には「略式曼荼羅」が次の5ヶ所に記されていると紹介し、その証拠だと言う。ちばみにそれらは、
①手帳4p

②手帳60p

③手帳149~150p

④手帳153~154p

⑤手帳155~156p

〈写真はいずれも『校本宮澤賢治全集 資料第五(復元版宮澤賢治手帳)』より〉
というようなものである。
そして、ここに登場している
上行菩薩
浄行菩薩
無辺行菩薩
安立行菩薩
の四菩薩は皆、多くの菩薩の中でトップの位置を占める者達である、と田口氏は教えてくれる(同192p~)。
実際、こうしてこれだけの回数曼荼羅が書かれている復元手帳を眺めていると、少なくともこの手帳が書かれたであろう昭和6年末頃までの賢治は熱心に法華経を信じていたこと、敬虔な日蓮宗の信徒であったことなどはたしかに間違いなさそうだ。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “〝『宮沢賢治と法華経について』より〟の目次”へ。
“〝『宮沢賢治と法華経について』より〟の目次”へ。“岩手の野づら”のトップに戻る。












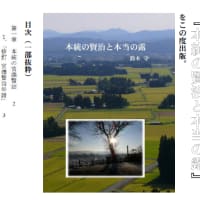
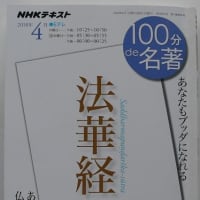
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます