
たしかに、教員になる前の
教育現場の仕事の時から、
いわゆる「発達障害」という
言葉が出てくることも
増えてきたのを実感してました。
たぶん、そう感じているのは
私だけじゃないはず。
医療関係者の筆者もそう感じていて、
専門家の目線で、それが
ただの感覚的な感じでは無いことを
詳しく、分析・説明してくれていて、
とても納得する一冊でした。
「発達障害」のように見えるけど
「発達障害」じゃない、
「発達障害もどき」。
実はこの、「発達障害もどき」が
増えているのでは、という推論から、
筆者は、どんなスーパードクターでも
どんな特効薬でもなく、
規則正しい生活と睡眠が、
「発達障害もどき」の症状を治す、
という結論に至るわけです。
いたってシンプル。だけど、
当然と言えば当然、の結論です。
私たち教員は、子どもたちに
発達障害かそうじゃないか、の
ジャッジを下すことが仕事じゃないはず。
子どもたちが安心安全の
日常生活を送れるように
配慮することが一番大事。
それを忘れちゃいけないですね。
興味のある方は、ぜひ一読を。














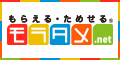
その後、病院等、先生が調べて手配してくれて
トレーニングをして今に至ります。
初めて言われた時はショックでしたが、この子の特性なんだと思うようになりました。
今、すぐに発達障害なんじゃない?って軽々しく言う人もいますが、もっとみんなに知ってもらえたらと思います
貴重なご意見、ありがとうございました🥰
周りの人達が、その人の「特性」を
知っているかどうか、って、
人間関係を築く上で大きいですよね。
そのための検査、助言でありたいですね。