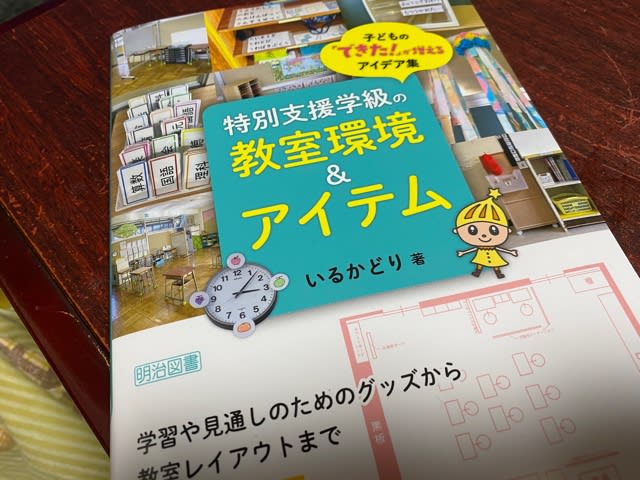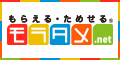複数のプログラマが関わる場合、
優れたコードを書くだけでは
プロジェクトは成功しません。
全員が最終目標に向かって
協力することが重要であり、
チームの協力関係は、
プロジェクト成功のカギとなります。
これって、Googleという組織に
限った話ではないですよね〜。
この本では、たくさんの
フリーソフトウェア開発に関わり、
その後Googleでプログラマを経て
リーダーを務めるようになった著者が、
「エンジニアが他人とうまくやる」
コツを紹介しています。
「チームを作る三本柱」や
「チーム文化のつくり方」、
「有害な人への対処法」まで、
エンジニアに求められる
社会性について解説しています。
専門用語があちこちに
飛び交っている本ですが、
「組織論」として耳を傾けて
損はない考え方が満載です。
興味のある方は、ぜひ一読を。