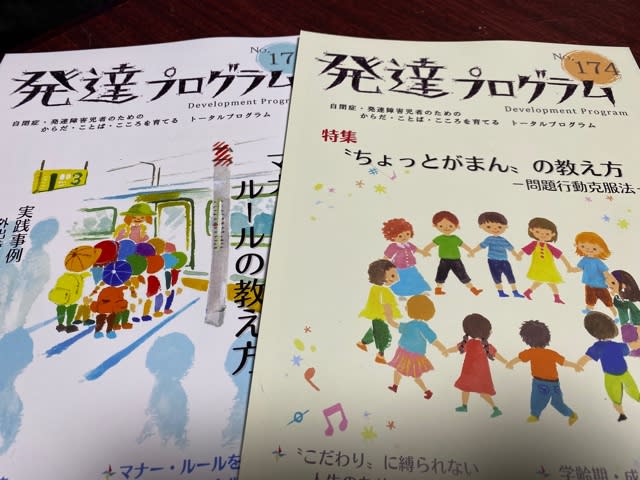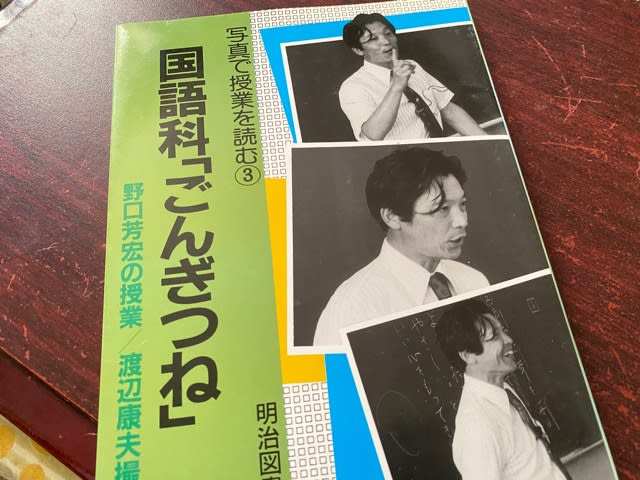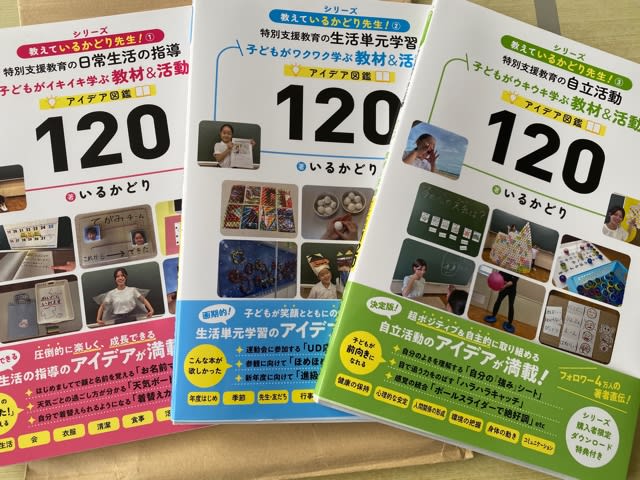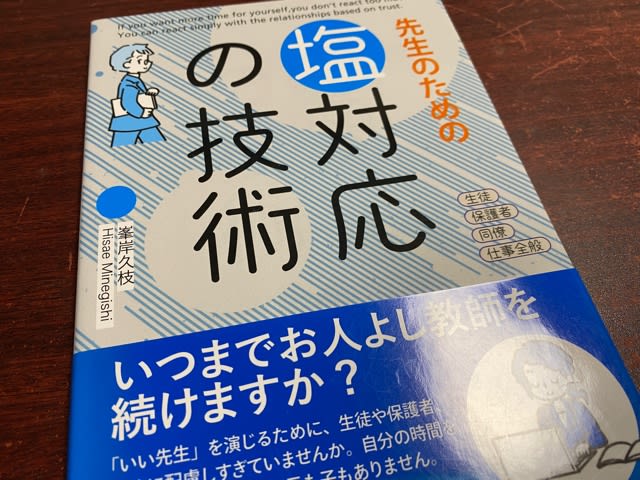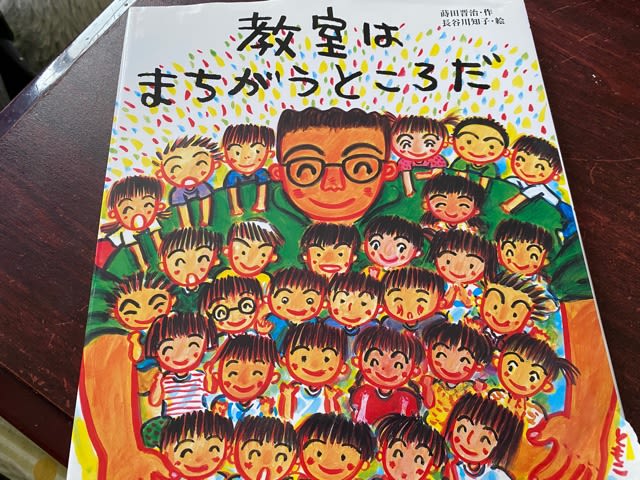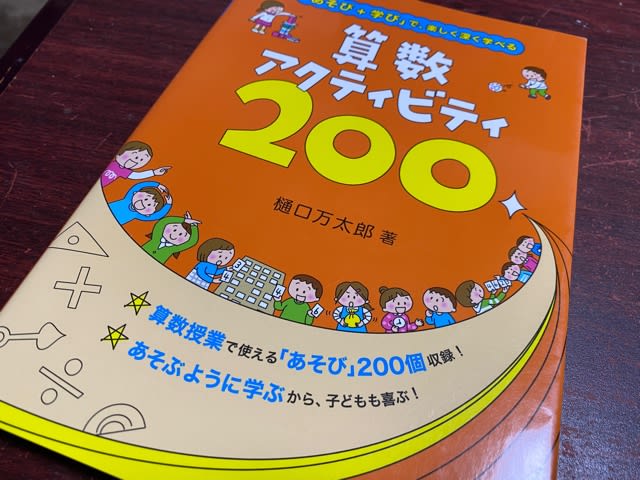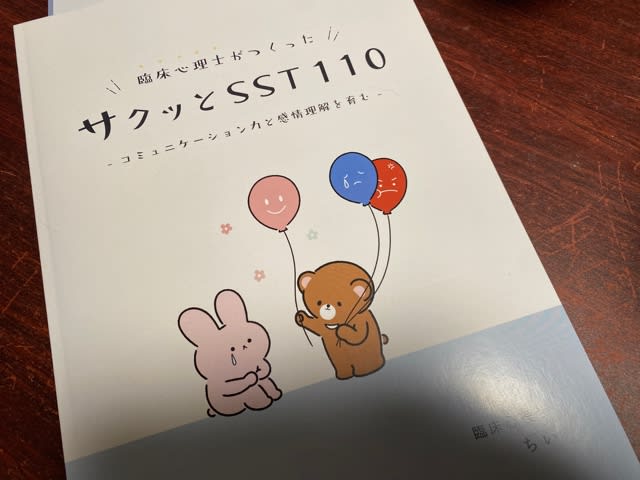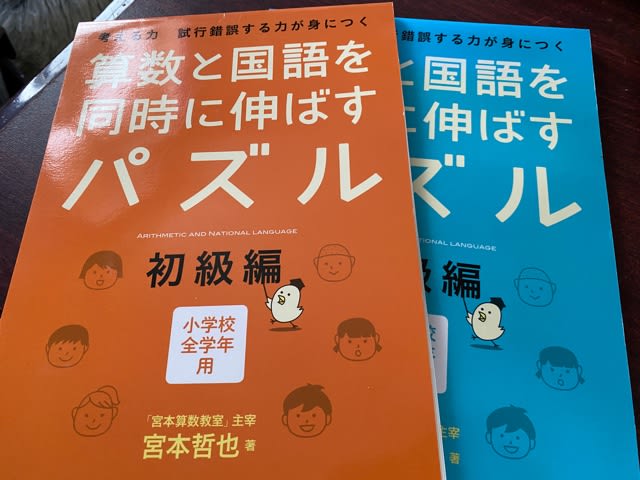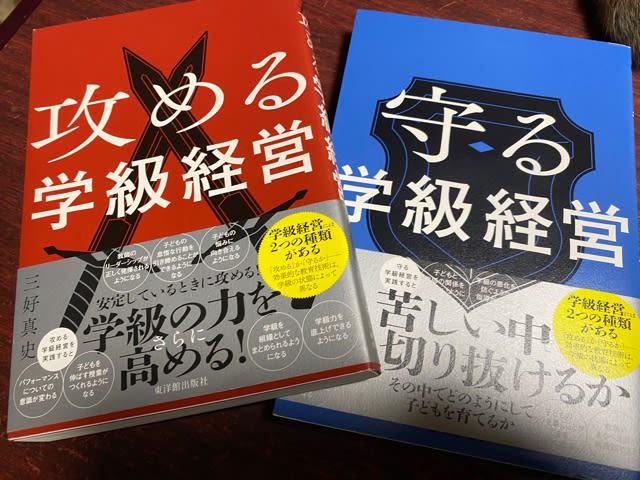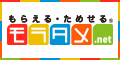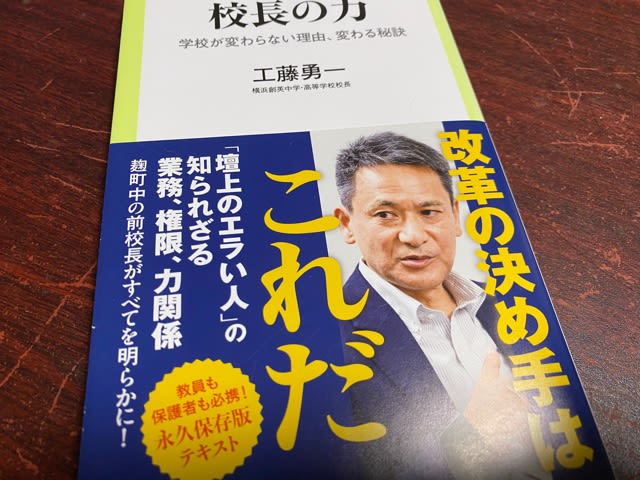
「壇上のエラい人」は日頃、
どんな仕事をしているのか?
どういうステップを踏んで
管理職になるのか?
実績を上げる校長は、どこが凄いのか?
PTA、教育委員会、議会との関係は?
現職校長が、知っているようで
実は知らない実態を明らかにしました。
その気になれば、校長は
ここまでできる!
そりゃそうですよね〜。
だって、校長は、会社組織なら
社長なんですから。
学校という組織も、
校長が代わると、ガラッと変わる。
だからこそ、トップが
一番そういう意識でいてほしいですね。
興味のある方は、ぜひ一読を。