
お雛様研究一筋の、藤原愛子先生のお話から
昔は”雛祭り”今は”雛飾り”
幕末頃から、2月の中頃からひな壇を飾り始めたらしい。(室町は公家、江戸初期は武士、中期は豪商、庶民はその後)
3月2日になると、桃家(とうけ)と門の脇に札を出した。それを子供たちが見つけて各家を訪問。雛壇をほめて、おひねりとしてアラレやアメをもらった。何軒もハシゴしてオヤツ稼ぎ!のヒナアラシ。
3日の午後には札を外す。供えてあったお料理を夕食で頂く。食事の後片付け、そして”雛片付け”当然その日のうちに!!
その程度の片付けも出来ない家で育った器量無しは、相手に見初められず”嫁に行けない”だから3日にはしまいましょう。
今は、昔の風習を知っている人の方が少ない。雛飾りとして4月3日(旧暦3月3日)まで飾る新しい流れも。
昔は”雛祭り”今は”雛飾り”
幕末頃から、2月の中頃からひな壇を飾り始めたらしい。(室町は公家、江戸初期は武士、中期は豪商、庶民はその後)
3月2日になると、桃家(とうけ)と門の脇に札を出した。それを子供たちが見つけて各家を訪問。雛壇をほめて、おひねりとしてアラレやアメをもらった。何軒もハシゴしてオヤツ稼ぎ!のヒナアラシ。
3日の午後には札を外す。供えてあったお料理を夕食で頂く。食事の後片付け、そして”雛片付け”当然その日のうちに!!
その程度の片付けも出来ない家で育った器量無しは、相手に見初められず”嫁に行けない”だから3日にはしまいましょう。
今は、昔の風習を知っている人の方が少ない。雛飾りとして4月3日(旧暦3月3日)まで飾る新しい流れも。















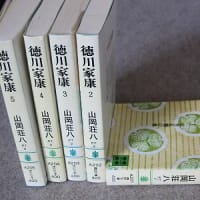




その日のうちに片付けなければならないのですね。(我が家はたいがい4日に片付けです)
どうりで姉も私も嫁に行けないわけです。
私もこの年齢になるまで知りませんでした。
あっ、お雛様を早く片付けないと「嫁に行き遅れるよ」というのだけは知ってたけど・・・
面白いお話を有難うございます。
この講演は一週間あったそうです。7:3で女性の方が多かったのですが、お雛様の事、知っていそうで知らない方がほとんどでした。多い方は3回通い、メモ用紙持参だったそうです。