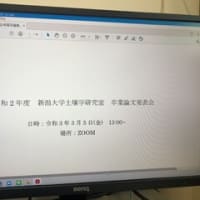かつて新潟大学で「放射性降下物の土壌ー植物系における汚染とその除染に関する研究」で学位を取られ、元土壌学研究室助教授 横山先生(83歳)に話を聞き、学位論文と当時の研究の様子を聞いてきました。
この研究は新潟大学医学部・理学部も参加して「環境と放射能」汚染の実態と問題点(東海大学出版会、昭和46年)でまとめられています。関係者は横山先生しか生存していません。
横山先生の了解が得られましたので学位論文の内容を図・表等をリメイクして、このメーリングで紹介して行きたいと思います。横山先生は土壌分析のプロでしたのでデータは信頼できます。
この論文の内容を示します。
新潟地方の農作物の放射能汚染
水稲・野菜
牧草中のストロンチウム90及びセシウム137濃度
土壌の放射能汚染
土壌中のストロンチウム90の抽出法
水田土壌中のストロンチウム90とセシウム137濃度
畑地土壌及び草地土壌中のストロンチウム90とセシウム137濃度
原野、林地、山岳、湖底土壌中のストロンチウム90とセシウム137濃度
汚染除去機構に関する研究
各種土壌中に添加したストロンチウム90の行動
各種資材添加土壌中におけるストロンチウムの行動
各種の酸を処理した土壌中のストロンチウムの行動
各種塩類を添加した土壌中におけるストロンチウムの行動
各種土壌中に添加したセシウムの行動
アンモニウム及びカリウムイオン共存土壌中におけるセシウムの行動
以上です。
土壌の放射能汚染では土壌の断面調査をもとにセシウムと137とストロンチウム90の垂直分布を調べています。1954年~1977年まで核爆発実験が行われ、土壌採取は1964年~1966年までで、原水爆実験により放射能核種が新潟に降下してから10年後の土壌採取とのことです。横山先生の話では放射能核種が降下し始めて10年が経過しているので雨により土壌下層への移行が起きていること、また、農地ではその間、耕起による攪拌で下層への移動も起きていたと推測しています。
つまり、この論文は放射能核種が新潟に降下し始めて10年後のデータと考えてほしいとのことです。
10年後の実際の割合は、
佐渡のドンデン山山頂の土壌中の全ストロンチウム90中、0~10cmに66%、10~20cmに12%、20cm以下に22%移行していました。全セシウム137中、0~10cmに81%、10~20cmに14%、20~30cmに5%です。
佐渡赤泊林地土壌ではストロンチウム90は0~16cmに84~94%蓄積し、セシウム137は100%でした。
水田土壌では土壌型・土性・施肥管理・耕作により変動しますが、ストロンチウム90は0~10cmに全ストロンチウム90の70~30%が残りますが、50cmの深さまで移行しています。
セシウム137は0~10cmに96%から50%残りますが、50cmより深く移行していません。腐植含量が多い土壌は下層への移行が比較的少なくなります。表層に有機物が多いほど、表層にとどまる割合は高くなるようです。
これは当時、放射能核種が降下してきましたから、耕起しても均等には混じらず、毎年表層に蓄積したと考えられます。
当時、農家の耕作は普通に行われたのでストロンチウム90やセシウム137が耕作で攪拌して、下層土壌まで長く残ってしまったことが何より残念であった、と話していました。
深耕や天地返しのように土壌を攪拌して薄める行為は土づくりをしてきた農家にとって最も避けなければならないと思います。
表層土壌だけの汚染にとどめ、それを除去し、有機物を投入して放射能核種が除染された夢のある新しい農業を始めることができるようにすることが最善と考えます。
これから、時間が許す限り、横山論文の解説をしたいと思います。